『ヨブ記 その今日への意義』 浅野 順一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
八 ヨブ記における死後の生命
今日のところは、「八 ヨブ記における死後の生命」である。ヨブは、サタンにより痛めつけられ、「友人の説得」も功を奏さずに、死を望むほどに弱り果てていた。
ヨブ記にしばしば「死」や「陰府」という言葉がでてくる。ここでは、旧約聖書では、死後の生命をどのように見ていたかについて解説されている。それでは読み始めよう。
ヨブ記における陰府の意味
ヨブ記には、「死」や「陰府」という語が用いられる。旧約聖書では、死後の問題をどのように見ていただろうか。
雲が消えて、なくなるように、
陰府に下る者は上がってくることがない。
彼は再びその家に帰らず、
彼の所も、もはや彼を認めない。(七ノ九、一〇)(抜粋)
まず、陰府の語源は、「うつろなところ」が最も妥当である。その意味において穴や墓に通じる。陰府は地下にあり、暗黒で塵にみちている。陰府は暗黒の地と呼ばれ(ヨブ記一〇ノ二一)、死人は塵と称される(詩編三〇ノ九)。
人は死後、貴賤の別なく誰もが陰府に降りなければならない。地上における身分はそのまま地下に続くが、陰府にある死人は全く活動しない。そして、地上に生きている人との交通は断ち切られ、さらに、神との関係も斬絶する。
それゆえ
死においてあなた(神)を覚える者はなく、
陰府においてはだれがあなたを
ほめたたえることができましょうか。(詩編六ノ五。なお三〇ノ九)(抜粋)
と詩人は嘆くのである。
そういうわけであるから、へブル人は陰府を非常に恐れ忌み嫌った。(抜粋)
旧約における霊魂不滅の否定
旧約聖書には、肉体は死によって朽ち果てるが、霊魂は永遠に生きる、という考えはない。死後の霊魂不滅という信仰なり、思想はへブル人からは遠い。
人間が死ねば肉体のみならず霊魂も共に陰府に降り、まったく無活動の状態に移されるのである。(抜粋)
この点について最も徹底的な死後感を示しているのは、「伝道の書(=コヘレトの言葉)」である。
わたしはまた人の子らについて心に言った、「神は彼らをためして、彼らに自分たちが獣に過ぎないことを悟らせられるのである」と。人の子らに臨むところは獣にも臨むからである。すなわち一様に彼らに臨み、これの死ぬように、彼も死ぬのである。彼らは皆同様の息をもっている。人は獣にまさるところがない。すべてのものは空だからである。皆一つのところに行く。皆塵からでて塵に帰る。だれが知るか、人の子らの霊は上に昇り、獣の霊は地に降りるかを。(三ノ一八-ニ一)(抜粋)
ここでは、人間も獣もその肉においても、霊においても同じであり、死んだとき人が天に昇り、獣が陰府に降りるなどということはなく、同じであるということを言っている。
前述の如く旧約による死後感は霊魂不滅でないのであるから、いわゆる永遠の生命というものも霊魂不滅とは別の角度から取り上げられているといわなければならない。しかしてそれは死人の復活ということである。(抜粋)
この復活は新しい生命となることを意味して、霊魂不滅ということではない。
しかし、旧約聖書では死者の復活は例外的にしか語られない。はっきりと死者の復活について述べているのは旧約以後の黙示文学に属し、それが新約聖書に伝えられる。
霊肉のたとえとキリスト教徒の生と死
旧約では、霊と肉は一体であり「霊肉二元的」な存在として、考えられていない。この霊肉について
デンマークのある聖書学者(ベテルゼン)は人間を一つの山にたとえているが、霊肉というのは人間を構成する素材と考えるべきではなく、人間の示す面或は占める位置だとみるべきとだといっている。そこで、ある人間が霊的だという場合、彼は山の頂点に立っているのであり、希望と力に満ちた姿である。それに反して肉的とであるという場合は山の谷底に立っているのであり、無気力、絶望の姿であるというのが、これがなかなか当を得た説明であると思う。それ故人間はたとえ生きていても陰府にあるような無活動、無気力な状態にある時、彼は死んでいるといえようし、逆に死人の状態になった場合でも新しい生命に甦るということが考えられるわけである。(抜粋)
著者は、パウロがいうように「イエス・キリストを信じるとは彼の十字架によって信ずる者が罪に死に、彼の復活によって新しい生命に甦る」と言っていることは、このことであると言っている。
キリスト教徒にとって生死ということは現実の死をいわば肉体の死を境としたその前と後というように機械的に区別されず、生きながらにしてそこに生もあり、死もあるわけである。(抜粋)
個々の議論は、なるほど・・・・わからない。クリスチャンでないので、復活といってもなんだか実感ないしね。でも、「生きながらにしてそこに生もあり、死もある」というのは、なるほど、そういうこともあるなぁ~と思ったのでした。(つくジー)
『ヨブ記』における陰府
ヨブ記も旧約の死後観に沿っていて、そこには死者の復活という考え方はない。むしろ復活という思想自体がヨブ記には出てこない。
そのため、ヨブ記には陰府における人間の存在、死者の生命について積極的な意味を認めていない。
人は伏せして寝、また起きず、
天のつきるまで目ざめず、
その眠りからさまされない。
どうぞわたしを陰府にかくし、
あなたの怒りのやむまで潜ませ
わたしのために時を定めて
わたしを覚えさせてください。(一四ノ一二、一三)(抜粋)
ここでヨブは、神の怒りの打撃から身を隠すために陰府にまでおりたい、つまり死にたいと言っている。そして、陰府はヨブにとって永遠に生きるとか、そこから甦るという場所ではない。
これは、「自分の日を呪う」とか「生まれて来なかった方がよかった」という言葉と符合する(ココ参照)。さらにヨブはたびたび「命をいとう」といっている。つまり、現在の生活に望みも喜びも持たないだけでなく、死後の存在にも希望を感じていない、問うことである。
ヨブ記には以上のように復活の希望を未だ見ることはできない。また陰府に対してヨブは積極的な期待を抱いていないというところから彼の生命への絶望が如何に大きなものであるかが想像されるのである。それ故ヨブ記の死後観についてはこれ以上積極的なことをいえぬのを遺憾とする。(抜粋)
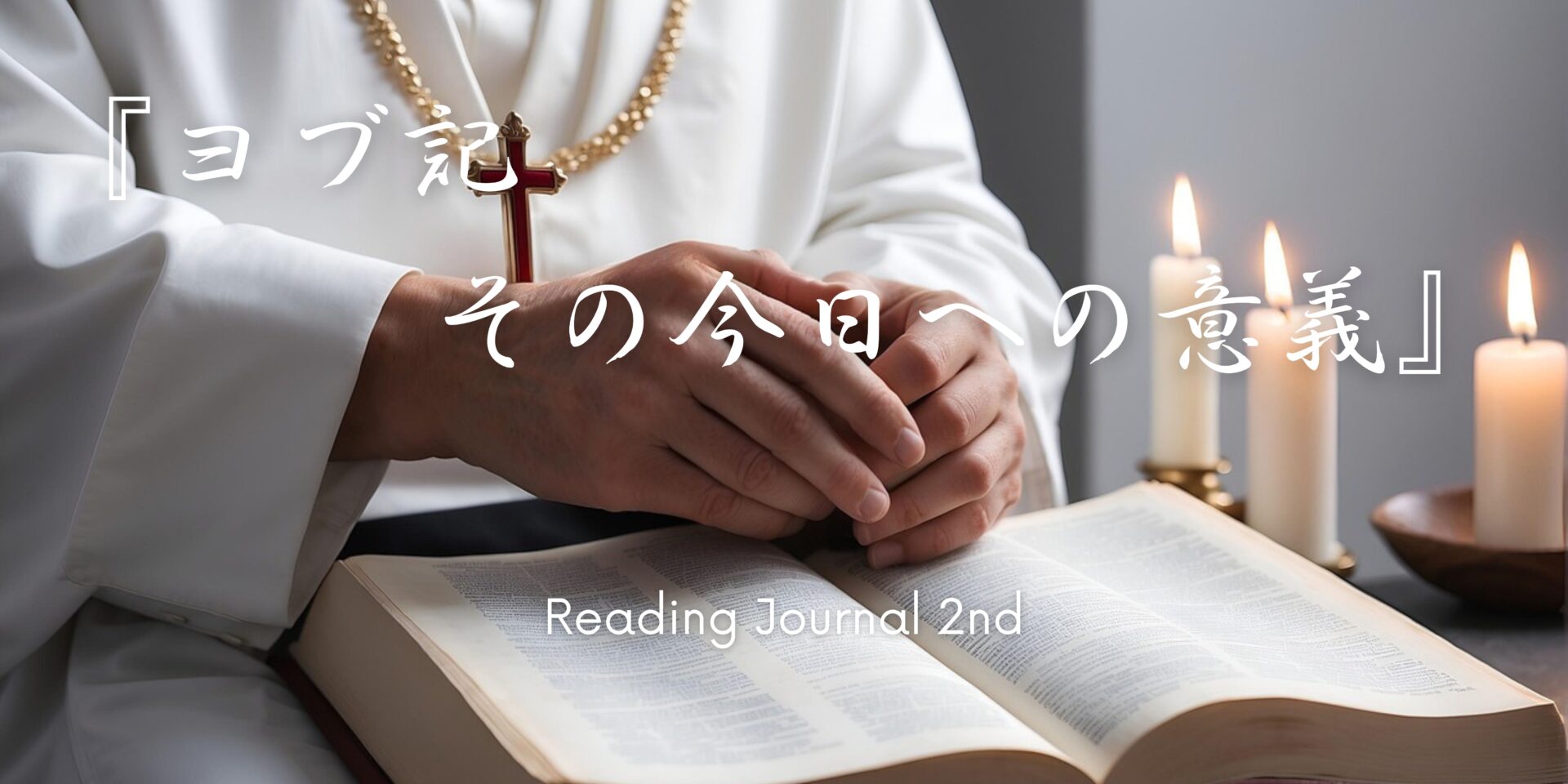


コメント