『ヨブ記 その今日への意義』 浅野 順一 著、岩波書店(岩波新書)、1968年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
一 旧約におけるヨブ記の位置
しばらく前から旧約聖書の『ヨブ記』が気になっていました。それは、「NHKこころの時代」のテキスト・小友 聡の『それでも生きる 旧約聖書「コヘレトの言葉」』とその放送の若松英輔と小友との対談の記録・『すべてには時がある』を読んだからです。
この放送は、同じく旧約聖書の『コヘレトの言葉』について紹介するものでしたが、旧約聖書の『ヨブ記』そして『夜と霧』で有名なフランクルの思想と『ヨブ記』の関連、さらには日本の内村鑑三の『ヨブ記講演』の話が書かれていた(ココやココやココを参照)。
フランクルはちょっと違うし、いきなり難解で知られる『ヨブ記』を読んでもなぁ~。内村鑑三の『ヨブ記講演』にしても信者向けだろうから・…敷居が高いかな?
そこで、岩波新書の本書『ヨブ記 その今日への意義』を読むことにした。この本は、もともと結構古い本で、初版は1968年である。なんと岩波新書の青版!そのアンコール復刊ということで、『ヨブ記』の手堅い一般書と見た!あとがきによると、もともとはNHKの「古典講座」で語ったものを本としてまとめたものだそうで、平易を旨としているとのことである。それでは、読み始めよう。
ヨブ記は旧約聖書中、創世記、詩編、イザヤ書等と共にもっともよく知られている書物である。しかもそれはひとりユダヤ教、キリスト教の信仰や神学と関係が深いのみならず、ヨーロッパの文学や哲学ともかかわるところが大きい。(抜粋)
旧約聖書の文学的構造
旧約聖書の文学的構造は次のようになっている。
- モーセの五書:創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記
- 歴史及び物語:ヨシュア記、士師記、ルツ記、サムエル記、列王紀、エズラ記、ネヘミヤ記、エステル記
- 詩歌と教訓:詩篇、詩歌(雅歌など)、箴言、教訓(伝道の書など)
- 予言:イザヤ書、エレミヤ哀歌、エザキエル書、ダニエル書、ホセア書など十二の予言書
ここで「ヨブ記」ま③の冒頭に置かれ、内容としては詩歌でありある意味教訓である。
ここの分類であるが、『それでも生きる 旧約聖書「コヘレトの言葉」』でも言及されている(ココ参照)。用語の問題ですが、そこでは、「モーセ五書」、「歴史書」、「文学書」、「予言書」となっていて、「ヨブ記」や「コヘレトの言葉」は「文学書」のなかの「知恵文学」に分類されると書いてある。そして「コヘレトの言葉」=「伝道の書」である。(つくジー)
この後、著者は、この旧約聖書のヘブライ語の原典における配列を示している。
この中にあって『ヨブ記』は、通常「知恵文学」と呼ばれている。この「知恵文学」には、「ヨブ記」「箴言」「伝道の書」、詩編のうち律法を歌えるもの(一、一九、一一九)、自然を歌えるもの(二九、一〇四)、人間、その罪をうたえるもの(四九、五一)、人間社会を歌えるもの(三七、七三)である。
「知恵文学」の意味
次に「知恵文学」の特徴を律法、歴史、予言に対比させて考察している。
第一の特徴:個人的であること
まず第一に考えられることはそれが個人的だということである。(抜粋)
聖書の宗教は旧約であれ新訳であれ、契約の宗教である。旧約においては神ヤーウェと民イスラエルの契約的関係であり、それは選民関係と言ってもよい。
旧約の律法、歴史、予言においては、民族的な性格が強い。しかし、「ヨブ記」のような知恵においては、民族的要素は背景となり個人的な傾向が著しくなる。
「ヨブ記」は、紀元前五世紀ごろの成立と言われている。その頃ユダヤ人はすでに国家を失って、民族として大きな苦しみを味わい、それが背景となってヨブ記のような悲しみの文学が生まれた。
ヨブ記自身においては、そこに直接取り上げられている問題はヨブという一個人の苦しみである。従って民俗的苦悩の問題は背後に退いている。(抜粋)
ここのユダヤの歴史の部分であるが、『それでも生きる 旧約聖書「コヘレトの言葉」』でも書かれている(ココとココ参照)。
それによると、知恵文学のうち「箴言」には、「因果応報」的な知恵が書かれているが、それに対して「ヨブ記」と「コヘレトの言葉(伝道の書)」には悲観的な知恵が書かれている。それはユダヤの民も歴史に影響されていて、つまり「箴言」が書かれたのは、安定したソロモン王の治世だったのに対して、「ヨブ記」「コヘレトの言葉」は、国家が失われた流浪の民となった後に書かれたのである。小友は次のように書いている。
「箴言」の時代は、正しく生きていれば報われる社会でした。しかし、コヘレトの時代には、平和的な時代の応報思想は通用しません。神を信じたからといって、豊かになる保証はない。それどころか、明日の命さえ危ういような、先を見通せない時代。これからをどう生きるかについて考えたのが「コヘレトの言葉」や「ヨブ記」だったのです。(抜粋)
今の時代が「箴言」の時代なのか、「ヨブ記」の時代なのか謎ですが、つまりそういうことですね。(つくジー)
第二の特徴:人間の経験の要素
信仰を人間が生きるための原理的なものと見るならば、それは経験を離れて成り立たない。律法や予言に示されるものが原理的なものとすれば、知恵はもっと経験的なものである。
ヨブのような切実な苦しい経験を通して、信仰とは何ぞやということが追究されている、それがヨブ記だといえる。(抜粋)
第三の特徴:民族を超えた国際性
知恵の性格が、個人的なものであるためそれは、民族を超えている。律法・予言・歴史では、信仰はナショナルなものであるが、知恵ではインターナショナルとなる。ヨブ記でもヨブとその三人の友人は、セム人であるがへブル人ではなく外国人と言える。
それが舞台に登って長い対話もしくは論争を繰り返すわけである。そこにこの書の超民俗的ないし国際的性格がある。それはまた普遍的性格とも言えよう。(抜粋)
第四の特徴:人間から神へという方向性
知恵文学において信仰のあり方が、「神⇒人間」とともに「人間⇒神」が示されている。もちろん「神⇒人間」の方が太く一貫されるが、「人間⇒神」の方向も重要になっている。
つまり「神の啓示を人間がどう受け止めるか」に重点が置かれている。
そのためヨブ記は、キリスト教徒・ユダヤ教徒によって重く見られるだけでなく、文学者、思想家によって問題とされ、西欧の思想、芸術に関係を持っている。たとえば、ゲーテのファウスト、ミルトンの失楽園、哲学ではライプニッツ、キェルケゴールなどである。
最後に著者の『ヨブ記』の研究歴について書かれている。著者が『ヨブ記』に関心を持ったのは、内村鑑三の『ヨブ記講演』を読んで大きな感銘を受けたからであると書かれている。そしてヨブ記と内村鑑三の関係については、著者の『ヨブ記註解』(II)の巻末を参照とのことである。
関連図書:
関根 正雄(訳)『旧約聖書 ヨブ記』、岩波書店(岩波文庫)、1971年
小友 聡 (著)『それでも生きる 旧約聖書「コヘレトの言葉」』、NHK出版(NHKこころの時代)、2020年
若松 英輔、小友 聡(著)『すべてには時がある 旧約聖書「コヘレトの言葉」をめぐる対話』 、NHK出版(別冊NHKこころの時代宗教・人生)、2021年
ヴィクトール・E・フランクル『新版 夜と霧』、みすず書房、2002年
内村鑑三(著)『ヨブ記講演』、岩波書店(岩波文庫)、2014年
浅野 順一(著)『ヨブ記註解』(1)(2)(3)(4)、講談社(創文社オンデマンド叢書)、2023年(電子版のみ)
目次
一 旧約におけるヨブ記の位置 [第1回]
二 ヨブ記の構造 [第2回]
三 義人ヨブ、その試練(一)[第3回]
四 その試練(二)[第4回]
五 ヨブの嘆き [第5回]
六 友人の説得 — その神学 [第6回][第7回]
七 ヨブの立場と友人の立場 [第8回][第9回]
八 ヨブ記における死後の生命 [第10回]
九 人の道と神の前 —- ヨブの良心と信仰 [第11回]
一〇 ヨブを贖う者 [第13回][第14回]
一一 宗教の益 [第15回]
一二 聖書と自然 [第16回][第17回][第18回]
一三 苦痛による救い [第19回][第20回][第21回]
一四 神の呼びかけ [第22回][第23回]
一五 ヨブは何を懺悔したか [第24回]
一六 ヨブの回復 [第25回]
一七 結語に変えて [第26回]
附 説教者エリフ [第27回]
あとがき
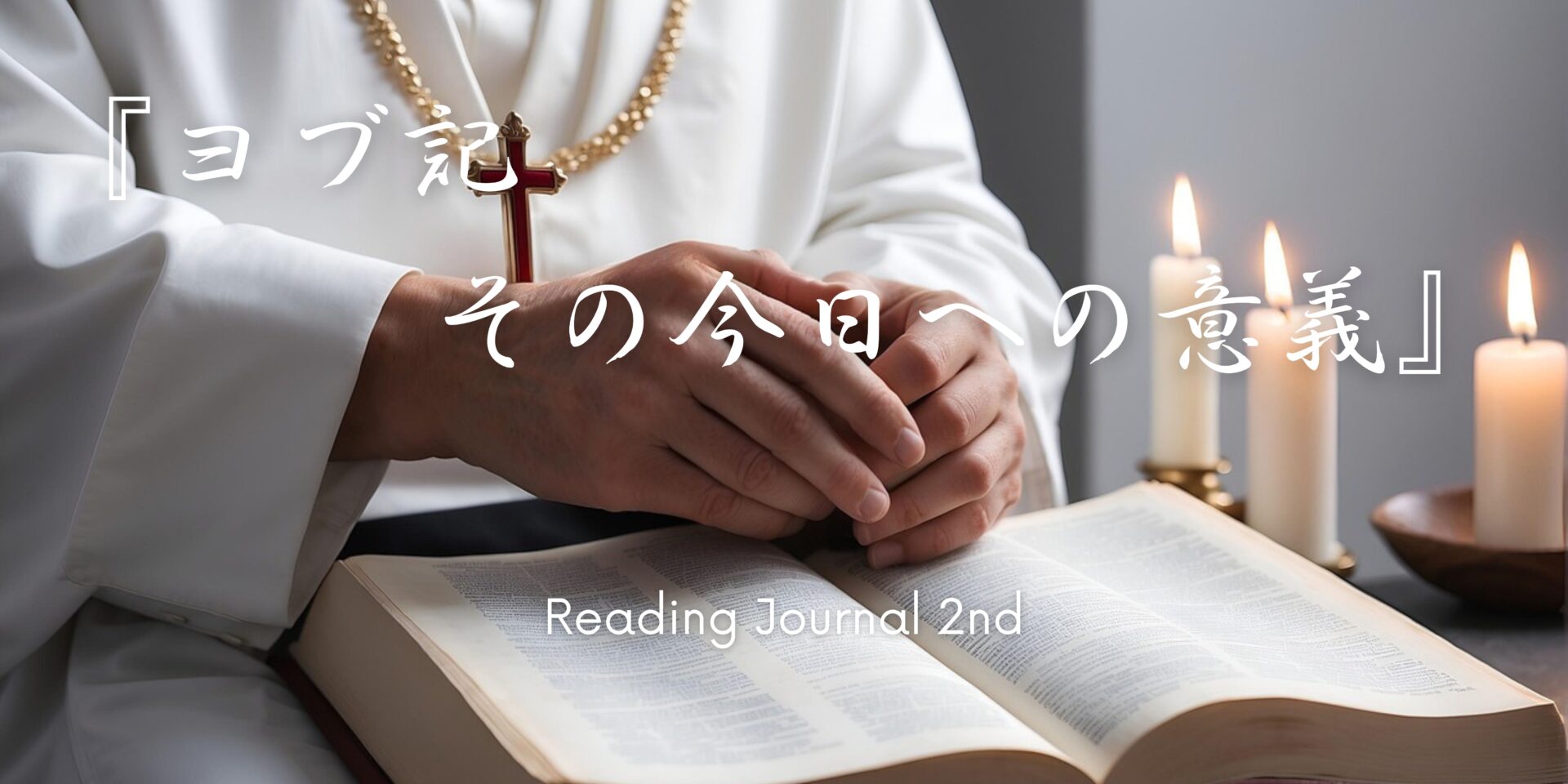


コメント