『ポピュリズムとは何か』ヤン=ヴェルナー・ミュラー 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
訳者あとがき 板橋 拓己
巻末に本書の訳者である板橋拓己によるあとがきがある。ここには、本書の内容の解説のほか、ポピュリズム研究における本書の意味、また著者のヤン = ヴェルナー・ミュラーの業績などが解説されている。それでは、読み始めよう。
「ポピュリズム」とは何にかについて、いまのところ共通了解は存在しない。日本では「大衆迎合主義」と訳され、基本的に負のレッテルとして使われているが、実際のところは共通の了解は存在しない。
本書は、このような状態のなか「ポピュリストとは何か」という問題に正面から、しかも簡潔に答えようとしたものである。
本書が二〇一六年九月に大統領選を控えたアメリカで出版されるや、瞬く間に話題になり、各紙誌で「ポピュリズムを理解するための最良の書」とされた。
本書『ポピュリズムとは何か』の特徴は、ポピュリズムを「反多元主義」と捉え、明確に民主主義にとっての脅威と位置づけていることである。(抜粋)
ポピュリズムの定義として、しばしば「エリート批判」が挙げられるが、ミュラーは、それだけでなく反多元主義であるとした。そしてポピュリズムの反多元主義は、単なる反多元主義ではなく、政治世界を道徳主義的に認識するものと捉えている。つまり「道徳的に純粋な人民」と「腐敗したエリート」あるいは「怠慢なマイノリティ」を対置させるのがポピュリズムである。
ミュラーは、ポピュリズムを「特定の心理傾向でもない」「特定の階級の問題でもない」「政治の質の問題でもない」「政治スタイルの問題でもない」と言っている。そうではなく、ポピュリズムは「ある特定の言語を用いる政治である」と言っている。つまり「自分たちが、それも自分たちだけが真の人民を代表する」という主張がポピュリズムなのである。
そして、ミュラーはこのポピュリズムが民主主義の脅威であると明確に捉えている。
ここで訳者の板橋は、ミュラーは「人民」に依拠する政治自治体は否定していないと、注意している。ポピュリズムの問題な反多元主義でありその排他性である。そのため、アメリカの人民党やバーニー・サンダースなどの存在は、反多元主義でないためポピュリストとは言えないとしている。
また、板橋も本書のポピュリスト理解が唯一のものと言い張るつもりはないとしているが、少なくとも今後のポピュリズムの研究は本書と格闘することが必要だとしている。
関連図書:(あとがきで紹介されているミュラーの著書(邦訳のみ)及びポピュリズム関連の和書)
ヤン・ヴェルナー・ミューラー(著)『カール・シュミットの「危険な精神」— 戦後ヨーロッパ思想の遺産』、ミネルヴァ書房、2011年
ヤン = ヴェルナー・ミュラー(著)『憲法パトリオティズム』、法政大学出版局(叢書・ウニベルシタス)、2017年
ヤン = ヴェルナー・ミュラー(著)『試される民主主義 — 二〇世紀ヨーロッパの政治思想』(上・下)、岩波書店、2019年
大嶽 秀夫(著)『日本型ポピュリズム: 政治への期待と幻滅』、中央公論新社(中公新書)、2003年
吉田 徹(著)『ポピュリズムを考える 民主主義への再入門』、NHK出版(NHKブックス)、2011年
水島 治郎(著)『ポピュリズムとは何か – 民主主義の敵か、改革の希望か』、中央公論新社(中公新書)、2016年
国末 憲人(著)『ポピュリズム化する世界 ―なぜポピュリストは物事に白黒をつけたがるのか?』、プレジデント社、2016年
[完了] 全20回
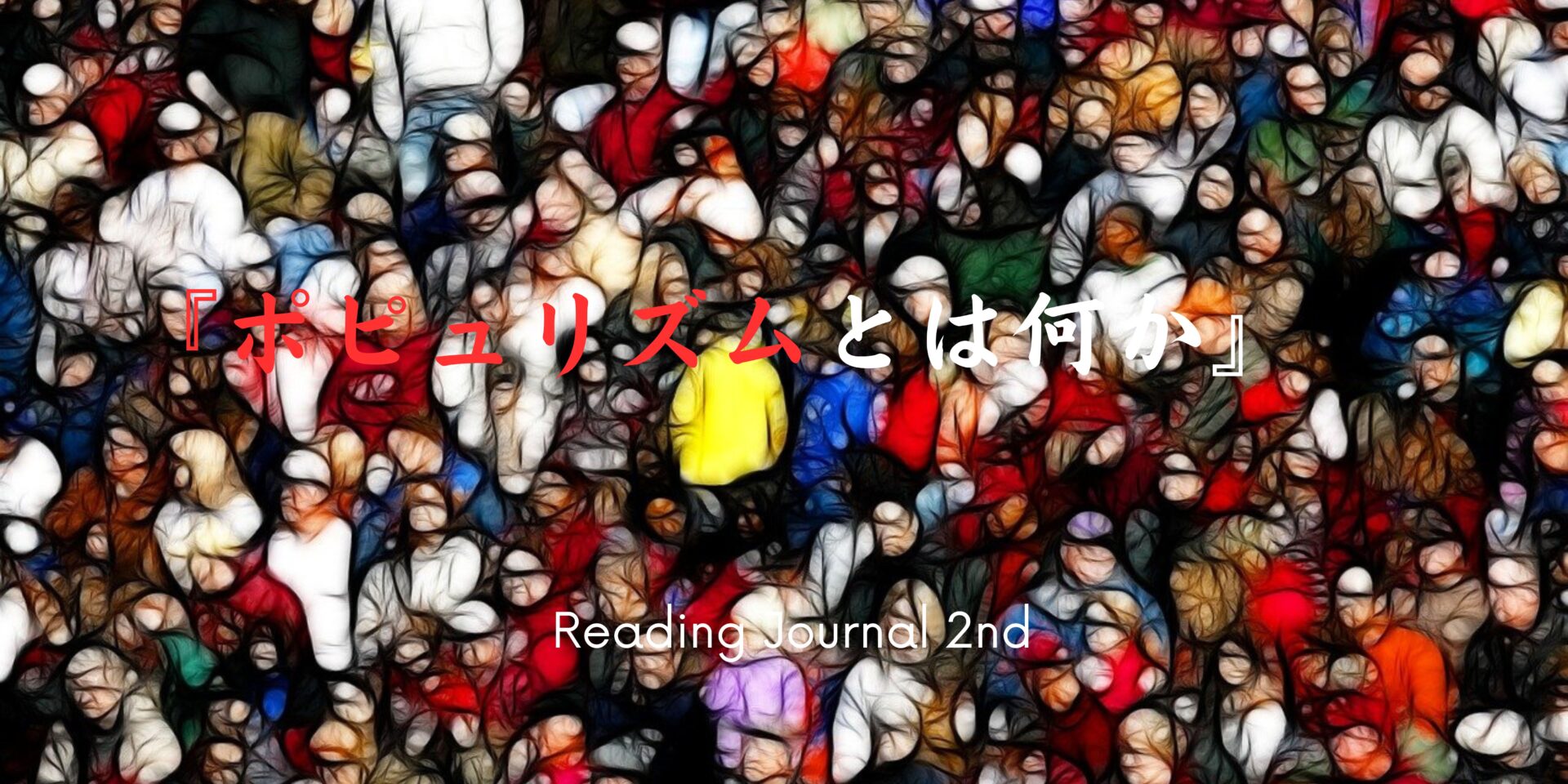
-1-120x68.jpg)

コメント