『ポピュリズムとは何か』ヤン=ヴェルナー・ミュラー 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
結 論 ポピュリズムについての七つのテーゼ
今日のところは、最終章「結論 ポピュリズムについての七つのテーゼ」である。ここでは、今まで行ってきた議論を七つのテーゼとしてまとめている。それでは、読み始めよう。
テーゼ1
ポピュリズムは、代表政治の永続的な影である。エリートに異議を唱えるために「真の人民」の名において語る可能性は常に存在する。ポピュリズムは代表政治にのみ存在し、政治的代表制に反対はしない、しかし、自分たちのみが正統な代表だと主張する。
テーゼ2
ポピュリストは「反エリート主義」だけでなく「反多元主義」である。反多元主義者であるポピュリストは、自分たちだけが人民を代用するとし、自分たち以外の政治勢力を非正統とし自分たちを支持しない人たちは、人民の一部でないと主張する。また、自分たちが反対派(野党)のときは、エリートが非道徳的であり、一方人民は道徳的で同質であり、その意志を誤ることはないと主張する。
テーゼ3
ポピュリストは、「共通善」を代表すると主張する。しかしそれは本当の共通善ではなく、「真の人民」を象徴的に代表することである。この共通善を代表することにより、ポピュリストの政治的立場は経験的な論駁から守られ、選挙で負けた時も「真の人民」や「サイレント・マジョリティ」を掲げて対抗することができる。
テーゼ4
ポピュリストは、しばしばレファレンダム(国民投票)を要求する。しかしその意図は、人民の意思だと決定したものを追認するときだけである。ポピュリズムは政治参加の拡大へ通じる道ではない。
テーゼ5
ポピュリストは、統治することもできる。しかしそれは、自分たちだけが人民を代表するという約束にしたがった統治である。具体的には「大衆恩顧主義」、「腐敗」、「批判者への抑圧」などである。そして、これらは道徳的に正しいと正当化され、公然と行われる。
また、ポピュリストは憲法も起草できる。その憲法は、真正な人民の意思を永続化するという名目のもと、自分たちの権力維持をもくるむものであり、党派的あるいは「排他的」となる。
テーゼ6
ポピュリストは、民主主義の真の脅威であるその実態ゆえ批判されるべきである。しかし、彼らと政治的議論をしないということではない。ポピュリストと話すことは、ポピュリストのように話すことと同じではない。
彼らが提起した問題を、彼らの問題の組み立て方を受け入れることなく、真剣に受け止めることは可能である。(抜粋)
テーゼ7
ポピュリズムは、自由民主主義を矯正するものではない。一部の人々が代表されていないことを明確にすることには有益であるが、彼らの支持者だけが「真の人民」であるという主張が正当化されることはない。
ポピュリズムは自由民主主義の擁護者に、現代における「代表制の失敗」について考えることを強い、「全般的な道徳的問題」への取り組みを強いる。つまり、「政体の一員である基準とはなにか」「多元主義の維持の価値」「ポピュリストに投票する人たちの理解とその懸念への取り組み」などである。
本書がこれらの問題に対して、少なくともいくつなの予備的な答えを提示できたことを願っている。(抜粋)
あとまだ、「訳者あとがき」がありますが、一応ここで本編が終わった。やった~。ここまで長かったね。途中、ちょっと読み切れないなと思って、『難解な本を読む技術』を読んで、読書ノートの取り方を学び、そこからノートをとりながら、なんとかかんとか読みました。(ノートをとりながら読むと理解が進みますよ・・・まぁ中途半端なノートですがね)
この本を読んでいる間にアメリカ大統領選があり、なんとトランプ大統領が再選されて、ビックリだったりした。これから先が思いやられるけども、アメリカでは、「真の人民」=(見捨てられた)白人は、すでにマジョリティを張れないだろうから、これからどうするんだろうね?さらには、支持しているそれらの人々が、ますます追い詰められるような気もするが?
それはそれとして、本書では、結局は、テーゼの6,7が著者の言いたいことのように思うのだが、どうだろう。(つくジー)
関連図書:高田 明典(著)『難解な本を読む技術』、光文社(光文社新書)、2009年
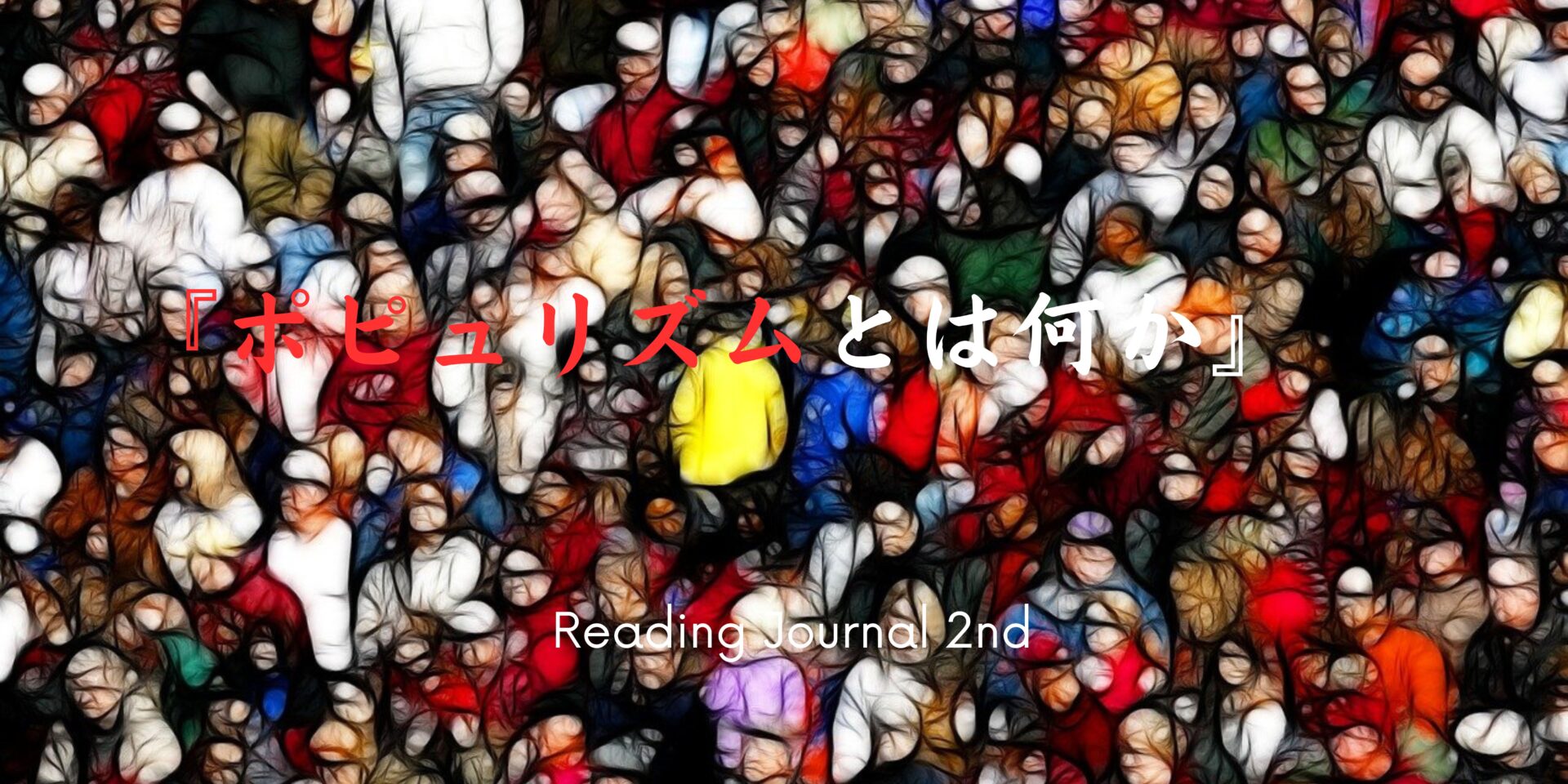
-1-120x68.jpg)

コメント