『ポピュリズムとは何か』ヤン=ヴェルナー・ミュラー 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二章 ポピュリストがすること、あるいは政権を握ったポピュリズム(その7)
今日のところは「第二章 ポピュリストがすること、あるいは政権を握ったポピュリスト』“その7”である。今日のところは「人民は「われら人民」と言えないのか」の節の後半であるが、ここでは、人民の問題について取り扱われる。
人民は「われら人民」と言えないのか
「人民」という概念が内在する危機
ここで著者は「人民」という表現が、「不安定かつリスキーで、ことによると完全に危険な表現である」ことを指摘する。このような危険性は、すでにフランス革命時のアドリアン・デュケノワやアメリカ第二代大統領、ジュン・アダムズによって指摘されている。
民主主義は、人民をめぐる問題をつねに再燃させ、ときに全く新しい条件で提起することを可能としてきた。その意味で、民主主義は恒常的な危機に苦しむことになる。
そして、この人民をポピュリストは次にように主張すると著者は言っている。
実のところ、人民はいまや確実かつ最終的に同一化されうる --- そして人民はいまや現に存在するものであり、もはや潜在的なものではない --- と主張することによって、要求形成の連鎖を断ち切るのが、ポピュリストである。(抜粋)
正当な「人民」とポピュリズム的「人民」
ここで著者は、タハリーム広場での「ひとつに社会」「ひとつの要求」やかつての東ドイツでのシュプレヒコール「われわれは人民だ」のようなものについて、体制が人民を政治的に締め出された場合には、正当であるとしている。
社会主義のような非民主主義社会で体制が排他的に人民を代表し人民自身は他の何かであり他の何かであろうとした場合に、この「われら人民」という言葉はまったくポピュリスト的ではない。
しかし、代表制民主主義がかろうじて尊重されているポピュリスト体制においては、このような小さな異議申し立てでさえ、巨大な反響を与えうる。
スタンディング・マンの事例
ここで著者は、トルコでの「立っている男」の事例を持ち出している。
イスタンブールのゲジ公園での抗議者たちが取り締まられた後、タクシム広場で、ひとりで立っている男が現れた。男は禁じられたデモせずただ抗議の意思として立っているだけだった。続いて多くの男女がスタンディングに加わったが、誰も何も言わなかった。
この時、エルドリアンは、ポピュリストの典型的な統治のテクニックを使った。エルドリアンは彼が、外国のエージェントと示そうとしたのである。
著者は、このような行動が民主主義的かポピュリスト的かは、つねに明白でわかりきったものではないとしている。しかしエジプトでのタハール広場の講義関して次のように言っている。
二〇一二年から一三年の間に、ムスリム同胞団が、明らかにポピュリスト的で党派的な憲法を創ろうとしていた事実は残る。すなわち、純粋な人民についての自分たちのイメージを定義し、何が良きエジプト人を構成するかに関する、彼らの特殊な理解から導き出された制約を定める憲法を創ろうとしたのである。こうして対決は避けがたいものになった。(抜粋)
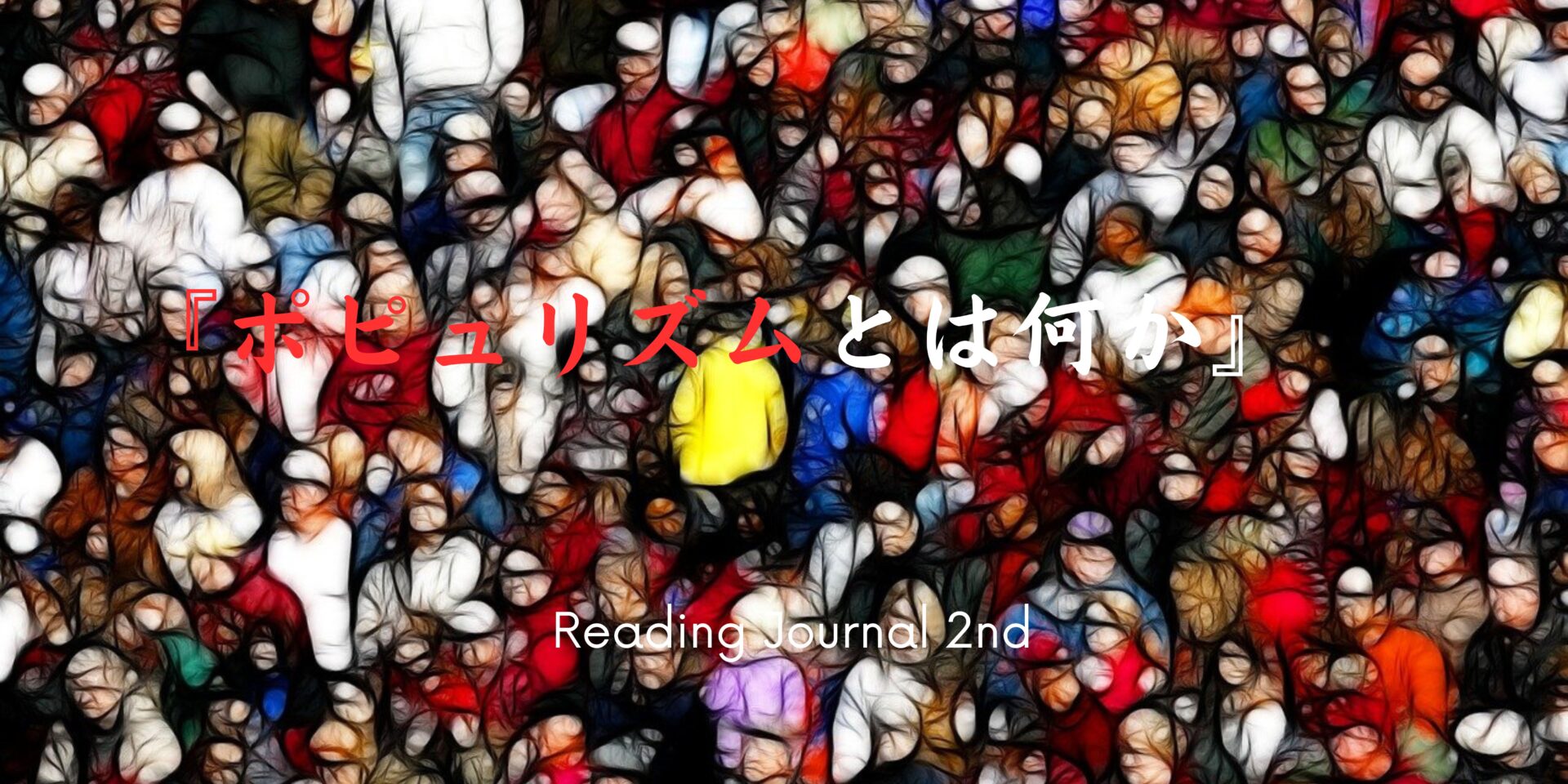

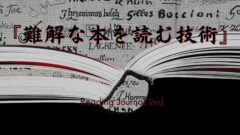
コメント