『チャーリーとの旅』ジョン・スタインベック 著、岩波書店(岩波文庫)、2024年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
『チャーリーとの旅』
毎日新聞の書評(今週の本棚:Web版)に紹介されていた『チャーリーとの旅』を買ってみた。著者は、ノーベル賞作家のジョン・スタインベックである。この本は、この2年後にノーベル文学賞を受賞するスタインベックが、犬一匹を連れて車でアメリカ大陸を一周する旅の記録であるそうだ。なるほど・・・スタインベックって、よく知らないけども、読んでみることにした。
『チャーリーとの旅』を読み終わった。まずは、本題とあまり関係ないが、冒頭が面白い。
とても若くて、どこかに行きたいというジリジリした思いにつかまれていた頃、おとなたちから、おとなになればそんなうずきはおさまるもんだ、と説得された。(抜粋)
に始まり、しかし、そのどこかに行きたいという、うずきはいっこうに収まらないと、延々と綴っている。結局五八歳にしてアメリカ一周の旅に出発するのだが、その書き方が、どこか『奥の細道』冒頭の芭蕉の焦燥に似ているような気がするなぁ~と思った。
それはそれとして、この本は、ジョン・スタインベックによるアメリカ一周の旅の記録である。スタインベックは、この計画のために荷台にキャビンを乗せたトラック — キャンピングカー? — をしつらえ、助手として老プードルのチャーリーだけを連れて旅立つ。
旅の目的と強いアメリカ人
旅の目的は単純である。彼は「自分の国を知らない」ことに気がついてしまったからである。スタインベックは、ニューヨークに住み、多くの旅をしてきた。しかし、パリがフランスでないように、ニューヨークはアメリカではないことに気がついた。アメリカの変化を“二五年”の間、本や新聞に教わるだけで、生身で感じてこなかったことに気がついてしまったのだ。
この“二五年”という具体的な数字は、訳者解説によると、スタインベックの小説が始めて売れたときからの年月であるそうだ。
そしてもう一つのひそかな理由があった。それは病気である。スタインベックは前の冬に結構な病気となった。すると医者には、年齢もとってきたのだから、ペースを落とすように、体重を減らすようにコレステロールの摂取を制限するように言われる。しかしスタインベックは、このような忠告を、一人の男を精神的にも肉体的にも半病人にし、第二の幼児期に移らせるものだと反抗する。
わが身をふりかえってみたこともある。なにしろ、わたしはつねに荒っぽく生きてきた。酒もどっさり飲んだし、食べるときも山盛りか、あるいはまったく食べないかだった。二四時間ぶっとうしで寝もするし、二晩ぜんぜん寝ないこともあった。好調なときははげしすぎるほどいつまでも仕事をしたし、しばしば完璧なまでにだらしなくデレットしたこともある。持ちあげ、引っぱり、ぶった切り、登り、歓喜のセックスをしたから、気が抜けたようになることもあったが、それは当然のなりゆきで、罰があたったわけではない。荒々しさを捨ててすこしでも距離を稼ごうなんて思ったことはなかった。妻はひとりの男と結婚したのである、赤ん坊を引き受けねばならない理由などない。トラックを一〇〇〇から一二〇〇〇マイル(1600㎞~1930㎞)運転する。ひとりきりで誰のアテンドもなく、ありとあらゆる種類の道路を進む。それはハードワークになるだろうことはわかっていたが、そうすることが病気のプロが抱える毒への解毒剤になるようにわたしにはおもえた。(抜粋)
スタインベックのこのような、西部の男、強い男への思いは、ところどころに出てくる。
そして美しいと思うのは、主に森のなかである。ナイアガラの滝をすてきであると言い、モンタナには恋をしてしまった。さらに、レッドウッドの巨木に驚愕し二日間キャンプをしている。面白いのは、スタインベック本人は山の中で育ったのではなく、カルフォルニアのモントレーで海に近い、しかも彼は、大学で海洋生物学まで学んでいる。さらに言えば、東海岸の海沿いに住み、船まで持っている!! でも、海じゃないんだ、と思った。
貧しい人虐げられた人への眼差し
しかし、貧しい人や虐げられている人、恵まれない人への共感もこの“強い男の旅”の背景に潜んでいる。
メーン州に行ったとき、カナダからジャガイモの収穫期にやってくるフランス系の季節労働者、カナックと出会う。スタインベックは、このような季節労働者たち — 故郷を離れたインド人やフィリピン人やメキシコ人やオーキーたち — に出会ってきたという。そして、ここでオーキーには注がある。
※1 意味はオクラホマ人だが、一九三〇年代の不況時に仕事を求めて渡り労働者になった人々を指す蔑称にもなった。スタインベックの『怒りの葡萄』はかれらをめぐる小説(抜粋)
スタインベックは、そこで出会ったカナックの一家 — 彼らは家族や家族のグループでキャラバンをしき移動する — を自分のキャビンに招き、語らっている。そして彼らのことを頑健で、礼儀正しい、すてきな人であると評している。
別れの言葉も、当然のように、短くてきちんとしたものだった。夜のなかへ出ていき、リーダーのジョンが錫の灯油ランタンで道を照らし、みんな、眠たくてよろよろ歩く子どもたちにはさまれ黙って歩いていった。その後は二度と会うことはなかった。しかし、わたしはかれらが好きだ。(抜粋)
そして、さらにこの旅の最終盤の南部では、人種差別がテーマになっている。スタインベックがこの旅をしている一九六〇年当時、黒人の公民権運動が盛んになっていた。
スタインベックは「南部に対面するのが怖かった」と書いている。彼は「自分が人種差別主義者としては失格だということ以外でも、わたしは南部ではお呼びでないのがわかっている。」とも書いている。
ちょうどそのころ、ニューオリンズで人々を賑わしていた事件が起こっていた。ふたりの小さな黒人の子どもが小学校に入学しようとしていたのだ。
このいたいけな黒い肌の子どもたちをうしろで支えていたのは法の権威と法の力だった。 --- 正義の秤と剣は幼児たちに味方していた ---- 、いっぽう、子どもたちを阻んでいたのは三〇〇年におよぶ恐怖と怒りで、世界がどんどん変わっていくことへの怖れであった。(抜粋)
子供たちが学校にくると、多くの「母親」たちが、集まって大きな声で罵倒していた。そんな女性たちの中でもひときわ目立つ小さなグルプが「チアリーダーズ」として有名になり、それに喝采する人たちが毎日どっと集まってきた。
この奇異なドラマがまったく信じられず、わたしは、この目で見なければ、と思った。(抜粋)
そして、スタインベックは、ニューオリンズで目撃したことを詳細にレポートし、また現地の人々とも話をしている。この事件や南部の人たちの言葉について、スタインベックは驚き、そして困惑している。そしてこの事件の記述に対して、最後に
ひとつだけははっきりしておきたい。わたしには断面のようなものを提示するつもりはなかったし、また、提示したいともおもっていないので、「南部のほんとうの姿を提示したと著者はおもっている」と言ってほしくない。わたしは提示していない。何人かの人間が言ったこと、私が見たことを語っただけである。(抜粋)
と書いている。
関連図書:松尾 芭蕉 (著)『芭蕉 おくのほそ道』、岩波書店(岩波文庫)、1957年
目次
地図
第一部
第二部
第三部
第四部
訳者あとがき
登場地名一覧
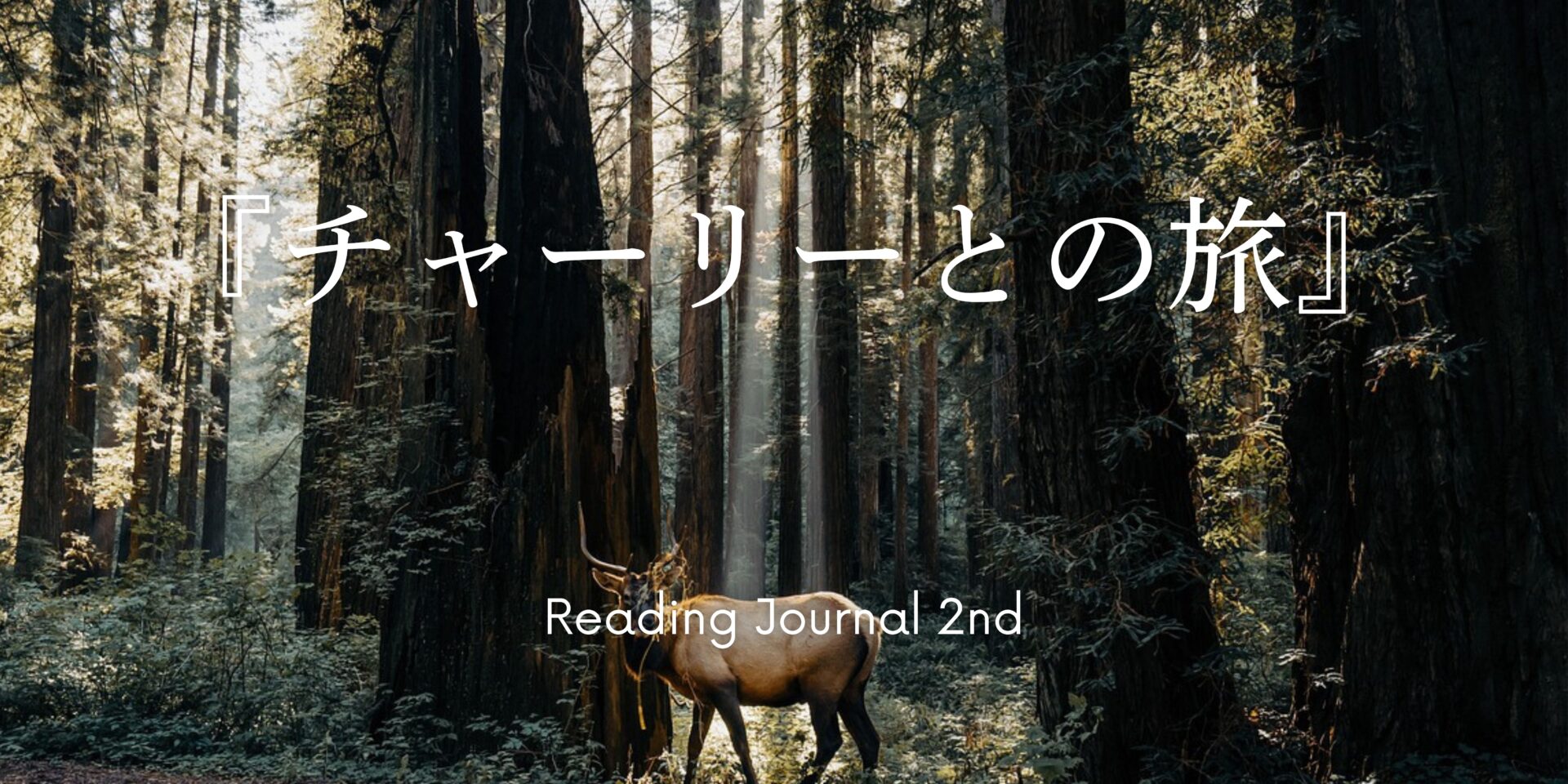
-1-120x68.jpg)

コメント