『問いかける技術』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第4章 自分が動き、自分が話す文化(後半)
今日のところは「第4章 自分が動き、自分が話す文化」はどう違うのか」の”後半“である。である。”前半“では、「謙虚に問いかける」を困難にする文化的な弊害と最大の問題「人間関係の構築よりも、課題の遂行に価値を置く文化」を取り上げた。
今日のところ“後半は”第二の問題である「自分が話す文化」について、そして、なぜこのような問題を取り上げるのが重要であるのかについてである。それでは読み始めよう。
第二の問題 — 自分が話す文化
「謙虚に問いかける」を困難にする文化的な問題の2つ目は、「自分が話す文化」である。
アメリカ人は、自分が話す方が大事であるとあたりまえのように考えている。正しい質問をすることは評価されるが、一般には質問をすることは自分の無知という弱みを見せることと認識される。そして、ものを知っていることが評価され、自分の知っていることを人に話そうとする。
アメリカ社会では、管理職になると人に指示のが当然という考えであるが、これには危険な思い込みがある。それは「昇進すれば部下に何をさせるべきかわかるようになる」ということである。そのため、管理職が部下に意見を求めるのは、職務を全うにできず、みずから役職を放棄したとみなされる。
一九五〇年代に風刺作家スティーブン・ポッターがゲイムズマンシップ(勝つための駆け引き)、ワン・アップマンシップ(相手を出し抜くこと)という言葉を用いて見事に表現した文化を、私たちはいまだに引きずって生きている。(抜粋)
この二つの言葉は、会話のなかでさえ競い合うことを是とするような欧米文化について、実に深い洞察をしている。われわれは、いちばん話がうまいのは誰かということについて競いあっている。それが極端になると駆け引きやハッタリの達人になるために「正真正銘のズルをしないで勝つ方法」や「イヤな奴だと思われずに目的を達する流儀」を身につけることになる。
このような文化にあるため、私たちには「どちらも勝利できる双方向の協力関係」といった考えが浮かばない。
ここで著者は、もう一つ聞く立場の人間にとって、すでに知っていることを話題にされたり、わかっていることを助言されたりすること、ほど不愉快なものはないと指摘している。
しかし、われわれは自分が話し手になることに一生懸命になるため、相手がそのことについて検討した可能性があるかを考慮せずに助言してしまう。
文化の偏りと「謙虚に問いかける」が必要なわけ
著者は、米国の文化には他にも多くの側面があるのに、なぜいまこのような米国文化の偏りについて問題提起するのかについて次のように語っている。
世界は今、技術がますます複雑化し、人々が互いに依存するようになり、社会が文化的に多様化している。このことは、人間関係の構築が仕事を進める上でますます重要になってきたことを意味すると同時に、人間関係を築くこと自体が以前よりも難しくなっていることも意味する。円滑なコミュニケーションをおこなうためには、人間関係が重要な役割をはたす。課題を遂行するためには、コミュニケーションが円滑におこなわれていることが肝要だ。良好な人間関係を維持するためには、「今ここで必要な謙虚さ」を軸として相手に「謙虚に問いかける」ことが、かぎとなる。(抜粋)
仕事は以前にもまして、チームワークが必要になってきている。すべてのポジションの人が機能しなければならない。そのためみんなで協力する必要がある。
グループで行動する場合は、単に「一緒に仕事をするプロフェッショナル」という関係に留まらず互いにもっと踏み込んだ人間関係を築くことが必要となっている。このとき「謙虚に問いかける」を実践することにより、初期段階で必要な人間関係を築くことができ、メンバーが一緒に学んでいくことも可能となる。
米国では、メンバーがしっかりした人間関係と高いレベルの信頼があったからこそ、良い仕事ができたという事例があると、それは賞賛される。しかし、それはそれが異例であるということを暗黙の内に認めているからである。
強い絆で結ばれた人間関係は異例なものと見なされ、ビジネスの現場ではチームづくりのための仕組みなどは、真っ先にコスト削減の対象となってしまう。
リーダーが「謙虚に問いかける」ことの必要性
通常は、地位の高いほうの人が会話を主導し、部下はもっぱら聞き手や質問役にまわる。しかし、これが適切に機能するには以下の三つが必要である。
- 上位の目標を上司も部下も共有している。
- 上司は解決策を心得ている。
- 部下は指示された内容を理解している。
もしこの条件が整っていない場合は、初期段階で「謙虚に問いかける」を実践しておかなければ、後になってからコミュニケーションが良好かの判断が難しくなる。
なぜならば、部下は多くの場合、指示を理解できなかったことを認めたがらず、あるいは上位の目標を共有していないため、メンバーから情報が上がってこないことが起こる。
課題が複雑になればなるほど、互いに依存度が高くなるので、上司は「今ここで必要な謙虚さ」の必要性を認め「謙虚に問いかける」を実践する必要がある。上位にある人間はつねに部下たちの面子を守り、立場を確保するようにして安心させることが大切である。そうしない常に弱い立場である部下とのコミュニケーションが取れなくなる。
さまざまな技術がここまで複雑になってしまった昨今、リーダー自身が自分でできる仕事はあまりにも少ない。だからこそ、「今ここで必要な謙虚さ」を心得て生きる術を学ばなければいけないのだ。(抜粋)
まとめ
米国では実用主義と個人主義、そして自分の力で地位を築くことを重んじることが暗黙の仮定となっている。しかし、一方でこれらの仮定は、物事を片付けることを第一義的に考え、人間関係の構築やリームワーク、協働を軽んじることにつながっている。
しかし現在のように、仕事の複雑さが増し、人々が互いにもっと依存しあうようになると、協働やチームワーク、そして人間関係の構築がより重要になる。そのためリーダーには「謙虚に問いかける」ための必要なスキルが求められる。
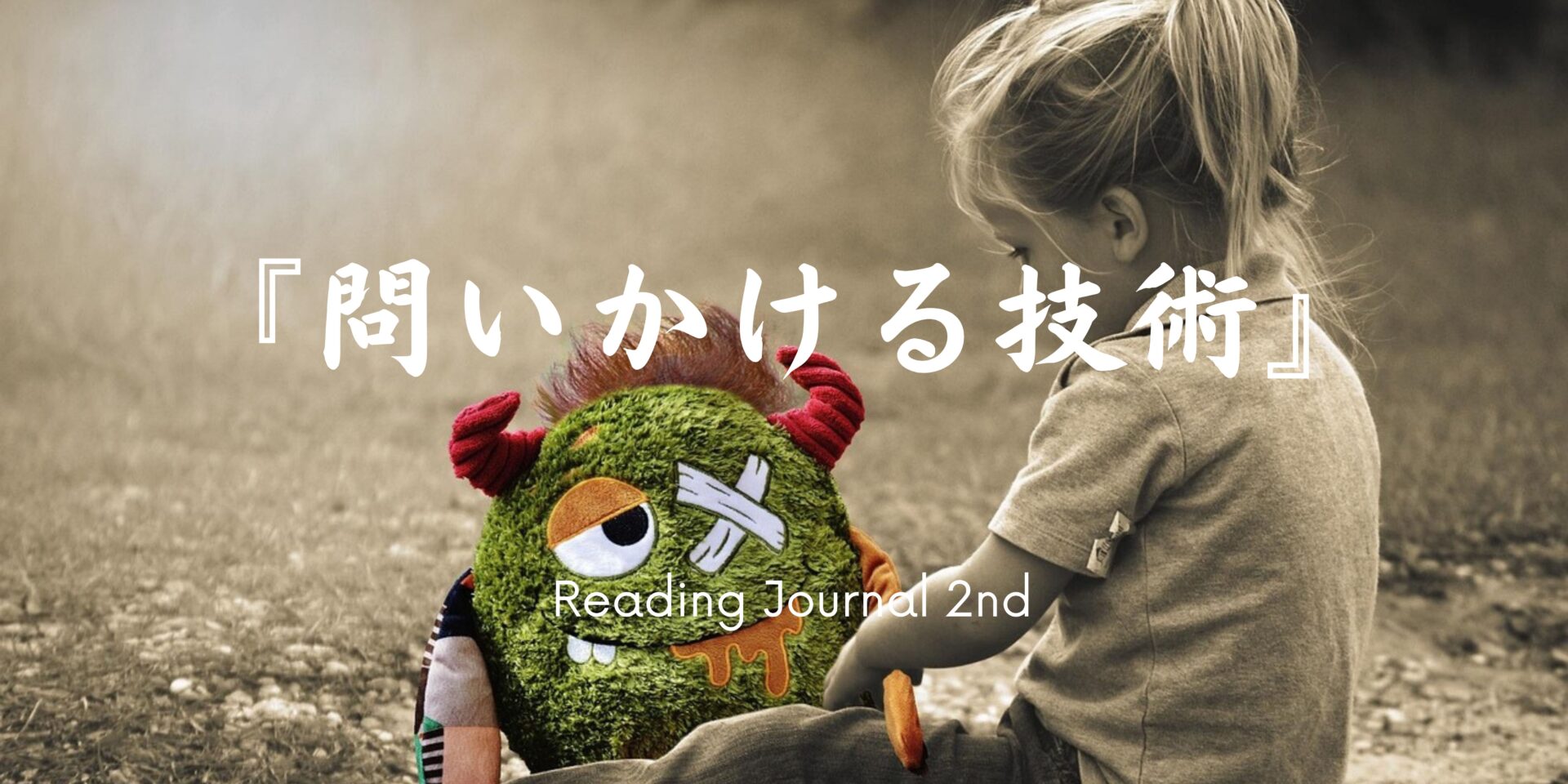


コメント