『問いかける技術』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第4章 自分が動き、自分が話す文化(前半)
今日から「第4章 自分が動き、自分が話す文化」である。著者は、「謙虚に問いかける」を困難にする要因は、自分たちが育った文化にあるとしている。ここでは、そのような2つの文化、「人間関係の構築よりも、課題の遂行に価値を置く文化」と「自分が話す文化」についての問題を考察する。
第4章は、二つに分け”前半“では、文化の弊害の概説と「人間関係の構築よりも、課題の遂行に価値を置く文化の問題」について、”後半“では、「自分が話す文化」の問題と、そのような文化を背景した「謙虚な問いかけ」の重要性について、まとめることにする。
「謙虚に問いかける」を難しくする文化的側面
「謙虚に問いかける」を困難にする最大の要因は、実は私たちが育った文化そのものだ。(抜粋)
著者は、このように語り本章を始めた。
それぞれの文化には特有の「(標榜された)価値観」があり、アメリカでは、自由、機会の平等、個人の権利のほか、「憲法で定められた権利」が含まれる。
しかし、ある文化を深く掘り下げると「暗黙の仮定の価値観」も存在する。それは、意識するまでもないほど社会の前提になっている。しかし、そのようなものが人々の特徴的な行動原理を際立たせ文化を形づくるエッセンスとなる。
アメリカでは、チームプレーの大切さ(「標榜された価値観」)が訴えられるが、実際の昇格や報酬のシステムなどは、完全に個人主義(「暗黙の仮定の価値観」)に基づいている。この個人主義は、機会の平等や自由を大切にしつつも、充実していない教育制度、就労機会の少なさ、マイノリティー対する差別などを見ると、実用主義や「いびつな個人主義」となっている。
謙虚なふるまいといった人々の行動もそれに関する文化における暗黙の了解が影響している。そのためその文化における暗黙の了解、特に権力や人間関係、信頼といったことに関して、どのようなことが暗黙に仮定されるかを理解する必要がある。
この謙虚にふるまうことに関しては、多くの社会では生まれながらにして社会的地位が定まっている人に敬意を表すという文化がある。一方、欧米諸国では平等主義と個人主義が進んでいるために、実力で成功をおさめた人だけを尊敬する傾向がある。
つまり、欧米では、自分よりも成功した人に「任意に示す謙虚さ」を実感する。しかし、相手への依存を自覚したうえで感じる「今ここで必要な謙虚さ」の方は、往々にして見落とされる。
権威主義が色濃く残っている社会では、地位や業績による上下の差が大きくなるので、上司が部下に謙虚になることは難しい。
そして、アメリカでは一般論を越えたところに「謙虚に問いかける」を難しくする独特の一面が存在する。
ここにきて、以前に説明があった「三つの謙虚」(ココ参照)について、意味が分かったような気がした。つまり封建的な社会での「基本的謙虚さ」、欧米などにみられる「任意に示す謙虚さ」では、自分より社会的に下に人に謙虚になることは難しい。そこで必要なのが「今ここで必要な謙虚さ」である。その謙虚さが人間関係の向上、チームワークに必要で、さらに、「謙虚に問いかける」を通して人への支援につながるってこtだな!・・・きっと(つくジー)
最大の問題 — 人間関係の構築よりも、課題の遂行に価値を置く文化
米国の文化は個人主義に根差していて、競争が激しく、楽観主義的であり、実用を重んじる風潮がある。(抜粋)
ここから著者は、「謙虚に問いかける」を困難にする、二つの問題につい考察する。まずは、「人間関係の構築よりも、課題の遂行に価値を置く文化」についてである。
アメリカ人は個人が成し遂げたことをとても高く評価し、激しく他人と競争し合う。そしてその楽観主義と実用主義は、物事を短期的に捉え、長期的な計画をたてるのが苦手である。
なかでも特筆に値するのは、人間関係の構築よりも課題の遂行のほうに、私たちは価値を置くという点だ。しかも、自分にそういう文化的傾向があるとは自覚していない。それどころかもっと悪いことに、私たちはそんなことはどうでもいい、そういう問題で煩わされたくない、とまで考えている。(抜粋)
アメリカ人は集団を好まないし信用もしていない。チームワークの価値を認める(「標榜されてきた価値観」)発言をしばしばするものの、実際にはスター選手が他の誰よりもはるかに高い報酬を得る(「暗黙の仮定」)ことが普通であり、チームのみんなが等しく報われるべきだという発想はない。
アメリカ人は、個人が競争力を発揮する方が、人とうまく付き合うより大事で、勝つために競い合い、話しあいでも人を論破し、巧みに相手の弱みに付け込み、さらには騙される方が悪いと搾取する方を正当化することさえしてしまう。
このような傾向により、人に対する信頼を高める方法論を持ち合わせず、人に対し警戒心と不信感を持ってしまう。
米国では、部下を持つようになると支持を与える資格を手にし、異なる地位や立場のあいだに社会的な距離が生じる。
このような文化においては、チームワークの重要性を認識するものの、実際には上の立場の者が、敬意を持たずに接するようなことが多くなり、うまく機能しなくなる。
このような米国文化を「暗黙の仮定」と言うレベルまで考えると、「謙虚に問いかける」をむずかしくしていることがわかる。
人々が実用主義と個人主義を主張し、競い合い、架台の遂行に重きを置くという文化が生まれた結果、米国では謙虚であることは低い価値観として位置づけられてしまったのである。(抜粋)
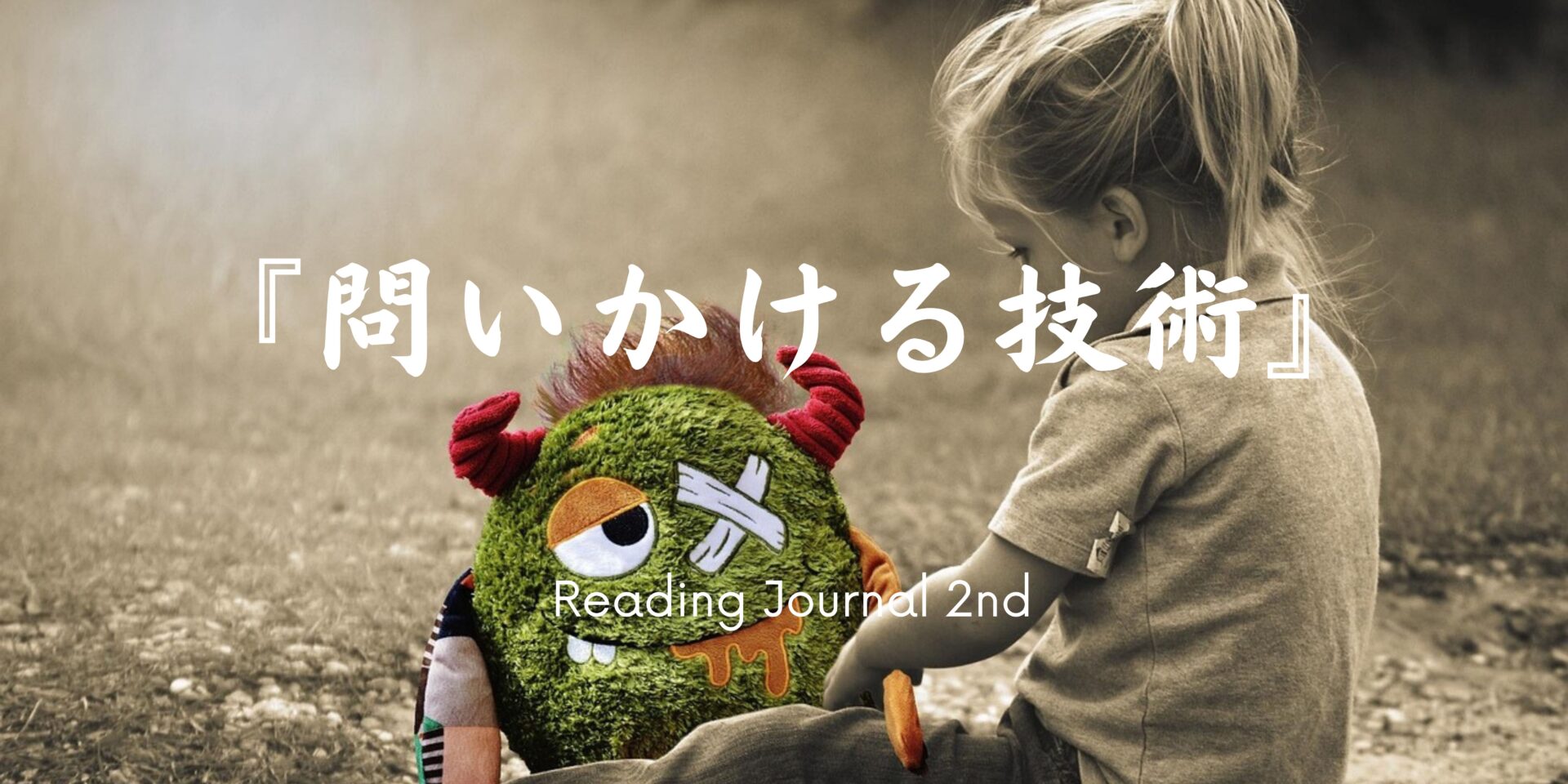


コメント