『問いかける技術』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第1章 謙虚に問いかける
今日のところは「第1章 謙虚に問いかける」である。ここでは、本書の中心である「謙虚に問いかける」ということの説明がなされる。ここでいう「謙虚」とは、年長者や身分の高い人、偉業を成し遂げた人に対してなされる謙虚さではなく、われわれが目的の達成のために誰かにたよるときの「今ここで必要な」謙虚さのことである。そしてこの「謙虚に問いかける」ことが、グループなどが機能するためのカギとなることが、分かりやすい例を通して説明されている。それでは、読み始めよう。
気まずい状況になったとき
- 話し合いがよからぬ方向へ逸れてしまった
- こちらからの助言として最良のものが無視された
- 人から忠告されて自分が不愉快になった
- 言ってくれれば状況を改善できた、あるいは落とし穴を回避することができたかもしれないのに、部下がそれを報告してくらなかった
- 議論が泥沼化して歩み寄れなくなり、お互いに傷つけ合ってしまった
このような状況にしばしば陥ることがある。
このような状況になったとき、次のように行動するべきであると著者は言っている。
- 自分から一方的に話すのを控える
- 「謙虚に問いかける」という姿勢を学び、相手にもっと質問する
- 傾聴し、相手を認める努力をする
しかし、これはいざ実行するとなると難しい行動である。
これまで「人に話すこと」「人の話を聞くこと」については、さまざまな本で取り上げられているが、「質問すること」については、不思議と疎かにされている。
しかし、このある特定の流儀(「謙虚に問いかける」)で相手に問いかけるということは、人と人が信頼関係を築く土台となる。
質問することで、どのように人間関係が築かれるのか
われわれは「話す文化」にいるため「質問すること」は不慣れである。
まず著者は、なぜ話すことがそんなに悪いのか?という疑問に答えている。それは、社会学的な視点から見ると、質問せずに「一方的に話す」ことは、相手を上から見下ろすような恰好になるからである、としている(上の①に関係)。
一方「質問する」という行為は、相手が自分の知らないこと(知りたいこと)を知っているということを示唆し、相手に力を与え、一時的に自分を弱い立場に置くことである。
そのため立場のバランスがとれより良いコミュニケーションと良好な関係が築かれる。社会学的な観点から両者は公平で、バランスがとれていなければならない。
この「質問する」という行為により、相手から知らなかったことや求めていることについて情報が入る。そして、主導権を向こうに渡すことにより「信頼」が生れる。
ここで著者は次のように、この「質問すること」について注意を促している。
ところが、こうした連続的な流れは当たり前のようには発生しない。それはなぜだろう。・・・中略・・・自分では質問しているつもりでも、それは単に言葉づかいが変わっただけで、結局自分の言いたいことを質問の形式に置きかえただけか、あるいは自分が正しことを確かめるために相手に問いかけているに過ぎない場合が多い。しかし、自分ではそのことに気がついていないのだ。(抜粋)
われわれは、話す文化にいるため質問することは、自分の無知や弱い部分をさらけ出すことと考える。だからその行為をしたがらない。しかし、問いかける方が良い結果を生む。
「謙虚に問いかける」ことを実践することで、相手に真摯に耳を傾けるというサインを送り、力を与えることができる。このとき「今ここで必要な謙虚さ」が示されている。
三つの謙虚(小見出し)
ここで著者は、「謙虚な問いかけ」の「今ここで必要な謙虚さ」について説明するために、三種類の謙虚さについて説明を加えている。
① 基本的謙虚さ
伝統を重んじる社会におけるでは、上流階級に属する人や身分の高い人は世間から本質的に敬われている。このような社会では謙虚なふるまいは任意に示すものではなく、人と接する時の前提である。
②.任意に示す謙虚さ
個人が努力によって社会的地位を築くことができる社会では、自分よりも多くのことを成し遂げた人物に対して謙虚になる傾向がある。しかし、謙虚にならざるを得ないほど輝かしい成功をおさめた人と接点を持つかどうかは、個人に委ねられるため、どのような態度をとろうと自由である。
③.今ここで必要な謙虚さ
もし自分が相手に頼っているときに必要な謙虚さが「今ここで必要な謙虚さ」である。相手が何らかの情報を持っていたり、便宜を図ってくれようとしているとき、自分の立場はいつもより劣っている。そのため、一時的にせよ相手に対して謙虚にならざるを得ない。
この「今ここで必要な謙虚さ」は、自分が誰かの部下や患者、来談者であるときに感じやすく、同僚との間では実感しにくい。そして、部下の業績は自分の肩書に付随する公的な権限によって保障されていると考えるようなタイプの上司は、こうした謙虚さの存在を全く認識していない。
しかし、自分が相互に依存しあうグループのメンバーのリーダーである場合、参加者全体が公的な地位に関係なく、互いに依存しあっていることを認識し、「謙虚に問いかける」を実践して、誰とでも仕事にざっくばらんに話せる関係を築いておく必要がある。
三つの「謙虚さ」を外科チームに当てはめた例
この後、この三つの謙虚さを外科チームという例を通しての解説がなされる。
「謙虚に問いかける」について
「謙虚に問いかける」の検討のため、まずは「謙虚さ」の定義について検討した。ここでは「問いかける」とはどういうことかについて検討する。
「どのような聞き方をすれば、相手から聞きたいことを引き出せるか」については、長い歴史があり、セラピスト、カウンセラー、コンサルタントのような人たちは、それを高いレベルまで引き出している。しかし、普通の人はそのような意識などなく「どのように質問すべきか」など考えたこともない。
著者が語っている「謙虚に問いかける」は、単に聞くことを指しているのではない。
私が本書で語ろうとしている「問いかける」はという行為は、相手に対して興味や好奇心を抱くという態度から導かれるものなのだ。(抜粋)
率直に語り合える関係を築きたいと願い謙虚になると相手からの影響を受けやすくなり、その結果として協力を得やすくなる。「今ここで必要な謙虚さ」を示す心のありようが、人に対する興味と好奇心を育むための根っことなっている。
相手に支援をしてほしいとき、一時的に相手より弱い立場に置かれる。そうして相手を立てるからこそ、警戒心を解き、有益な情報を与えてくれたり、ひと肌脱いでくれたりするのである。
このような流れのなかで考えると、「問いかける」というのは、質問することを指す。しかしそれは、古い頭で考えたタイプの質問であってはならない。(抜粋)
そして、著者はもう一つの注意として、「謙虚に問いかける」と
- 誘導的な質問
- 巧妙な言葉づかいで煙に巻こうとする質問
- 相手を困らせる質問
- 質問に見せかけた意見
と区別する必要があるとしている。このような質問の背後には、議論をふっかけるという意図があり、相手をやりこめるという目的がある。
この「謙虚に問いかける」ことを組織のリーダーや管理職にかかわらず、あらゆる職業の人が学べば、みな質問のタイプを注意深く見極めなければならないことに気づき、人間関係の構築にとって有効な質問を見極める必要に気づくはずである。
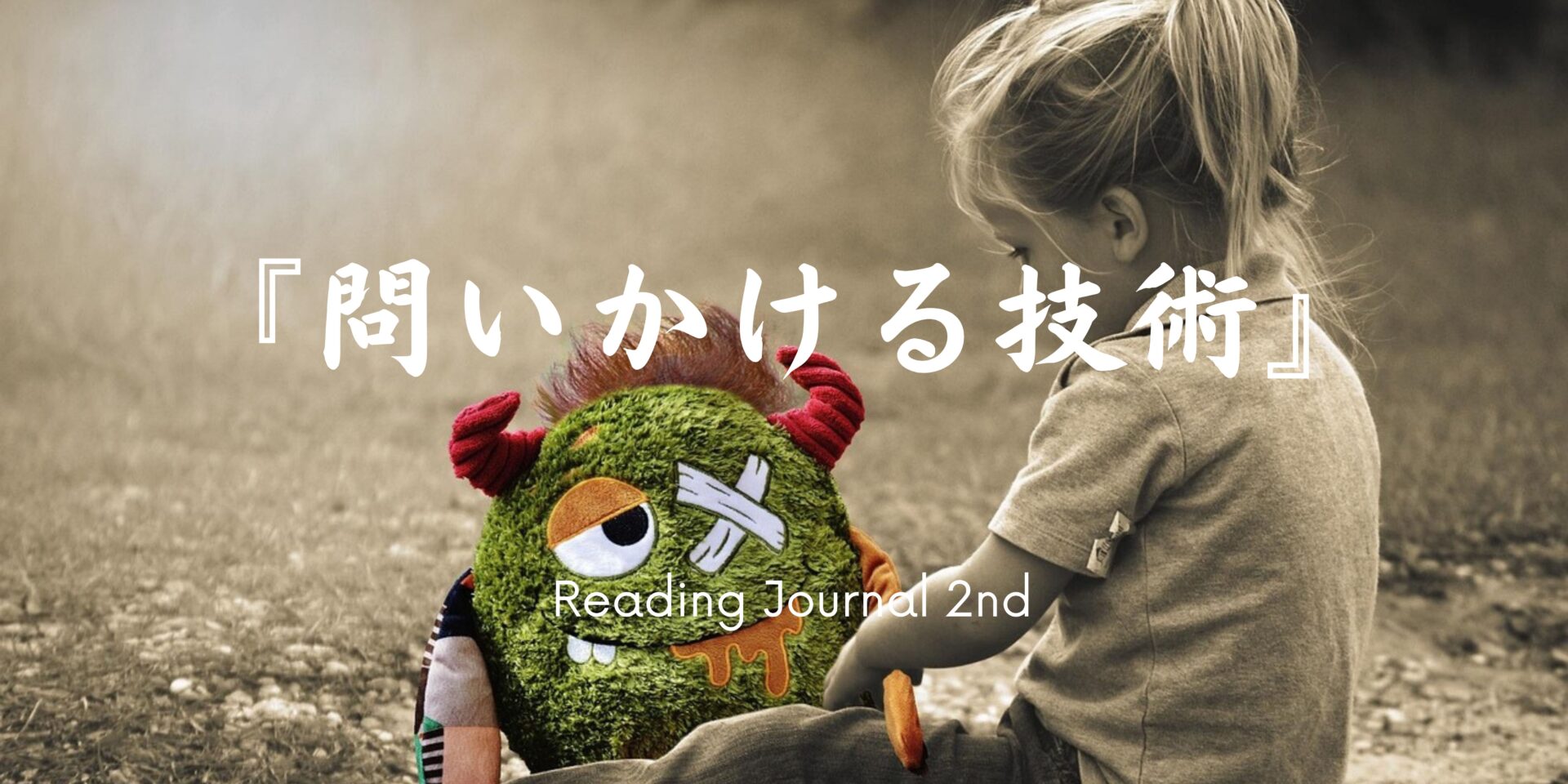


コメント