『問いかける技術』 エドガー・H・シャイン 著、英治出版、2014年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
エドガー・H・シャインの『人を助けるとはどういうことか』を読み終えた。なかなか良い本だったと思う。「経営学」、「組織心理学」の権威であるエドガー・H・シャインによる「支援学」の本である。
支援する状況を「社会的経済学」や「社会劇場」といった分かりやすい概念で示し、支援で大切なのは、支持することや教えることではなく、「控えめな質問」により相手の信頼と、さらなる情報を引き出し、共に解決のプロセスを支援するということ、という内容だった。(シャインはこれを「プロセス・コンサルテーション」と名づけている)
そして、これから読み始める『問いかける技術』は、前著『人を助けるとはどういうことか』の次に出版された本である。
シャインの「支援学」のカギとなるのが、この本の原題である「控えめな質問 (Humble Inquiry)」であるので、この本はそこにズームアップしたものだと思う。前著も分かりやすい例を豊富に載せているが、でも自分の実際の場面となると、やっぱりどう言ってよいかわからない。この本でさらに勉強したいと思った。それでは、読み始めよう。
監訳者による序文
前著『人を助けるとはどういうことか』と同じく、本書もまずは監訳者の金井壽宏の序文から始まる。
良好な人間関係の鍵「控えめな問いかけ」
人との良好な人間関係は、日々の生活の基盤になるだけでなく、仕事をうまく進めたり、すぐれた組織をつくるうえで不可欠である。しかし、しばしば思いは伝わらず、どのように良い関係を築くのかについて思い悩む。
本書は、あらゆる人が直面するこのテーマについて、組織心理学で世界的に高名な学者が五十年にわたる研究と豊かな人生経験を踏まえて著したものだ。(抜粋)
そして、本書では良い人間関係を築くための鍵は「問いかける」という日常の行為であるとしている。しかしむやみに質問するのではなく「謙虚に問いかける」ことが必要である。これが、本書の原題(Humble Inquiry)となっている。
シャイン集大成としての支援学
シャインは組織心理学、組織開発、経営学の第一人者である。そしてシャインがその集大成として取り組んでいるのが、協力関係や対人関係というテーマであり、編み出した手法がプロセス・コンサルテーション(内容そのものについて助言するのではなく、相手が自ら納得のいく答えを見出せるようにプロセスを設計し支援する方法)である。
「自分が働き、自分が話す文化」
金井はシャインが「支援学」がテーマの前著『人を助けるとはどういうことか』に続き、本書を書いた理由を次のように説明している。
本書執筆の背景には、よい人間関係を築くスキルが今後ますます重要になるという思いや、にもかかわらず世の中には「自分が働き、自分が話す文化」がはびこっていることへの問題意識があるようだ。(抜粋)
この「自分が働き、自分が話す文化」は、他者との関係を大事にするのではなく、自分が主導権をとって話し、物事を動かすことを重視する文化で、「謙虚に問いかける」の反対である。
シャインはこのような文化が蔓延していると危惧している。
金井は、日本では「謙虚さ」が美徳とされているが、複雑化し多様化した現在では、そのような文化は限界に来ていると指摘している。
自分自身を弱い立場へ置く
この「謙虚な問いかけ」は、自分をあえて弱い立場に置くことである。
本書で著者は、弱い自分を見せることが、関係性を深めるうえで最も重要だと述べている。(抜粋)
さまざまな対人関係において、「自分をあえて弱い立場に置く」ことを学べばよりよい人間関係が築ける。
この解説を読むと、本書は前著の「支援学」から「自分が働き、自分が話す文化」や「自分をあえて弱い立場に置く」という部分が進んでいるのかな?と感じた。この二つのフレーズをキーフレーズとして置けば理解が深まるように思う。(つくジー)
関連図書:エドガー・H・シャイン (著)『人を助けるとはどういうことか』、英治出版、2009年
目次
監訳者による序文 [第1回]
はじめに 良好な人間関係と強い組織を築くために [第2回前半]
本書について [第2回後半]
第1章 謙虚に問いかける [第3回]
質問することで、どのように人間関係が築かれるのか
謙虚さには三種類ある
問いかけるとはどういうことか
第2章 実例に学ぶ「謙虚に問いかける」の実践 [第4回]
1 妻のメアリーをお茶に誘う
2 勤務先の大学で通話料金を削減する
3 厳しい質問をするCEO
4 タスク・フォースを創設する
5 道案内をする
6 文化の変革を起こす
7 仕事の中身をはっきりさせようとして浮上した問題
8 相手の立場になって考えるがん専門医
まとめ
第3章 ほかの問いかけと「謙虚に問いかける」はどう違うのか [第5回][第6回]
四種類の問いかけ方
・謙虚な問いかけ
・診断的な問いかけ
・対決的な問いかけ
・プロセス指向の問いかけ
まとめ
第4章 自分が動き、自分が話す文化 [第7回][第8回]
最大の問題――人間関係の構築よりも、課題の遂行に価値を置く文化
第二の問題――自分が話す文化
なぜ今これが重要なのか これからの仕事では求められるものが変わる
リーダーにとっての特別な挑戦課題
まとめ
第5章 地位、肩書、役割 人々に行動をためらわせる「境界」の存在 [第9回][第10回]
地位や肩書
組織、職種、国に特有の文化
信頼と社会的経済学
まとめ
第6章 「謙虚に問いかける」を邪魔する力[第11回][第12回]
「ジョハリの窓」 社会心理学の観点から語る四つの側面
知覚と判断における心理的なバイアス(ORJI)
まとめ
第7章 謙虚に問いかける態度を育てる [第13回]
学んだことを捨て、学び直す――二種類の不安
結び
謝辞
著者について — 著者自身の言葉で
原注
解説 [第14回]
用語解説
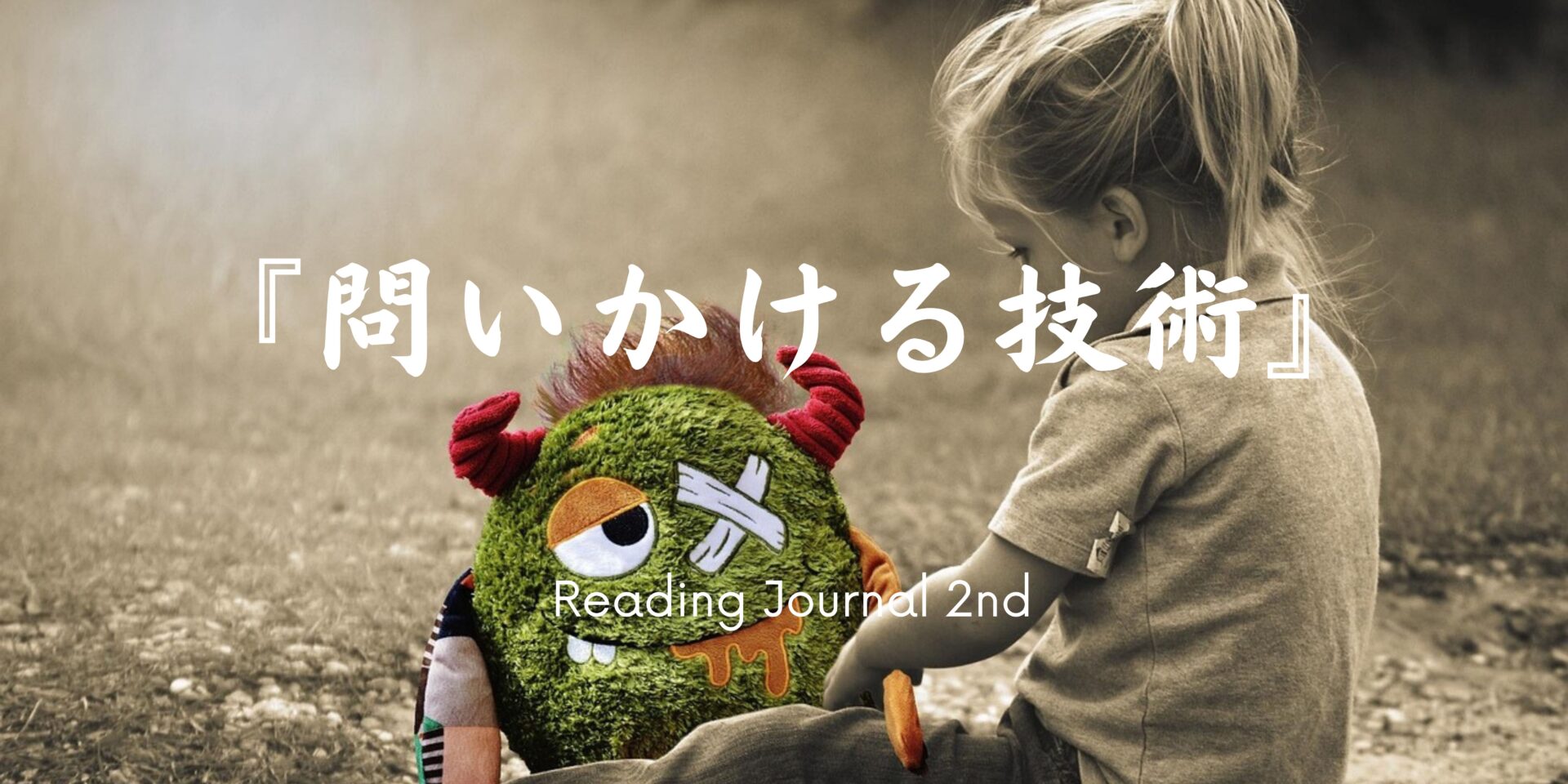
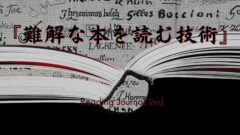

コメント