『成長を支援するということ』 リチャード・ボヤツィス 他 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
5 生存と繁栄(後半)
今日のところは「5 生存と繁栄」の“後半”である。前回の“前半”では、「ポジティブな感情を誘引する因子( PEA)」と「ネガティブな感情を引き起こす因子 NEA)」と脳内の二つのネットワーク、「問題解決ネットワーク(AN)」と「共感ネットワーク(EN)」の関係について説明された。今日のところ”後半“は、PEAとNEAの最良のバランスについてである。それでは読み始めよう
PEAとNEAの最良のバランス
人生がNEAを引き起こす課題の連続だったら、根気や強靭さのような気質は強化されるかもしれないが、長期にわたって変化や学びへの努力を続けることは難しいだろう。・・・・・・だからポジティブな感情を(PEAを、ひいては共感ネットワークや副交感神経を)できるかぎり活用する必要がある。(抜粋)
人は生存が脅かされるような状態になるとNEAが発動する。この状態では成長や繁栄を追求するのは難しい。そしてこの生存がある程度の安定が続いた場合、このままNEAを保って生きるか、PEAを発動するかの選択の余地ができる。
ここで問題なのは、PEAとNEAのバランスである。この割合について、バーバラ・フレドリクソンの初期の研究では、PEAとNEAの割合は3対1が望ましいとしている。さらにジョン・ゴットマンの研究では、5対1である。さらに、著者らによるfMRIを用いた研究では、NEAの働きかけをするセッション1回にたいし、PEAを働かせるセッションを2回行うと副交感神経に働きかける脳の部位が優位に活性化することがわかった。つまり、
私たちが思っている以上に、PEAは必要なのだ。(抜粋)
そのためコーチは、対象者の強みに焦点を合わせてPEAを呼び起こすことが必要である。
再生とストレスのバランス
支援者は持続的な変化をもたらすためのコーチングをするとき、対象者がPEAとNEAのバランスを取れるように手助けしなければならない。これはストレスとそれに拮抗する再生とのバランスを取ることも含まれる。ここで、ストレスの体の反応はNEAの一部であり、体の再生の反応はPEAの一部である。
ストレスは、必要に応じて視野を狭め、意識を集中させる。しかし問題なのは今日の社会ではこのストレスの量が多すぎることである。支援者は、対象者がストレスと再生のバランスを取れるように導くことともに、いずれは対象者がストレスを自分で対処できるようになる準備をすることも必要である。
ストレスへの対処としては、瞑想、適度な運動、ヨガ、慈悲深い神への祈り、将来の希望、大事な人と一緒に過ごすこと、恵まれない人や年配の人のケアをすること、ペットと遊ぶこと、笑うこと、自然のなかで散歩すること、などがあげられる。
このような再生の方法は、1つか2つではなく多様性をもって行うことが必要であり、またその行動もまとめて行うよりも少しずつ頻繁に行うほうが有効である。
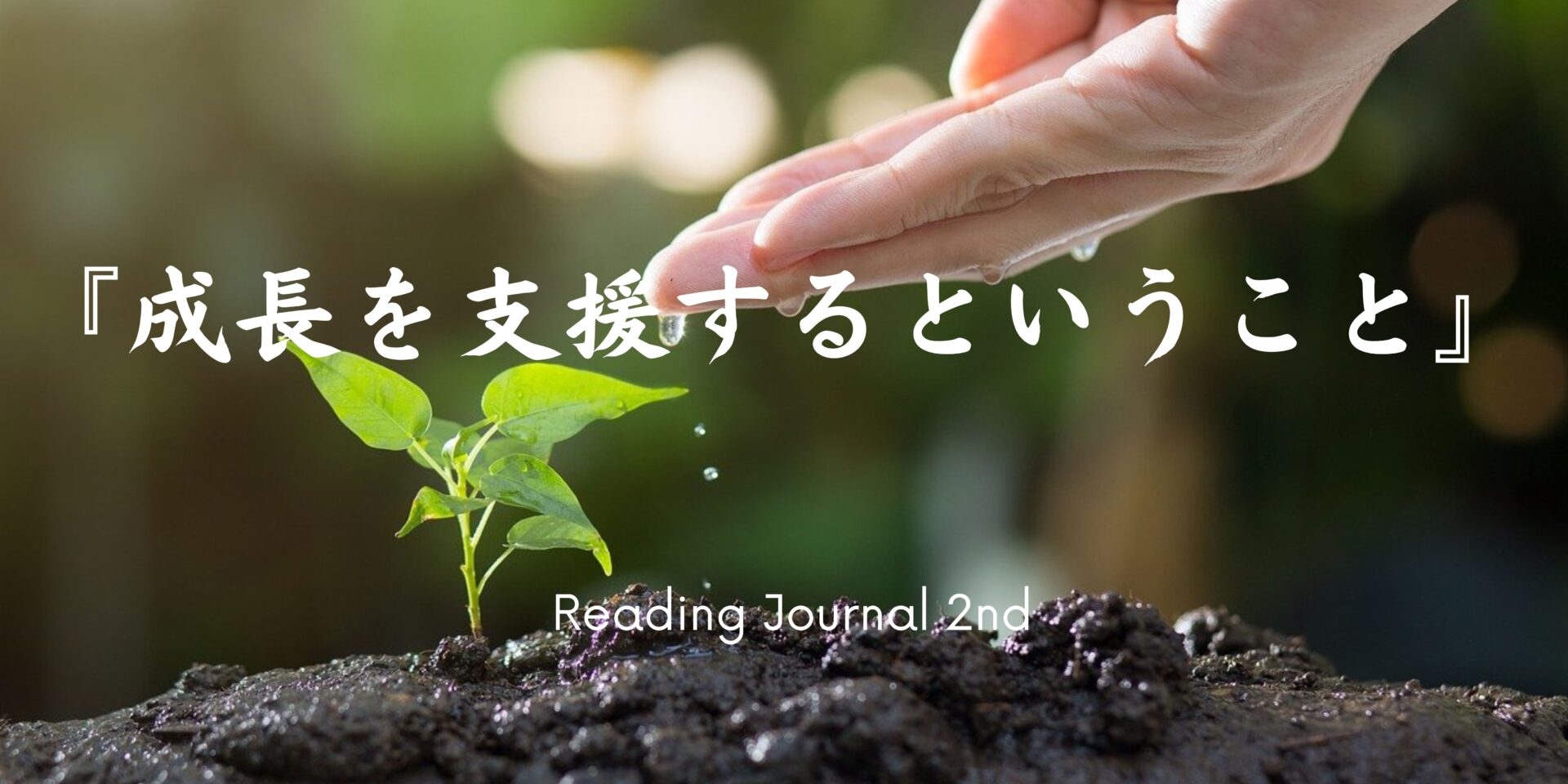


コメント