『成長を支援するということ』 リチャード・ボヤツィス 他 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
3 思いやりのコーチング
人は変化を望んだときに望んだ方法で行動を変える。その変化は自分自身の内側に強い願望がなければ、目に見える変化は長くはつづかない。そのため、コーチが相手に何をすべきかを指導する「従来のコーチング」では、持続的な行動変容につながることは少ない。この章では、誘導型コーチングと思いやりのコーチングの違が説明され、さらに持続する望ましい変化を生み出すための5つのステップが示される。
意識的変革モデルと5つのステップ
持続する望ましい変化につながる「思いやりのコーチング」を説明するために、ボヤツィスは「意識的変革モデル(ICT)」を提案した。この意識的変革モデルには、次の5つの発見が必要であるが、この行動変容は直線的に起こるものではない。
ディスカバリー1 理想の自分
第1のディスカバリーの支援は、「理想の自分」を見極めることへの支援である。ここでは、現在の生活やキャリアステージは考慮に入れるが、それにとどまらず人生のすべての側面において自分の理想の未来を描くことを支援する。
コーチは相手が自己効力感を高められるように、何が可能かについて希望や楽観を持てるように励ます。(抜粋)
ここで大切なことは、コーチングを進めるときに、相手が本当になりたい自分や、本当にやりたいことをきちんととらえているかを確認することである。理想の自分と表明していると思いこんでいても、それは実際にはこうあるべきと思う姿、他の人からの期待された姿であるケースも多い。
人が理想の自分を本当に発見するのを手伝うには、相手が内なる情熱に火がついたと感じるような、感情的経験につながるプロセスを進める必要がある。
ディスカバリー2 現実の自分
次のディスカバリー2は、相手が正確な「現実の自分」を明らかにすることの手助けである。この「現実の自分」は、その人の強み、弱みの評価だけでなく、「なりたい自分」と比較としての現在の姿を意味している。
ここでのコーチの役割として重要なことは、理想の自分と現実の自分との間ですでに一致している領域を特定する手助けをすることである。そして理想とのギャップは、狙いを定めた行動変容の努力によって埋めることが適切である。
また、現実の自分を見極めるには、他人からみた自分を考慮に入れる必要がある。それもコーチの役割のひとつで、定期的に他人からのフィードバックを求めることを勧める必要がある。
ここで重要なことは、その人の弱みに目を向けるのではなく、その人の強みに目を向ける事である。
思いやりのコーチングで手助けするのは、変化への努力がどうしたら実を結ぶかを理解するところだ。それにはまず対象者の強みを認識し、活かすのだ。個人のビジョンに向かって最大の進展が見こめるように配慮するなかで、判明した弱みに目を向けるのは後回しでいい。(抜粋)
ディスカバリー3 学習アジェンダ
次のステップ・ディスカバリー3は、「学習アジェンダ」の作成である。コーチはディスカバリー2で特定された強みを活かし、理想とのギャップを埋めるように促すことである。そして、その時対象者が何をするとき一番高揚するかを考えることが大切である。
コーチがすべきなのは、いままでやってきたことを続ければ、いままでの自分でありつづけるだけだと対象者に気づかせることである。変化を起こすには何か違うことをする必要がある。(抜粋)
この今までと違う何かをするということは、次のディスカバリー4の前半の核心でもある。
ディスカバリー4 新しい行動の実験と実践
ディスカバリー4では、コーチはたとえ意図した結果につながらなくとも、新しい実験を続けるように奨励する。望ましい突破口がひらけるには、うまくいく方法が見つかるまで対象者が実験を続ける必要がある。
そしてそれが見つかったら、コーチは実験を実践に移す手助けをする。これがディスカバリー4の後半部分である。ここでは、実践をつづけることが重要になる。たいていの人は、少し慣れたところで実践をやめてしまう。しかし、実践を繰り返すことにより、本当に持続する行動を変えることができる。そして、その実践が新しい習慣となるまでコーチは実践を奨励すべきである。
ディスカバリー5 共鳴する関係と社会的アイデンティティ・グループ
意図的変革プロセスの最後のディスカバリーは、「共鳴する関係と社会的アイデンティティ・グループ」である。変革をつづけるために対象者に必要なのは、信頼でき支えとなってくれる人々とのネットワークから引き続き助力を得ることである。コーチや支援者は、その必要性を対象者にしっかり認識できるように手伝う。
大きな行動の変化は「共鳴的な関係」があって初めて成功する。コーチと主要な支援者とこうした人間関係を築くことが必要であり、このようなネットワークは、元気をなくしたり、変化のための努力の焦点を見失ったりする場合にも役に立つ。
思いやりのコーチングの機能の仕方
思いやりのコーチングと感情や神経系の反応
思いやりのコーチングは、自分で決めた未来の理想像へ進む手助けをするアプローチである。この方法は、変わらないと人に言われた場合よりも変化の持続が可能な方法である。
もっとも持続するのは、本人や周りの人々がそうすべきと思うから起こした変化ではなく、自発的に望んだ変化である。その変化を起こすとき、感情、ホルモン、神経の一連の作用がある(詳しくは第4章)。
「誘導型コーチング」の場合は、コーチは対象者から防衛的な反応を引き出すことが多い。そのため、感情や交感神経系の活発さを伴い、学習や変化を遮断するいくつものホルモンの作用の引き金となる。そして対象者はNEA1)ゾーンへと押しやられ、サバイバルモードとなる。そのため、コーチの意図に反して、実際にはストレス反応を引き起こし、学びや成長、望ましい変化を阻害してしまう。
「思いやりのコーチング」では、全く別の反応を引き起こす。望ましい将来のビジョンを持ち、強みに焦点を合わせることで、ポジティブな感情が刺激され(PEA)2)、思いやりのコーチングの原理によって興奮や高揚感が引き起こされる。そしてそれは副交感神経を活性化して、よりリラックスしたオープンな状態に変化させる。そのため、新たな学びや持続的な変化が可能となる。(この部分は第4章、第5章で詳しく説明される)
1)NEA=「ネガティブな感情を誘因する因子」
2)PEA=「ポジティブな感情を誘引する因子」
コーチに求められる感情の認識
誰かを支援する役割を果たすためには、人が変化を起こそうと努力する際に感情が果たす役割をきちんと理解しなければならない。そしてそれと同時にその感情に影響を与えられるくらい同調する必要がある。そのためにはコーチ自身が自分の感情をきちんと自覚し、それが対象者に及ぼす影響を認識する必要がある(詳しくは第7章)。
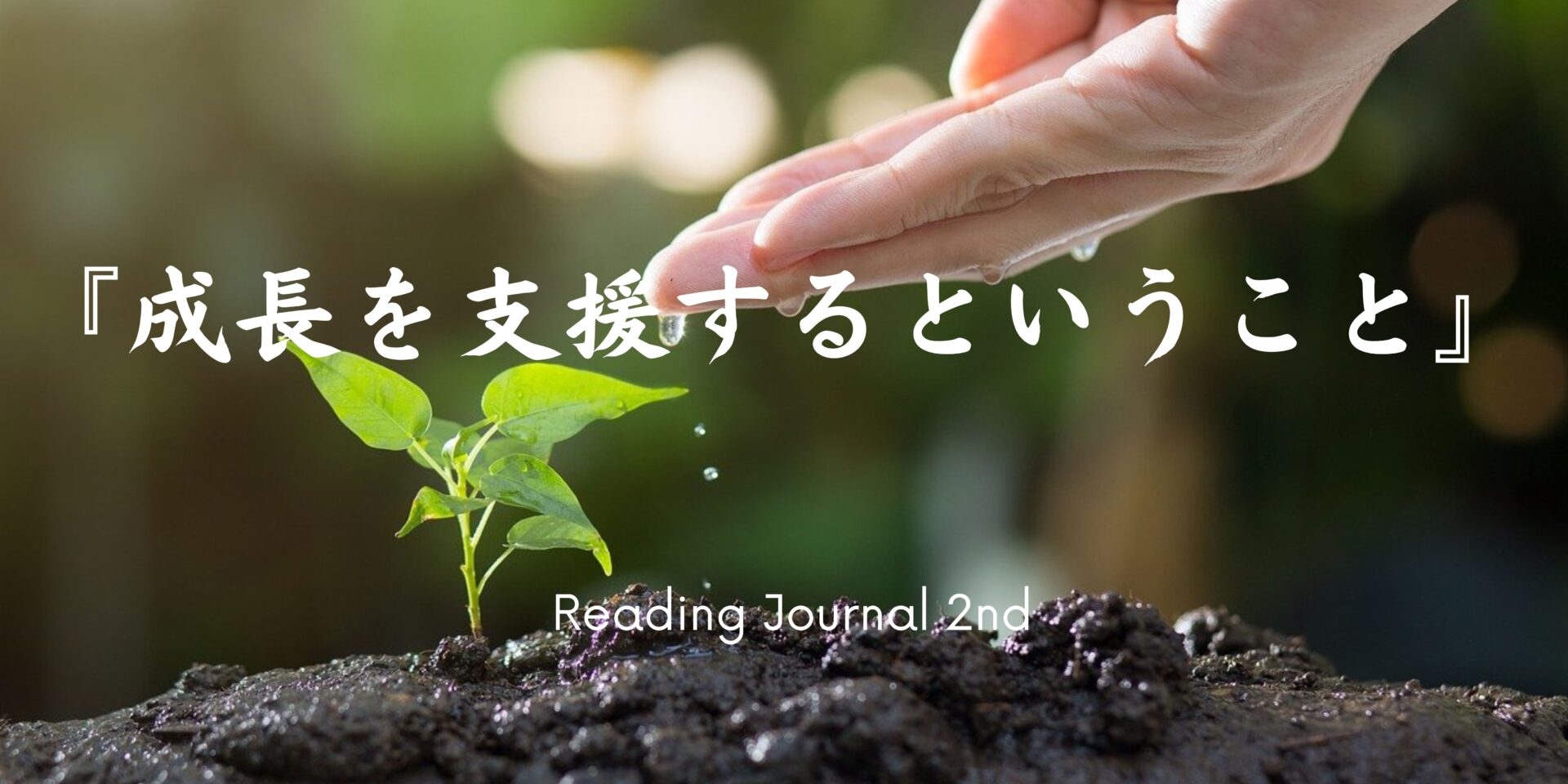

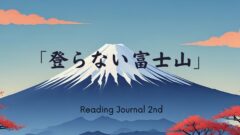
コメント