『成長を支援するということ』 リチャード・ボヤツィス 他 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
2 インスピレーションを与える対話
今日のところは「インスピレーションを与える対話」である。この章では、適時具体的な例を示しながら、「思いやりのコーチング」、すなわち他者が成長、変化をするのをどう促し、どう支援するかを探る。その本質はコーチする人とされる人の間に「共鳴する関係」を築くことにある。そしてそのためには、まずコーチをする側が、自身の感情を、自身のモチベーションを熟知することが必要になる。さあ、読み始めよう。
コーチングの意味について
まずここで、本書でのコーチングの意味についての解説がある。本書でのコーチングは、プロが行うエグゼクティブコーチングと日々の生活や役割(教師・医師・親・友人など)におけるコーチングの両方について当てはまる。
そしてコーチングの定義は「変化や学習、また、個人や組織のパフォーマンスの新たな水準を達成することを目的にした協力関係、支援関係を築くこと」であるとしている。そして、何十年も続くことがあるメンタリング(カウンセリング)と違い、期間は短期間で焦点を絞って行うのが一般的であるとしている。
思いやりのコーチングにおける「共鳴する関係」
思いやりのコーチングの本質は、他者の変化、学び成長を手助けすることである。そのためには、「共鳴する関係」を築く必要がある。この関係において持続できる全体的な変化を生み出すことが出来る。このような人間関係には
- 全体的にポジティブな感情をベースとし
- コーチする人とされる人のあいだに本物のつながりができる
という特徴がある。
また、リチャード・ボヤツィスとアニー・マッキーは『実践EQ 人と組織を活かす鉄則』という本で上の①,②の要素を「再生への道」として論じている。そしてそれは、
- マインドフル(自己認識が高く、自身の感情をコントロールできる状態)である
- 希望を喚起する
- 思いやりを示す
という特徴があり、すなわちマインドフルのコーチは、相手に意識を完全に向け、相手に波長をあわせ、相手の感じていることを察知できる(上の①)。そして常に自分個人の考えや感情を認識しそれを相手に投射しないように注意している。また、優れたコーチは、相手にとって一番重要で意義のある物事を照らすかのような問いかけを投げかける、そして、希望を生み出す手助けをすることが出来る(上の②)。また、そのようなコーチは他者を気遣い、心からの思いやりを示し、相手に必要な助言やサポートを差し出す(上の③)。
内省のためのエクササイズ
ここで、誰かを支援したいと願う人にとって大事なエクササイズとして「内省のためのエクササイズ」の意義が説明されている。
「内省のためのエクササイズ」は、本章の章末に書かれている。
ここにある「内省のためのエクササイズ」は、自分が誰かの言葉や支援で変われた、向上できた時のことを思い出させ、その時の相手との関係が即ち「共鳴する関係」であり、相手から受け取ったインスピレーションが、つまりは目指すものだ!ということを体験させるためにあるのだと思う。・・・・やってないんだけどもね。(つくジー)
関連図書:リチャード・ボヤツィス/アニー・マッキー(著)『実践EQ 人と組織を活かす鉄則』、日本経済新聞社、2006年
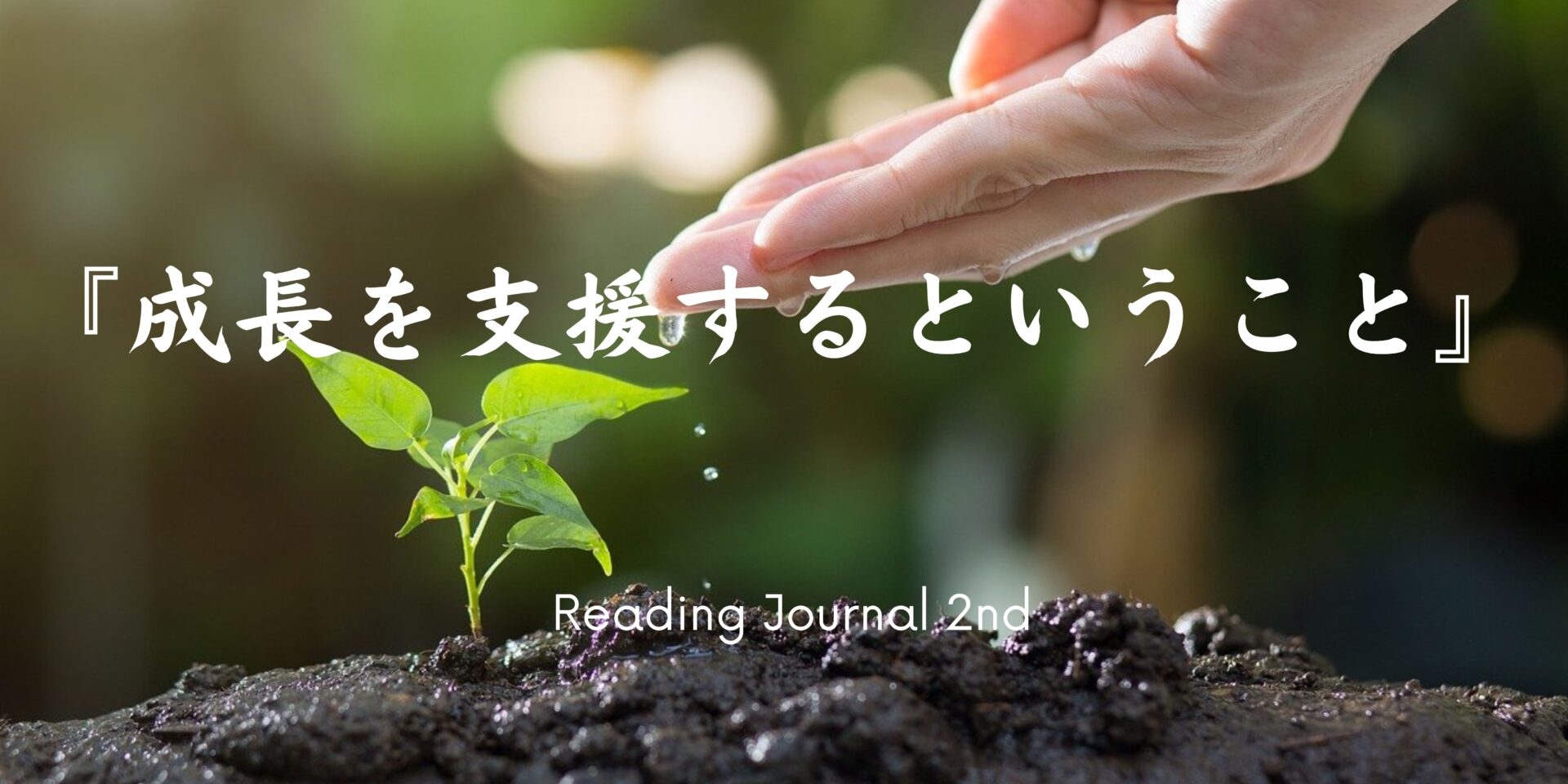


コメント