『成長を支援するということ』リチャード・ボヤツィス、メルヴィン・L・スミス、エレン・ヴァン・オーステン 著、英治出版、2024年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
監訳者序文
アマゾンを見ていたら気になった本を見つけた。つまりこの本『成長を支援するということ』。『モチベーションの心理学』や『無気力の心理学』などを読んだが、「では、がっくりしちゃった人をどう励ますか」という問題は、なかなかむずかしそうだ。なので、この本が気になったわけです。
この本は、いわゆるコーチングの本である。「従来のコーチング」⇒「思いやりのコーチング」へ、という趣旨の本のようである。それでは、読み始めよう
今日のところは「監訳者序文」である。「監訳者序文」ってのは、あまり無いな?と思ったが、監訳者である和田圭介と内山遼子は、この本で紹介される「意図的変革理論(Intentional Change Theory = ICT)」を利用して、企業の組織改革を支援する仕事をしているとのことである。
人が心から願うありたい姿に向かって成長し続けるために、私たちはどう支援すればよいのでしょうか?本書はその効果的な方法を解き明かした理論とそれに基づく実践的なコーチング手法について書かれた本です。(抜粋)
まずはこのように監訳者序文は始まる。そしてこの本の著者リチャード・ボヤツィスは、『EQ こころの知能指数』で知られるダニエル・ゴールドマンとの共同研究でも知られていると紹介されている。(ダニエル・ゴールドマンからの言葉が本書の帯にある。)
次に本書で紹介されるICTコーチングは、従来のコーチングに比べ3つの特徴があるとしている。
第1の特徴は、コーチの対象者との関わり方を「誘導型コーチング」と「思いやりのコーチング」に区別し、「思いやりのコーチング」が人の持続的な成長に寄与することを、脳科学の実験結果から明らかにした点です。(抜粋)
ここで、従来の「誘導型コーチング」と本書の「思いやりのコーチング」に違いを
- 誘導型コーチング:外部から定められたものに向けて相手の行動変容を促すアプローチ
- 思いやりのコーチング:相手を心から気遣って関心をもって接し、サポートや励ましを差し出し、相手が自分のビジョンや情熱の対象を自覚、追究できるようにするコーチング
と定義している。
第2に、これまではコーチ自身のEQの重要性が語られてきましたが、ICTコーチングでは相手のEQを高めることも重視しています。(抜粋)
コーチは、相手の「真にありたい自分」を追求できるように支援し「他者が規定した自分」と区別がつけられるように手を貸す。
第3に、ICTコーチングは誰でも実践できて一定の成果を生むことが出来ます。(抜粋)
コーチングはいざ実践するとなると、個別のケースにどう対処したらよいかわからないという声を聞くが、このICTコーチングでは、具体的なプロセスを明示している。
関連図書:
鹿毛雅治 (著)『モチベーションの心理学 : 「やる気」と「意欲」のメカニズム』、中央公論新社(中公新書) 2022年
波多野誼余夫/稲垣佳世子 (著)『無気力の心理学 改版 : やりがいの条件』、中央公論新社(中公新書)2020年
ダニエル・ゴールドマン(著)『EQ こころの知能指数』、講談社(講談社+α文庫)、1998年
[目次]
監訳者序文 [第1回]
1 支援の本質 [第2回]
他者が学び、成長するのを真に助けるには
2 インスピレーションを与える対話 [第3回]
一番大事なことを発見する
3 思いやりのコーチング [第4回]
持続的な望ましい変化を呼び起こす
4 変化への渇望を呼び起こす [第5回]
喜び、感謝、好奇心に火をつける問いかけ
5 生存と繁栄 [第6回][第7回]
脳内の戦い
6 パーソナルビジョンの力[第8回]
単なるゴールにとどまらない夢
7 共鳴する関係を育む [第9回][第10回]
ただ聞くより、深く耳を傾ける
8 コーチングや助けあいの文化を築く[第11回][第12回]
組織変革への道筋
9 コーチングに適した瞬間を感じとる [第13回]
チャンスをつかめ
10 思いやりの呼びかけ [第14回]
夢への招待状
謝辞
参考文献
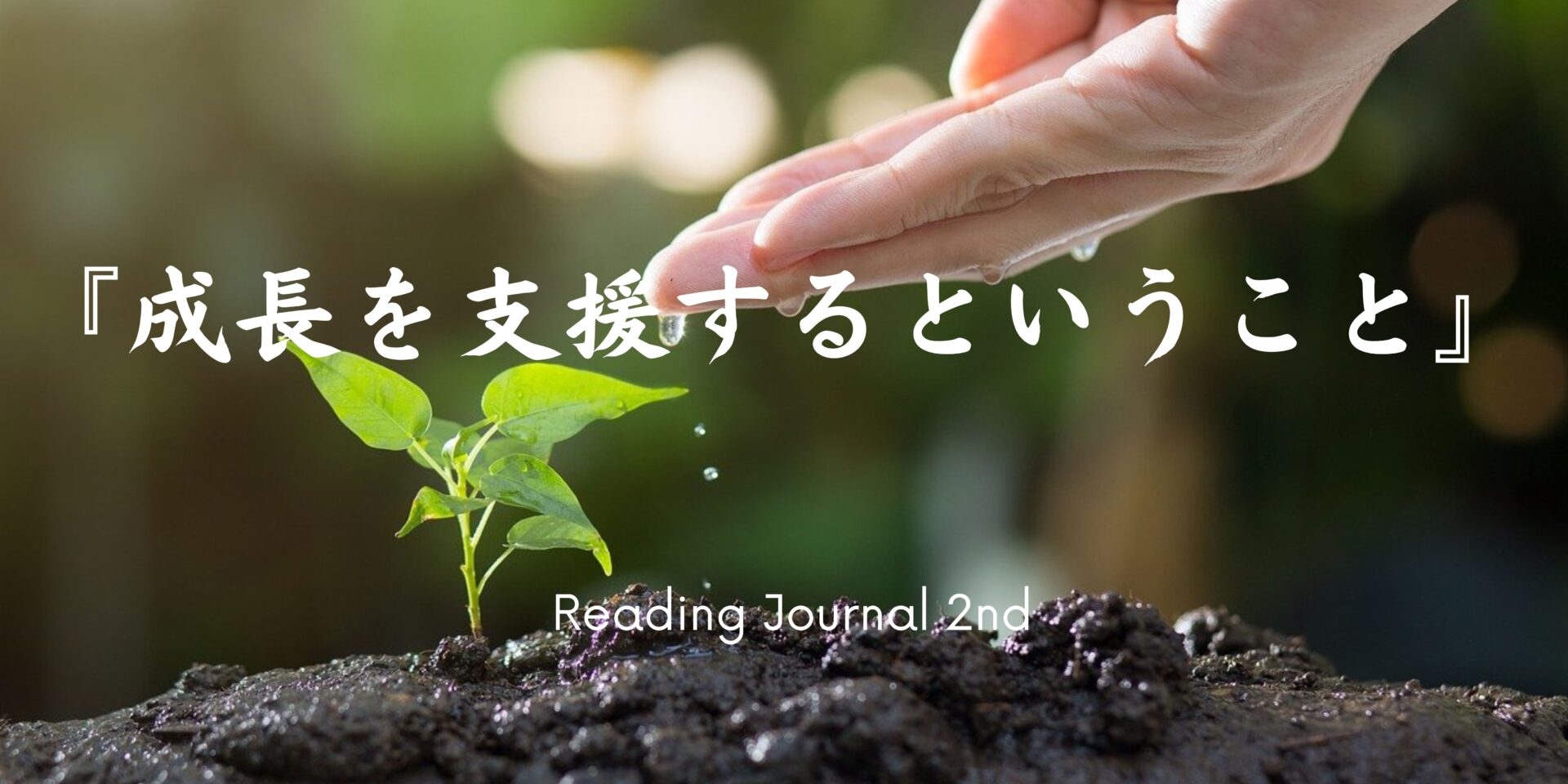


コメント