『論語入門』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第三章 弟子たちとの交わり(その1) — 1 教育者としての孔子
今日から「第三章 弟子たちのとの交わり」に入る。ここでは、孔子とその弟子たちの逸話が集められている。
第三章は、7回に分けてまとめることにする。まずは、教育者としての孔子についてである。それでは読み始めよう。
教育者としての孔子
No.72
子曰く、君子は重からざれば則ち威あらず。学べは則ち固ならず。忠信を主とし、己に如かざる者を友とすること無かれ。過てば則ち改むるに憚ること勿かれ。(学而第一)(抜粋)
先生は言われた。「君子は重々しくなければ威厳がない。学問をすれば、頑固でなくなる。真心と誠実さを主とし、自分より劣る者を友人とするな。過ちをおかしたならば、ためらわずに改めよ」。(抜粋)
これらの文章は、一見、つながりのない断片的な発言に見えるため、別々のときに言った言葉をまとめて収録したという説がある、しかし、著者は多様な角度から、君子に不可欠の条件を述べたと解釈すると腑に落ちると言っている。
そして、末句の「過てば則ち改むるに憚ること勿かれ」は、間違ったと思ったときは、あっさり「前言は之れに戯むるるのみ」と、非を認める人物だったので、より実感がこもっている。
No.73
子曰く、憤せずんば啓せず。悱すれば発せず。一隅を挙げて三隅を以て反らざれば、則ち復たせざる也。(述而第七)(抜粋)
先生は言われた。「知りたい気持ちがもりあがってこなければ、教えない。言いたいことが口まで出かかっているようでなければ、導かない。物事の一つの隅を示すと、残った三つの隅にも反応して答えてこないならば、同じことを繰り返さない」。(抜粋)
孔子の基本的な教育方針を述べたもの。ここで
- 憤:心が疑問でふくれあがること
- 悱:いいたいことが口まで出かかっているのに、うまく表現できないこと
である。
孔子は、画一的な詰め込み教育を否定して、あくまで弟子の自発性を重視していた。彼ら自身の知への欲求がおのずと高まってくるのを待つ偉大な教師だった。
No.74
子曰く、之れを如何、之れを如何と曰わざる者は、吾れは之れを如何ともする末きのみ。(衛霊公第十五)(抜粋)
先生は言われた。「「どうしよう、どうしよう」と悩まない者を、私はどうしてやることもできない」。(抜粋)
前条と同じく、孔子が弟子自身の問題意識や知への欲求を重要視したことを、より明確に述べたものである。
「如何」という語に焦点をあて、「如何、如何」と言わない者に対しては、自分は「如何とする末きのみ」とする表現には、ユーモラスな機智の閃きがあり、孔子の言語感覚の鋭さがうかがわれる。(抜粋)
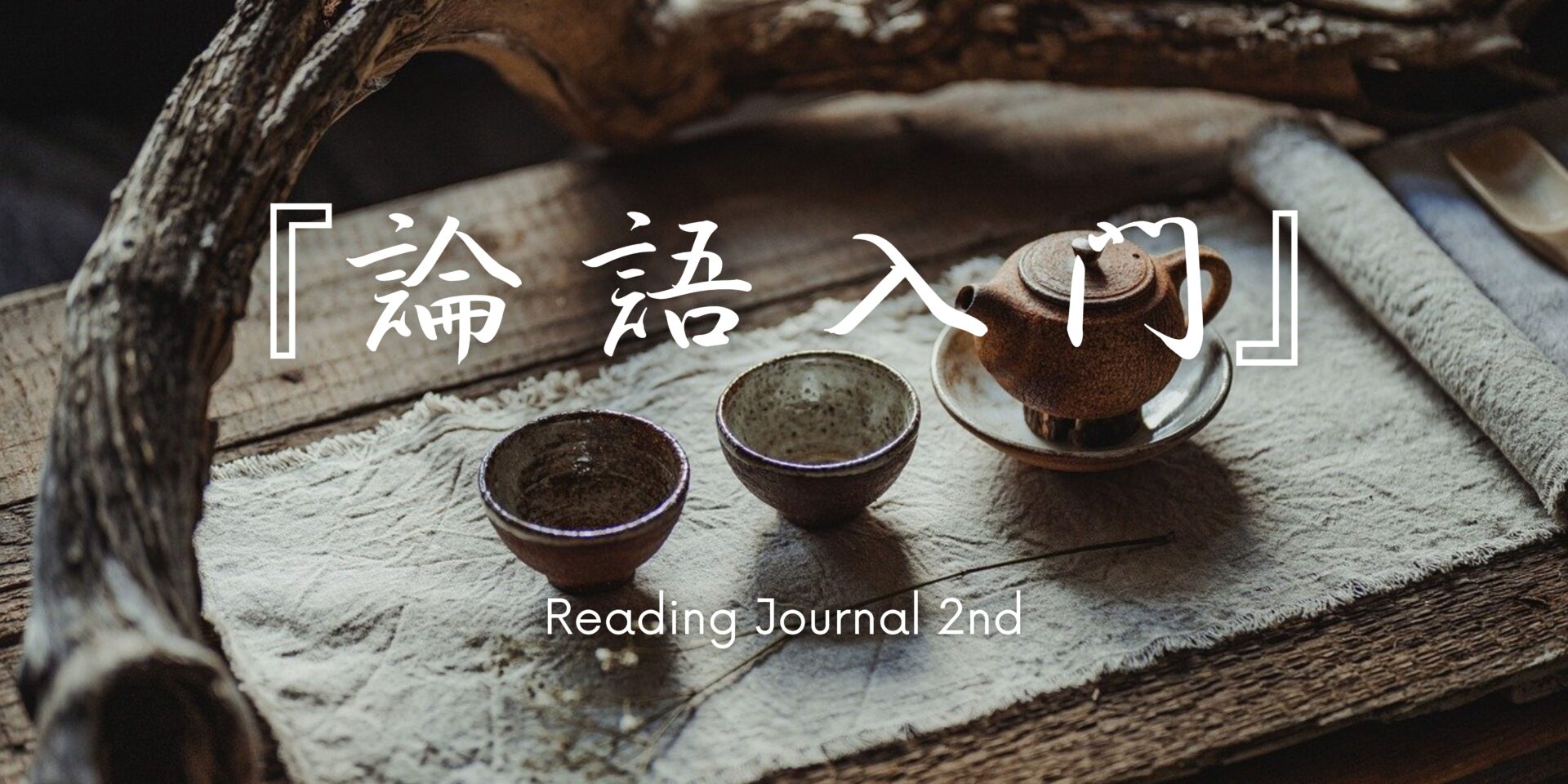


コメント