『論語入門』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第一章 孔子の人となり(その3)
今日のところは「第一章 孔子の人となり」の“その3である。“その1”で、孔子の言葉により、その人生を概観し、“その2”では、孔子の学びについての考え方がわかる話が集められていた。今日のところ“その3”では、プライベートな空間での孔子の様子が描かれている。それでは、読み始めよう。
生活のなかの美学
No.20
子の燕居は、申申如たり。夭夭如たり。(述而第七)(抜粋)
先生が自宅でくつろいでおられるときは、のびのびと、またいきいきとしておられる。(抜粋)
孔子は、自宅ではくつろいでいた、ということである。そして、そのくつろぎ方を表す「申申如」と「夭夭如」は、いきいきとつややかなさまを表す「オノマトペ」である。
孔子は「場」を厳密に区別して、その「場」に応じた話しかたや身ぶりをした。
ここの「オノマトペ」については、『日本語のレトリック』に詳しい(ココを参照)。ちなみに「オノマトペ」ってもとは、フランス語なんだってよ…・知ってた?!(つくジー)。
No.21
孔子 郷党に於いて、恂恂如たり。言う能わざる者に似たり。其の宗廟・朝廷に在るや、便便として言い、唯だ謹しめり。(郷党第十)(抜粋)
孔子は自分が住む地域では、ひかえめで慎み深く、口下手な人のようであった。しかし、宗廟(国家の君主や先祖を祭る霊廟)や朝廷(君臣が集まる会議場)では、ハキハキと発言するが、あくまでも謹厳だった。(抜粋)
孔子は、自分が住む地域では、控えめであまり話さなかったが、公の場では、控えめながらもハキハキと発言したという話である。
これに対して著者は、
公的な場では右顧左眄してろくに意見を述べないのに、私的な場では居丈高になって威張りちらす人々が多いなか、きわだってすぐれたものである。(抜粋)
と評している。
No.22
斉するときは必ず食を変じ、居は必ず座を遷す。食は精げを厭わず。膾は細きを厭わず。食の饐して餲せる、魚の餒れて肉の敗れたる、食らわず。色悪しき 食らわず。臭いの悪しき 食らわず。飪を失える 食らわず。時ならざる 食らわず。割りめ正しからざるば 食らわず。其の醤を得ざれば 食らわず。肉は多しと雖も、食の気に勝たらしめず。惟だ酒は量無し。乱に及ばず。沽う酒 市う脯は食らわず。薑を撤てずして食らう。多く食らわず。(郷党第十)(抜粋)
(孔子は)ものをいみのときは、ふだんとちがう食事をとり、座席もふだんとちがう場所に移した。(平生の食生活では)米は精白されたものほど好み、膾(魚肉の刺身)は細かく刻んだものほど好んだ。ご飯が異臭を発して味が変になったのや、いたんだ魚や腐った肉は食べなかった。色のわるいものは食べず、悪臭のするものは食べなかった。飪(煮かげん)がよくないもの食べず、季節はずれのものは食べなかった。肉はいくら多く食べてもご飯の量は超さなかった。ただ酒にはきまった分量はないが、乱れるまで飲まない。市販の酒とほし肉は買わない(自家製でまかなう)。(魚肉に添えた臭み消しの)ハジカミは捨てずに食べるが、大量には食べない。(抜粋)
この条には、孔子の食生活が描かれている。孔子は繊細な美意識とレベルの高い味覚もち、食材の選び方や盛り付けまで神経を行き届いたものを好んだ。
孔子が単純素朴に清貧をよしとし、食の快楽をことさらに否定する並みの道学者とは、およそ異なる人物であったことが、この一事を以てしても明らかになるであろう。(抜粋)
No.23
食らうに語らず。寝ぬるに言わず。(郷党第十)(抜粋)
(孔子は)食事中は口をきかず、就寝中は口をきかなかった。(抜粋)
孔子は、何事も集中するのが肝要であると考え、食べるときは食べること、寝るときには寝ることに集中した。
No.24
席正しからざれば、坐せず。(郷党第十)(抜粋)
(孔子は)座席は、ちゃんとした方向に向いていないと座らなかった。(抜粋)
これは、孔子が座席をまっすぐに直してから坐ったという逸話である。著者は、これは孔子が潔癖症であったということではなく、礼の一種だったのだろうと言っている。
No.25
君 命じて召せば、駕を俟たずして行く。(郷党第十)(抜粋)
(孔子は)君主からお召があると、馬車の用意ができないうちに、すぐ外へ歩き出した。(抜粋)
これは、呼び出しがかかった時に機敏な行動をとったという逸話である。
ここで著者は、
君主にかぎらず、人と約束した時間を守るのは、いつの時代においても基本的ルールである。遅刻癖のある向きには拳拳服膺すべき言葉であるといえよう。(抜粋)
と評している。
No.26
斉衰の者を見ては、狎れたりと雖も必ず変ず。冕者と瞽者とを見てば、褻れたりと雖も必ず貌を以てす。凶服の者には之れに式す。負版の者に式す。盛饌有れば、必ず色を変じて作つ。迅雷・風烈には必ず変ず。(郷党第十)(抜粋)
(孔子は)斉衰の喪服(五段階に分かれた喪服のうち、二番目に程度の重い喪服。たとえば母の死にあった者が着用する喪服)を着た人に会うと、親しい間柄であっても必ずハッと居ずまいを正した。公式の冕の冠をかぶった人や目のわるい人に会うと、親しい間柄であっても必ず改まったおごそかな態度をとった。凶服(斉衰よりは軽い喪に服する者が着用する喪服)を着た人には、車中で軽く前かがみになって敬礼し、負版の人(戸籍簿を背に担いだ役人)にも同様に敬礼した。豪勢なごちそうをふるまわれると、必ずハッと顔色を変え態度を改めて立ち上がり、感謝を表した。激しい雷や暴風にあうと、必ずハッ居ずまいを正した。(抜粋)
この条では、孔子が、さまざまな場面で、その度合いに応じて、顔つき、身ぶり、しぐさなどで、敬意を示したことを具体的に書かれている。これは礼のルールにのっとった身振り、しぐさ、誠意の表現である。
ここで著者は、最後の「迅雷・風烈には必ず変ず」のみ事前現象に遭遇したさいの態度を述べているが、これは臆病さを表すのではなく、孔子が自然の驚異に対しても常に敏感かつ敬虔であったことを示していると注意している。
関連図書:瀨戸賢一(著)『日本語のレトリック』、岩波書店(岩波ジュニア新書)、2002年
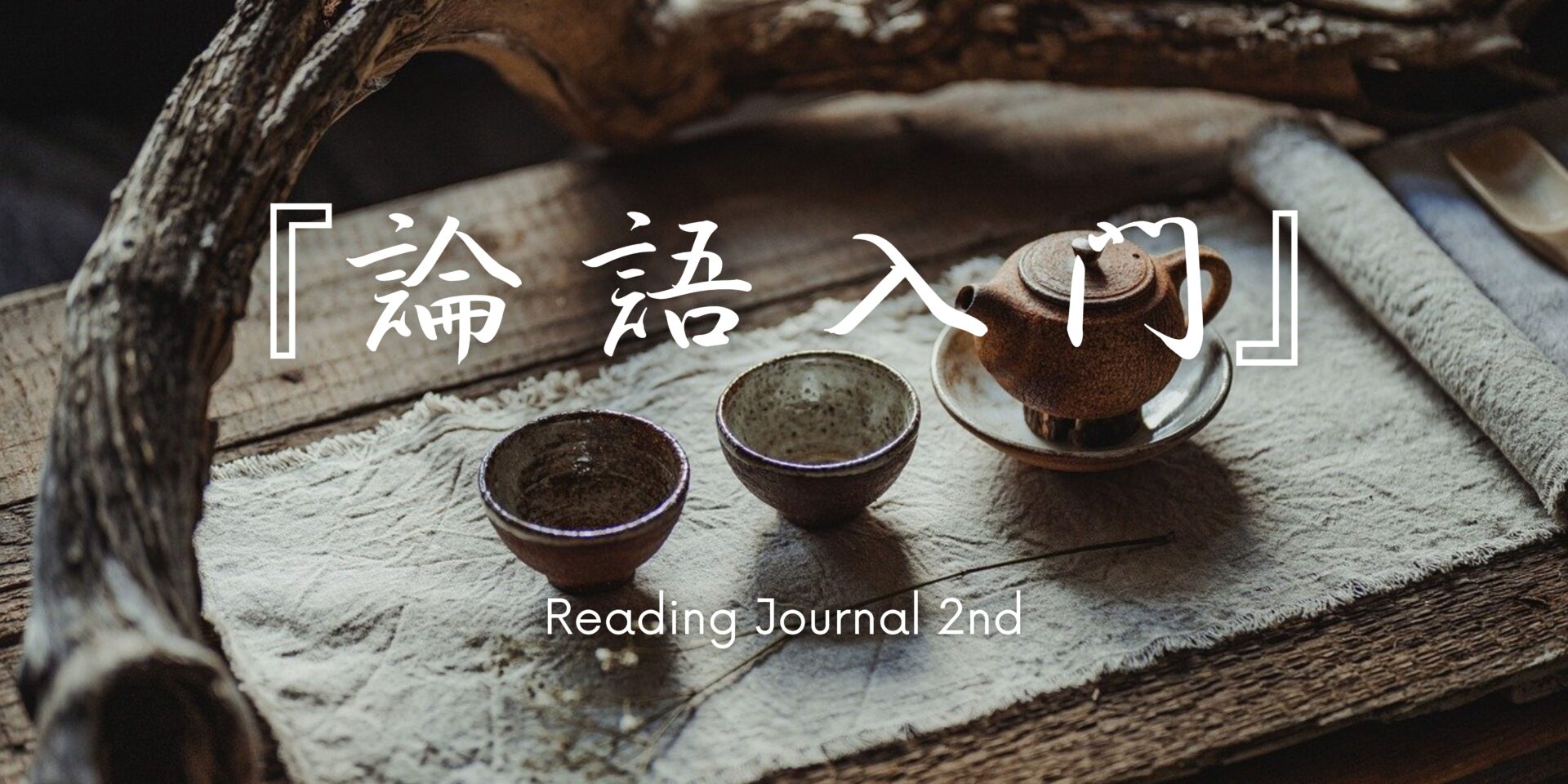
-120x68.jpg)

コメント