『それでも日本人は「戦争」を選んだ』加藤 陽子著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
1章 日清戦争 民権論者は世界をどう見ていたのか [前半]
シュタインからの教示(前節)を受けてヨーロッパから帰国した山県は、総理大臣となり民党(政府反対派)が過半数を占める国会で軍部拡張予算に賛成してもらわないといけない立場となる。
まずこの節では、民党を結成していた民権論者がどのような意見を持っていたかを概観する。
日本では、民権派の人といえども、国会開設と条約改正のどちらが先と言われると条約改正が先と言う人が多かった。このころ、岡義武(吉野作造の弟子)は、日本とイギリスの外交史を研究するなかで、
日本の民権派の考え方は、どうも個人主義や自由主義などについての理解が薄いように思われる。(抜粋)
と言うことに気づいた。つまり個人主義・自由主義的な思想が弱く民権派は国権を優先してしまい、国家のなすことを是認する心配があることを認識する。
つまり、著者は、このころは民権派の人々にとっても不平等条約の改正は、重要な関心事でその点では、あまり政府と意見に違いが無かったと言っている。
民権派といっても、また反政府といっても、どうも事が外交や軍事に関する問題となると、福沢や山県の考えていることと、あまり変わらなそうだなぁと言いうイメージが描けるのです。日本の場合、不平等条約のものとで明治国家をスタートさせましたから、自由だ民主だとの理想をいう前に、まずは国権の確立だ、という合理主義が全面にでてしまう、(抜粋)
また、国会の開設が第一と考える民権派の人も、国会を兵力(パワー)や対外的な力をまとめあげる場所ととらえていて、つまるところ国会の役割や対外的な方向性などは、福沢や山県とあまり変わるところが無かった。

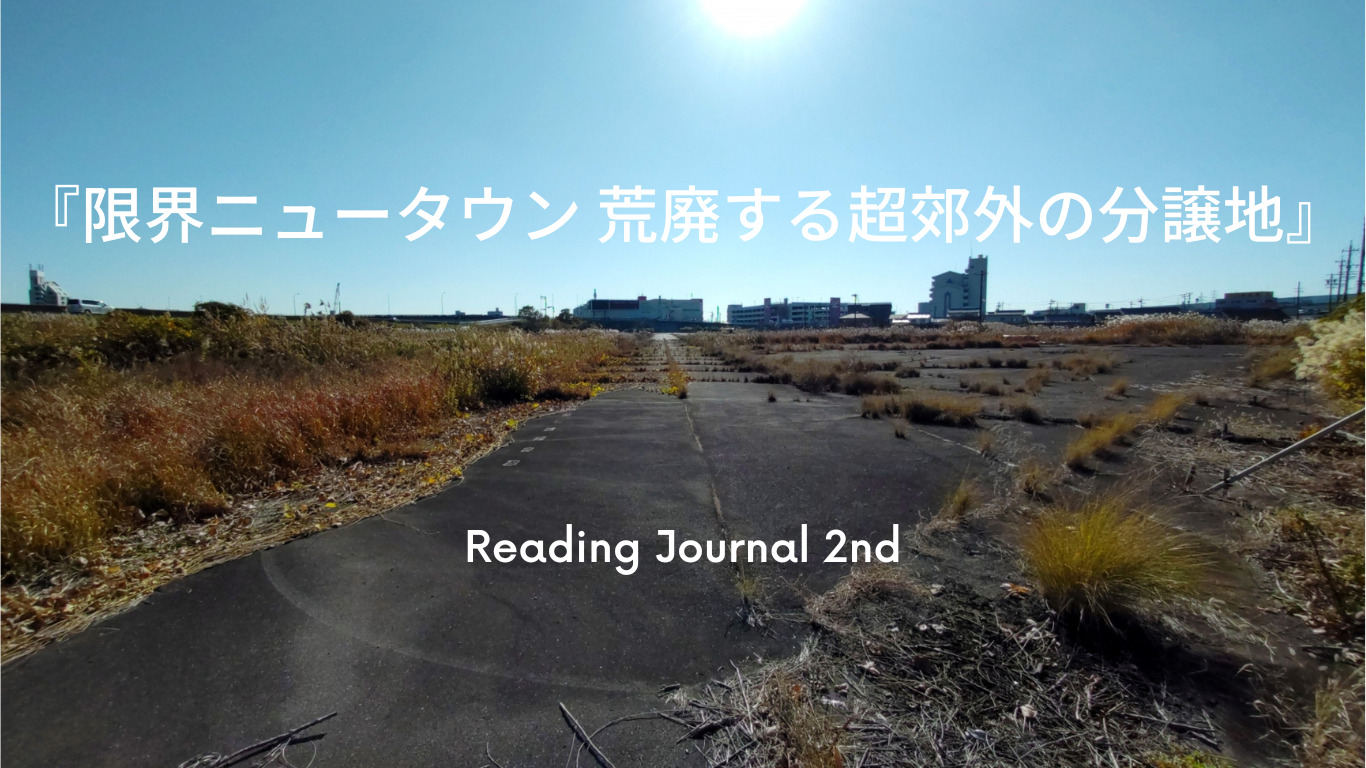
コメント