『日本語のレトリック』 瀨戸賢一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
擬人法 人に見たてる(意味のレトリック1 意味を転換する)
「擬人法」は、人ではないものを人に見たてて表現するレトリックである。「見たてる」という点から隠喩の一種である。
隠喩の中で人に見たてるものを、とくに擬人法というのです。(抜粋)
擬人法は、隠喩であるがこのような例が多いため特別扱いされる。
ここで著者は、建築家安藤忠雄のエッセー「冷房」(「朝日新聞」一九九一(平成三年)七月三〇日夕刊)には、風の表情が描かれているとし、その文章を引用している。
このエッセーのなかで、
戸の間から忍び込む隙間風は・・・・・私を苛立たせた。
うららかな風は、時に花の甘い香りを運んでくる・・・・
うららかな風は・・・・私を和やかな気持ちにさせた。(抜粋)
を注目すると、「風は私を苛立たせた」「風は香りを運んでくる」「風は私を和やかな気持ちにさせた」と英文法のSVO(日本語なのでSOV)の構造を持つ構文となっている。
風が、行為者として、意思のある主体として描かれているのがわかるでしょう。これも擬人法の重要な一面です。(抜粋)
関連図書:安藤忠雄(著)「冷房」、「朝日新聞」、1991年7月30日夕刊
共感覚法 五感を結ぶ(意味のレトリック1 意味を転換する)
「共感覚法」は、「深い味」のようにある感覚に対する表現が他の感覚の表現を借りて表わされるレトリックである。(ここでは、味覚表現が視覚表現を借りている)
著者は、勝見洋一の味エッセー『恐ろしい味』から例文を引用して、「共感覚法」を解説している。
「すみれ色」の夕暮れの空を見て、口の中が「甘くなった」。子供のころにほおばった飴玉の色に似ていたからです。思い出のなかで一体となっていた視覚と味覚が、ふと追体験されたのでしょう。ここでは視覚が味覚を刺激しました。・・・(中略)・・・・共感覚法は、五感のつながりによって生まれます。(抜粋)
味覚は、五味(甘味・苦味・酸味・塩味。旨[うま]味)に加えて、「おいしい」、「まずい」を合わせてもそれほど多くの表現がない。そこで、その不足を他の感覚で補う必要がある。
共感覚法は、味覚以外でも展開する。例えば、聴覚では「大きな音」「明るい声」「暗い声」「高音」「低音」「甘い声」「黄色い声」などがある。
関連図書:勝見洋一(著)『恐ろしい味』、文藝春秋、1995年
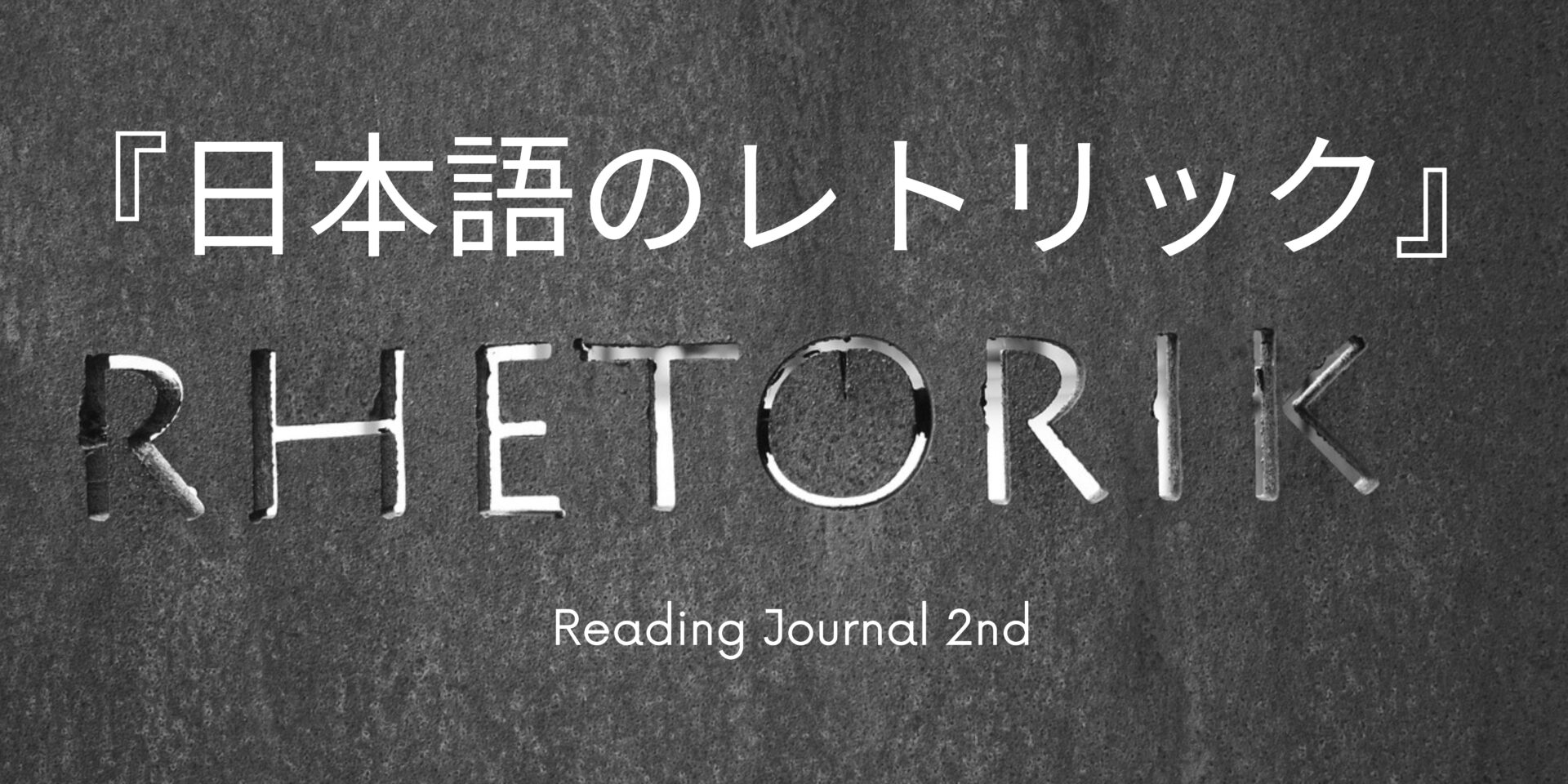


コメント