『日本語のレトリック』 瀨戸賢一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
レトリックを文章に生かす
いよいよ最終章「レトリックを生かす」である。これまで、著者は三○の道しるべとして、レトリックを一つずつ解説してきた。そのうえで、そのレトリックをどのように生かすかが本章の主題である。この章では、本書の冒頭の「はじめに」を素材にして、その表現一つひとつについて、著者がどのように考えどのようなレトリックを使ているかについて説明している。それでは、読み始めよう。
まずは「はじめに」の冒頭であるが、こうであった。
宿題がどっさりあるとき、ふうとため息をついて、「山のような宿題」とか、「宿題の山」とかいうことがあるでしょう。このとき、あなたはすでにレトリックの世界に入り込んでいるんです。山は文字通りの山ではありません。比喩的な山なのです。(抜粋)
この文章を書くとき、著者は、はじめからむずかしい話では、この本を手に取った人が、たちまち放り投げてしまうと思い、ひと工夫してわかりやすい具体例から入ったとしている。そしてその具体例に「宿題の山」を選んだ。この表現がすでにレトリックであるからである。
そして、レトリックという話題がそれほどポピュラーでないため、出来るだけ読者の目線に合わせた文体を使うように語りかける気持ちで書き進めた。
「宿題がどっさりあるとき、ふうとため息をついて・・・」の書き出しも工夫している。ここでは、「どっさり」(擬態語)、「ふう」(擬音語)という声喩(オノマトペ)を使って臨場感を出している。
この語りかける調子は、「このとき、あなたはすでにレトリックの世界に入り込んでいるのです」に引き継がれます。修辞疑問法を思い出してください。大切なポイントは、文章はいいっぱなしの一方通行であってはならない、ということでした。読者との対話(ダイアローグ)がときには必要です。「あなた」は、読者をテクストの中に呼び込む働きをします。(抜粋)
以下も同じように、「はじめに」の文章を引用して、そこにどんなレトリックを使っているかを細かく解説している。
なるほどなるほど、この本の「はじめに」を読んだとき、「妙に凝っているなぁ~」と思ったんですが、最後にそういう”落ち”があったんですね!まさか、レトリックの見本を仕組んであったとか、しらなんだ!(つくジー)
あとがき
現在、レトリックに対する関心が高まっている。そしてその中心は「隠喩」・メタファーである(著者も、『メタファー思考』現代新書)を書いている)。そのようなこともあり、著者はレトリックの用語を整理したいという気持ちがあったと言っている。
そしてもう一つの理由として、隠喩はともかくとして直喩、換喩、提喩になると専門家でも言うことがバラバラであり、それを出来るだけわかりやすく整理するのが自分の仕事の一部だと感じたことである。
さらに個人的な理由として、英語学者である著者は、よく言われる「日本語の独自性」は、実は英語にもあり、本質的な意味で「日本語も英語もそんなにかわらない」と思っていて、レトリックの分野にたずさわると、そのような共通性に気づいたからであると言っている。
読者のみなさんと、このような思いを共有できないか。これが、ほんとうは一番強い動機だったかもしれません。(抜粋)
関連図書:瀬戸 賢一(著)『メタファー思考』、講談社(講談社現代新書)、1995年
[完了] 全18回
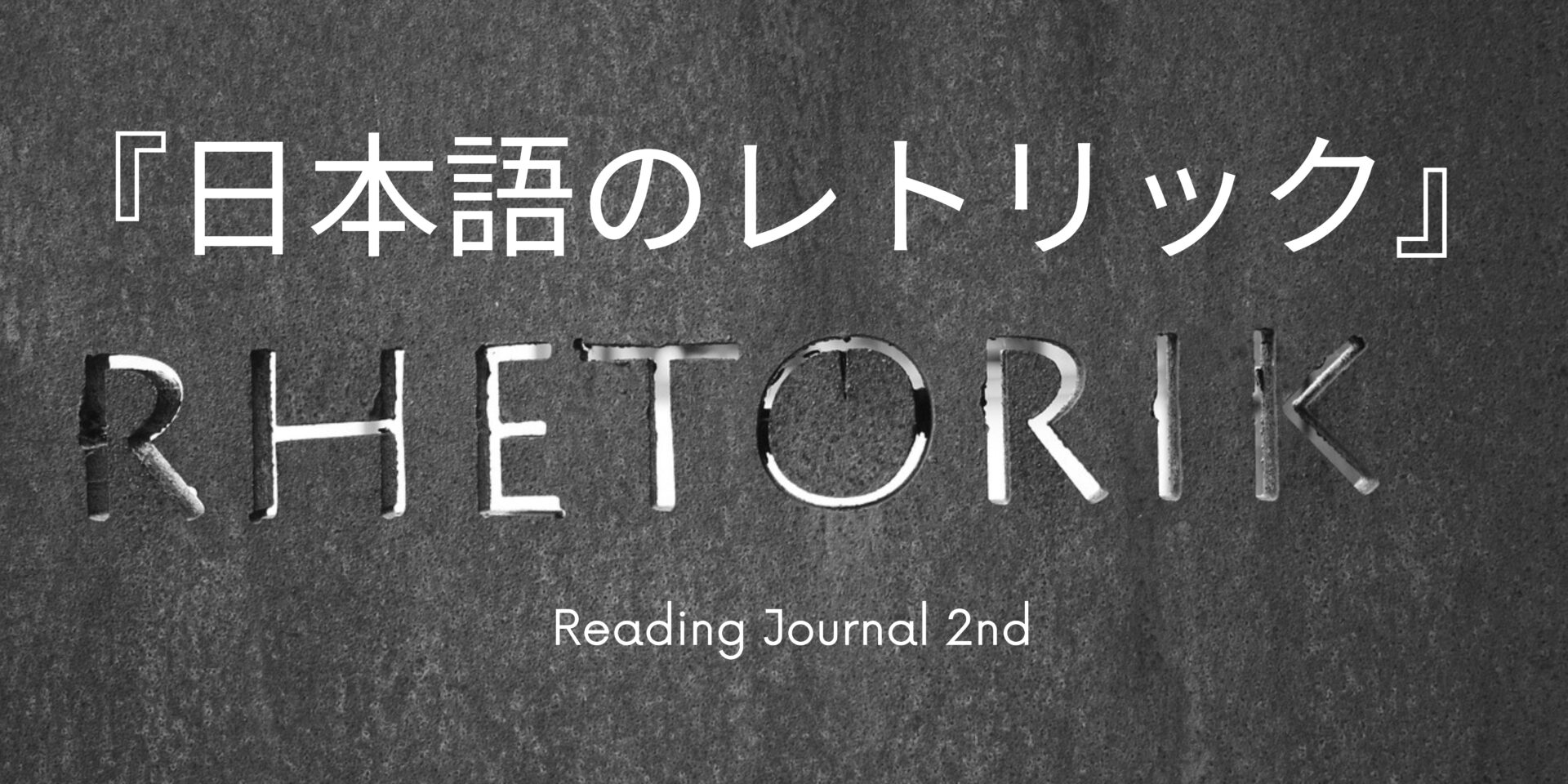


コメント