『日本語のレトリック』 瀨戸賢一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
反語法 引用して皮肉る(構成のレトリック2 引用で語る)
「反語法」とは、皮肉で意味を伝える方法である。そしてその有効手段として、相手のことばをそのまま引用して、オウム返しに言うという方法がある。
たとえば、夏休みの終わりに焦って宿題をしている子どもが、「あー、もう時間がない」と言ったときに、親が「そりゃ、時間がないでしょうねぇ」という場合は、「反語法」で、子どもに皮肉が伝わる。さらに、著者は、北村薫の『スキップ』からの引用により「反語法」を説明している。
この表現は、相手のことばを引用して、その妥当性をもういちど相手に判断させるという皮肉のテクニックである。
そして、相手のことばは、必ずしも直前のことばでなくても良い。ここで著者は、夏目漱石の『こころ』からの引用で、そのような例を提示している。
「反語法」のもう一つの用法に、引用によらない方法がある。それは、相手を持ち上げて落とすというやり方である。つまり相手を「天才だ」と言ってけなす用法である。
上手くまとめられなかったが、夏目漱石の『こころ』からの引用があった。「撞着法」のところで、夏目漱石はレトリックでもすごいと、著者が言っていたが、ここの部分も、なるほどすごいなぁ~と思ったつくジーでした。あ…まとめられなかったんですけどね。(つくジー)
関連図書:
北村薫(著)『スキップ』、新潮社(新潮文庫)、1995年
夏目漱石(著)『こころ』、新潮社(新潮文庫)、1952年
引喩 引用に重ねる(構成のレトリック2 引用で語る)
「引喩」とは、引用による比喩のことである。この引喩には、古くは本歌取りという形があった。ここで著者は、柿本人麻呂の本歌と藤原定家の新歌を引用している。
まず、柿本人麻呂の本歌は、
足引きの山鳥の尾のしだり尾の長々し夜をひとりかも寝む(抜粋)
それを本歌取りした藤原定家の新歌は、
ひとり寝る山鳥の尾のしだり尾に霜おきまよふ床の月影(抜粋)
となる。
ここで山鳥のつがいは、夜べつべつに寝るといわれ、ひとり寝の象徴である。本歌取りは、本歌を下敷きにして新しい意味を造型する技法である。
ここで著者は、井上ひさしの『ブンとフン』、そして筒井康隆の『文学部唯野教授』から引喩の例を引用している。この例のように、引喩が諧謔と笑い傾くとパロディーに急接近する。
引喩の本質は、よく知られた原典(詩歌や文章やことわざなど)に託していまの気持ちを述べることにあります。(抜粋)
関連図書:
井上ひさし(著)『ブンとフン』、新潮社(新潮文庫)、1974年
筒井康孝(著)『文学部唯野教授』、岩波書店(岩波現代文庫)、2000年
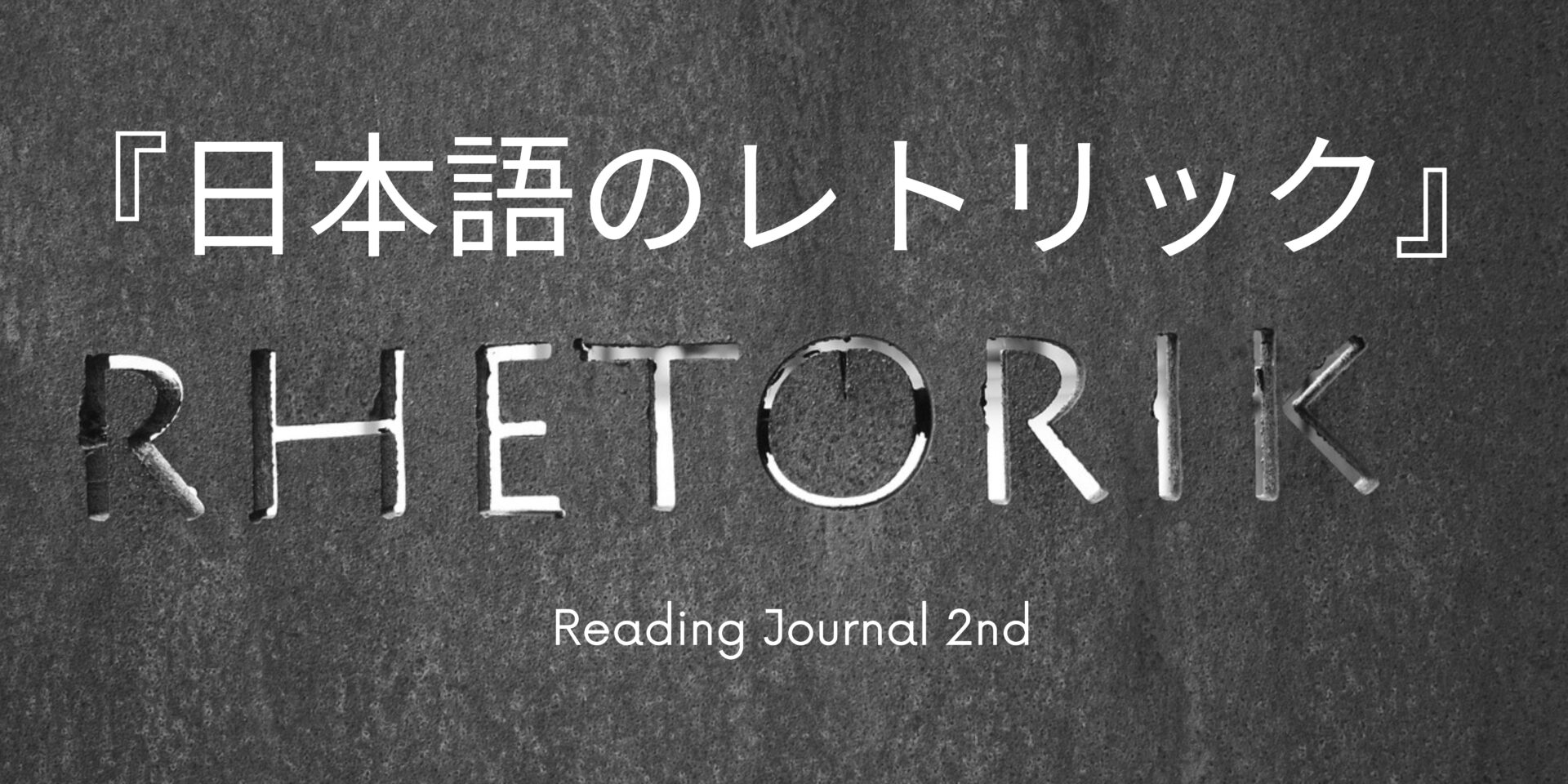


コメント