『日本語のレトリック』 瀨戸賢一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
倒置法 語順をひっくり返す(形のレトリック2 形を工夫する)
日本語は、わりと語順が自由なので、ひとつの文でもいくつかの倒置のバリエーションができる。ここで著者は、池波正太郎の『むかしの味』にでてくる文を使って実際にいくつかの倒置のバリエーションを作り、その違いについて説明している。
- どうして、イノダのコーヒーは、あんなに上手いんでしょうね?
- イノダのコーヒーは、どうして、あんなに上手いんでしょうね?
- どうして、あんなに上手いんでしょうね、イノダのコーヒーは?
- どうして、こんなにうまいんでしょうね、イノダのコーヒーは?
ここで、①が、元の文である。それに比べると②は、①との差が微妙である。③になると、語順がひっくり返ったという感じがする。
そして、③と④を比べると、③で「あんなに」出るところが④では、「こんなに」になっている。二つの文の倒置法の効果としては、③の「イノダのコーヒーは?」は単なる確認程度の意味であるが、④となると、文の重心が「イノダのコーヒーは?」の方に移動し、強調部分が「イノダのコーヒー」となっている。
つまり、④では、「イノダのコーヒー」という強調部分をあとまで取っておいたという、サスペンス(宙づり)効果が効いている。
つぎに、ひとつの文が主説と従属節からなる文の倒置法について書かれている。ふつう日本語では、従属節・主節の語順が普通である。この従属節は、「理由、比較、目的、条件」などの説がある。具体的には、理由の節ならば「Aだから、B」の語順になる。
そして、この節を倒置した時の効果を、中島敦の小説『山月記』からの引用で説明している。
ここでは、比較の節と目的の節を倒置することにより普通の語順を破っているが、ある意味で感情の流れに忠実な表現法となっている。
隠喩や直喩などは意味で変化をもたらしますが、倒置法は形で変化をもたらします。(抜粋)
そして最後に、現代の例として大平健の『精神科医のモノ・グラフ』からの文を引用している。
・・・・・・・(区切り線)・・・・・・
なるほど!「ポン」と手を打ったよ!って、言いたいが・・・・・確かに、そう言われればそんな感じがするねぇ、くらいでして。・・・ようするに、「に・ぶ・い? つくジー😢」。
・・・・・・・(区切り線)・・・・・・
関連図書:
池波正太郎(著)『むかしの味』、新潮社(新潮文庫)、1988年
中村敦(著)『李陵・山月記』、新潮社(新潮文庫)2013年
大平健(著)『精神科医のモノ・グラフ』、岩波書店、1994年
対句法 形を決める(形のレトリック2 形を工夫する)
「対句法」は、形を決めて対立的な意味を浮き彫りにする表現法である。ここで著者は、斎藤美奈子の『文壇アイドル論』からの引用で対句法を説明している。
ここでは、「Aと思えばBになり、Cと思えばDとなる」「AすればBし、CすればDする」という対句法が使われている。この対句法では、AB対CDの対立の構図が浮かび上がり、AはCとBはDと意味的に対立することにより、対比が引き立つ。
つまり「対句法」は、対比を際立たせるときに便利である。そして、この前半と後半を同じ形に統一の形を崩さないことが対句法のポイントである。
この対句法は論を成すときに便利である。ここで、著者は宮崎市定の『古代大和朝廷』から一節を引用している。
およそ学問研究の上において、専家には専家の長所があると同時に、それに伴う弱点が生ずることを免れない。非専家には常に非専家の弱点が伴うこと勿論であるが、しかし時には非専家でなければ得られぬ長所があって、かえって専家の欠を補うこともありうる。(抜粋)
この文章では専家と非専家の長所と短所が鮮やかに対比されている。さらに、日常的な場面での対句法の例として、向田邦子の『女の人差し指』から例を示している。
ここで対義語についてのコメントがある。この対義語は、一筋縄でいかず「白」の対義語は「黒」、「黒」の対義語が「赤」、「赤」の対義語が「白」のようなことがおこる。さらに火の用心のセリフ「魚焼いても家焼くな」では、「魚」と「家」が対義語となっている。
もっとも、「魚焼いても家焼くな」では、前半と後半に対等の力配分がなられているわけではありません。力点は明らかに後半にあります。(抜粋)
また、対句はその調子のよさにより慣用句に定着することがあるとして、「芸術は長く、人生は短い」「百聞は一見にしかず」「一寸の虫にも五分の魂」などを紹介している。
そして最後に、対句法の形式をゆるめた「AではなくてB」という対比の例として、村上春樹の『風の歌を聴け』から引用している。
関連図書:
斎藤美奈子(著)『文壇アイドル論』、岩波書店、2002年
宮崎市定(著)『古代大和朝廷』、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、1995年
向田邦子(著)『女の人差し指』、文藝春秋(文春文庫)、2011年
村上春樹(著)『風の歌を聴け』、講談社(講談社文庫)、2004年
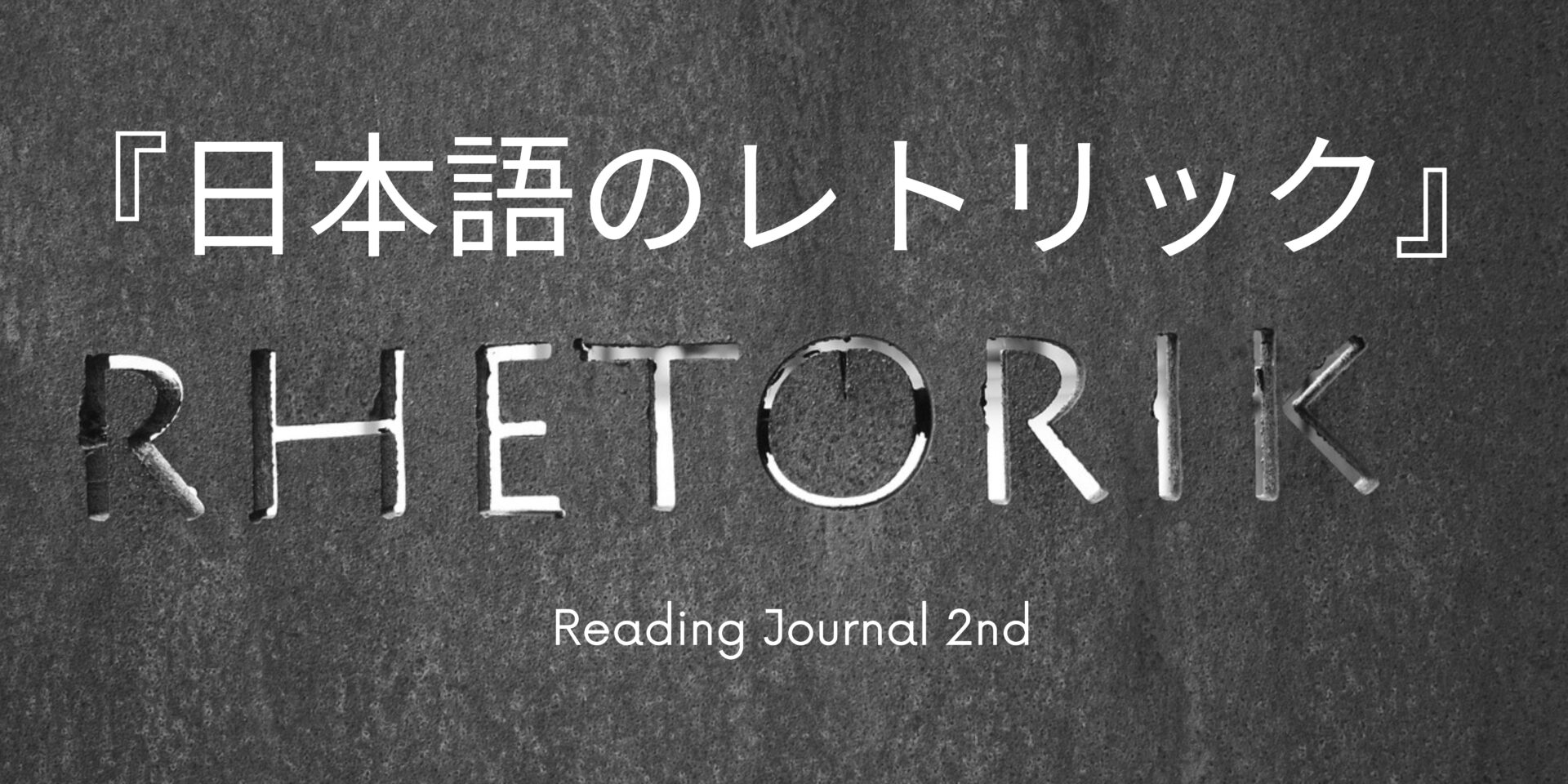


コメント