『日本語のレトリック』 瀨戸賢一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
省略法 省いて伝える(形のレトリック1 形を加減する)
省略がレトリックの技法になるかは、省いて当たりまえということでなく、省くことである効果が生じることが必要である。
著者は、まず、この省略法を松尾芭蕉の『奥の細道』から引用を用いて説明している。
不二の峰幽にみえて、上野・谷中の花の梢、又いつかはと心ぼそし。(抜粋)
ここでは、「又いつかは」の後が省略されている。富士の峰や上野・谷中の花などに、「無事に戻れば再び見ることが出来る」ということを省略し客死してしまうかもしれないという「心細さ」を導いている。
省略法とは、より正確には、すでに決まった語句を省くのではなく、これから言おうとする思いを伏せて、なおかつ、その意味にふくらみと余情をもって伝える方法です。(抜粋)
ここで著者は、省略法を高田康成の『キケロ』、筒井康隆の『ロートレック荘事件』からの引用で、説明している。
どちらも、省略部を補えるが、あとにぴったり続かなかったり、補うことばが人により違ってもよかったりなど、省略することによってむしろその部分の表現のふくらみが増している。
そして省略法の中には、接続詞省略法という名前をつけてもよい表現方法がある。ここで、著者は太宰治の『喝采』から長文の一節を引用して、説明している。その文は、接続詞が一切なく、短く句読点で句切る文体で、若者の性急な息づかいを表わしている。
この接続詞省略法の部分は、うまくまとめられなかったが・・・・ようするに、接続詞なし、短文で句切れていて・・・とんとんとんとん・・・と調子よく続いている文章になっているってことである。
っで、そういう文章をちょうど今、 ポール・オースターの『冬の日誌/内面からの報告書』の中で読んでいる。わりと複雑なことをポンポンポンと短文で句切って続けていて、下手な書き手(訳者??)だと、何を言っているのか分からなくなってしまうんだけども、なんと、ぐんぐん、と読めてしまう。ような文章である。(ちょっと真似してみた)(つくジー)
関連図書:
松尾芭蕉(著)『芭蕉 おくのほそ道 付 曾良日記 奥細道菅菰抄』、岩波書店(岩波文庫)、1957年
高田康成(著)『キケロ』、岩波書店(岩波新書)、1999年
筒井康隆(著)『ロートレック荘事件』、新潮社(新潮文庫)、1995年
太宰治(著)「喝采」『太宰治全集 2』、筑摩書房、1998年
ポール・オースター(著)『冬の日誌/内面からの報告書』、新潮社(新潮文庫)、2024年
黙説法 黙って伝える(形のレトリック1 形を加減する)
「黙説法」は、なにかことばが期待されるときに黙ることによって、ある意味が伝わるという表現方法である。沈黙によって語ることは決して珍しいことではない。著者は、ここで谷崎潤一郎の『細雪』から、一節を引用している。
雪子の手前、自分がお春を糺さねばならない責任を感じた。
「なあお春どん、・・・・・・・・」
「・・・・・・・・」
お春は下を向いたきり、「悪うございました」と云うことを恐縮しきった体つきで示した。(抜粋)
この部分は、雪子の見合いばなしを、うっかりしゃべってしまったお春が問い詰められている場面である。お春は無言で詫びているのである。
黙説法の効果がよく出るのは、感情が高まり絶句する場面である。つまり言葉を尽くそうとするが、あるところで絶する点に達する表現である。
「一度でもこの位憎むべき言葉が、人間の口を出た事があるだろうか?一度でもこの位呪わしい言葉が、人間の耳に触れたことがあるだろうか?一度でもこの位、--――」(芥川龍之介『藪の中』)、「わたしは、一体どうすればよいのでしょうか?一体わたしは、――――わたしは、----」(同)、「アジアだって月だって、おまえは背中をかくよりたやすく盗むことができるのだ。しかし、そんなことをされたらこのわたしはいったい―――」(井上ひさし『ブンとフン』、「会社が、一人の人間を、ここまで追い詰めるとは--ーーー」(山崎豊子『沈まぬ太陽』)など。(抜粋)
また、黙説法は、適切な言葉を探して言いよどむ、という用法もある。著者はこの用法を、江國香織[えくにかおり]の「夏の少し前」(『つめたいよるに』)と連城三紀彦」の『恋文』からの引用を元に解説している。
そして最後に、黙説法について次のようにまとめている。
黙説法は、読者の想像力をかきててて、読者のテクスト解釈の場面に引き込みます。‥‥(中略)・・・・ 黙説法はしばしば余韻を生むとされていますが、その大きな部分は読者の参加によるものなのでしょう。(抜粋)
関連図書:
谷崎潤一郎(著)『細雪(上)(中)(下)』、新潮社(新潮文庫)、1955年
芥川龍之介(著)『藪の中』、講談社(講談社文庫)、2009年
井上ひさし(著)『ブンとフン』、新潮社(新潮文庫)、1974年
山崎豊子(著)『沈まぬ太陽(一)-(五)』、新潮社(新潮文庫)、2001年
江國香織(著)『つめたいよるに』、新潮社(新潮文庫)、1996年
連城三紀彦(著)『恋文・私の叔父さん』、新潮社(新潮文庫)、2012年
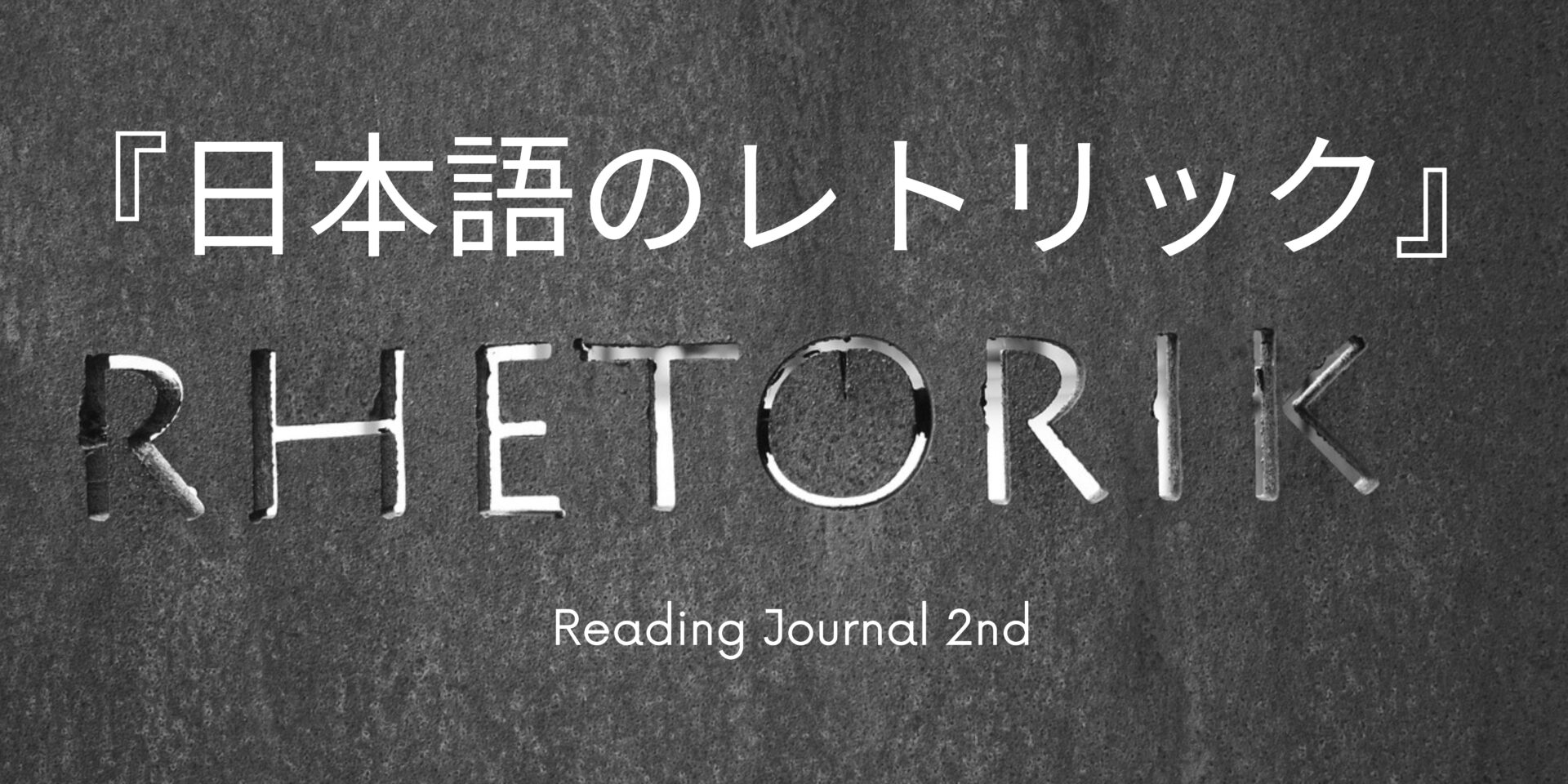


コメント