『日本語のレトリック』 瀨戸賢一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
反復法 同じ形をくりかえす(形のレトリック1 形を加減する)
ここより「形のレトリック」に入る。今日のところは「反復法」である。
反復はリズムを生み、リズムは反復を呼びこむ。この反復法の例を示すために著者は、幸田文のエッセー「濡れた男」(『幸田文文学全集 第十一巻』)を引用する。
鮭の漁を見に行くのである。東京から札幌・釧路・根室を経てノサップ岬を訪ね、北に進んで知床半島の漁場、羅臼という町に行くのである。(抜粋)
ここで「行くのである」の繰り返しと東京・札幌・釧路・根室・知床・羅臼と二拍の音の連続により目的地にぐんぐんと進む様子が描かれている。そして、漁場では、
かけ声の拍子が短く高くなって、網は寄せられて来、早くも慣れた眼がまだまだ水深くいる魚の数を、「百か!」と読む。「はいってないね」と云う。えいやえいや。「しけあとでまだちょっと早い時間だ。」えいやえいや。私にもやっと見えた。丸くふとった青黒い背中で、魚は右往左往の速さで行きかう。えいやえいや。ぱしゃぱしゃと重なりあった魚としぶき。よっしょつ!と大きく手繰られて魚は水をあがった。嬉しさとほっとした表情の男たちは、胸もズボンもずぶ濡れである。濡れて、これもきらきらと光る男たちである。(抜粋)
ここで、三回繰り返す「えいやえいや」の反復が効果的である。また、「えいやえいや」「まだまだ」「ぱしゃぱしゃ」「きらきら」は、同じ音の繰り返しである。
「男たち」や「魚」も反復され、「魚」の表現で「右往左往」と「行きかう」もやはり反復を感じさせる。
反復は、生のリズムそのものです。脈拍、呼吸、一歩一歩、活動と休息。これらと同調するように昼と夜が交代し、季節が巡ります。反復は、またパタンを生みます。生地に文様が浮かび、建造物に装飾が彫り込まれます。反復は、また音楽を奏でます。手拍子、足踏みにはじまり、各種の楽器に受け継がれています。反復は、また詩歌を創ります。とりわけ、終わりの繰り返し部分はリフレーンと呼ばれます。(抜粋)
ここで著者は、東洋では還暦という円環リズムがあり、西洋にも「太陽の下、新しいものは何ひとつない」(コヘレトの言葉、新共同訳)にあるような円環リズムがあったとしている。そして、そのような時間感覚が失われていることを嘆いている。
そして、最後に幸田文の文の最後の部分の「ない」の繰り返しがリフレーンのようになって静かに尾を引いているとしている。
しっぽも鰭も大概は形をなしていない。(・・・・・)もうどこへ行く処もないし、何をすることもないのだ。(・・・・・)美しかった銀鱗もいまはない。(抜粋)
ここで、突然「コヘレトの言葉」が出てきて驚いてしまった。コヘレトの言葉については、NHKの番組で興味をもって、関連書を三冊読んでいる。意外なところで出会うものですね。(つくジー)
(ココとココとココを参照)
関連図書:
幸田文(著)「濡れた男」『幸田文文学全集 第十一巻』、岩波書店、1995年
小友 聡 (著)『コヘレトの言葉を読もう 「生きよ」と呼びかける書』、日本キリスト教出版局、2019年
若松 英輔、小友 聡(著)『すべてには時がある 旧約聖書「コヘレトの言葉」をめぐる対話』、NHK出版(別冊NHKこころの時代宗教・人生)、2021年
小友 聡(著)『それでも生きる 旧約聖書「コヘレトの言葉」』、NHK出版(NHKこころの時代)、2020年
挿入法 ちょっと割り込む(形のレトリック1 形を加減する)
文章は、ある定まった視点から一貫させて書くものである。しかし、ちょっと別の視点を挿入することがある。
挿入法は、いわば舞台横(いや、裏かもしれない)から陰の声を差しはさむ手法です。(抜粋)
著者はここで、林達夫の『ファーブル 昆虫と暮らして』の「まえがき」を引用している。
人類の知識の進歩に大きく寄与したすぐれた科学者の伝記のなかには、いつも何かしら教訓になり模範になり励みになるものがあるが、『ファーブル 昆虫と暮らして』が諸君の心の糸にひびかせるものはなんだろう。わたしははじめ、この本から諸君が汲みとるべき数々のヒントを書こうと思っていたが、よく考えてみるとそれは、ファーブルの精神----諸君がそれを学んでほしいとわたしが切に望んでいる----その精神に反するおろかな企であることがわかった。「自得」(自分でさんざん苦労し、工夫してさとること)が、知識への道では何よりも大事なことだ。(抜粋)
ここで、「ファーブルの精神」と「自得」に、挿入法によって注が補われている。
挿入法は、乱用すると文の流れが悪くなる。しかし、工夫しだいで文書を豊かにする。
この「挿入法」であるが、前に読んだ『悪文』では、悪文のひとつとなっている(ココ参照)。なので、よくよく考えて使わないと、ダメって事だと思う。あ・・・・それから、前の林達夫の引用部を長々と再度抜き出しました。それは、この文章になるほどと思ったからです。(つくジー)
工夫しだいで文章を豊かにしている例として、宮部みゆきの『初ものがたり』と斎藤美奈子の『文章読本さん江』から「ちょっと違った視点」からの挿入と「批判的な視点」からの挿入の例を引用し説明している。
さらに、挿入法のもうひとつの用法として、小説(とくに三人称小説)のなかで、著者が自ら地声を挿入する場合がある。として、井上ひさしの『ブンとフン』から一節を引用し説明している。
関連図書:
林 達夫(著)『ファーブル 昆虫と暮らして』、岩波書店(岩波少年文庫)、1956年の『ファーブル 昆虫と暮らして』
宮部みゆき(著)『初ものがたり』、新潮社(新潮文庫)、1999年
斎藤美奈子(著)『文章読本さん江』、筑摩書房(ちくま文庫)、2007年
井上ひさし(著)『ブンとフン』、新潮社(新潮文庫)、1974年
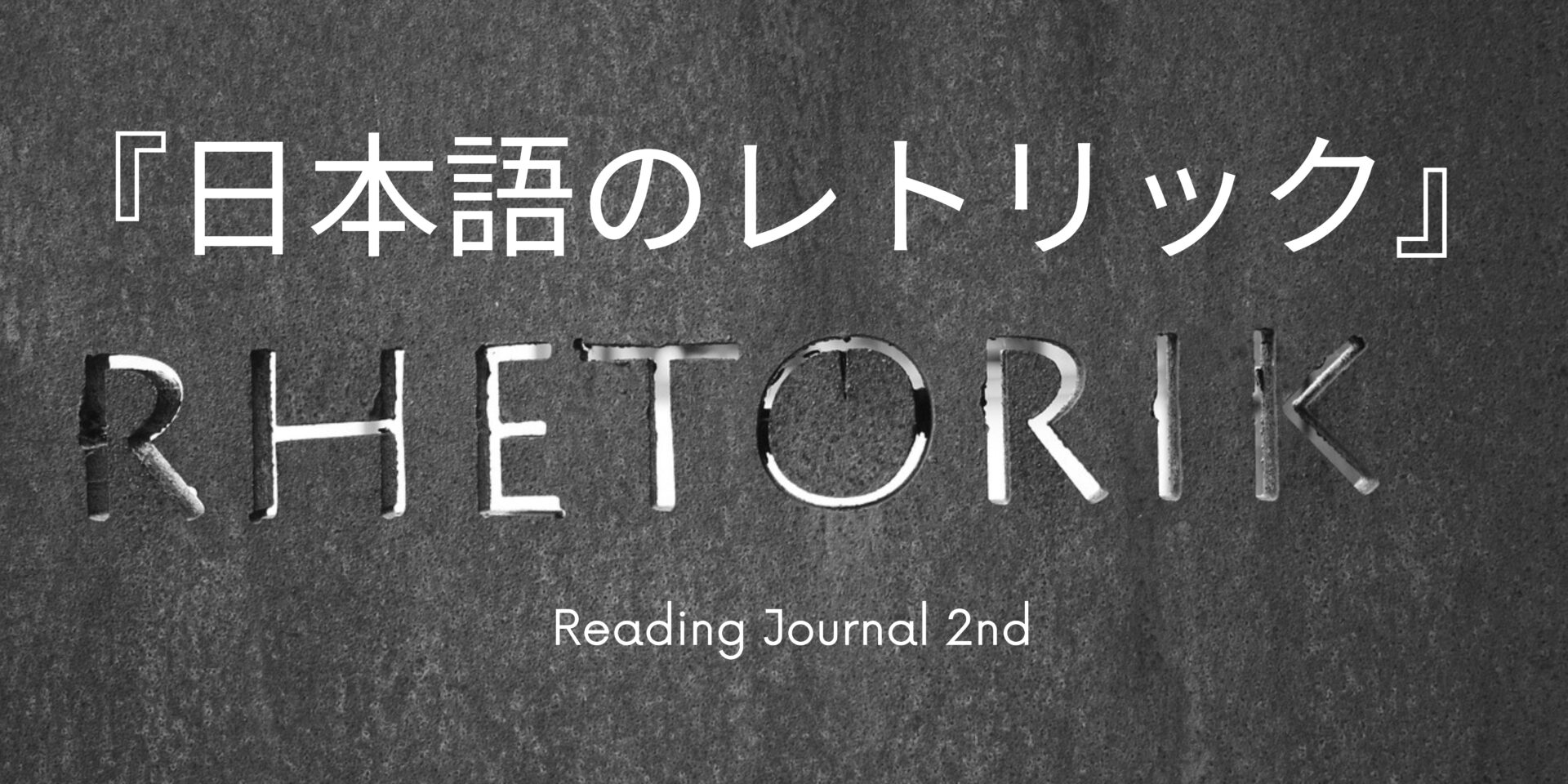


コメント