『日本軍兵士』 吉田 裕 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2章 身体から見た戦争 — 絶望的抗戦期の実体II (その1)
今日から「第2章 身体からみた戦争 — 絶望的抗戦期の実体II」に入る。「第1章 死にゆく兵士たち」(“その1”、“その2”、“その3”)では、アジア・太平洋戦争の絶望的抗戦期における、餓死を中心とした水没死、自殺、処置などの様々な兵士たちの死を部隊史などの実例をもって示した。
そして「第2章 身体から見た戦争」では、心の問題を含めた身体という側面から、日中戦争からアジア・太平洋戦争を捉えなおすとしている。
第2章は、節ごとに3つに分けてまとめるとする。今日のところ“その1”では、戦争が激化するにつれ、兵士の体格・体力がどのように変化していったかを追っている。それでは読み始めよう。
1 兵士の体格・体力の低下
兵士一人ひとりの身体には、その時代その時代の歴史が刻まれている。同じ兵士だということで、日清・日露戦争期の兵士の身体とアジア・太平洋戦争期の兵士の身体とを同一視することはできない。(抜粋)
徴兵制のシステム
日本軍は、日中戦争やアジア・太平洋戦争の開戦によって、年々多数の兵力を必要とした。ここで著者は、年次別の兵力数の表により、それがアジア・太平洋戦争期に急激に増えていることを指摘している。そして、その兵員数を満たすために徴兵検査などの見直しを取り組んだ。
徴兵検査は、満二〇歳の青年に対して受験することが義務づけられた。そして、全国一律の基準で身体検査が行われ、「格付け」された。
格付けは優越にしたがって、
- 甲種:現役に適する者
- 第一乙種:現役に適する者
- 第二乙種:現役に適する者
- 丙種:国民兵役に適する者
- 丁種:現役に適さない者
- 戊種:翌年再検査の者
となる。
日中戦争がはじまるころまでは、おおよそ甲種合格者が現役兵として入営し、第一乙種が第一補充兵役、第二乙種が第二補充兵役とされた。ここで、第二補充兵役と国民兵役は事実上の兵役免除だった。
現役徴収率の増大と兵士の体力の低下
しかし、日中戦争が激しくなると大規模な兵力動員が始まり、第一乙種までを現役兵とした。それに伴い、第一補充兵役に第二乙種が当てられ、さらに第二補充兵役要因として第三乙種が新設された。これに伴い、一九四〇年には、陸軍身体検査規則が改正荒れ徴兵検査の基準が大幅に引き下げられる。
改正のポイントは、「身体または精神にわずかな異常があっても、軍陣医学上」、軍務に支障なしと判断できる者は、「できるだけ徴集の栄誉に浴し得るよう、身体検査の条件を全面的に緩和した」ということである。(抜粋)
このような措置の結果、現役兵の徴収率は急速に増大し、現役徴収率は一九四四年には七七%に達した。そのため、体格や体力の劣る兵士、病弱な兵士が軍隊のなかで増大することになる。
ここで著者は、このような兵士の変化がわかるエピソードをいくつか紹介している。
知的障害者の苦悩、結核の拡大、虫歯の蔓延
知的障害者の入営も新たな事態であった。そのころ「精神薄弱」の兵士が3~4%に達したという報告がある。軍はこのような知的障害者の存在に関心を持つようになったのは、彼らが軍務になじめず自殺する事例が多く発生したからである。
また、兵士の体格、体力の低下は、大量の兵力動員とともに、社会で生じている変化の反映でもあった。特に結核の蔓延や国民生活の悪化などである。特に結核の問題は深刻で、軍需産業の工場や軍隊において感染が拡大した。
虫歯の蔓延は、なおも問題だった(ココ参照)。ここでは、そのような虫歯の問題についての幾つかのエピソードが加えられている。
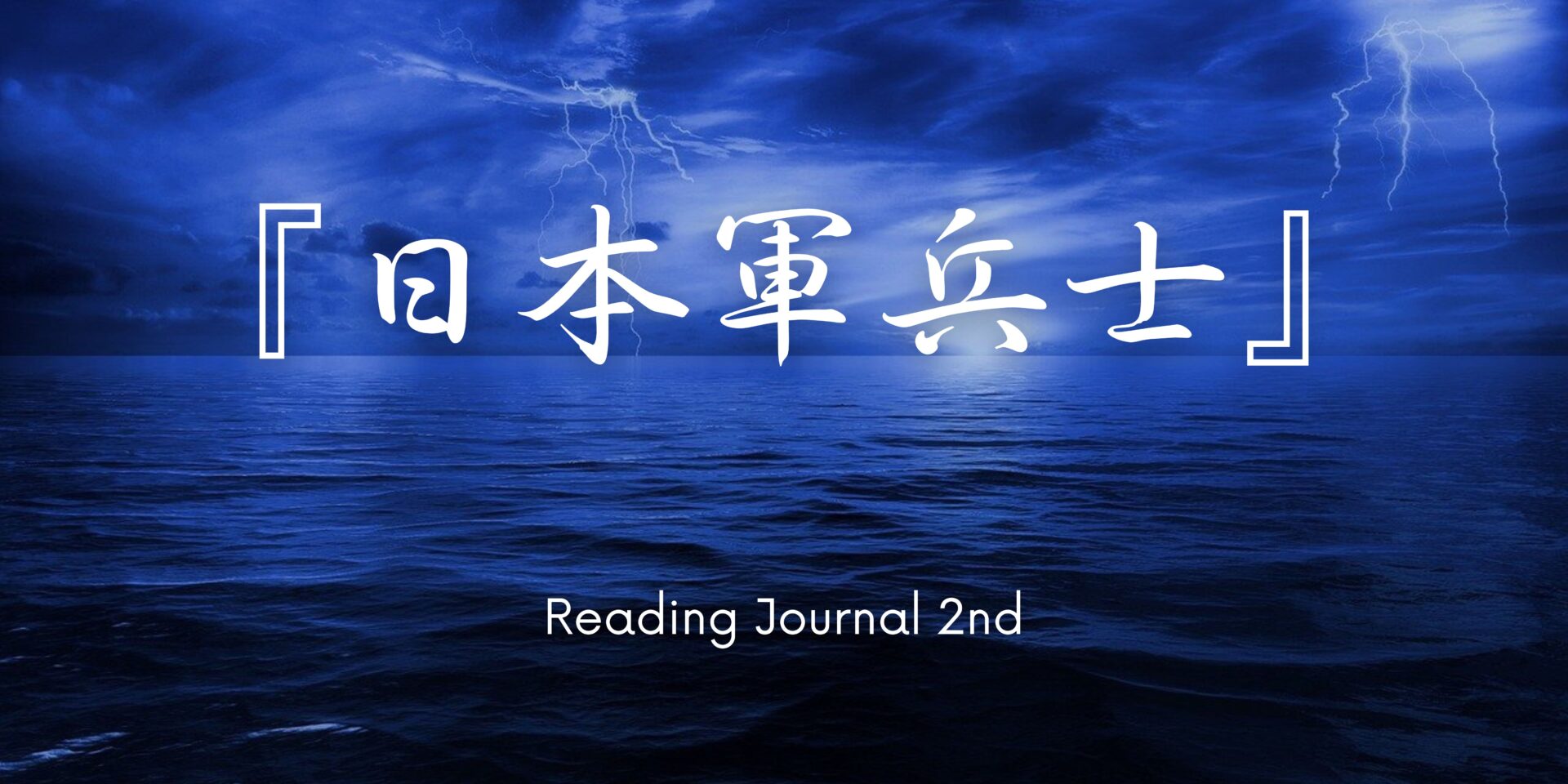


コメント