『日本軍兵士』 吉田 裕 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
序章 アジア・太平洋戦争の長期化(後半)
今日のところは、「序章 アジア・太平洋戦争の長期化」の”後半“である、”前半“では、日中戦争が戦線の硬直化し、また無理な作戦もあり、徐々に日本軍の中に厭世気分が蔓延するなど行き詰った様子が描かれていた。そして、今日の部分”後半“では、その後に起こったアジア・太平洋戦争を四期に分けて概観し、最終期「絶望的抗戦期」に戦争犠牲者が集中していることなどが解説される。それでは、読み始めよう。
アジア・太平洋戦争と戦争犠牲者
開戦 一九四一年一二月八日
一九四一年一二月八日、日本陸軍の侘美支隊が英領マレー半島に上陸を開始し、そして日本海軍の攻撃隊がハワイ真珠湾に対する空爆を開始し、アジア・太平洋戦争が始まった。
この戦争は、日本が日中戦争の行き詰まりを東南アジアにおける勢力圏の獲得によって打破するために開始した戦争である。また、それは、満州事変以降に獲得した日本の権益にあくまで固執したために始まった戦争でもある。
一九四一年の春から戦争を回避するために行われていた日米交渉では、アメリカは日本軍の中国からの撤兵を求めた。しかし、日本があくまでも駐兵に固執したため、交渉は決裂した。
ここで著者は、中国からの撤兵というアメリカ側の要求が、日中戦争の発端となった盧溝橋事件以前の状態への復帰、つまり、日本の傀儡政権である満州への日本軍の駐留は黙認すると理解されていたと指摘している。
このことは、満州国の現実の黙認という形で日米間の妥協が成立する可能性が客観的には存在したことを意味する。(抜粋)
しかし、日本側は撤兵一般にこだわったため、戦争が開始された。
第一期 — 戦略的攻勢の時期 開戦(一九四一年一二月) – 一九四二年五月
日本軍は、東南アジアから太平洋にかけての広大な地域を短期間のうちに占領する。日中戦争以降、軍備拡張を続けていた日本軍に対して、米軍・英軍・オーストラリア軍は、戦争準備が遅れ、共同作戦体制も整っていなかった。開戦時の日本の戦力は陸海軍ともにアメリカを上回っていた。
第二期 — 戦略的対峙の時期 一九四二年六月 – 一九四三年二月
戦線を拡大しようとした日本軍に対し連合軍が反撃に転じ、日本軍と連合軍が対峙する。
- 一九四二年六月:ミッドウェー海戦、米軍は日本軍の空母四隻を撃沈し勝利
- 一九四二年八月-二月:米軍はガダルカナル島に上陸、激しい攻防の末、日本軍は撤退、紺の戦いにより日本軍は、多数の艦船、航空機を失う。また多数の輸送船の損失は日本の戦時経済に大きなダメージを与える。
日本の敗勢が明確になるのは、ミッドウェー海戦より、このガダルカナル島攻防戦の敗北によってである。(抜粋)
このころ、米軍の戦力はまだ十分でなく、米軍を支えたのは、ニューギニアなどで日本軍と交戦したオーストラリア軍だった。
第三期 — 戦略的守成勢期 一九四三年三月 – 一九四四年七月
米国の戦争経済が本格的に稼働し、戦力を急速に充実させる。その結果、日米間の戦力比は完全に逆転し、戦力格差は急速に拡大。米軍は各地で本格的は攻勢を開始、日本軍は拡大しきった戦線を縮小して後方の防備を固めつつ、米軍との決戦に備えようとした。
- 一九四三年九月:「絶対防衛圏」を設定。(千島・小笠原・内南海・西部ニューギニア・スンダ・ビルマ)
- 一九四四年六月-八月:米軍はサイパン島上陸、日本軍はマリアナ沖海戦に敗れる。日本軍の機動部隊は壊滅、日本軍守備隊がサイパン島・グアム島・テニアン島で全滅、米軍はマリアナ諸島を制圧。
このマリアナ諸島の陥落により、日本国土の大部分が新型爆撃機B29の行動範囲内に入る。
第四期 — 絶望的抗戦期 一九四四年八月 – 敗戦(一九四五年八月)
この時期は、敗戦必至の状況にありながら、日本軍が抗戦を続けたため、戦争がさらに長期化した時期である。
- 一九四四年一〇月 – 四五年一月:米軍がフィリピンレのレイテ島、ルソン島と支配下におさめる。
- 一九四五年三月:小笠原諸島の硫黄島で日本軍守備隊が全滅
- 一九四五年三月 – 四月:米軍が沖縄本島に上陸、激戦の末日本軍守備隊が破れる。
この時期は、陸上兵力の面でも、日米格差は圧倒的となった。
航空戦でも新たな局面となる。
- 一九四四年一一月:B29により日本全土に対する空襲が始まる。
- 一九四五年三月:東京大空襲
これ以降、日本の都市は中小都市に至るまでB29による空襲で焼き払われた。
陸海軍に輸送船として徴傭された商船や民需用の商船の損失も深刻化し、軍事輸送に大きな支障が出ただけでなく、南方占領地からの資源輸送も途絶えた。そのため、戦時経済が崩壊した。
また、この時期には、日本軍の戦意も低下し始めていて、それを米軍は的確に認識していたことが米軍のレポートから読み取れる。
見落としてはならないことは、この四期の全体にわたって中国軍が抗戦を続けていたことだろう。(抜粋)
中国軍は、この時期にも抵抗を続けていて、多くの陸軍部隊が中国戦線に釘付けされて、連合軍と戦う日本軍の背後を脅かし続けた。
- 一九四四年四月 – 四五年:一号作戦(大陸打通作戦)を結構。日本軍は大兵力を動員して華北から華南におよぶ中国内陸部で作戦を展開した。
この時も中国軍は抗戦を断念することなく、日本軍の損害は大きかった。
そしていよいよ日本の敗戦が決まる。
- 一九四五年七月;米、英、ソ連の参加国首脳が会談し、日本に幸福を求めるポツダム宣言を発表する。
- 八月六日の広島への原爆投下、八月七日のソ連の対日参戦、八月八日の長崎への原爆投下が決定的なきっかけとなり、八月一四日に御前会議でポツダム宣言の受諾を決定、八月一五日に「玉音放送」によりその事実が日本国民に知らされた。
ここで、中国軍の必要な抵抗について書かれていたが、それには、加藤 陽子の『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』に書かれている胡適の「日本切腹、中国介錯論」(ココ参照)が参考になるはずである。日中戦争時にすでに中国は、この戦争にソ連とアメリカを引っ張り出すために、中国軍は負け続け膨大な犠牲を払っても、絶対に逃げずに戦い続ける必要があると覚悟を決めていたのだそうである。
また、ここの一号作戦については、
藤原 彰の『餓死した英霊たち』 のココとココに日本軍の被害(餓死)という観点から詳しく解説されている。(つくジー)
アジア・太平洋戦争の犠牲者たち
アジア・太平洋戦争での日本人戦没者数は、日中戦争を含めて
- 軍人軍属:約二三〇万人
- 外地の一般市民:約三〇万人
- 日本内地の一般市民:約五〇万人
であり、合計約三一〇万人である。
さらに外国人の犠牲者は、
- 米軍:九万二〇〇〇人から一〇万人
- ソ連軍:二万二六九四人(張鼓峰事件、ノモンハン事件、対日参戦以降)
- 英軍:二万九九六八人
- オランダ軍:二万七六〇〇人(民間人を含む)
さらに中国やアジア各地の人的被害は、正確な統計は残っていないが、推定で
- 中国軍と中国民衆:一〇〇〇万人以上
- 朝鮮:約二〇万人
- フィリピン:約一一一万人
- 台湾:約三万人
- マレーシア・シンガーポール:約一〇万人
その他、ベトナム、インドネシアをあわせて早計で一九〇〇〇万人以上になる。
日本が戦った戦争の最大の犠牲者はアジアの民衆だった。(抜粋)
一九四四年以降の犠牲者が九割か
日本人に関していえば、この三一〇万人の戦没者の大部分がサイパン島陥落後の絶望的抗戦期の死者であると考えられる。(抜粋)
日本政府は、年次別の戦没者数を公表していない。また、県別では岩手県が唯一陸海軍の年次別の戦死者数を公表している。
著者らは、この岩手県の戦没者数のデータから、軍人・軍属の戦死者数に当てはめると、全体の戦死者数二三〇万人のうち約二〇一万人が一九四四年一月以降の戦没者数となる。そして、民間人の戦没者は約八〇万人の大部分は絶望的抗戦期のものと考えられる。これを合わせると、二八一万人となり、全戦没者のなかで一九四四年以降の戦没者は、九一%に達することがわかる。
日本政府、軍部、そして昭和天皇を中心とした宮中グループの戦争終結決意が遅れたため、このような悲劇がもたらされたのである。(抜粋)
関連図書:
加藤 陽子(著) 「それでも日本人は戦争を選んだ」 新潮社(新潮文庫) 2016年
藤原彰(著)『餓死した英霊たち』筑摩書房(ちくま学芸文庫)2018年
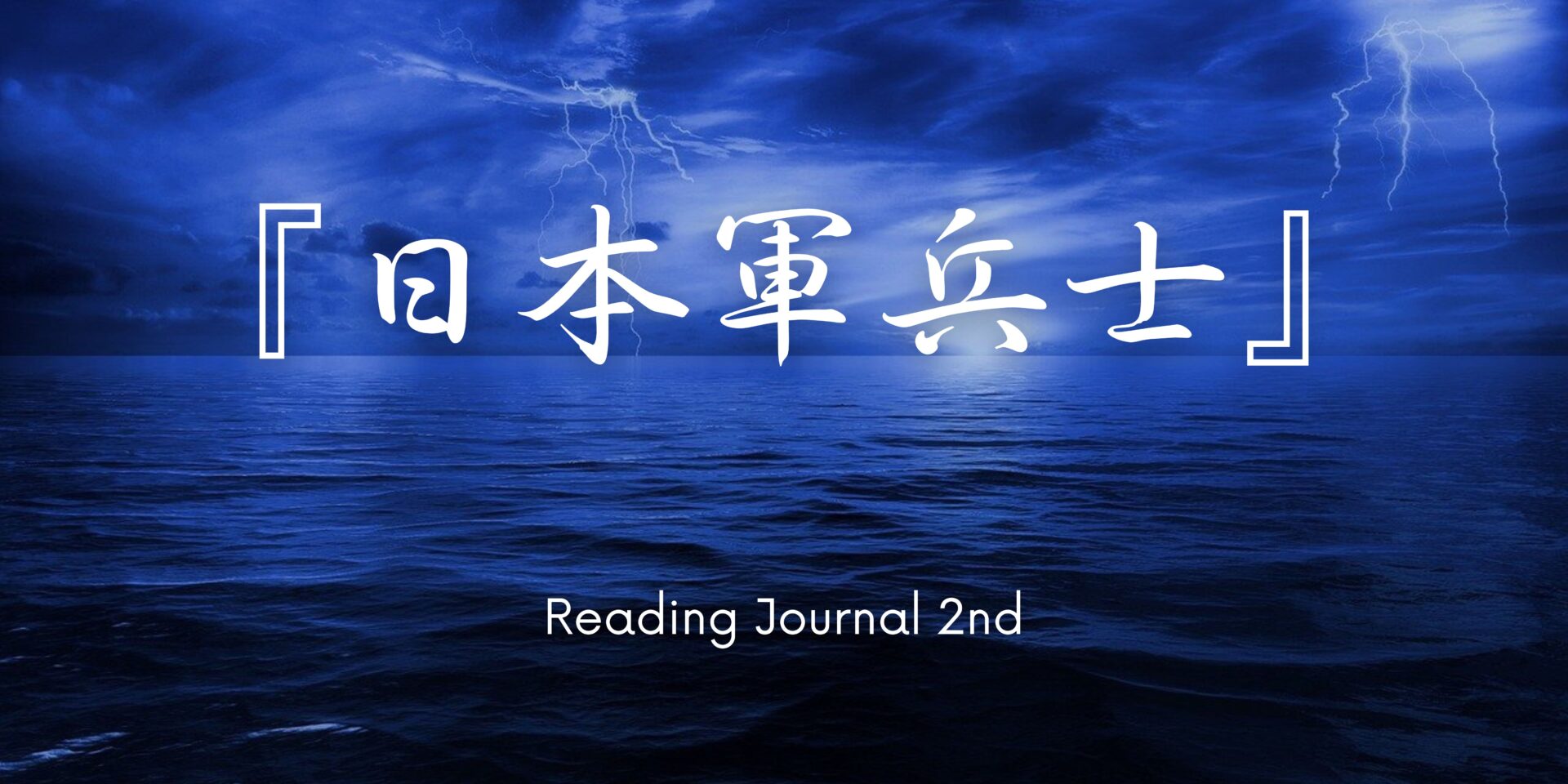


コメント