『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第五章 猫を愛した禅僧(前半)
第五章は「猫を愛した禅僧」である。ここでは、禅と猫の関係をその詩や公案などを通して探る。第五章は二つに分けてまとめる。また後半の最後に、ね・こらむ2 「犬に嚙まれた猫」がある。それでは、読み始めよう
禅僧と猫
室町時代になると禅宗が勢力を持ち始める。そして禅僧も猫を飼い、可愛がる。この猫好きの禅僧の数は、大変多く数えきれないくらいである。
どうして禅僧の猫好きがこんなに多いのかと思うくらいである。というより、禅僧は猫をいろいろ姿態をもつ詩句に書き残しているから、その数が多いと感じるだけなのだろうか。(抜粋)
中世の禅僧が用いた辞書『方語』や入門書『句双紙』には、「牡丹花の下で睡むる」という画題に「心が穏やかで悟った様子」という中国禅僧の解釈を載せている。この宋時代の禅問答の一節は、禅僧ならば承知の事実であった。
したがって、猫を詠んだ詩句の猫のたたずまいを禅の教養と関連づけて解釈すべき場合が多いことに気をつけておきたい。(抜粋)
しかし、著者はすべての詩句が画題に沿った絵画や典籍に依拠したものだとは思えないとしている。
猫が詠まれた詩句
ここで著者は、具体的に禅僧が猫を詠んだ詩を幾つか挙げている。十四世紀の有名な僧侶、義堂周信の『空華集』には、「猫画二首」として猫の絵を見て詠んだ詩が載っている。
猫児母の傍らで眠る 己に歃血の気有り
言を寄す鼠輩宜しく知るべし 真箇後生畏るべし
(猫の子が母の傍らで眠っている。それをいいことにちょっかいをだしているねずみたちも、ねずみたちも、眠りから覚めた猫が、その真の能力を発揮したときには慌てふためくだろう)(抜粋)
禅僧にとって、書物をかじるねずみは厄介者だった。そこで猫の出番であるが、本物の猫がいない場合には、猫の絵を掛けた。
この時代にすでに「ねずみよけの絵」というのがあった。十四世紀半ばの『仏日庵公物目録』に「猫児二舗」という絵画があった(藤原重雄『史料としての猫絵』、山川出版社、2014年)。
周信より二百年後の策彦周良も猫の詩を詠んでいる。この詩は、周良が飼っていた猫の死を詠んでいる。この詩について著者は、彼は単にねずみ捕りためだけに猫を飼っていたのでなく、学問の友として扱っていた、と想像している。
鉄山宗鈍は、『金鉄集』において、猫の死を悼んで、猫を「長老」と名づけた。猫に戒名はつけえないが、それに準じたものである。
猫児の死にいたるに、昨、道願上坐と名づく 八月朔日
一刀両断祖生の鞭 成仏すべからく群鼠を先んぜしめん
(猫が死んだので、昨日、「道願長老」と名づけた。八月一日のことだ。お前が幾多のねずみを退治した行為も、成仏の妨げになることがないように祈っているので、極楽でも鼠たちを追い回しておくれ)(抜粋)
(この詩には二句目があるが、それは後にふれる)
猫が死んだとき成仏できるかが問題になる。そこで、猫がした殺生は必要だったと仏に祈ることは大切な供養だった。
桃源瑞仙と猫
十五世紀の禅僧・桃源瑞仙は猫好きで知られている。瑞仙は中国や日本の古典に注釈をつける仕事で有名だが、その識語、つまり、あとがきで猫の消息を綴っていた。
『百衲襖抄』という『周易』の注釈書では、各章の最後の識語のうち三か所に猫の消息が書かれている。
前の章を見ると、これを書いたのは七月十四日だった。その後暇がなくて十月二十二日まで放っておいた。そこでまたこの章を書く。ああ、日はなんて短いのだろう。一日の大半は他人のために暮れてしまう。ここまで放置していたのも私の罪ではない。執筆は二十三日、真夜中に終わった。弟子の尤沙は眠って傍らにいる。私の二匹の猫もまた眠っている。私も眠るとしよう。これで私を加え「四睡」となるのみである。(抜粋)
ここで「四睡」とは、画題の画題で、豊干和尚と弟子の寒山、拾得そして虎の四者が身を寄せて眠る構図である。これは穏やかで安定した境地を表わす絵とされている。
この瑞仙の猫好きは同時代の禅僧の記事にも出てくる。『蔭涼軒日録』の長享二年(一四八八)十二月二十二日の条に、
瑞仙は猫を抱いて炉辺に座っていた。まるで唐の高僧を彷彿させるようだった。(抜粋)
著者は瑞仙の猫好きのエピソードのついでに、蛇足としながらP・J・デーヴィスの『ケンブリッジの哲学する猫』(社会思想社、1992年)を思い出すとしている。
挿絵には、修道僧が猫をだっこして書き物をしている絵が載っており、とても可愛い。九世紀のアイルランドでも、ねずみが書物を害するので、猫が修道院に飼われていたのだろう。時代や国は違っていても、こんな猫と人間の関係があったということは、猫好きにとって喜ばしいことではないだろうか。(抜粋)
関連図書:
藤原重雄(著)『史料としての猫絵』、山川出版社、2014年
P・J・デーヴィス(著)『ケンブリッジの哲学する猫』、社会思想社、1992年
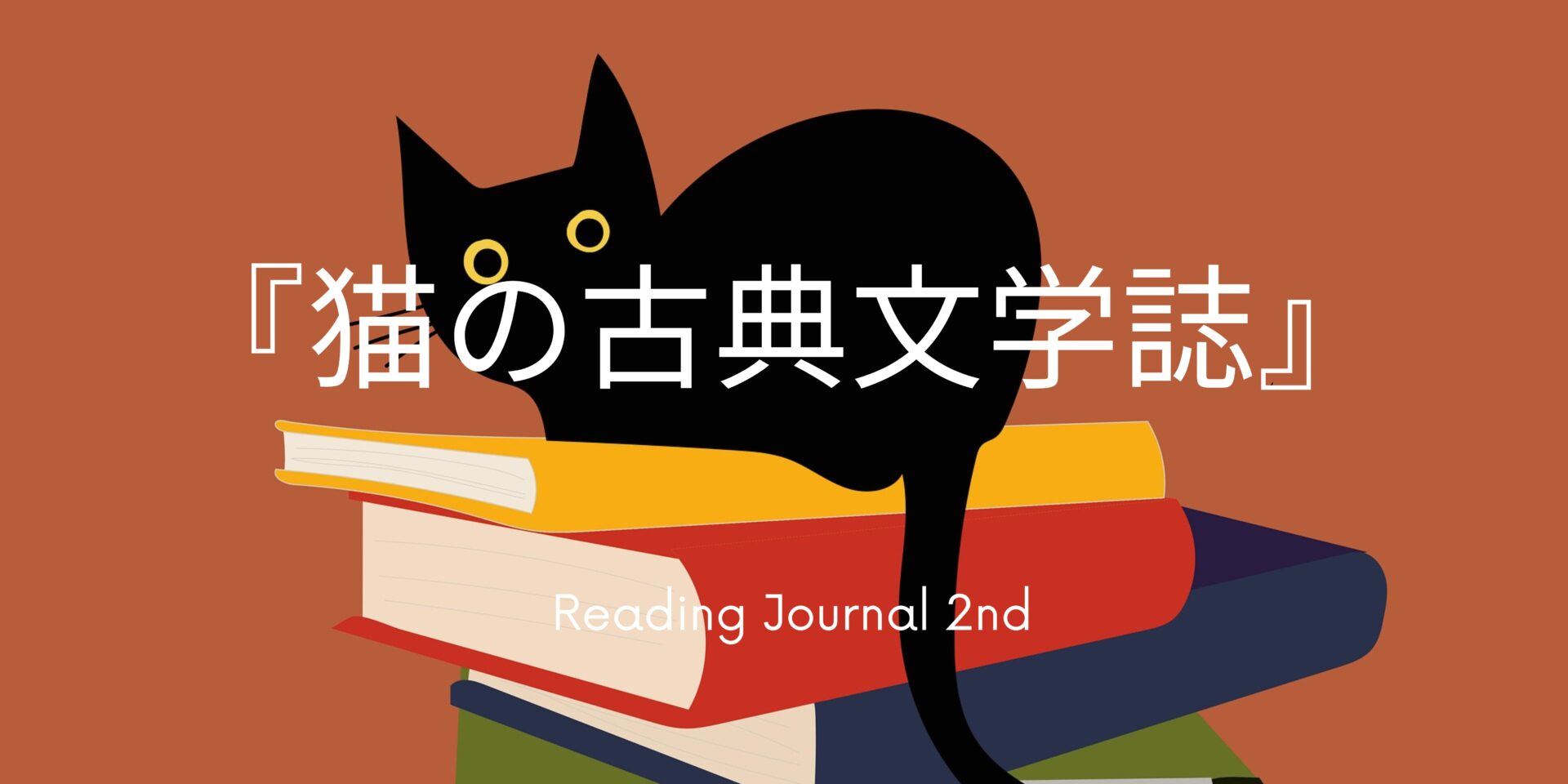


コメント