『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第三章 ねこまた出現(その1)
今日のところは第三章である。前章・第二章 「王朝貴族に愛された猫たち」では、平安時代の中頃までは、猫は、高級輸入品の唐猫であり権力の象徴として可愛がられ、そして末期になると、しだいに可愛いだけでない不思議な存在に変わり始めていた。それを受けて第三章では、猫が次第に恐ろしい存在としてとらえられ「ねこたま」が登場する。さて、読み始めよう。
『古今著聞集』のねこまた 2
前章・第二章の最後で『古今著聞集』では、珍しい猫の例を2例挙げられていた(ココ参照)。そして同じ『古今著聞集』には、猫の怪異を示す話がある。その話では、まだ「ねこまた」と呼ばれていないが、実質的にはねこまたである。
巻二十、六〇九話には、観教法師が山で捕らえた唐猫と遊んでいる時に、唐猫が秘蔵の守り刀をくわえて遁走し行方知れずになったという話がある。
この猫は、もしや魔物の変身で、守り刀を奪った後、なんの遠慮もなく人々をたぶらかすのではなかろうか、恐ろしいことである。(抜粋)
著者は、この猫の正体が何であったかは分からないとしながら、十三世紀にすでに猫が化ける可能性がささやかれていたことは、注目に値すると言っている。
『本朝世紀』のねこまた
猫の化け物のもっとも早い記述は、久安六年(一一五〇)の『本朝世紀』である。ここでは、まだ「猫また」という言葉はみられないが、「山猫」と呼ばれる化け物が近江と美濃の山中に出現したという。ここで、なぜ奇獣を「山猫」と呼んだかわからないが、すでい「猫は魔性」という風評が地方に運ばれたのではないか。平安から中世に向かうにつれて、猫はその暗い側面を人間によって増幅させられていった。
『明月記』のねこまた
藤原定家の『明月記』(一二三三年)が「ねこまた」という言葉が使われた初例ではないかと著者な指摘している。
『明月記』には、「ねこまた」が京の町に現れた事件が書かれている。そして「ねこまた」は、
目は猫のようで、その体の大きさは犬のようでした(抜粋)
と記載されている。
犬のように大きいねこまたは、その噂だけでも人々を震撼させた。
『四季物語』のねこまた
ねこの化け物は、このように人々を震撼させたが、同じく人と一緒に暮らす動物でも犬の化け物は、全く見られない。この違いの理由の一つと考えられることが、「仏教が必ずしも猫を歓迎していない」からである。仏典には猫があまり良く書かれていない(水野忠一『日中を繫ぐ唐猫』習俗同攻会、一九八二年)。
鴨長明に仮託された『四季物語』には次のように書かれている。
仏のいらっしゃる国でも、ねこまという獣は、姿形は虎に似ていても心はねじまがっている。虎といっても恐ろしいことばかりでなく、・・・中略・・・・やさしいこともあるが、ねこまはお釈迦様のご入滅にも悲しいと思わないやつである。涅槃図にも描かれていないおどろおどろしさである。・・・・後略・・・・。(抜粋)
ただし、涅槃図にも描かれていないというのは誤りである(第九章を参照)と著者は指摘している。
『徒然草』のねこまた
『徒然草』には有名な「ねこまた出現事件」の話がある。
これは、「山の奥には猫またというものがいて、人を食うそうだ」とか「いや、山だけではない。このへんでも長生きした猫が猫またという怪物になって人を取ることはあるだろう」というような噂を聞いた法師が、夜道を家に帰ると途中、猫またに襲われたという話である。この話には『徒然草』独特の皮肉っぽい落ちがあって、
これは、法師が飼っている犬が、暗かったけど主人のお帰りだとしって飛びついてきたのだという。(抜粋)
この『徒然草』の話から分かることは、次の3つである。
- ねこまたは、人を取って食らうということ
- ねこまたは、長生きした猫が化けたものであること
- ねこまたは、犬ほどの大きさだということ
この犬ほどの大きさというのは、『南総里見八犬伝』でも、猫の化け物が「その大きさは犬に等しい」と記されている。
関連図書:水野忠一(著)『日中を繋ぐ唐猫 : 中国の猫文化史』、習俗同攻会、1982年
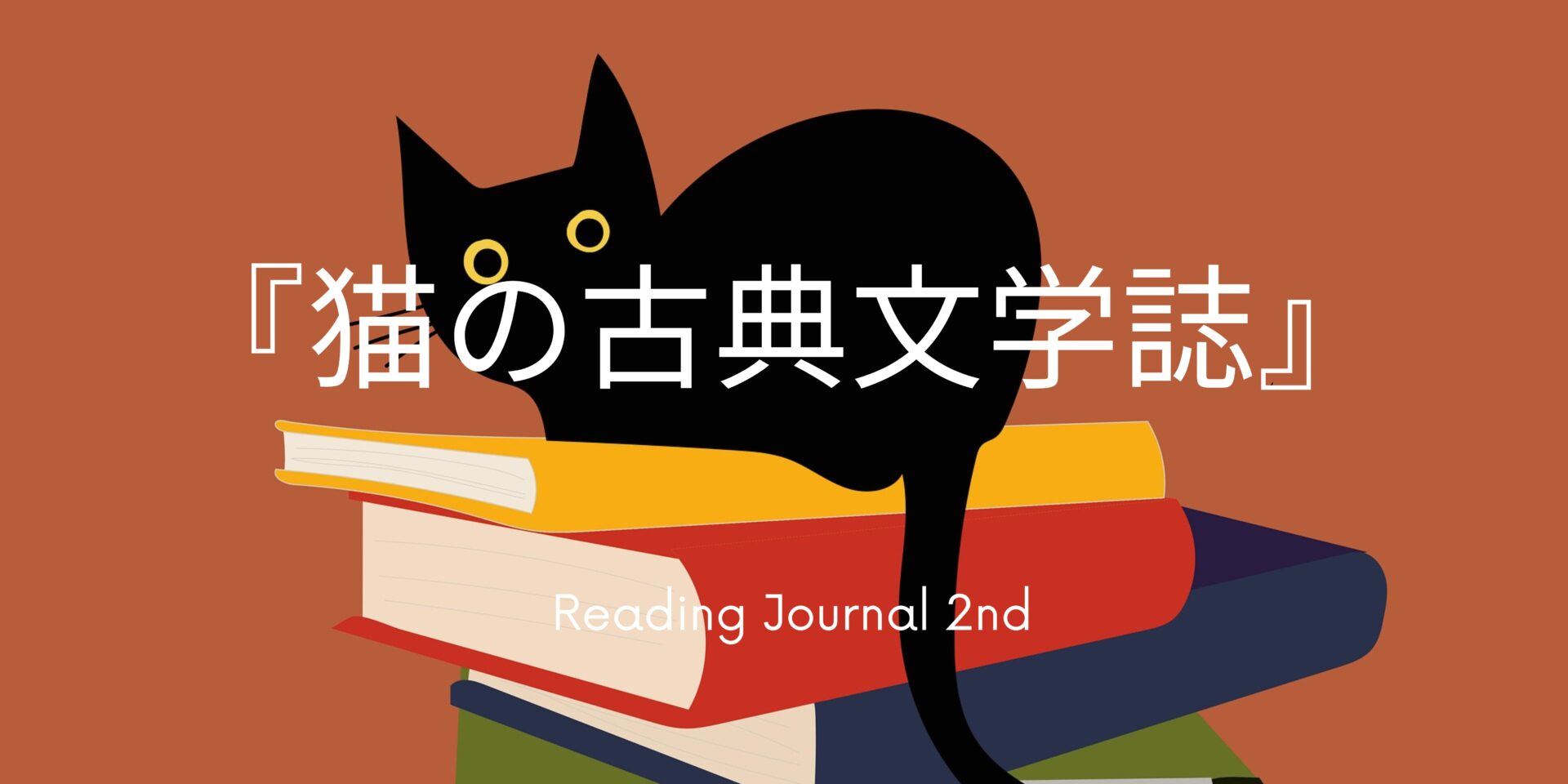


コメント