『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第八章 江戸お猫さまの生活(後半)
今日のところは、第八章「江戸のお猫さまの生活」の”後半“である。江戸時代になると俳諧、芝居、草双紙などの文芸に多くの猫が登場する。”前半”では、俳諧の中に登場する猫と、当時の猫の様子を資料をもとに描かれた。さらに後半では、文人と猫の話と、回向院と猫の話が書かれている。それでは、読み始めよう。
江戸の文人と猫
中世の禅僧に猫好きがいたように、江戸時代の文人にも猫好きがいた。ここでは、その中から二人が紹介されている。
一人目は太田南畝・蜀山人である。彼には『猫の賦』という一文がある。(「賦」とは、中国の詩の六つの形態の一つで「所感をありのまま述べるもの」という意である)
この『猫の賦』には、蜀山人の猫が死んだことを暗示させる箇所がある。著者は、この一文を適時意訳しながら、として次のように書き下している。
鶏は朝ときを告げ、犬は夜の安眠を守る。みな養い慣れ親しむべきものである。そういった動物はたくさんあるけど、鳥は心を慰めるが、すり餌やまき餌がわずらわしく、魚は見ていて気持ちいいが、水にぼうふらが湧いて困る。ほかにもいろいろあるが飼うのには損があって、益のないものである。ここに一つの動物がある。それを飼うのは飯を以てする。アワビ貝一つ、鰹節いくつかで一年もつ。顎のしたにきれいな毛を隠し、眼で六つの時間をはかる。たまたま涅槃図に書きもらされたのも、中国の詩人・屈原が『楚辞』に梅の詩を入れ忘れたのと同じだろう。夏は牡丹の影に眠り、蝶々になってたわむれる夢を見ていても、ついに垣根に埋められて、隣りの藪の筍の肥やしとなると思うとあわれである。(抜粋)
ところどころに故事を引いて猫を礼賛している。
この蜀山人の文章には驚いた。鰹節がご飯というのは当時の常識だったからよいとして、「猫の目で時間を測る」こと、「(禅画の)猫と牡丹と蝶々」の関係、「猫は涅槃図に描かれない」ことなど、ここまでこの本で学んだことがちゃんと書いてある。さすがですね!蜀山人さん!!(つくジー)
蕉門十哲の一人、各務支考は「猫を祭る文」(『風俗文選』所収)という文章を残している。ここには、「李四」が、可愛がっていた猫が井戸に落ちて死んだとき、墓を作り「釈自円」という仏名に改名し猫を供養したことが記されている。
このように、猫好き文人は中世の禅僧のように猫を愛し、猫のために詩文を作ったのである。作者の感情を詩文に投影して読むのは少し危険だと思うけど、その心は今の人間と変わることはないと思いたい。家族同様の猫が、愛し愛された一つの記念碑として、詩文があるのだ。(抜粋)
回向院の猫
近世の猫の章を閉じる前に、ぜひとも言及しておきたいのが回向院である。(抜粋)
回向院は、両国にある寺院で、鼠小僧次郎吉の墓があることで有名である。ここは、動物供養の寺としても有名で、猫の墓がある。著者は学会のついでに回向院に向かった。
回向院の開設は、明暦三年、「振り袖火事」の起こった年である。回向院は、その火事でなくなった十万人もの人々を手厚く葬る。浄土宗の寺であったが、宗派にこだわらずどんな人でも受け入れたため、天災等があった後は無縁仏が多くここに祀られた。
回向院の境内にはさまざまな動物の供養塔や慰霊碑がある。通常、動物は成仏できないものと考えられているが、それをあえて供養して成仏を願おうとしたのが回向院なのだ。(抜粋)
そしてここに有名な猫の墓がある。この墓には、猫の報恩伝説がつたわっている。
江戸時代の随筆『宮川舎漫筆』(文久六年(一八六二))には、その由来が書かれている。
江戸両替町の時田喜三郎の飼い猫は、出入りの魚屋がいつも魚を与えてくれるので、魚屋が来るたびに魚をねだっていた。しかし、魚屋は病気にかかってしまい、出入りがなくなってしまった。魚屋の病は長引き、ついに一銭もなくなったころ、誰かわからないが二両もの大金を置いて行った。ようやく快気した魚屋は商売の元手を借りようと喜三郎のもとへ行くが、いつもの猫が出てこない。理由をたずねると、「あの猫は撃ち殺してしまった」と言う。先だって金二両が紛失し、その後も猫が金をくわえているのを見つけ、さては前の二両も猫のしわざかと合点し、家中の者で撲殺したというのである。
魚屋はそれを聞いて涙を流し、二両は自分がもらったものだ。と言って差し出した金の包み紙が、間違いなく喜三郎の筆跡のある反故だったのである。これはいつも魚をもらっていた猫が魚屋に恩返しをしたのだと喜三郎は感じ入り、二度にわたってくわえていった金を魚屋に与えたという。魚屋も、猫のなきがらをもらい受けて回向院に手厚く葬った。(抜粋)
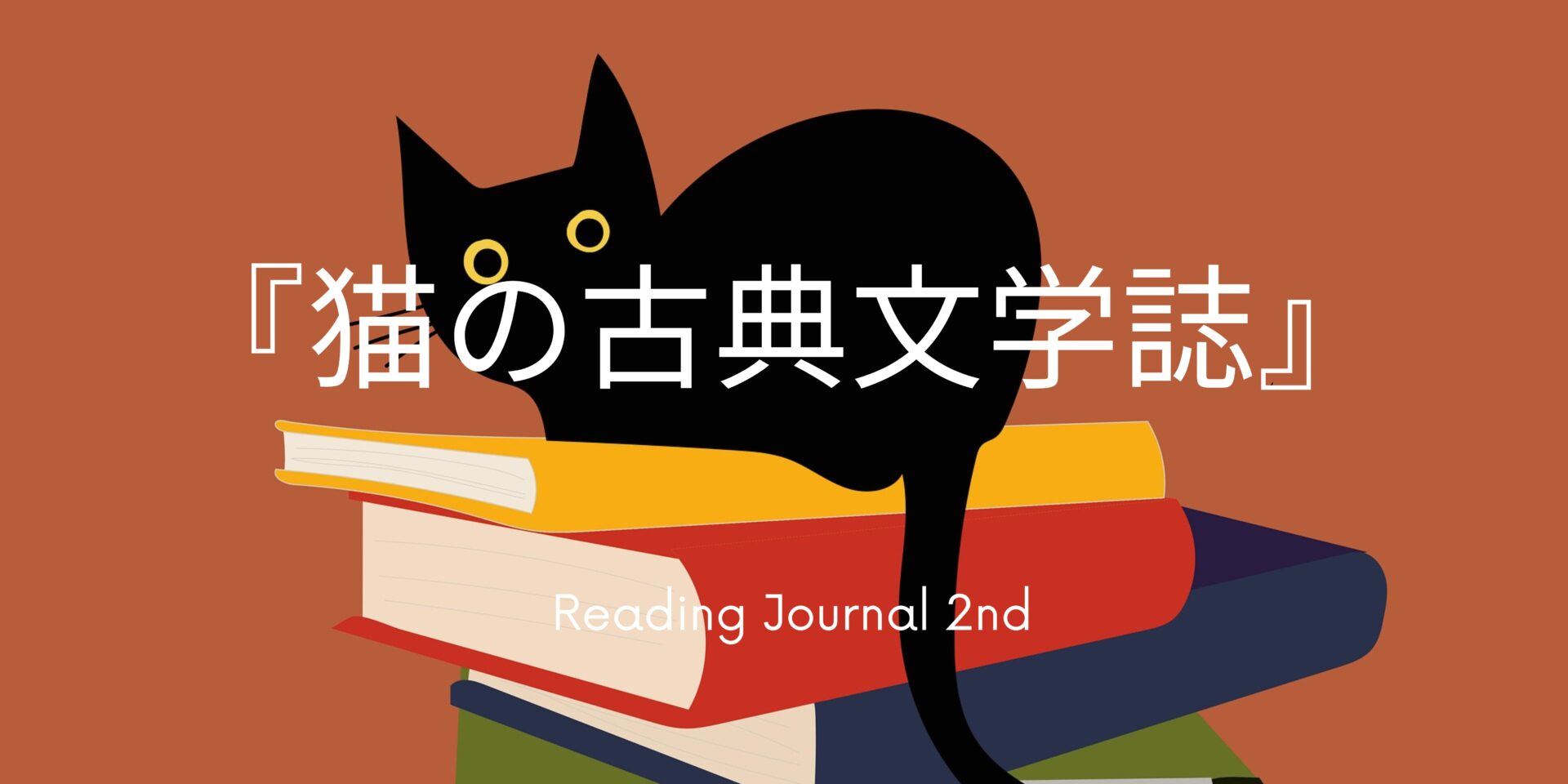


コメント