『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第七章 猫神由来(前半)
今日のところは、第七章「猫神由来」である。ここでは、著者が長年気になっていた、島津家の猫神の由来について、時系列で書かれている。第七章は前半と後半に分けてまとめる。前半では、著者が「猫神」との出会いと「猫の瞳で時刻を読む」ことについてである。読み始めよう。
猫神とは?
著者が高校を卒業した春の家族旅行で、薩摩藩の島津家の別荘だった磯庭園(仙厳園)を訪れた。そしてそこには、「猫神」と呼ばれる場所があった。
ここには、秀吉の朝鮮出兵についていった猫が埋められているというのである。
猫が戦争に従軍した理由をいうと、当時は時間をはかる正確な器械がなかったため、猫の目で時間をはかるというものだ。信じられないことだが、たしかに「猫の目が変わるように」などといわれるように、猫の目は一日の光の動きをとらえ変化する。(抜粋)
この時は、それ以上は追求せずにいたが、猫の本を書くに当たって、その光景が蘇ってきた。
この話は、猫の研究書にほとんど取り上げられていない。むかし読んだ、實吉達郎の猫に関する本で「島津家ではお時計衆にかごを背負わせて猫を運ばせた」という記述を見つけただけである。しかし、そのニュースソースが示されていなかったので謎は深まるばかりだった(後に、田中祥太郎の『時計のかわりになった猫』、廣済堂出版、1987年という本で紹介されていたことを知ったとのこと)。
そして著者は二十年ぶりに鹿児島を訪ね、磯庭園に調査に向かった。そして、昔行った時は、塚のようなものしかなかった「猫神」の場所は、立派な神社になっていた。神社の案内板には、
文禄慶長の役に活躍した島津家十七代義弘は七匹の猫を朝鮮半島まで連れていき猫の目の瞳孔の開き具合によって時刻を推測したといわれています。この神社には生還した二匹の猫の霊が祀られており、六月十日の時の記念日には鹿児島市の時計業者の人々のお祭りがおこなわれています。(抜粋)
と書かれていた。
ここで著者は、がぜん「猫神」の話に興味を持った。この話にはいろいろと疑問もあったが、
本当であってもそうでなくても、主君につかえて遠い朝鮮半島まで行った猫の話は魅力的である。けなげでもある。(抜粋)
とし、これについてもう少し調べることにした。
猫の瞳と時刻
まず、猫の目で時間をはかる習慣についてであるが、これは中国から伝わってきた古法である。九世紀の『西陽雑俎』に
旦と暮れは円く、午に及べば竪に引き締め線の如し(抜粋)
とあり、通常の天候のときの猫の目の変化と同じである。また、平岩米吉の『猫の歴史と奇話』(築地書館、一九九二年)には蘇東坡の『物類相関志』にも同様な記述があるとしている。
そして、中国近世の日用便利辞典である『玉匣記』に、猫の目で時刻を知る方法が載っている。
子、午、卯、酉の刻は、一条の線のように、寅、申、巳、亥の刻は丸い円のように、辰、戍、丑、未はなつめの種のようになる、ということである。(抜粋)
しかし、これでは子の刻、午前零時ごろに猫の瞳が「一条の線」のように細くなることになり、実情と矛盾している。これは中国では猫の瞳が明るさによって変化するのではなく、時刻で変化すると考えられていたために起こった矛盾である。
そして、この方法が中世の日本にやってきた。
それは、中世後期の百科事典『塵添壒囊鈔』や江戸時代の『和訓栞』に同様のものが載っていることから明らかである。
そして、中国の故事を集めた『分類故事要語』には、鷗陽公が牡丹の花の下に猫がいる構図の絵をみて、この絵がいつの頃の絵であるかを呉正粛に聞いたところ、猫の目の瞳孔が黒い線のようになっている様子から正午であると答えた、というエピソードが載っている。
さらに江戸時代の梅川夏北は、猫の瞳について諸家の説を引用して、それに考察を加えた本『猫瞳寛窄弁』を文化十三年(一八一六)に書いている。
最近の話題として二〇一四年の松濤美術館の「ねこ・猫・ネコ」展図録所収の「猫の話あれこれ」(味岡義人)で、さいとう・たかおの『ゴルゴ13』(第四十一巻)に、猫の目で時を知り暗殺に成功する話があると紹介されている。
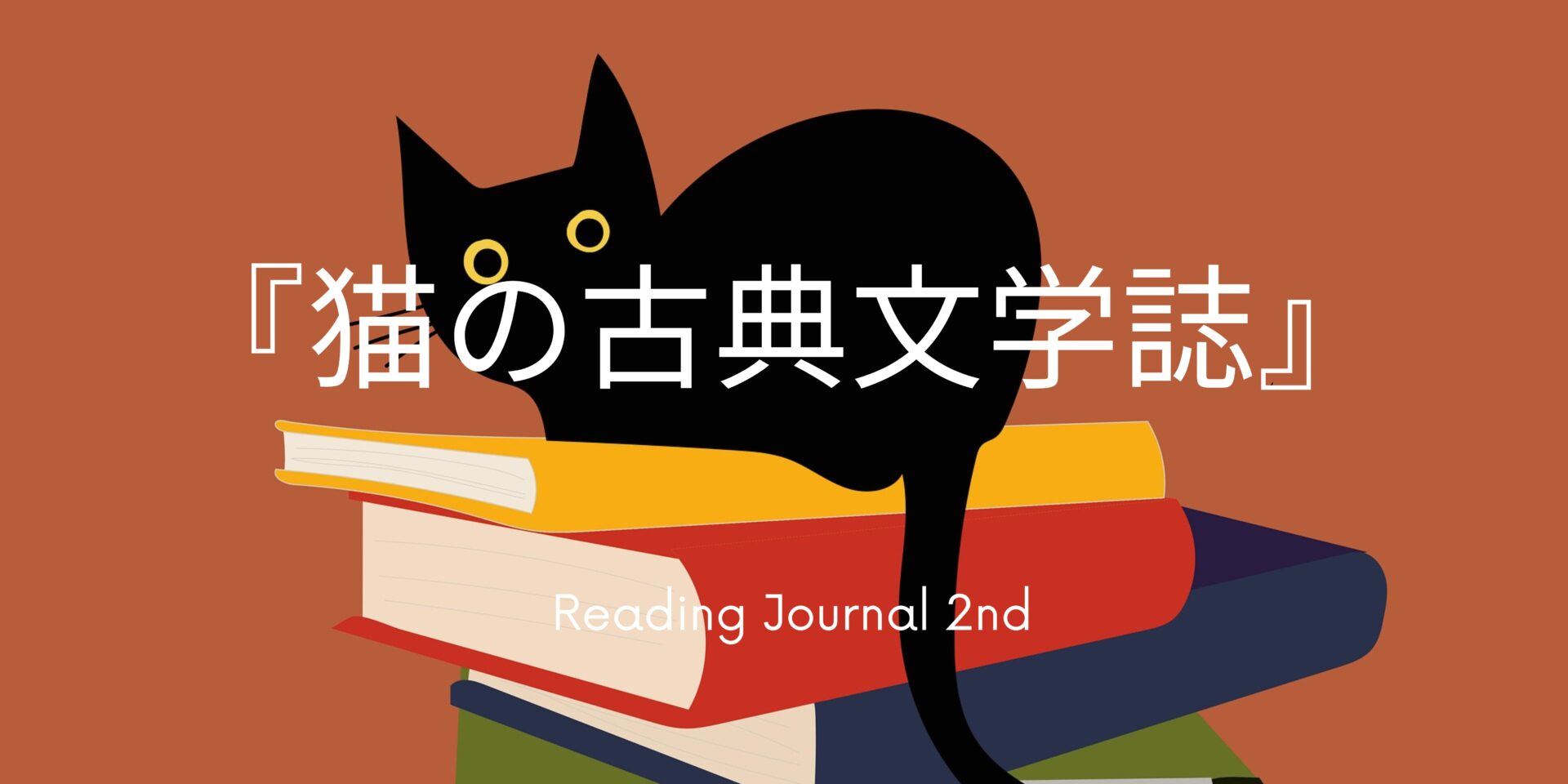


コメント