『猫の古典文学誌』田中 貴子 著、講談社(講談社学術文庫)、2014年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
プロローグ
『日本語の古典』が読み終わった。古典は学校であまり勉強しなかったため、原文はほぼ読めない、そしてさして興味もないのだが、たまたま本屋で書棚を見ていて、なんとはなくであるが、この本つまり『猫の古典文学誌』が気に入った。なぜだろう?さしてネコも好きでないんですけども。ちなみに、先の『日本語の古典』ですが、うちの本棚に・・・もう一冊ある・・・・これも、不思議な出来事の一つですね。では、読み始めよう。
今日のところは、「プロローグ」である。著者と猫との出会いの話が書かれている。最初に観た映画が、猫映画(「トマシーナの三つの命」)だったり、講談社の絵本での猫との出会いだったりがあり、著者は小さい頃から猫好きだった。そして、幼稚園のころに初めて猫が家にもらわれてきて、それ以来ずっと猫との生活がつづいた。
その間、内弁慶な女の子はいつしか研究者となった。そして、彼女の「いつしか必ず猫の本を出したい」という気持ちは年々強くなる一方だった。(抜粋)
しかし、猫の本は古今東西の猫好きによって書き尽くされている感があり、著者は、雑誌『国文学』に「猫の文学博物誌」という特集を組むに至って、一度断念している。あまりに多くの猫の記事が碩学によって列挙され、もう新しい資料は見つからないと思われたからである。
しかし、その資料を自分なりに読み解いていくことはできるのではないかと思う。また、著者は猫の伝説や民俗よりも、文字で書かれたテキスト(文献)の網羅の方に興味がった。そこで「書かれたものとしての猫」と、それが書かれた背景について調べようと決めた。
だから、本書はある意味では猫の資料の列挙にすぎなくなってしまうかもしれない。だが、そういった文学のあわいにある、人と猫との結びつきを感じて頂ければ幸いである。
ほら、耳を澄ましてみよう。どこからともなく聞こえてこないだろうか。あなたを慕ってやってくる、猫の首にかかる鈴の音が・・・・(抜粋)
目次
プロローグ [第1回]
第一章 「猫」という文字はいつごろから使われたか [第2回]
第二章 王朝貴族に愛された猫たち [第3回][第4回]
ね・こらむ1 和歌のなかの猫
第三章 ねこまた出現 [第5回][第6回][第7回]
第四章 金沢文庫の猫 [第8回]
第五章 猫を愛した禅僧 [第9回][第10回]
ね・こらむ2 犬に噛まれた猫
第六章 新訳 猫の草子 [第11回]
第七章 猫神由来 [第12回][第13回]
ね・こらむ3 猫の島
第八章 江戸お猫さまの生活 [第14回][第15回]
第九章 描かれた猫たち [第16回][第17回]
エピローグ
【付録】漱石先生、猫見る会ぞなもし [第18回]
参考文献一覧
本書で取り上げた「猫」の文献資料
原書あとがき [第19回]
学術文庫版あとがき
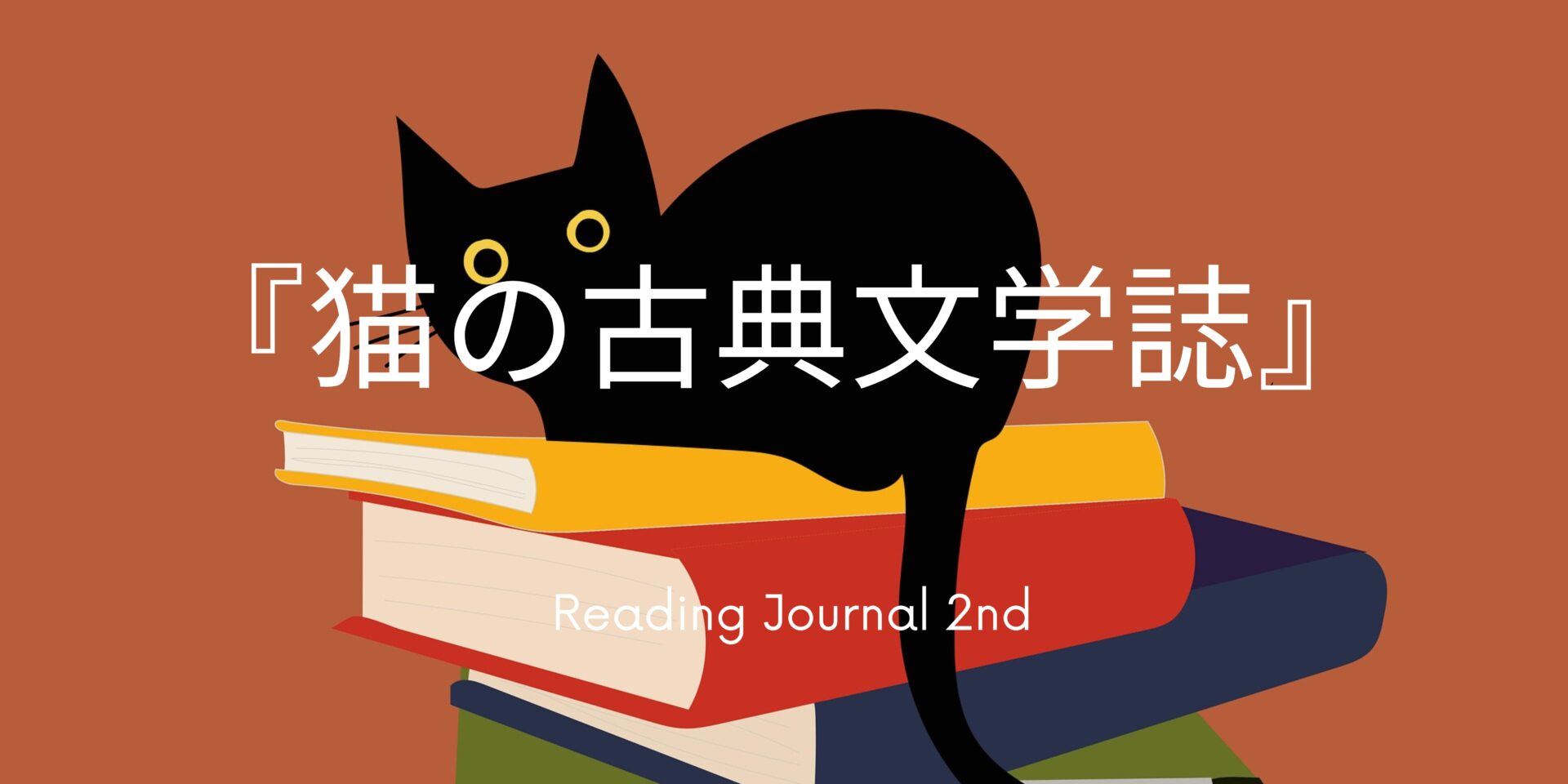


コメント