『難解な本を読む技術』 高田 明典 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第5章 さらなる高度な本読み(その3)
今日のところは「第5章 さらなる高度な本読み」の“その3”である。“その1”、“その2”に続き、ここでは「著者読み」、「究極の同化読み」、「批判読み」が取り扱われる。
ある著者について追っていくのが「著者読み」であり、そして「その著者と同じ頭になる」ことが「究極の同化読み」となる。逆にこの本やあやしいと、疑りながら読むのが「批判読み」である。それでは読み始めよう。
「著者読み」
「著者読み」とは
「著者読み」とは、「一人の著者」の著作をひたすら追いかけていく読み方である。多くの研究者が、この「著者読み」を偉大な思想家や研究者の思想を現代の文脈で読み直し、活かすという目的で行っている。
「包括著者読み」
「包括著者読み」とは、一人の著者の著作全体を「包括読み」する方法である。これは、その著者の著作や解説書を詳細には読まずに、著作の全体像を把握するために行う。方法は「包括読み」と同じであり、文献リストを作る作業が主になる。その文献リストはさらなる進んだ著者読みをする前提となる。
「系統著者読み」
これは「文献リスト」をもとに一人の著者に関して「系統読み」をする方法である。著者の作品群の中で「根」「茎」「花」を考えて、系統・体系を想定し、その順番で読む。
「縦断著者読み」
これは、一人の著者の思想の変遷を中心に考えながら「縦断読み」をするものである。
「究極の同化読み」 — 著者と同じ頭になる
ある著者に関して「包括読み」からさらに踏み込んだ意味での「著者読み」を行うことができたならば、「究極の同化読み」をしたといっても過言ではないでしょう。(抜粋)
一つの著作にその思想家の思想が凝縮している場合もあり、そのような本を「詳細読み」することにより「究極の同化読み」が行われることもある。
この「究極の同化読み」とは「著者と同じ頭になる」ことを言う。
もっとも、実際には自分の内部に著者の思想を再構成することは、達成できない理想であるので、「著者の思想を自分の中で再構成できたと感じられる」ような状態になることを「著者と同じ頭になる」と表現している。
この「究極の同化読み」をするには、著者の感じ方、価値観、思想に没頭することを目指す。そして論理レベルでの理解をするための「詳細読み」に加え、著者がその部分を書いていたときを想像することが必要である。
大学の教員が行っている授業は、ある思想家や研究者の「考え」を自分の言葉で語るという作業であるため、この「究極の同化読み」の良い訓練になっている。
そのような作業を繰り返していると、自分がその本のすべての部分を「的確に、何の曇りもなく説明できる」という、一種の「錯覚」に陥ることがあります。(抜粋)
この種の同化読みをするためには、著者や書籍をことさら注意深く選ぶ必要がある。
「批判読み」
「批判読み」とは
本書は「同化読み」を中心に扱っているが、本読みの方法はそれだけでなく、この本は怪しいぞと疑いながら読む「批判読み」もある。
本は出来るだけ「悪い本」は、読まないことが基本である。しかし「評価の定まっていない本」を読む必要があったり、最近はやっている本に関して「その内容を押さえておきたい」と考えたりする場合もある。
そのような本を「同化読み」するのは危険である。そのような「誤りを含む」可能性がある本を読む場合は「批判読み」が役に立つ。
ただし、「ハイキング型の本」を「登山型の本」と思って読んだり、「開いている本」を「閉じている本」と思って読むと、「論理展開が不明瞭」「概念の定義が不明確」「著者の主張がわからない」などと思ってしまうので、本のタイプをしっかり見極める必要がある。
批判読みの方法
基本的な方法は同化読み(ココ参照)と同じである。ただし、不明確な概念や、不明瞭な論理展開が存在した場合、それを丹念に追わずに「著者の誤謬」だと考える方法を取る。
- 用語・概念が不明確である。
- 論理展開が不明確である。
- 本文で扱おうとする問題が不明確である。
の3つの事態に遭遇した場合、以下のように検証する。
- .読書ノートで関連部分の周辺を探し、その概念や論理展開、問題に関しての記載がないかどうかを確かめる。また、論理展開が不明確である場合には、ある主張にいたる論理的筋道を探索しながら読書ノートに引き写して、矢印でつないでいく。
- その分野の解説書などを参考にして、概念の使用法や論理展開、問題が、一般的に使用されているものであるかどうかを確認する。もしくは、その分野に詳しい人に質問してみる。
- 著者がその用語や概念に「特殊な意味」を持たせていると考えられる場合や、論理展開が特殊な方法である場合、もしくは、一般的な問題と異なる場合など、それに関して説明がなされている部分を探す。また、何を目的として「一般的でない表現」を採用しているのかを考え、読書ノートにメモしておく。
- 上記の①~③の方法を試しても、まだ不明確であり、その部分の目的や役割が不明瞭である場合には、読書ノートに「この概念は不明確」「論理展開が不明確」「問題が不明確」などとメモしておく。
批判読みの意義
読書では、このような読み方が必要な本もたくさんある。ここで著者は、だからといってそのような本が「悪い本」であると言えないと注意をしている。
概念を一つ一つ正確に積み上げていく本ばかりが「よい本」ということではなく、比較的曖昧な概念を使って、見事な思想へと読者を導くという種類の本もたくさん存在しています。(抜粋)
明確さに欠ける概念や展開によって書かれた本は「批判読み」をすることによって「同化読み」に劣らない充分な理解に達することが可能である。
著者は、この「批判読み」をする秘訣は、「やさしくなる」ことだとしている。概念が論理的でなかったり、矛盾していたりする場合などは、著者の側に立ち一歩踏み込んで、理解してあげることである。
この批判読みに習熟してくると、その本の問題点を指摘する過程で、新しい論点や、論理の筋道が見えてくることがあります。(抜粋)
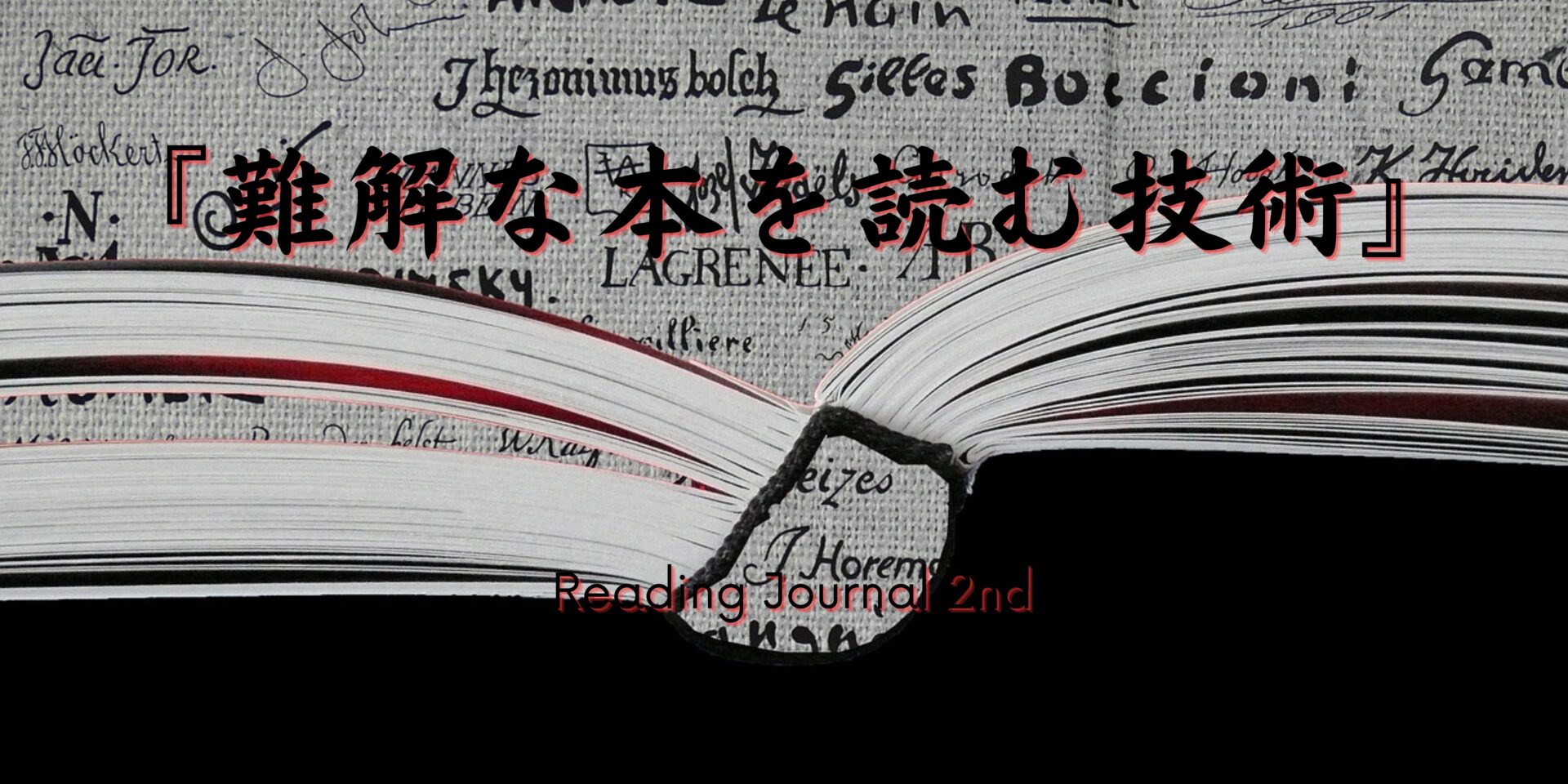


コメント