『難解な本を読む技術』 高田 明典 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第5章 さらなる高度な本読み(その2)
今日のところは「第5章 さらなる高度な本読み」の“その2”である。“その1”に続き、ここでは「包括読み」・「縦断読み」、「系統読み」という高度な読みについて書かれている。
この「包括読み」・「縦断読み」は、あるテーマに沿って多くの本にあたり、そのテーマに関する地図を作ることを目的とする。そして、その地図ができたら、次に行うのが「系統読み」である。それでは読み始めよう。
「包括読み」・「縦断読み」 — テーマに関する地図を作る
「包括読み」とは
「包括読み」とは、あるテーマを設定し、それについて記述される様々な本を読むことによって、そのテーマの地図を作ることである。
また、「包括読み」の一種に、ある概念に関する「変化の過程」に主眼を置くものを「縦断読み」と呼ぶ。
この「包括読み」では、これまでの技術と違い読書ノートをとらずに「読み捨てる」本が重要な役割を担う。「包括読み」では、テーマ中心で書物を渉猟していく。
ここで大切なのは、詳細なノートは取らないが、「文献リスト」としてのメモを取っていくことである。
テーマを把握する
まず自分が興味を持った「テーマ」を正確に把握することから始める。このテーマは最初のうちは漠然としているため、多くの本に触れ、思想家がどんな文献を残しているかを把握する。この時の方法は「第2章」の方法と同じだが、「包括読み」では、出来るだけ多くの本に直接触れることが必要となる。
このような作業を通して、次第に「テーマ」が具体的な言葉となって認識される。そのようになったら、「自分の知ろうとするテーマ」を、文字にすることが重要である。
「文献リスト」を作る
このようにして、基本文献のおおまかなイメージが見えてきたら、それらの基本文献をメモして「文献リスト」を作る。
文献リストは、大学ノートやレポート用紙、もしくはPCの文ファイルなどで作り、以下の項目を記入する。
- 著者名
- 訳者名(翻訳の場合)
- 書名
- 出版社
- 発行年
- 余白のメモ
大学ノートやレポート用紙の場合は、1冊に1ページをあて、多くの余白を作る。
注意しなければならなのは、文献リストに載せるものは原則として、少なくとも「見る」つもりのもの、すなわち「一度は通読」するものに限定するということです。(抜粋)
そうしないと、すぐに大量のリストになってしまう。
入門書・概説書で「文献リスト」を補充する
この「文献リスト」が出来上がってから、その「問題」をもっともよく扱っていると思われる入門書・概説書を購入する。
「包括読み」とは、先に作成した文献リストと、ここで購入した入門書・概説書を「ガイド」として、その分野を探検していくことだと言えます。(抜粋)
入門書・概説書は、
- 各章ごとに、参考文献表がある
- その表に、日本語に訳されている文献があげられている
- 人名索引/事項索引がついている
- おおむね300ページ未満である(少ないほうがよい)
を満たすものを購入する。
購入した入門書・概説書を参考にしながら、自分の文献リストを充実させる。
- 自分の文献リストに載っていないものがあれば、それをリストに載せるかどうか考える。
- リストに載せたものについて、必ず何らかメモをしておく。:あとでその本の位置づけがわかるようにメモをする。
- すでに自分のリストに載っている場合は、そのメモ欄に追記しておく
読むべき本を選定する
このようにして作った文献リストをもとに「これは読んでおかなければいけないな」と思われるものを決定する。決定したら文献リストのメモ欄に記入。
自分の専門分野以外のことに関しての知識を効率的に得ようとする場合、多くの研究者は、まず「包括読み」のようにその分野の全体像から理解する方法をとります。それは、「大枠からの理解」によって、情報を集めやすくなるという理由があるからです。(抜粋)
「系統読み」 — テーマに沿っての読書
「包括読み」により文献リストが出来たら、今度はその基本文献を読む作業になる。あるテーマに沿って多くの基本文献や名著を丹念に読む必要がある。しかし、そのすべてを読むのは、いくら時間があっても足りない。
そこで、体系立てて本を選び読み進めていくのが「系統読み」である。
ここで、包括読みによる「文献リスト」を作ってあることが前提である。そして、まず読書に充てる時間と期間をおおまかに決める。そこから逆算して、読書する本の冊数が決まる。
この系統よみでは、文献リストよりその冊数の本を選ぶことになる。その場合、互いに関連ある文献を選ぶことに念頭を置く。まず文献リストから「基本文献」を1冊、2冊選ぶ。そして選んだ本が根や茎となっていると考えられる本を選んでいくようにする。
そのようにして、選書しあるテーマについて系統だて読書をする。読書する際にも読書ノートを作る際にその系統を意識し、選書した本の影響などが感じられる場合はそれも記入してメモを残すようにする。
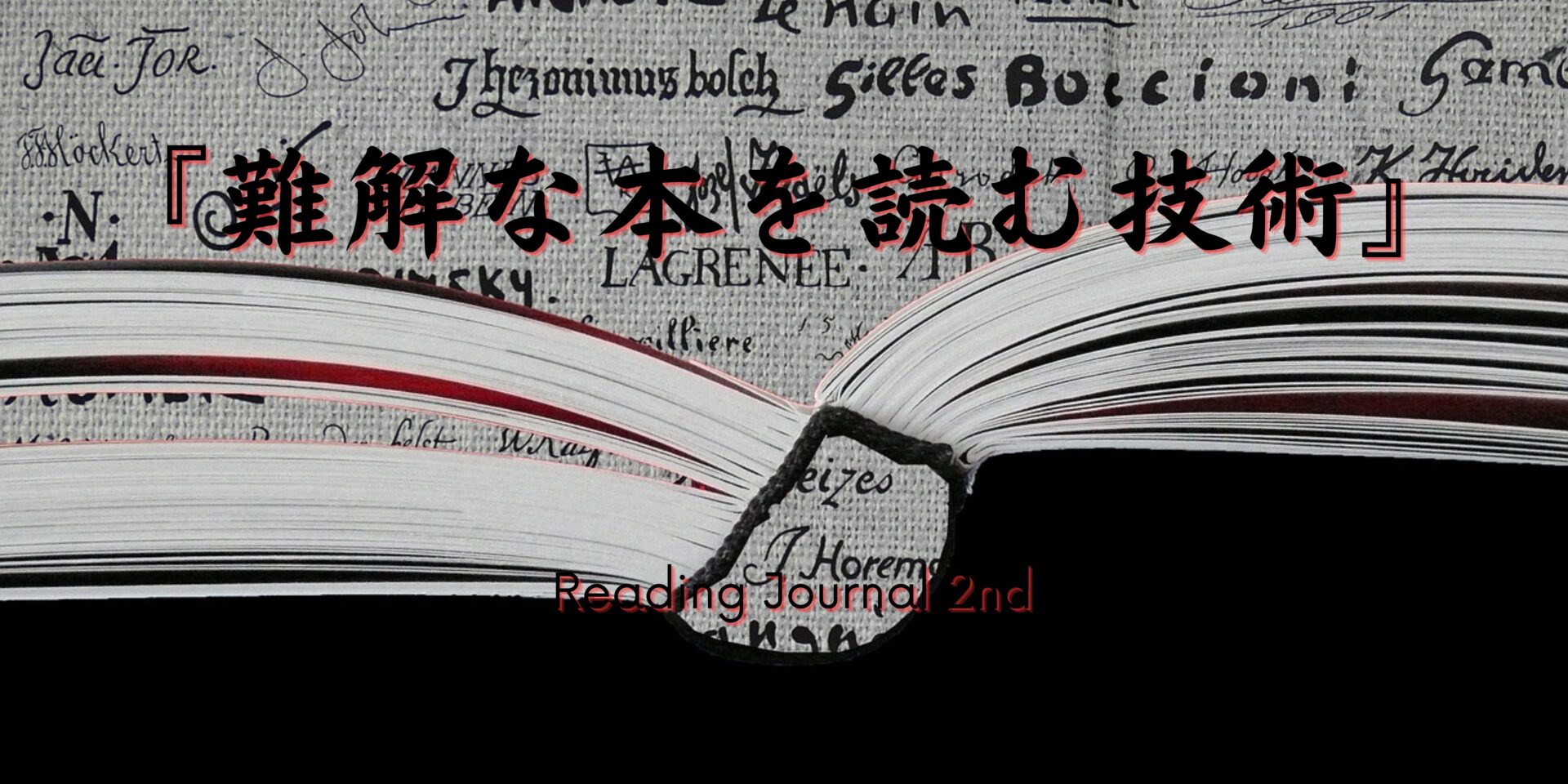


コメント