『「モディ化」するインド』湊 一樹 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2章 「カリスマ」の登場(その3)
今日のところは、第2章の“その3”である。“その1”、“その2”でモディが権力の階段を駆け上がり、グジャラート州首相に昇りつめた。さらに首相になってから起こった「グジャラート暴動」までの足取りをおった。今日のところ“その3”では、モディが、州首相としてグジャラート暴動での責任をどのように回避し権力を固めたかについてまとめる。では、読み始めよう。
「暴力の配当」としての権力
グジャラート暴動後の政治と産業界の反応
前回、著者が「グジャラート暴動」の解説に使った「イギリス政府の報告書」では、インド人民党(BJP)の会議においてインド首相のヴァージペーイによりモディが交代させられるかもしれないと書かれていた。しかし、実際にはその予想は外れてしまう。
実際、ヴァーチペーイは、モディを州首相の地位から降ろそうとしたが、結局はRSSの強硬派は屈服してしまう。また、当時は、BJPを中心とした連合政党である国民民主連合(NDA)であったが、グジャラート暴動のために参加政党が離脱し、政権が崩壊するとの予想もあった。そのためBJP内でもモディの責任を追及しようとする勢力があった。しかし、実際には離脱した政党は三党のみであった。そのため、グジャラート暴動の責任をだれも取ることなしに、モディは引き続き州首相を務めた。
産業界もモディ率いる州政府の対応を批判し、投資先としてのグジャラート州に疑問を持っていた。しかし、政治と同様に産業界も巧みな策略に屈してしまう。
モディは、暴動の発生直後から現在まで一貫して、自らの責任を一切認めず、遺憾の意も釈明もしていない。そしてインドを代表する実業家たちに向かって、自己正当化の言葉を並べ立てた。また、グジャラート州出身の実業家を集めて「グジャラート再生グループ」を組織して圧力をかけた。
二〇〇二年選挙での圧勝
このように産業界に強い態度に出られた背景は、グジャラート暴動から一年もたたずに実施した選挙(二〇〇二年)でのBJPの圧勝がある。
つまり、モディがグジャラート暴動について謝罪どころか釈明さえしないのは、選挙での勝利を自らへの無罪判決であるかのように都合よく解釈しているからにほかならない。・・・中略・・・・別な見方をすれば、非民主的な行動や言動のすべてを正当化するためには、モディにとっては選挙での勝利が絶対に必要なのである。(抜粋)
暴動から間をおかずに行われた、この二〇〇二年の選挙では、モディがイスラム教徒に対する嫌悪に満ちたヘイトスピーチを行った。
これらの発言は、「イスラム教徒の人口爆発よってヒンドゥー教徒が少数派に転落し、インドがイスラム勢力に乗っ取られてしまう」という、ヒンドゥー至上主義勢力が拡散し続けてきた陰謀論にもとづくものである。(抜粋)
選挙では、ゴードラでの列車炎上をきっかけに起こったグジャラート暴動を追い風にかえ、BJPは、国境を接するパキスタンからのテロの脅威を強調して、イスラム教徒を「内なる敵」と位置づけるなど、ヒンドゥー至上主義を全面にい出す選挙運動をすすめた。そして、BJPは、前回を上回る議席を獲得し州政権を維持する。
選挙の裏側
ここで著者は、グジャラート暴動の死者数に関する実証研究に着目し、暴動がヒンドゥー至上主義勢力に冷徹な計算によって行われていると言っている。この暴動による死者数には、地域差があるが、研究により二つの点が明らかになっている。
- 多くの死者が出た地域は、前回の選挙でBJPが対立候補と激しく競り合った地域である。反対にBJPが圧倒的に有利もしくは不利な地域は、死者数が少なかった。
- 多くの死者が出た地域ほどBJPの得票率が大きく上昇した。
つまり、この暴動がBJPの狙い通りに機能したことがうかがわれる。
BJPは、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の間に宗教間の対立と分断を作り、ヒンドゥー教徒の支持を集めた。
ただし、モディが一二年以上にわたって州政権を率い、さらには国政へと一気に躍り出ることになった原動力はそれだけでなない。「グジャラート・モデル」という言葉に象徴されるように、同州での「開発志向のガバナンス」の実績をすべてモディ州首相の手腕に帰するPR戦略もまた重要だった。この点は、ヒンドゥー至上主義者としての顔を隠すために、イメージ転換を図ろうとする狙いがあったことも深く関係している。(抜粋)
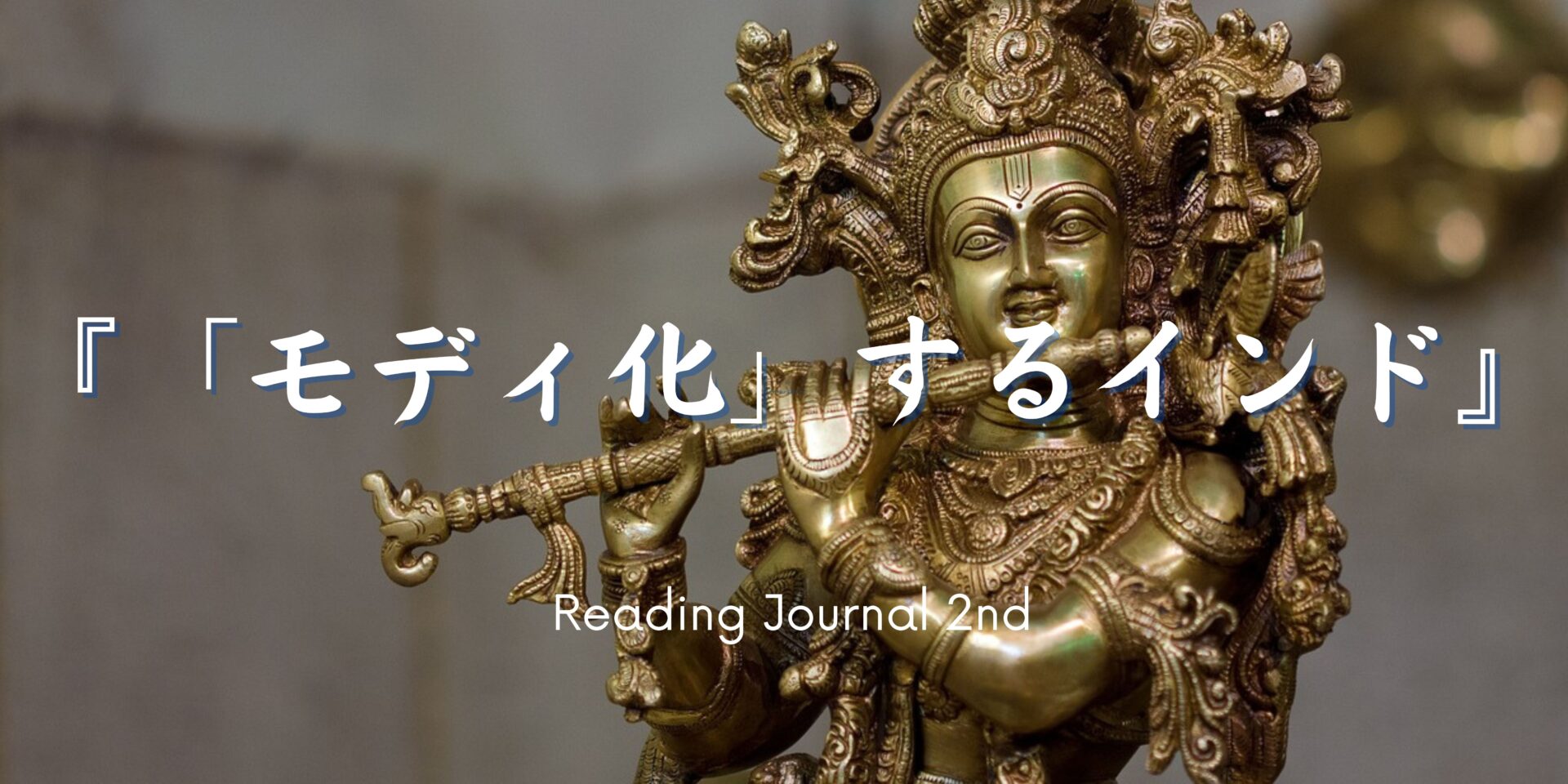


コメント