『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』 北川前肇 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第3回 「ほんたうのたべもの」としての童話(その3)
宮沢賢治の童話には、前回、その2の「どんぐりと山猫」のような軽妙洒脱な作品もあるが、現実社会を反映したような弱い者が強者に抑圧される物語もある。今日のところ、“「ほんとうのたべもの」としての童話”のその3では、そのような童話として「よだかの星」が取り上げられている。
「よだかの星」の救い
「よだかの星」は次のような文章で始まる。
よだかは、実にみにくい鳥です。 顔は、ところどころ、味噌をつけたようにまだらで、くちばしは、ひらたくて、耳までさけてゐます。 足は、まるでよぼよぼで、一間とも歩けません。 ほかの鳥は、もう、よだかの顔を見たゞけでも、いやになってしまふという工合でした。(『全集』8巻、一九九五)(抜粋)
そしてよだかは、ほかの鳥たちにばかにされ、名前が似ている鷹からは、改名しないと殺すと脅かされる。
ある夜、よだかが飛んでいると、カブトムシが喉に入る。それを、飲み込んでよだかはこう思った。
(あゝ、かぶとむしやたくさんの羽虫が、毎晩僕に殺される。そしてそのたゞ一つの僕がこんどは鷹に殺される。それがこんなにつらいのだ。あゝ、つらい、つらい。僕はもう虫をたべないで飢えて死なう。いやその前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向ふにいってしまはう。)(同前)(抜粋)
そして、よだかは太陽や夜空の星々のもとに向かったが、ここでも拒絶され絶望して地面に落ちかける。しかし、地上すれすれのところで再び舞い上がり、空高く昇って行き、静かに燃える美しい青い光になる。それがよだかの最期であった。そして、よだかの星は、今も静かに燃え続けている。
著者は、この結末がハッピーエンドかどうかは、読む人にゆだねるとしているが、自身はひとつの救いがあると受け止めているといっている。
よだかは、「差別」され苦しめられる存在だが、自分もほかの生き物を食べなければ生きていけないという宿命を持っている。よだかは、自分自身にも苦しみを抱えていたが、その苦しみを抱えて、最後、自分のありったけの力をふりしぼり空の彼方へのぼる。
そのような、よだかの姿を見て著者は次のように言っている。
仏教では、自分に内在する煩悩や美醜、上下の区別などのさまざまなしたらみのことを「繫縛」といいます。私は、よだかが天に向かっていく力に、繫縛を超えていこうとする強い意志、そして賢治の願いを感じるのです。 最期、よだかは「燐の火のやうな青い光」になります。そして「たしかに少しわらって」いたのだと書かれています。ここに繫縛から解放され救われたよだかを感じるのは、私だけでしょうか。(抜粋)
著者は、「よだかの星」に描かれているのは、私たちの人間社会における差別の問題であるとしている。そして賢治は、差別されるよだかを残酷なまでに詳細に描くことで、人間社会の問題を訴えた。そして、それは苦悩している私たちの「実相」であると指摘している。
賢治の童話のメッセージ
著者は童話集・『注文の多い料理店』の序文(ココ参照)から賢治は、自分の童話を「こう読むべきだ」という書き方をしていない、わかる人もいればわからない人もいるでしょうと、すべてを読者にゆだねている、と指摘している。そして最後に次のように言って第3回を締めくくっている。
私はこの序文に、宮沢賢治という人の慈愛を強く感じます。彼は感じたものを感じたまま描いて、「あなたも好きなように感じていいんですよ」と、少しも押しつけることなく「どうぞ召し上がれ」と差し出しているのです。わからなくてもいい、その一部だけでも「ほんとうのたべもの」になればいい。そんな賢治の温かな願いは、彼が生涯かけて目指した菩薩のような生き方につながっていると思うのです。(抜粋)
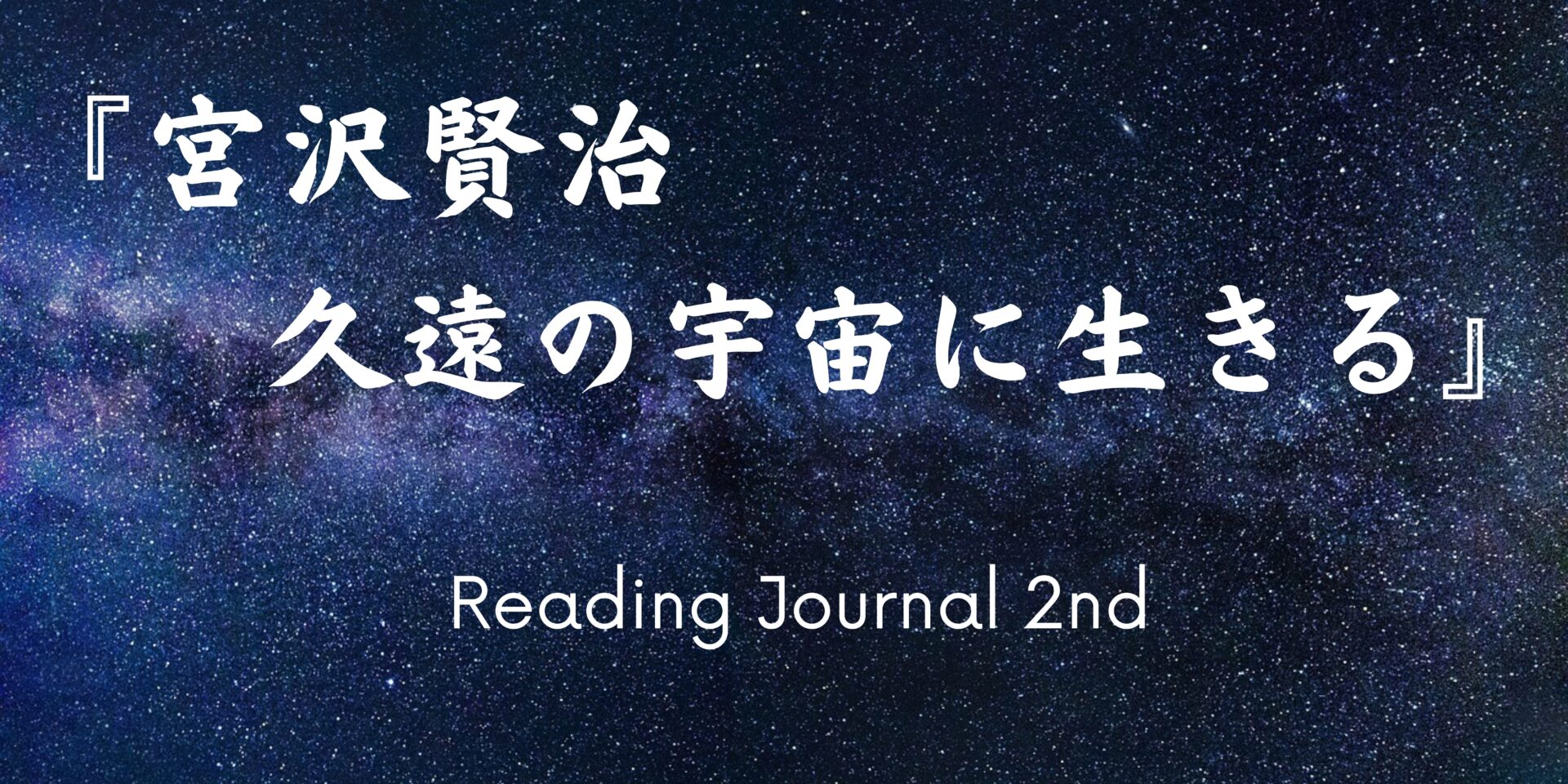


コメント