『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』 北川前肇 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2回 「春」と「修羅」のはざまで(前半)
第2回目は“「春」と「修羅」のはざまで”である。宮沢賢治が生前に出版したのは、『春と修羅』、『注文の多い料理店』の2冊であるが、第2回では、そのうち『春と修羅』をとりあげ、その法華経との関係を解き明かしている。この第2回も前半と後半に分けてまとめるとする。まず、今日のところ前半では、賢治の創作活動の開始とともに『春と修羅』の内容についてである。
創作の始まり
宮沢賢治は、大正九年に盛岡高等農林学校を終了した後、実家の家業を手伝っていた。しかし、大正十年に家族に無断で東京に向かって旅立つ。そして、上野の国柱会館に行って、下足番でもビラ配りでもなんでもするのでおいてくれと頼みこむが、断わられた。そして昼は近所の出版社で働き、夜は国柱会の会合などに出席していた。
日蓮主義の立場では、自己の職業や能力を持って社会に貢献することが、信仰の証であるとされる。そして、国柱会もそのような活動の多面性を持っていた。国柱会の理事であった高知尾智耀は、詩歌文学が得意な賢治に「作品には純粋に法華経信仰がにじみ出るようでなければならない」と諭さし、賢治の創作活動が始まった。
その後、賢治は花巻で教職についていた妹・トシの発病を機に、八カ月の東京生活を終えて、帰京した。
急いで帰京した賢治は、大きな茶色の皮のトランクに自筆の原稿をいっぱい詰め込んでいたそうです。(抜粋)
『春と修羅』の意味
賢治は、大正十年に花巻の稗貫農学校(のちに花巻農学校と改名)の教員となる。その後に書き留めた六十九編の詩をまとめて、大正十三年に『春と修羅』を自費出版する。
まず著者は、『春と修羅』の序を引用している。
わたくしといふ現象は
仮定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です
(あらゆる透明な幽霊の複合体)
風景やみんなといつしよに
せはしくせはしく明滅しながら
いかにもたしかにともりつづける
因果交流電燈の
ひとつの青い照明です
(ひかりはたもち、その電燈は失はれ)(抜粋)
著者は、ここで、なぜ自分のことを「現象」というのか?なぜ「明滅しながら」「ともりつづける」照明にたとえるのか?
その答えを求めるために、まずは「春と修羅」というタイトルから謎に迫るとしている。
この「春と修羅」は、作品集の題名でもあり、また一つの詩の題名でもある。
まずこの「春」を考えると、それは単なる季節の春ではないと、著者は指摘する。それは「修羅」との対応で考える必要がある。
「修羅」は、「阿修羅」の略で、常に戦闘をしている悪神である。その悪心が住む修羅界は、人間界よりも下位にある。そして、賢治は自分のなかの修羅を見つめて、「春と修羅」というタイトルをつけた。そう考えるとここの「春」は修羅とは逆の「仏界」のことを示している。
「春」と「修羅」という正反対の言葉を並べているところに、賢治の言語感覚の鋭さと、心の葛藤が表れていると私は思います。(抜粋)
十界と一念三千
ここで、天台教学の「十界」と「一念三千」の説明がなされている。
十界
「十界」とは、上から「仏界、菩薩界、縁覚界、声聞界」、ここまでが悟りの世界で四聖と呼ぶ。
そしてその下が、「天上界、人間界、修羅界、畜生界、餓鬼界、地獄界」で、これを六道といい、仏教では私たちが人生を終えると、六道のいずれかに生まれ変わるとし、これを六道輪廻と言う。
さらに、「人間界」より下の「修羅界」は、暴力に満ちた安らぎのない世界とされ、その下の「畜生界、餓鬼界、地獄界」は、「三悪道」と呼ばれる。
一念三千
「一念三千」であるが、上の十界の一つひとつの世界に、それぞれ他の九つの世界が具有されているとする。すると「十界×十界」で百界となる。その「百界」はそれぞれ「十如是」(十種の真実相)を備えているので、千如是となる。さらにそれぞれが「三世間」(五陰世間・衆生世間・国土世間)に渡っているので、「三千世間」となる。
この「三千世間」が宇宙の中のすべての事象(諸法)を含んでいて、私たちの一瞬の心の動きの中にも含有されているとする。
そして、この存在論のことを「一念三千」といい、これが天台教学のかなめとなる思想である。
この「一念三千」であるが、『日蓮 「闘う仏教者」の実像』にも、たびたび出てきて、日蓮の到達点とされている(ココとか、ココとか、ココを参照)。が、しかし、よくわからないのでした。(つくジー)
「副題:心象スケッチ」の意味
次に著者は、詩「春と修羅」の副題”menral sketch modified”(心象をスケッチして修飾したもの)を手がかりに、先の疑問—なぜ自分のことを「現象」というのか?なぜ「明滅しながら」「ともりつづける」照明に、自分をたとえるのか?– の答えを探っていく。
著者は、これはみずからの揺れ動く心のありさまと、それを映し出す風景を「スケッチ」のよう感覚的に描いたと、というものだとしている。そして、この詩には「一九二二・四・八」とあえて日付をつけ、「今の自分の心象をスケッチした」と主張しているとしている。
著者は、この賢治の姿勢に、仏教の基本思想である「諸行無常」を感じると言っている。諸行無常とは、「万物は移り行く」と言う意味である。私たちは無常の存在とし、今ここにあり、次の瞬間に消滅する。
仏教では、長い時間のことを「劫」(カルパ)といい、短い時間のことを「刹那」と称する。そしてその短い時間が生滅することを「刹那生滅」といい、この世はすべて明滅の現象と考える。私たちは自分のことを「連続して存在する」と思っているが、そうではなく、「明滅しながら」「ともりつづける」照明のように、ある瞬間に消滅し、また次に瞬間に生まれている。
賢治が序文で「わたくしといふ現象」と書いたのは、そんな無常の存在として自分を表現したのではないでしょうか。過去でも未来でもなく、間違いなく今、この瞬間に集約された自己を認識しようという意思がそこに表れています。(抜粋)
一瞬・一瞬、消えては無くなる私たちの心は、まさに明滅する「有機交流電燈」である。そしてそこには、全宇宙の事象のすべてが含まれる、まさに「一念三千」である。すなわち、自分の心象をスケッチすることで宇宙全体を見つめようとしたのである。
賢治は、迷っている自分を「現象」と呼び、「心象スケッチ」という形で切り取りました。それは「有限である自己」に責任をもち、一瞬ごとに移ろうと自己と世界を認識しようという覚悟の表れだったのかもしれません。(抜粋)
どんな「現象」をスケッチしたか
ここより、詩「春と修羅」の冒頭から、賢治がどんな「現象」をスケッチしたかを考えている。
心象のはいいろはがねから
あけびのつるはくもにからまり
のばらのやぶや腐植の湿地
いちめんのいちめんの諂曲模様(前掲『全集』2巻)(抜粋)
この詩は、一行目から心の陰湿な部分をあらわしている。そして、著者は「諂曲」という言葉に注目する。
そして、「諂曲」。これは他人におもねることであり、「修羅」です。本当は「こうしたい」と言う思いがあるのに、他人に慮って意思をねじ曲げてしまう。現代に生きる私たちにも、そんな葛藤を抱くことがあるでしょう。賢治は、そういう自分の状況と自然描写をマッチさせながら、この四行で修羅の世界を適切に表しました。(抜粋)
そして、著者は、この葛藤は、価値観と価値観のぶつかり合い、すなわち父、政次郎との確執があったと指摘している。
賢治は、父と対立しながらも、並々ならぬ恩義も感じている。父に反発しながらも申し訳なく思っている。そのような二律背反の感情を「修羅」という言葉で表している。
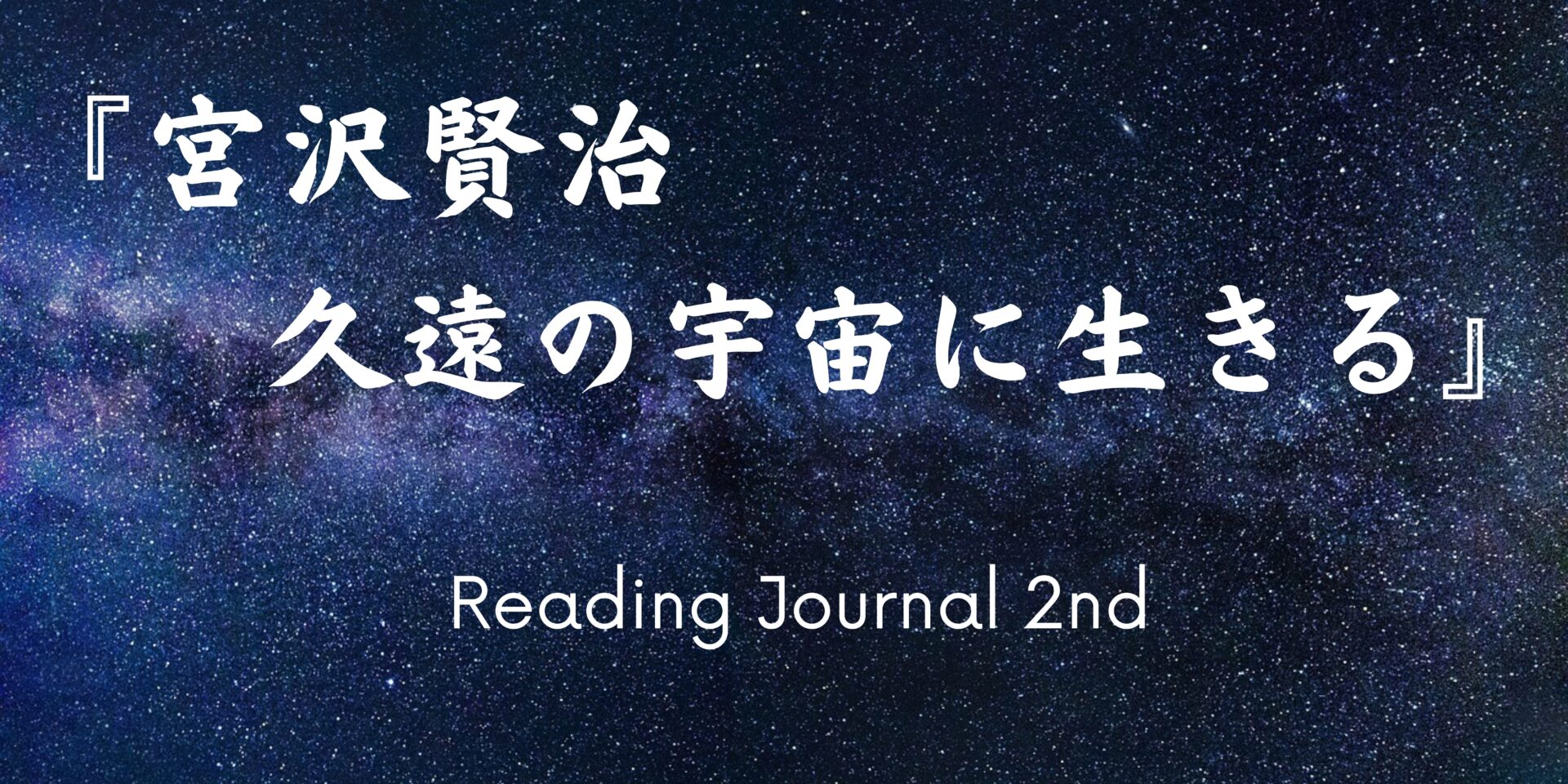


コメント