『行動経済学の使い方』大竹 文雄 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第3章 仕事の中の行動経済学(後半)
今日のところは、第3章「仕事の中の行動経済学」の“後半”である。”前半“では、タクシー運転手の研究とプロゴルファーの研究により、実際の仕事の中で参照点により行動が変化することが示された。今日のところ”その2“では、同僚が与える影響「ピア効果」についてである。それでは読み始めよう。
ピア効果
職場などで同僚が他の労働者の生産性に与える影響は「ピア効果(同僚効果)」と呼ばれる。たとえば、職場に生産性の高い同僚が入ってきた場合の変化の可能性として、行動経済学的に考えると
- 優秀な同僚の働きぶりを無意識に参照点にすることで、自分の努力水準が高まる
- 自身の互恵的選好のため、生産性の高い同僚が与える恩恵に報いるため努力する
- 社会的プレッシャーのために努力する
- 優秀な同僚から知識や技術を学び生産性が高まる
などの可能性がある。しかし、このピア効果を実証するためにはさまざまな課題があり、実際には難しい。ここではそのような課題を克服した研究例を2つ紹介されている。
スーパーマーケットのレジ打ち
アメリカのスーパーマーケットでのレジ打ち従業員に対するデータを使ってピア効果を測定した研究がある。
その結果、同僚の生産性が高いと働いている従業員各個人の生産性が上昇することが明らかになった。同僚の生産性が10%上昇すると、その職場の他の従業員の生産性は1.5%上昇するという結果であった。
ここで著者は、その結果よりもピア効果が発生する理由の方が興味深いとしている。レジ打ちの従業員は一列に並んでいるため、自分の前方にいる同僚の仕事ぶりは観察できるが、反対に、後方にいる同僚からは自分の働きぶりが観察されている。研究では、「生産性の高い同僚から見られている場合に生産性が高まり、生産性の高い労働者を見ている場合は、自分於生産性は影響を受けない」というものだった。そして、後方にいる同僚の生産性の高さを知っている場合のみこの効果は表れる。つまり「背中から生産性の高い労働者の視線を感じることが社会的プレッシャーになって努力水準が高まる」という仮説(上の④)と整合性がある。
つまり、同僚からの社会的プレッシャーというルートを使ってピア効果が発揮されていることがわかる。
競泳のタイム
次に日本の研究者による「競泳のタイム」に関する研究が紹介されている。この場合は、他の競技者と競争しているため、他人の生産性にただ乗りはできない。
この研究では、「日本の小学生から高校生までの水泳大会の100メートルの自由形と背泳ぎのタイム決勝のデータ」である。水泳の「タイム決勝」とは、すべての選手がベストタイムの近い人で構成された、いくつかのグループで泳ぎ、そのタイムで勝敗を決める方法である。この場合、優勝するためには同時に泳ぐ選手(ピア)の実力とは無関係に最大の努力をしなければならない。
つまり、隣が誰であれ全力で泳ぐというインセンティブ(行動を起こさせる刺激や動機)が選手にはある。それにもかかわらず選手たちはピア(隣の選手)に影響されるかを調べるのがこの研究の目的である。
まず自由形の場合は、隣の選手の場所を確認できるが、背泳ぎの場合は確認できない。さらに両側のコースに選手がいない状況も発生する。このような状況でピアの存在がどのように影響するかを調べた。
自由形のデータでの研究結果は、「自分より(ベストタイムが)遅い選手が隣のレーンにいる時には、両隣に誰もいない時(一人で泳いだ時)よりも速く泳げるが、自分より(ベストタイムが)速い選手が隣にいると一人で泳いだ時よりも遅くなってしまう」。そして背泳ぎのデータでの研究結果では、ピアの効果は観察されなかった。
この結果は「自分の隣のレーンで泳ぐ選手のスピードが参照点になって、ベストタイムが遅い選手に負けることが損失と感じられる」という仮説(上の①)と整合的である。
同じ研究チームは、水泳選手が所属チームを変更した場合について調査し、可優秀な選手が選手がチームすると、元からいる選手たちのタイムが向上することも明らかにしている。これは努力や技術の向上を通じたピア効果によると考えられる(上の④)。
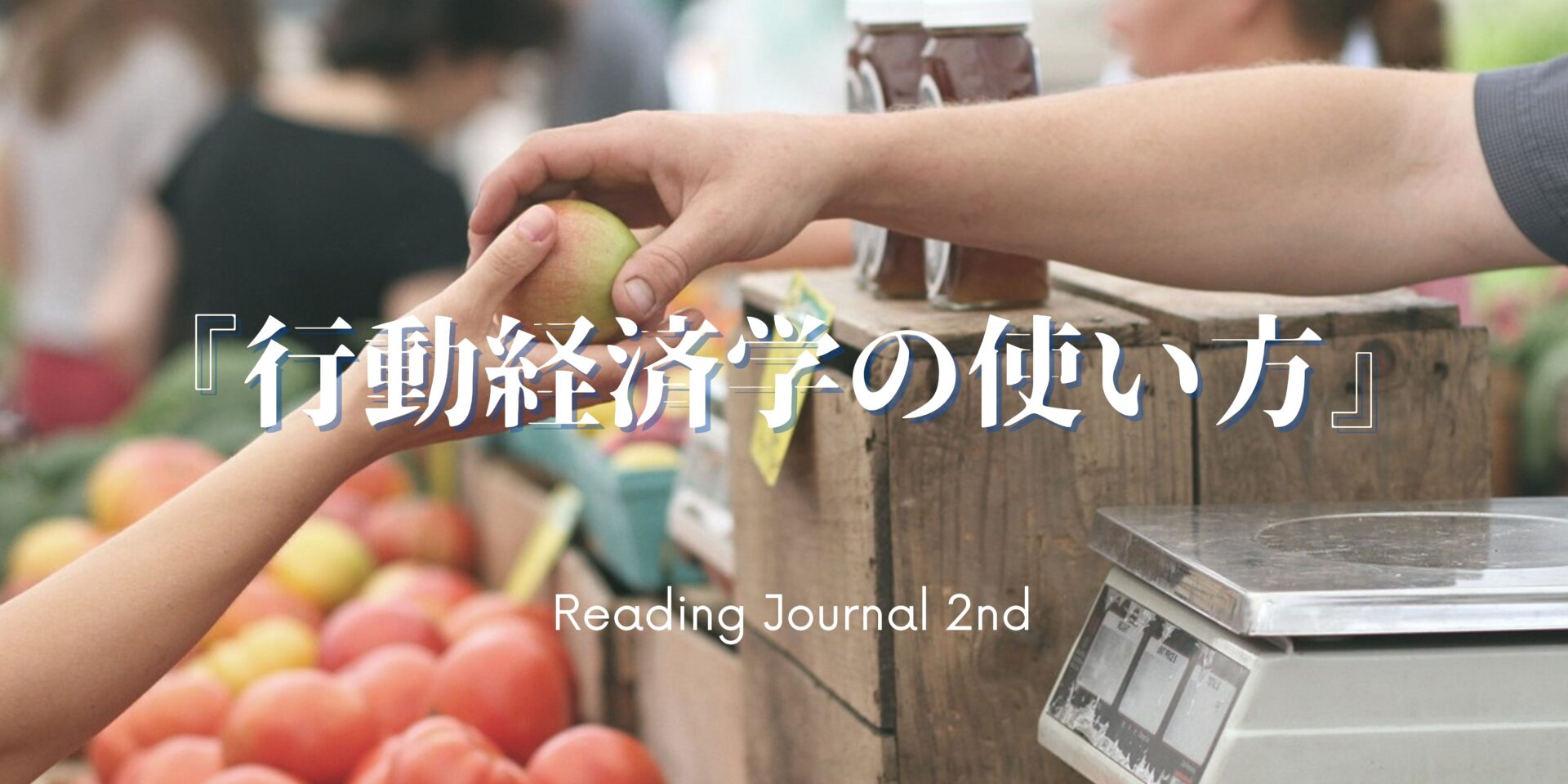


コメント