『行動経済学の使い方』大竹 文雄 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2章 ナッジとは何か(後半)
今日ところは、第2章「ナッジとは何か」の“後半”である。”前半“は、行動経済学でいうナッジとは何か、その作り方かたであった。今日のところ”後半“は、ナッジを作った際のチェックリスト、そしてその実例についてである。では読み始めよう。
ナッジチェックリスト
ナッジを設計した場合、それが適切であるかをチェックするためのチェックリストが複数提案されている。
Nudges
“Nudges”は、セイラーとサンスティーンにより作成されたチェックリストである。
- インセンティブ(iNcentive):対象者のインセンティブを考える
- マッピングを理解する(Understand mapping):意思決定プロセスをマッピング(図式化)しどこにボトルネックがあるかを明らかにする
- デフォルト(Defaults):望ましい選択がデフォルトとなっていれば利用する
- フィードバックを与える(Give feedback):本人がとった行動の結果をフィードバックできるように考慮する
- エラーを予測する(Expect error):選択ミスを予測し、修正する
- 複雑な選択を体系化する(Structure complex choices):全体を体系化し複雑な思考をしなくても望ましい選択ができるようにする
EAST
“EAST”は、イギリスのナッジ設計部門(Behavioural Insights Team:BIT)によるチェックリストである。
- E (Easy) : 簡単であるか、情報量が多すぎないか、手間がかからないか
- A (Attractive) : 魅力的なものになっているか、人の注目を集めるか、面白いか
- S (Social) : 社会規範を利用しているか、多数派の行動を強調しているか、互恵性に訴えているか
- T (Timely) : 意思決定をするベストのタイミングか、フィードバックは早いか
MINDSPACE
“MINDSPACE”は、EASTと同じくBITによるチェックリストである。
- M (Messenger): 情報を与える主体
- I (Incentives): インセンティブに対する反応を考慮する
- N (Norms): 社会規範
- D (Defaultes): デフォルト
- S (Salience): 目立つかどうか
- P (Priming): 「プライミング」という心理学用語。無意識の手がかりに私たちの行動が影響されることを表わす。(先行情報が無意識に行動に影響するなど)
- A (Affect): 情動。私たちの意思決定は感情に左右されること
- C (Commitments): 確約。公の場で確約したことや自分自身で決めたことに整合性のある行動をとる傾向。恩に報いるような互恵的な行動
- E (Ego): 自我。自分自身の満足度が高まるように行動するということ
ナッジの実例とナッジへの批判について
ナッジの実例
ここで著者は、「老後貯蓄の意思決定」「自然災害の予防的避難」の具体例を通してどのようにナッジが作られていくのかを解説している。
ナッジへの批判
このようなナッジに対しては、「人々の選択を特定の方向に誘導する」ことを危険視する批判がある。
ナッジを利用する政府は、人々が自身のためになる選択を自分でできないと考え、人々のためになるように、選択に影響を与えたり、修正したりする手段を提供すべきであるという温情主義的な考え方を背景に持つ。そして、ナッジに批判的な人はその温情主義的な政策に反対する。ナッジは、見えないところで人々を操作しているように感じさせるために拒否感を持っている。
そしてナッジに反対する人は、この温情主義が人々の厚生水準を下げるのではないかと心配をしている。この厚生水準を下げるという理由として
- 人々の好みは多様であること
- 人々は間違った意思決定をし、そこから学習をしている。ナッジはその学習の機会を奪ってしまう
- ナッジを作る政府や官僚にもバイアスがある
- ナッジにより特定の製品が好まれると自由な市場競争に影響がでる
といものである。
著者は、①については、ナッジは選択の自由が保障されていること、そして必ずしも自由な選択が本人の満足を高めることにならない。②については、人生に何度も行われないようなナッジには当てはまらないこと、情報や学習機会を提供するようなナッジならば問題ない。③については、政府がナッジを用いる際は、透明性と説明責任で対応すべき。④についてはもともと伝統的経済学においても市場が失敗した場合は政府の介入がある。ナッジは市場が失敗する場合に、外部性を減らしたり、市場競争を促進したりするような形で導入されるべきもので、市場競争と対立するものではない、とそれぞれ反論している。
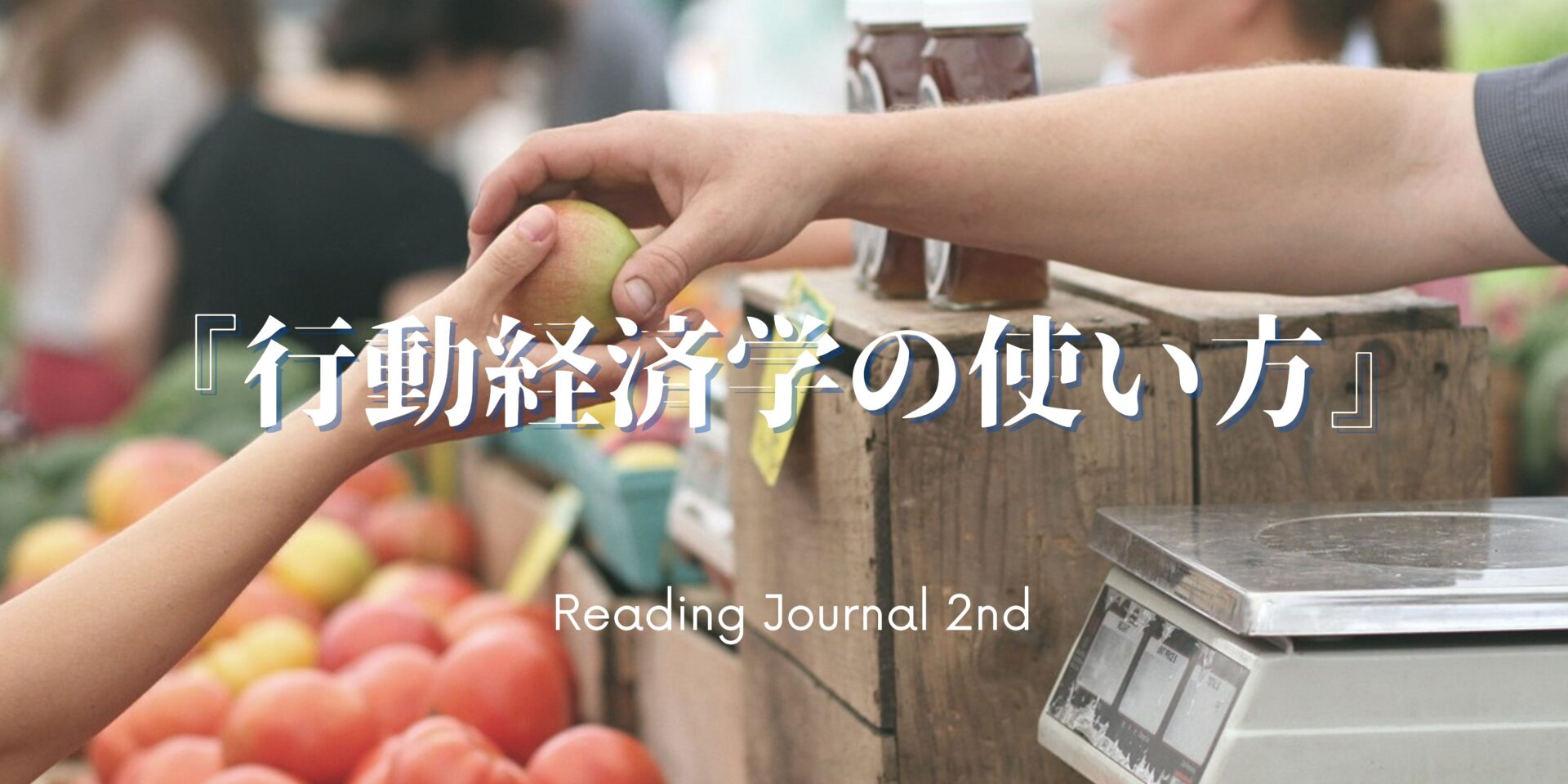


コメント