『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二章 「呉越同舟」 — 乱世の生きざま 3 戦国の群像(前半)
今日のところは、「第二章 呉越同舟」「3 戦国の群像」である。中国では、西周王朝が滅亡してから、秦の始皇帝が中国を統一するまでの五百年間、名目的に東周は存在するが、諸国分立の大乱世が続いた。 この大乱世の時代は、紀元前四〇三年を境に、春秋時代と戦国時代に区分される。
今日のところから、その戦国時代に入る。この戦国期には、孟子や孫子、荀子や韓非子などの諸子百家と呼ばれる多くの思想家が生れた。「3 戦国の群像」は(前半)と(後半)に分けてまとめることにする。それでは読み始めよう。
「唇亡べば則ち歯寒し」戦国時代の始まり
この戦国時代の最初は、大国晋が重臣に乗っ取られ、韓・魏・趙に分裂したことにより始まった。
春秋時代の終わりごろ晋でも下剋上の風潮があり、四人の重臣、智伯・韓康子・魏桓子・趙襄子が実権を握っていた。そして一番実力のある智伯が君主になろうと趙襄子の領土を奪おうとした。趙が抵抗すると智伯は、韓と魏に出兵を強要する。
このとき、趙襄子はひそかに韓康子と魏桓子のもとに使者を送り、「唇亡べば則ち歯寒し(唇と歯のように密接な関係にある者は、一方が滅びるともう一方も滅びる)」、すなわち、趙が滅ぼされたあと、韓も魏も同じ目にあうと、説得しました。」(抜粋)
その説得により韓と魏は趙と手を組み、反対に智伯が敗北し、殺害された。
この故事によりこの言葉は、共通の利害関係にある者が強敵に対するときの言葉となった。
そして、智伯の領土を韓・魏・趙の三者で三分割し、およそ五〇年後にそれぞれが正式に諸侯になった。
「士は己を知る者の為に死す」豫讓の復讐劇
智伯に苦汁を飲まされた趙襄子が、智伯の髑髏に漆を塗って酒器として使用した。これを聞いた智伯の部下だった豫讓は、
「士は己れを知る者の為に死す(男は自分を真に理解してくれた者の為に死ぬものだ)」と、智伯のために、身を賭して趙襄子に復讐する決意を固めます。(抜粋)
しかし、それは果たせずつかまって処刑された。
処刑直前、豫讓は趙襄子に懇願してその衣類を借り受けて三度斬りつけ、自刃して果てました。(抜粋)
「家貧しければ則ち良妻を思い、国乱れれば則ち良相を思う」魏の文候
戦後行く時代に入ると、弱小勢力がしだいに淘汰され、韓・魏・趙・斉・燕・楚・秦の「戦国七雄」が覇を争うようになった。そのなかで先んじて先進国としての体制を整えたのが韓・魏・趙である。
魏の文侯は、人材招集に熱心であり、彼のもとには優秀な人材が集まってきた。彼は人事に際して
「家貧しければ則ち良妻を思い、国乱れれば則ち良相を思う」という成句を引き合いに出して、適任者を決定していた。
「遂に豎子の名を成さしむ」馬陵の戦い
『史記』の「孫子呉起列伝」には大兵法家だった呉起と共に二人の孫子の電気が収められている。一人は春秋時代の孫武、そしてもう一人は戦国時代の孫臏である。
このうち孫武は、「彼知り己を知れば百戦殆うからず(敵情を知り味方の事情も知っていれば、百回戦っても危険はない)」の言葉で知られる兵法書『孫子』の著者とされている。
そしてこの孫武の子孫だとされるのがもう一方の孫臏である。彼は斉に生まれ早くから兵法を学んだ。そして相弟子に龐涓がいた。この龐涓は魏の恵王に仕えて将軍となると自分より優秀な孫臏を恐れ、罠を仕掛けて魏に呼び寄せて、罪をきせ、孫臏を両足切断の刑に処した。幸い孫臏は、魏を訪れた斉の使者と出会って帰国することができた。
そして孫臏は斉の威王に引きたてられ軍師にとなる。やがて「馬陵の戦い」で孫臏と龐涓は激突する。その戦いで孫臏は、「減竈の計(行軍のさい陣営の竈の数を毎日減らし、逃亡者が増えて戦力が低下したように見せかける計略)」を龐涓に仕掛けた。その罠にはまった龐涓は孫臏を猛追する。やがて馬陵に差し掛かると、大樹の幹に「龐涓、この樹の下で死す」と書いてあるのを見つけた。その時、待ち伏せしていた孫臏の伏兵が一斉に攻撃した。龐涓は、「遂に豎子の名を成さしむ(ついにあの小僧に手柄を立てさせたか)」と言って自刎した。
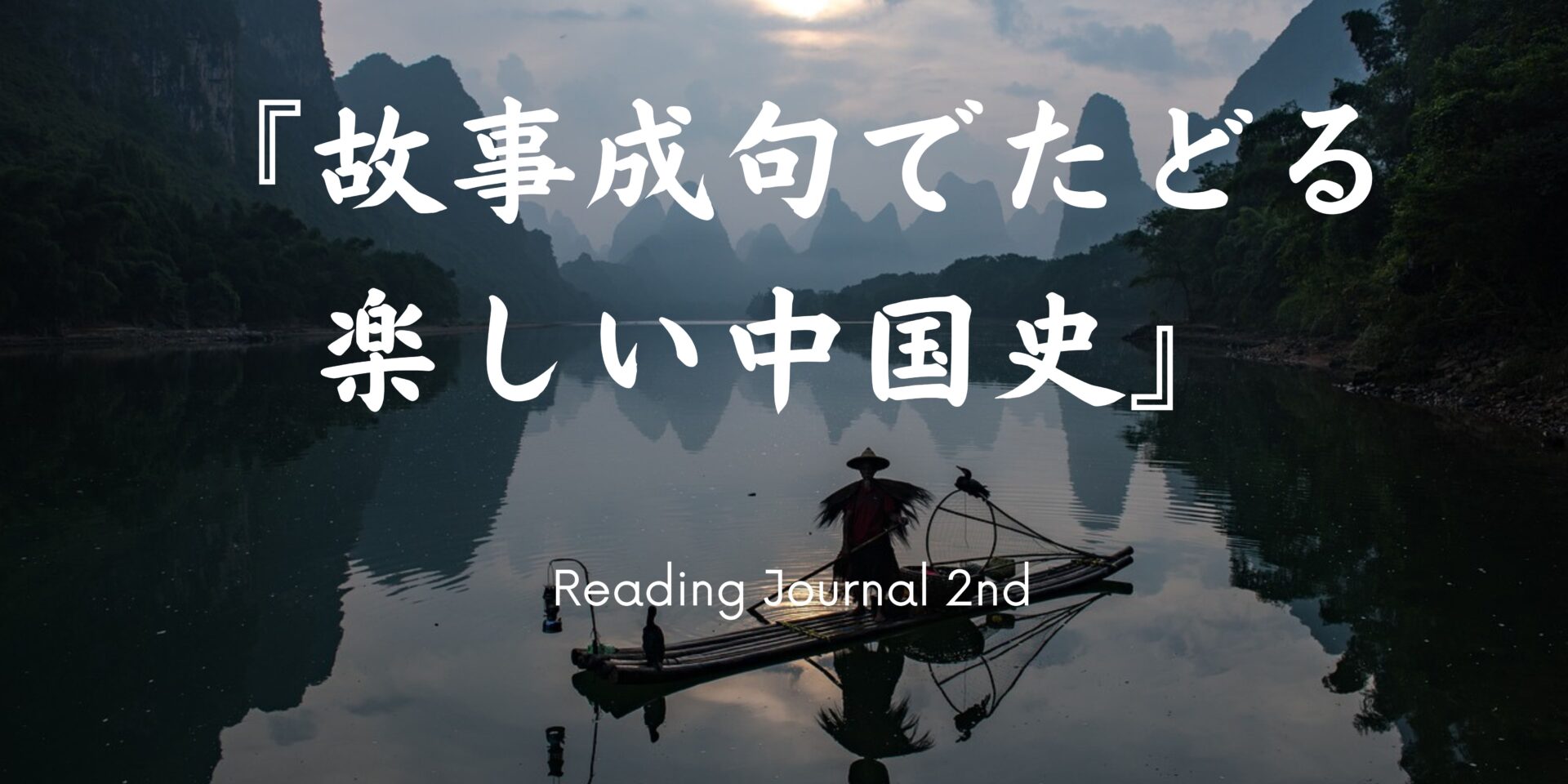

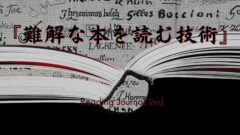
コメント