『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第四章 「春眠暁を覚えず」 — 大詩人のえがく世 1 唐・三百年の王朝(その2)
今日から「第四章 春眠暁を覚えず」「1 唐・三百年の王朝」の“その2”である。前回“その1”では、「初唐」を取り上げ、唐王朝の発足から則天武后により一旦周王朝になり、また唐王朝が復活するまでであった。
今日のところ“その2”は「盛唐」を取り上げる。ここでは、玄宗皇帝により唐の政治が安定するが、玄宗皇帝が楊貴妃に惑わされ衰退し、結局「安史の乱」により楊貴妃を絞殺せざるを得なくなるまでである。それ以降、唐は繁栄から衰退にむかう。また、この「盛唐」は中国古典詩の黄金時代でもある。それでは読み始めよう。
「開元の治」玄宗皇帝の政治(盛唐)
唐の王朝は復興したがその後も混乱が続いた。その混乱をおさめて唐の屋台骨を立て直したのが、玄宗皇帝である。玄宗は、政治・社会機構を整備し「開元の治」とたたえられる安定した時代を作った。
「解語の花」玄宗皇帝と楊貴妃(盛唐)
しかし、玄宗皇帝が老年にかかると政治が倦み始める。そして、玄宗は絶世の美女である楊貴妃との享楽におぼれ、政務もおろそかにした。
この楊貴妃の美貌は、中唐の大詩人白居易は、その長恨歌で、「花顔(花のかんばせ)」と形容した。そして玄宗自身も楊貴妃を「解語の花(言葉を理解する花)」と称した。
この「解語の花」は、以後美人のたとえとして用いられるようになる。
「口に密有り腹に剣あり」李林甫(盛唐)
玄宗皇帝のもとには「口に蜜有り腹に剣有り」と言われた李林甫が長く宰相を勉めた。
「安史の乱」楊国忠と安祿山(盛唐)
しかし玄宗が楊貴妃に夢中になると楊貴妃の一族の楊国忠が抜擢・登用された。そして李林甫が亡くなると楊国忠が宰相となる。
次に玄宗の寵愛を受け異民族出身の安祿山が強大な軍事力を手中に収めてしまう。
安祿山と楊国忠はかねてから不仲であり、安祿山は陽国忠討伐をスローガンに挙兵する。これが「安史の乱」である。
玄宗は楊貴妃や楊国忠を引き連れ首都長安を脱出。しかし途中、近衛兵に安国忠は殺害され、玄宗は楊貴妃を絞殺することでやっと蜀に落ちのびた。
その後玄宗は退位し息子の粛宗が即位、安禄山軍を追い払い長安を回復する。この「安史の乱」を契機として、唐王朝は繁栄から滅応へと向かっていくことになる。
「国破れて山河在り」詩聖杜甫(盛唐)
盛唐の時代は、中国古典詩の黄金時代で杜甫、李白、王維、孟浩然などの大詩人が排出した。
詩聖と称される杜甫は、「安史の乱」で安禄山軍に拘束されたさい、荒れ果てた長安の春景色を見て感慨をもよおし、「春望」、「国破れて山河在り 城春にして草木深し」の詩を作った。
さらに「酒債 尋常 行く処有り 人生 七十 古希稀なり(飲み代の借金はふつうのことで、行くさきざきにあってもかまわないが、むかしから七十まで生きた人はめったにいない)」と歌われる「曲江」などを作る。
この詩により七十歳のことを「古希」と呼ぶようになった。
「白髪三千丈」詩仙李白(盛唐)
詩仙と称された李白にも、ほとんど成句として成り立つ有名な詩句がある。
たとえば、「秋浦歌」の「白髪三千丈 愁いに縁って箇の似く長し」の「白髪三千丈」は、後世オーバーな表現のたとえとなった。
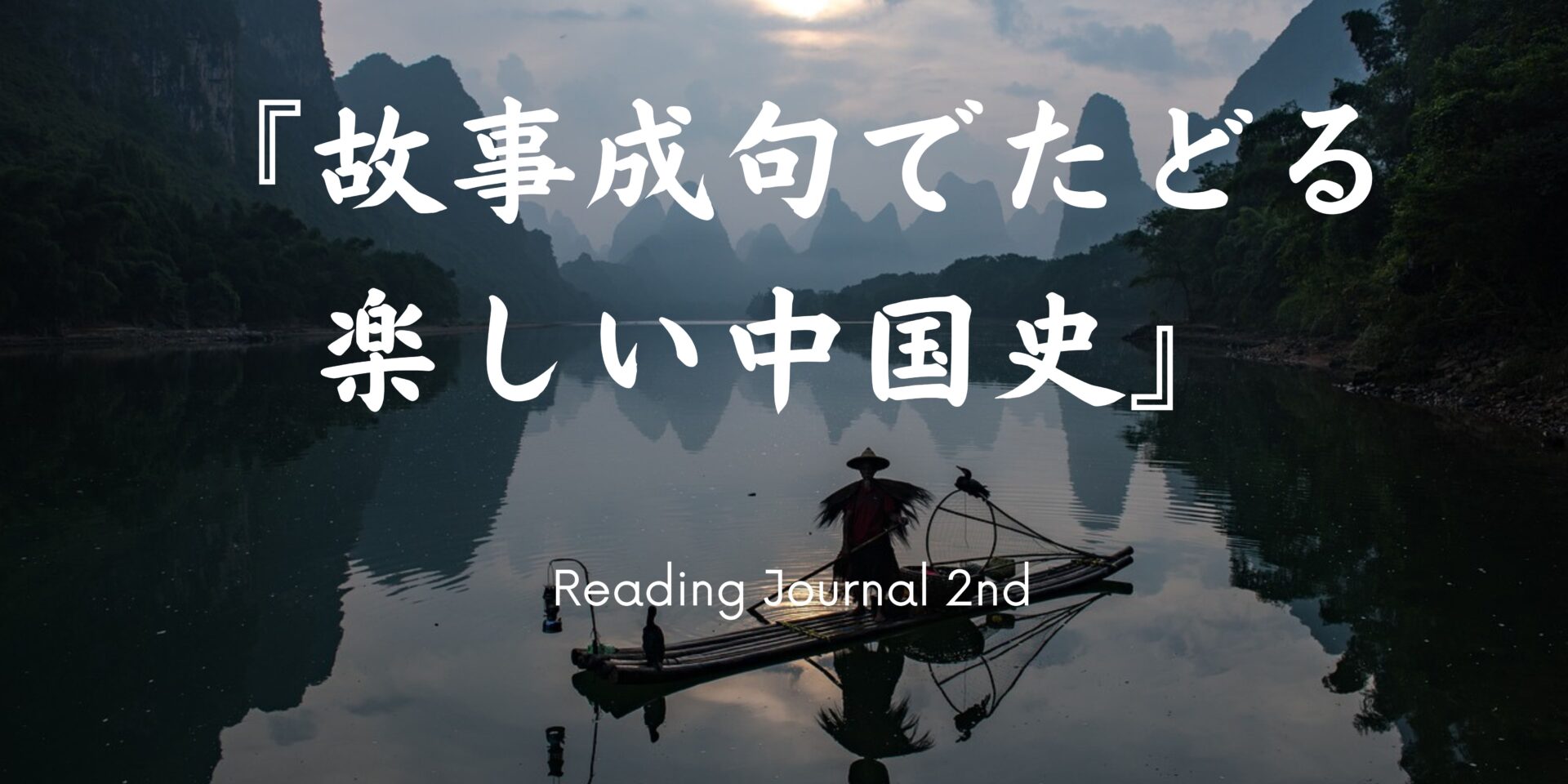


コメント