『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第四章 「破竹の勢い」 — 英雄・豪傑の時代 2 諸王朝の興亡(その2)
今日のところは「第四章 破竹の勢い」「2 諸王朝の興亡」の“その2”である。“その1”は、西晋による中国の統一とその文化、そして”八王の乱“を発端に西晋王朝が混乱したところまでであった。今日のところ”その2“では、華北が五胡十六ヵ国の異民族の支配地となる、一方、江南に東晋が成立する。そして安定した東晋における芸術などの発展についてである。それでは読み始めよう。
東晋の成立と「王敦の乱」「蘇峻の乱」
「八王の乱」とそれにつづく「永嘉の乱」で華北は大混乱となり大勢の人が長江を渡った。西晋王朝の一族は、琅邪王司馬睿を中心に結束し、司馬睿は、即位し(元帝)江南を支配地域にした東晋(首都は建康)を成立させる。
この東晋の成立は、琅邪王氏の王導と王敦が最大の功労者だったが、しばらくすると王敦が挙兵する(「王敦の乱」)。東晋は存亡に危機に陥るが王敦が病死したため一命をとりとめた。そしてその三年後、今度は「王敦の乱」で功績があった蘇峻が挙兵した(「蘇峻の乱」)。この乱は、東晋軍のリーダー郗鑒と陶侃により鎮圧された。
これ以降、東晋政権は行政担当王導、軍事担当郗鑒と陶侃という三巨頭体制で安定期に入る。
「東床」書聖王義之
このような時代背景でも多くの貴族たちはサロンを形成し清談にふけり、奇行を誇るような浮世離れした生活を送った。そして政治状況が安定した東晋に入るとますます貴族社会は洗練さていく。
その東晋貴族文化の代表格が「書聖王義之」である。
彼の妻は三巨頭の一人郗鑒の娘であるがどうして王義之が郗鑒の娘婿に選ばれたかという話が『世説新語』「雅量篇」に載っている。
郗鑒が娘婿を琅邪王氏から選びたいと思い王導の屋敷に配下の人を遣わした。郗鑒の使者が来たとみなが緊張する中、王義之は平然と「東床(東のベッド)」で腹ばいになり全く使者に無関心だった。これを聞いた郗鑒は「正に此れ好し」と言って、王義之を娘婿に決めた。
この故事により、中国では娘婿を「東床」と称するようになる。
「蘭亭序」王義之の隠遁生活
王義之は、権力がらみの堅苦しい官僚生活になじめず、希望して風雅明瞭な会稽の長官となり(後に隠居する)、そこで謝安をはじめとして友人と交友を楽しんだ。
王義之の最高傑作といわれる「蘭亭序」はそのような交流から生まれる。王義之は別荘蘭亭に友人たちを招いて「曲水流觴(屈曲した小川の流れに觴を浮かべ、順番に詩を作る)の宴」を催した。その時の詞を集めたものが『蘭亭詞』でその序文が「蘭亭序」である。
「一斑を見て全豹を知る」王献之
王義之の息子の王献之も書の名人で、父の王義之と共に「二王」と呼ばれた。
この王献之が子供のころ、書生たちが樗蒲をしているのを見ていて、勝負あったと思い、「『南風競わず』(『春秋左氏伝』襄公十八年に見える言葉で、一方の旗色が悪いときに使われる)だね」と言った。この王献之の言葉を聞いた書生が「此の郎も亦た管中に豹を窺い、時に一斑を見るのみ(この坊ちゃんもまた『管の中から豹をのぞき見て、たまたま一つの斑を見つけた』だけだ)」と、言い、勝負の全体がわかっていないと批判した。
この故事を元になって視野が狭いことを表す「一斑を見て全豹を知る(一つの斑を見て豹の全体を見た気になる)」という成句が生まれた。
「応接に暇あらず」王献之
また王献之は、山中散策を好んだ。そして「山陰(浙江省紹興市)の道を歩いていると、山川がおのずから映発しあい、応接する暇もないほどだ」という名言を残した。
これを典拠に「応接に暇あらず」という成句が生まれる。しかし、しだいに意味がかわり、さまざまな出来事や仕事が次々と出てきて、考える暇もないほど忙しい、という意味になった。
「三絶」画聖顧愷之
貴族文化が成熟し東晋時代は、絵画の世界も成熟した。絵画では、「画聖顧愷之」が出現する。この顧愷之はまた大変な奇人であった。
そのため「三絶」と称された。この「三絶」は「才絶(才の極み)」、「画絶(画才のきわみ)」そして「痴絶(阿呆の極み)」である。
またある人物の肖像画をかいたとき、最後に頬に三本の毛を書き加えると、たちまち肖像画に魂が入り生き生きとしたという逸話がある。
「画竜点睛」張僧繇
その逸話に似た話として、著者は後の南朝時代の張僧繇の話を付け加えている。
張僧繇が寺院の壁に二匹の龍をえがいたとき、龍の目に瞳を入れると龍が壁を破っ天に飛び去ってしまうと言って瞳を入れなかった。それでも人々にせがまれて、一匹の龍に瞳をいれると、たちまち壁を破って昇天し、まだ瞳を入れていない龍だけ残った。
この故事がもとになり、最後の仕上げをするという意味の「画竜点睛(龍を画て瞳をいれる)」という成句が生まれた。
「竹馬の好」「咄咄怪事」桓温と殷浩
東晋第二代皇帝明帝の娘と結婚した桓温は、軍事力にたけしだいに東晋王朝を威圧するまでになった。そのため東晋王朝は、世評の高い殷浩を対抗馬として起用した。しかし、殷浩は北伐に失敗したため桓温によって失脚させられた。
この桓温と殷浩は、幼馴染だった。『世説新語』「品藻篇」に、殷浩が失脚したとき、桓温が「小さいとき、淵源(殷浩のあざな)といっしょに竹馬にのって遊ぶと、私が乗り捨てるたびに、あいつはいつもそれを取っていた。当然、私にはかなわないさ」と言ったという話が載っている。
この話にがもとになって幼馴染のことを「竹馬の好」というようになった。
また、失脚した殷浩は、一日中、虚空に「咄咄怪事(ちきしょう、さっぱりわけがわからん)」という四字を書いていた。
桓温と謝安の政治
殷浩が失脚して意気上がる桓温を押さえるために、東晋は再度謝安を対抗馬に立てた。謝安は桓温と渡りあったため桓温は東晋簒奪までもう一歩のところで病死してしまう。
その後謝安は、行政のトップとして諸勢力の融和を図り、東晋王朝は安定した。
「風声鶴唳」謝玄、北方異民族を撃退
この謝安の在任中に、華北を統一した苻堅率いる前秦軍が攻撃してきた。これを謝玄が撃退する(「肥水の戦い」)。これにより北方異民族の江南への侵略を防いだ。
この時、百万の苻堅の大群は、八千の謝玄率いる東晋軍の攻撃を受け総崩れとなり「風声鶴唳(風の音や鶴の声)」を聞いても東晋軍の攻撃だと思って脅えたという。
この故事より、臆病風に吹かれた者がわずかな物音にも仰天することを「風声鶴唳」というようになった。
五胡十六国時代、華北の混乱
華北では、各地を割拠した五胡(匈奴、羯、鮮卑、氐、羌の五種類の異民族)の諸国が入り乱れる五胡十六国時代が続いていた。この間に氐族の苻堅が立てた前秦が一時的に華北を統一する。しかし「肥水の戦い」で東晋軍にやぶれた前秦急速に衰えて、華北の統一は潰えた。
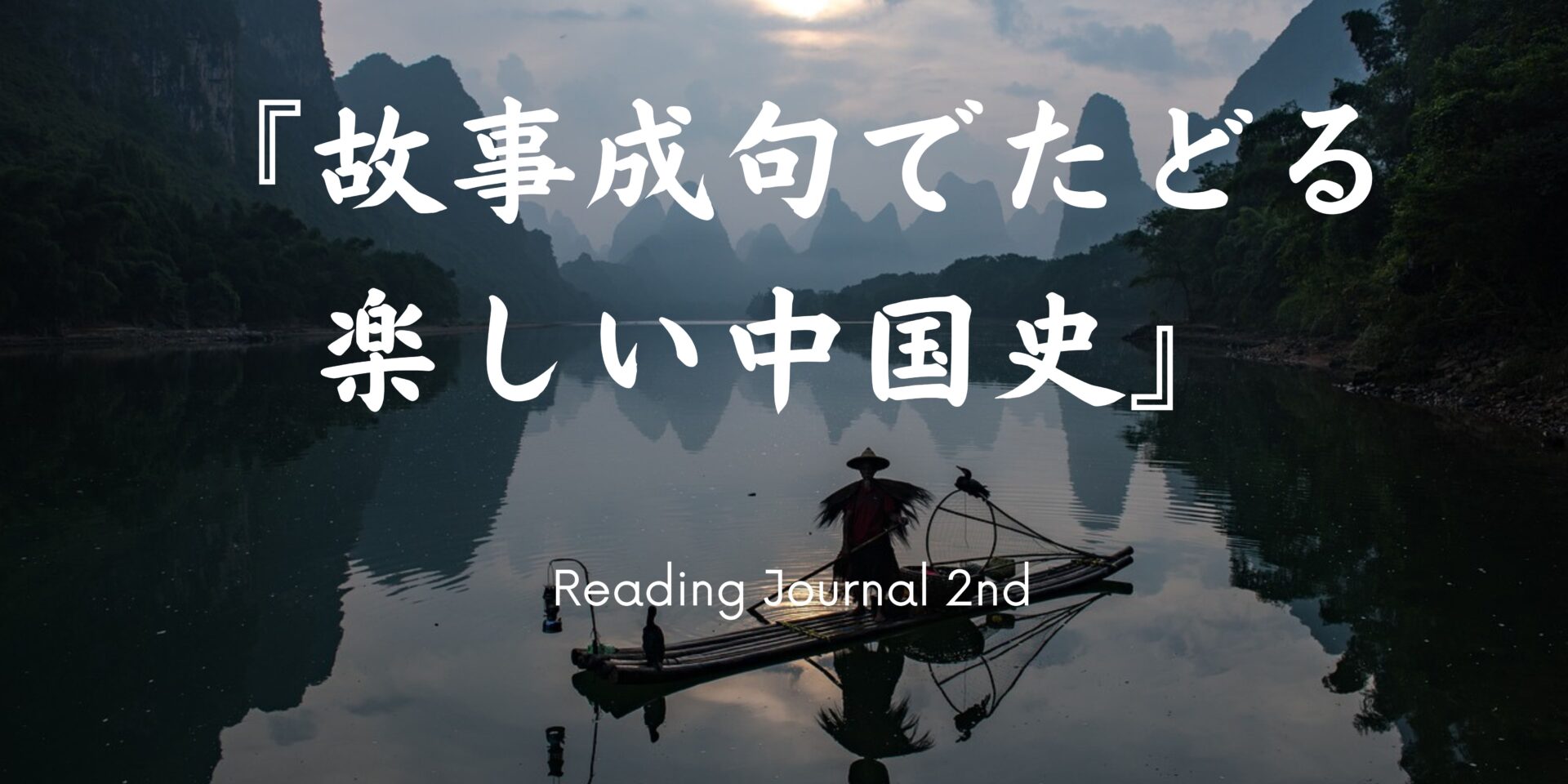


コメント