『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第三章 「水清ければ魚棲まず」 — 統一王朝の出現 3 前漢・後漢王朝(後半)
今日のところは「第三章 「水清ければ魚棲まず」「3 前漢・後漢王朝」の”後半“である。”前半“では、前漢王朝とその滅亡についてであったが、それを受けて”後半“は、光武帝による漢王朝の再建と後漢王朝についてである。それでは読み始めよう。
王莽の新王朝は、民衆反乱と豪族反乱に襲われた。そして王莽の死後、その主導権争いに、勝利したのが劉秀であった。彼は即位し前漢の命脈を継ぐ後漢王朝を立て、初代皇帝・光武帝となった。
「井の中の蛙、大海を知らず」、馬援と公孫述
後に後漢の重臣となった馬援は、王莽に叛旗をひるがえした英雄の一人、隗囂に仕えていた。隴西を本拠地としていた隗囂は、蜀を根拠地としている公孫述と手を組もうと思い馬援を派遣する。馬援は公孫述の尊大な態度を見て、「あの男は井の中の蛙です。相手にしない方が良い」と報告した。これを受けて隗囂は公孫述との同盟を諦め、光武帝と友好関係を結んだ。
この「井の中の蛙」には、さらに古い典拠がある。それは『荘子』(ココを参照)の「秋水篇」に見える、「井の中の蛙に海の話をしても仕方ない。蛙は自分の住処の井戸のなかにちぢこまっているからだ」という文章である。
日本での「井の中の蛙、大海を知らず」はむしろ『荘子』の言葉に由来するものと考えられる。
「隴を平らげ復た蜀を望む」、光武帝による統一
隗囂は、光武帝と友好関係を結ぶが、やがて叛旗をひるがえし、まもなく病死する。そして、息子の、隗純が降伏し、隴西も光武帝のものになった。
そしてこのとき、光武帝は「人は足るを知らざることに苦しむ、既に隴を平らげ復た蜀を望む」と言った。この言葉は、「隴」を得ただけでは満足せず、「蜀」まで手に入れたがる、という意味である。現在は「欲張ってもう一つの望みを持つ」という意味に使われるのはこの故事に由来する。
そして光武帝は、蜀の公孫述も滅ぼし、中国全土を統一した。
「大器晩成」、馬援の流転
光武帝の重臣となった馬援は、転進を繰り返した人だった。彼が若いころ、辺境で酪農や農業に従事しようと思い、兄の馬況に別れを告げた。すると馬況は「おまえは大器晩成だ。しばらく好きにするがいい」と励ました。
その後、馬援は地方の役人や牧畜業、さらには地方の長官、そして、隗囂の傘下など流転を繰り返し光武帝と出会った。
「矍鑠たるかな、是の翁は」、馬援の活躍
馬援は、軍事的才能もあり数々の戦功をたてる。そして老いても血気盛んで、六十二歳でみずから志願して、武陵蛮討伐に出陣した。馬援が最後の出陣を願い出たとき、光武帝は「矍鑠たるかな、是の翁は」といって許可を与えた。
後漢王朝は国内の敵対勢力や反乱を鎮圧すると、政策基盤を固めた。光武帝は、以後は領土の拡大を望まず、内政に注力した。官吏登用法として「孝廉制」を採用し、親孝行や清廉潔白などの儒教倫理の優等生を推薦・登用した。こうして儒教は後漢を通じて名実ともに国教となる。
「虎穴に入らずんば虎子を得ず」、班超の活躍
光武帝の対外的消極政策のため、西域諸国では争いが絶えなかった。光武帝の死後、二代目皇帝の明帝のころには、匈奴が勢いを強め後漢の国境近くまで攻め寄せるようになった。そのため、後漢王朝は西域に遠征軍を派遣することになった。
この遠征軍で活躍したのが班超であった。班超は学者の家柄で、前漢の歴史書『漢書』の著者、班固の弟である。また妹の班昭(または曹大家)は、『漢書』の未完部分を叙述した。
この『漢書』は前漢一代の歴史を記した「断代史」であり、のちの生死の原形となるスタイルを確立した歴史書である。
班超は、遠征軍に加わり後漢と匈奴の間で揺れ動く西域諸国を説得して回り聖域諸国を後漢に帰属することに成功した。
西域諸国の鄯善では、班超が到着してまもなく匈奴の使者も到着したため、鄯善の王は急に班超を粗雑に扱った。その時、班超は「虎穴に入らずんば虎子を得ず」と言って、匈奴の宿舎に焼き討ちをかけ、匈奴の使者一行を全滅させた。
班超のこの言葉は、危険をおかさなければ成功は得られないという意味で広く使われている。
「水清ければ魚棲まず」、班超のアドバイス
班超は、約三十年の間、西域に留まり、老齢のため洛陽に帰還した後、病没した。班超が帰還するとき、後任の任尚に、「水清ければ大魚なし」、つまり小さな問題にこだわると大事なものを失う、とアドバイスした。
これが元になり「水清ければ魚棲まず」という言葉が生れた。
しかし任尚はこのアドバイスを聞かず、結局、西域諸国にそっぽを向かれてしまう。
外戚と宦官の支配
班超が西域に留まっているころから、後漢では皇帝が若くして即位し、実際に権力を握っているのは皇后の一族である外戚であった。しかし若くして即位した皇帝も年齢が上がってくると外戚の傀儡であることに不満を持つ。そうした皇帝は身近な宦官を頼りにし外戚と争った。後漢王朝ではひっきりなしに外戚と宦官の主導権争いがおこり、しだいに宦官の勢力が強まる。
宦官はおおむね陰湿で貪欲であるが、紙を発明した蔡倫のような優秀な人物もいた。(蔡倫の紙は「蔡侯紙」と呼ばれた)
「天知る、地知る、我知る、子知る」、楊震
このような外戚専横の風潮の中で、楊震のような傑物もいた。楊震は、清廉潔白で学識が高く「関西の孔子」と呼ばれていた。
楊震が太守に任命され赴任する途中、宿に到着したとき、王密が訪ねてきた。王密はよもやま話をしながら、金十斤を取りだし、世話になったお礼としてどうしても受け取ってほしいと言った。この事は誰も知らないので、受け取っても大丈夫だといって賄賂を渡そうとした。
その時、楊震は「天知る、神知る、我知る、子知る。何ぞ知る無しと謂わんや(このことは天が知っており、神が知っており、私もきみも知っている。どうして誰も知らないなぞといえようか)」と、きっぱりはねつけた。
この楊震の言葉は、「天知る、地知る、我知る、子知る」という言葉として後世に伝わった。
「登竜門」、宦官派と清流派の争い
このような宦官と悪徳官僚が結託し実権を掌握すると、後漢王朝の命運は悪化の一途をたどった。この賄賂取り放題の宦官派に対して、大々的に批判をしたのは、清流派の知識人だった。この清流派は、宦官派による「党錮の禁」により徹底的に弾圧される。
このような弾圧の中で、清流派の陳寔と李膺は屈指の存在だった。李膺は高潔をもって鳴らした人物で、彼の説教を聞き「梁上の君子(梁の上に潜んでいた泥棒)」まで、恐れ入ったという故事がある。
この故事から泥棒のことを「梁上の君子」と呼ぶようになった。
一方、李膺はシビアな態度で宦官派と対決した。彼の屋敷の表座敷に通されることを「登竜門(竜門に登る)」と称された。これは、「登竜門」が「関門を突破し、世に出るお墨付きをもらった」という意味で使われた、早い用例である。
しかし、その後陳寔はかろうじて宦官派の弾圧を潜り抜け生き延びたが、李膺は処刑の憂き目にあった。
こうして宦官派にさんざんな目にあわされながら、がんばり抜いた清流派の生き残りやその子孫が、次の新しい『三国志』の時代に、大きな役割を演じるのです。(抜粋)
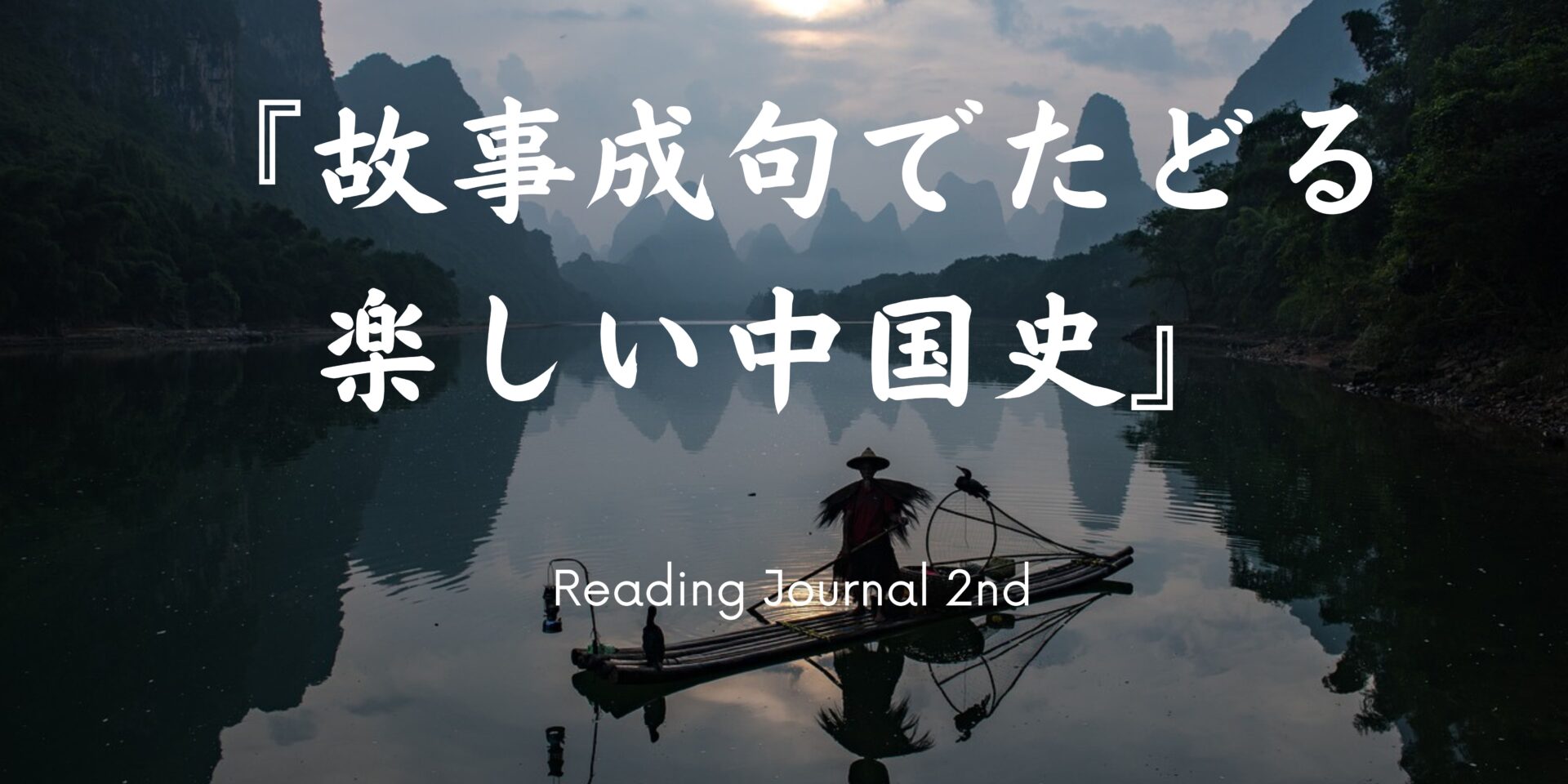

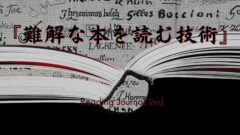
コメント