『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第三章 「水清ければ魚棲まず」 — 統一王朝の出現 2 漢楚の戦い
秦の始皇帝により天下が統一されたが、まもなくまた社会が混乱し始める。そして漢の劉邦と楚の項羽が台頭する。ここでは、秦王朝の崩壊と項羽と劉邦の戦いに対語られている。それでは読み始めよう。
「王侯将相、寧んぞ種有らんや」陳勝と呉広の反乱
始皇帝死後、秦王朝は混乱し、社会不安が激増、各地で反乱が勃発した。その引き金となったのは、辺境守備にあたっていた陳勝と呉広の反乱であった。
陳勝は若いころ貧乏でした。あるときふと雇い主に、「富貴の身になっても、緒おたがい忘れないようにしましょう」といった。雇い主が何を大言壮語するのかと笑うと、陳勝は「燕雀安んぞ鴻鵠を知らや(燕や雀のような小鳥にどうして鴻鵠の志がわかろうか)」と言った。
陳勝と呉広は、始皇帝の死後に辺境での守備に向かった。そこで、引率責任者を殺し、全員を集めて「王侯将相、寧んぞ種有らんや(王侯も将軍・大臣も生まれついての区別なぞあるものか)」と言って秦王朝に反旗を翻した。
秦王朝の滅亡
陳勝と呉広の反乱以降次々反乱がおきて、たちまち群雄割拠の状態となった。そこで項羽と劉邦という二人の英雄が頭角を現してくる。
その状況で趙高は二世皇帝胡亥を殺害する。趙高は自分が皇帝になろうとしたが、群臣こぞって反対したため、胡亥の兄・公子嬰を即位させる。公子嬰は先手を打って趙高を殺害する。しかし、時遅く首都咸陽に劉邦の軍が攻めてきて降伏を迫った。結局、始皇帝の死後わずか四年で、秦王朝は滅亡した。
「鴻門の会」項羽と劉邦
咸陽を制圧した劉邦は、厳格な法律を撤廃し、人を殺した者は死刑、人を傷つけたものは処罰する、盗みを働いたものは処罰する、の三項目だけの法律「法三章」を発布する。
そして遅れて咸陽に到達した項羽は、武将の范増の計を受けいれ、宴会に招待するという口実で自らの駐屯地に劉邦を迎え入れた。宴会が始まると項羽は劉邦の殺害をためらう。いらだった范増が劉邦の暗殺を支持するが、劉邦の猛将樊噲に阻まられ、結局逃げられてしまう。
范増はライバル劉邦を排除する千載一遇の機会を、おめおめ逃した項羽の優柔不断に失望し、「ああ、豎子ともに謀るに足りず。項王の天下を奪う者は必ず沛公ならん(小僧っ子とはとてもいっしょにやれない。項羽の天下を奪う者は劉邦にちがいない)」と罵りました。(抜粋)
これが「鴻門の会」である。
項羽と劉邦は何から何まで対照的であった。項羽は楚の豪族の出身だが、劉邦は沛の無頼漢である。項羽は剛勇無双だが、劉邦は腕っぷしもそれほど強くない。
しかし、劉邦は冷静に余裕をもって情勢を判断する知力の点では、項羽を完全に圧倒していた。
「背水の陣」韓信の活躍
咸陽に入った項羽の軍勢は破壊と掠奪の限りを尽くす。一方劉邦はあっさり咸陽から引き揚げ、まもなく漢王に封じられ、領地の蜀に向った。
この時点で劉邦の謀臣蕭何は、「国士無双(国に二人といない逸材)」と言って大将に韓信を推薦した。この韓信は、若いころ貧乏で怠け者だった。あるときならず者に脅かされると、相手にならない方が良いと考え、言われるままに、その股の下をくぐった。この故事により、負けるが勝ちという意味で「韓信の股くぐり」という言葉が生れた。
劉邦はこの韓信を大将に起用すると、わずか一万の軍勢で「背水の陣」をしいて二十万の大軍を撃破するなど、大活躍を続けた。
この韓信の故事が元になって、決死の覚悟で事にあたることを「背水の陣」というようになった。
そして、韓信この「背水の陣」によって捕虜になった趙王軍の軍師、広武君李左車に、燕や斉をどのように攻めるかを尋ねた。すると
広武君は「敗軍の将は以て勇を言うべからず。亡国の大夫は以て存を図るべからず(敗軍の大将は勇気について語ってはいけない。亡国の高官は他国の存続についての計画をしてはいけない)」と答えたとされます。(抜粋)
この故事が元になり「敗軍の将は兵を語らず」という言葉が生れた。
「四面楚歌」項羽の最期
このような韓信の働きもあり、劉邦の支配領地は広がり、ついに項羽を追いつめる。項羽は、垓下の砦に籠城する。
この時、項羽は砦を包囲する漢軍(劉邦軍)から、故郷の楚の歌をうたう声を耳にする。この「四面楚歌」により、項羽は自らの敗北を悟る。項羽は、愛姫虞美人をいとおしみ、「虞や、虞や、若を奈何せん」と歌って、涙を流す。そして、翌日項羽は包囲を突破して逃亡する途中で自刎して果てた。
劉邦はライバルの項羽が滅びたことにより、漢王朝が天下を統一する。
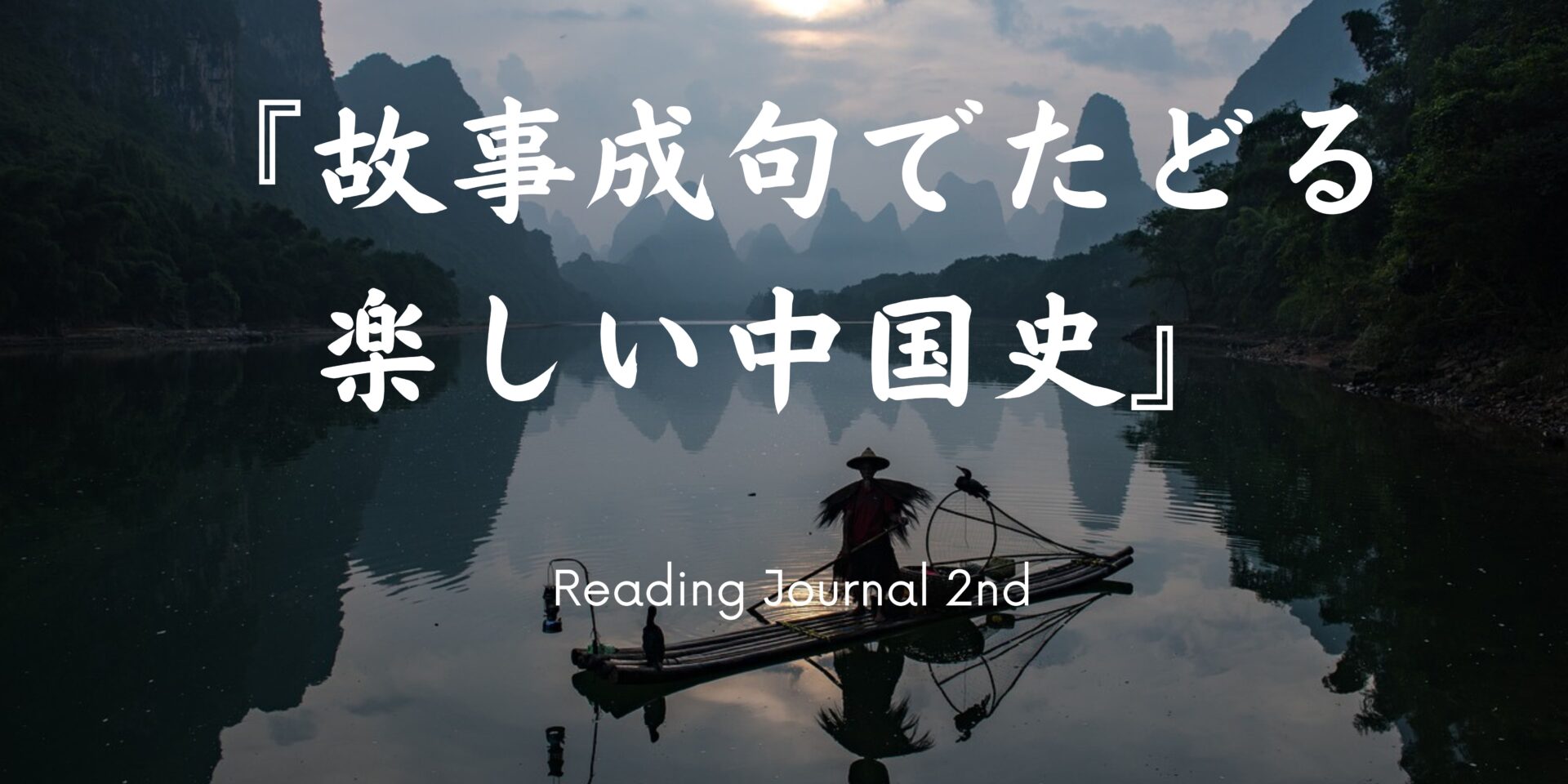

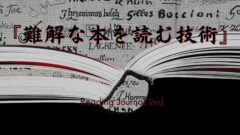
コメント