『人生の一冊の絵本』 柳田邦男 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
何をすることが、いちばんだいじか
災害時の避難所などでは、集まった多くの人が家族以外の避難者と食べ物を分けあったり、ほかの家族の高齢者や幼い子供の世話をしてあげたりなどの支え合う日常が生れる。そして同じ人間同士として連帯感を持って一日一日乗り越えていくそういう非日常の中で生まれた共同体のことを”災害ユートピア“と呼ぶ。しかし、そのような災害ユートピアも長続きはせず、しだいに人が去って行って災害ユートピアは消滅する。
しかし、“災害ユートピア”で体験した支え合いや人とのつながり、あるいは困っている他者への思いやりといったものは、多くの人々のこころに刻まれ、その後の人生観に影響を与えることが少なくない。(抜粋)
柳田は、ユートピアは作れなくても、このように支え合うという心の持ち方にこそ人間が人間らしく生きるうえで大切なものがあるという。
そして、そのような人生論あるいは生きがい論を寓話的に描いた作品として、アメリカの絵本作家ジョン・J・ミュースの『3つのなぞ』を紹介している。
『3つのなぞ』
翻訳者で詩人の三木卓によると、ミュースは、博愛主義者でロシアの作家レフ・トルストイの思想に共鳴して、この絵本を作ったという。
主人公のニコライは、<いい人間に なりたい>と願いつつも<そのために、なにをしたらいいのか>わからずにいた。そして次の3つの謎を解かねばならないと思う。
- いつがいちばんだいじなときなのか
- 誰がいちばんだいじな人なのか
- 何をすることがいちばんだいじなのか
そして、年老いたカメのレオ(トルストイのような賢者の象徴である)に、3つの謎を尋ねる。しかし、レオは、黙って答えなかった。
そして、ニコライは、レオに変わって畑を耕したり、突然の嵐でけがをしたパンダを助けたりする。そして、もう一度3つの謎についてたずねると、レオは<もうその答えはおまえさんがだしていしまっておる>と答えた。
柳田は、3つの謎の答えは絵本を読んで欲しいとしたうえで次のように書いてこの章を終えている。
人は何らかの行動をしていると、出会うべきチャンスが向こうからやってくる。その出会いが、人の人生を意味あるものに高めていく。私がかねて思ってきた人生訓だ。(抜粋)
関連図書:ジョン・J・ミュース(作)、三木卓(訳)『3つのなぞ』、フレーベル館、2012年
なにはともあれ外に出てみよう
ドキュメンタリー作家である著者は、取材などで行き詰りなかなか真実に到達できないことも多い。そういう時に焦らずに、粘り強く取材を続けているうちに、ある日突然答えが向こうからやってきたように突破口が開けることがある。
それは単なる偶然でなく、真実を求め続けたことによってもたらされる果実とも言うべきものなのだ。私はそう考える。
「犬も歩けば棒に当たる」という諺があるが、とにかく歩くこと、行動することが大事なのだ。(抜粋)
そして、著者はこのような仕事への姿勢は、他の職業のみならず「子供のこころの発達」にも共通の課題であるとしている。
そして、このようなこころの持ち方の大切さを語っているとして二つの絵本を紹介している。
『ホイホイとフムフム たいへんなさんぽ』
一冊目は『ホイホイとフムフム たいへんな散歩』である。二人は野ネズミの大人同士の友達である。杖を使っているホイホイが、フムフムを散歩に誘う。フムフムは毎日窓から外を眺めて暮らしているが散歩をしたことがない。散歩を嫌がるフムフムに寄り添って、ホイホイはしばらく一緒に窓の外を眺める。するとそのうちフムフムも出かける気になり、二人は散歩に出かけた。散歩に出かけているうちにフムフムがだんだんと元気になっていくという物語である。
なにはともあれ、外に出かけて歩いてみること。そのなかで生まれるこころの変化。家に引きこもっていてのでは、なにも変わらない。そういうときに必要となる、こころを理解して寄り添ってくれる他者の存在。ユーモラスな野ネズミの物語の奥に秘められた、深い人間関係の哲学と言おうか。(抜粋)
『いっしょに おいでよ』
2冊目は『いっしょに おいでよ』である。この絵本は、欧米で大きな時代的テーマとなっている、難民や不法入国などによって生じる人種差別の問題が根底にある。
テレビを見ている女の子が、<たくさんの ひとたちが にらみあってる>と怖くなってしまう。そしてお父さんに<どうしたら いいの>と尋ねる。お父さんは<いっしょにおいで>と女の子を誘って町に連れていく。
地下鉄のホームでヒシャブをかぶっているイスラム系の女性と目を合わせたお父さんは、帽子をひょいと上げて挨拶する。女の子もお父さんと同じように帽子を上げた。
それでもテレビのニュースは怖い出来事を報じている。<こんなせかいや いやだ>と女の子が言うと、お母さんが<いっしょに おいで>と言って女の子をとまちの食品店に行く。
食品店には、いろいろな国の食品がならんでいて、いろいろな国の人たちもいた。肌の色や髪の毛の色、話す言葉が違ってもみんなやっぱりおいしい者が好き。
こうして女の子のこころに、<ゆうきを だして こころを ひらいて まわりの ひとやいきものたちにも しんせつに>という思いが、しっかりと育ってくる。(抜粋)
関連図書:
マージョリー・ワインマン・シャーマット(文)、バーバラ・クーニー(絵)、福本美子(訳)『ホイホイとフムフム たいへんなさんぽ』、はるぷ出版、2018年
ホリー・M・マギー(文)、パスカル・ルメートル(絵)、なかがわちひろ(訳)『いっしょにおいでよ』、廣済堂あかつき、2018年
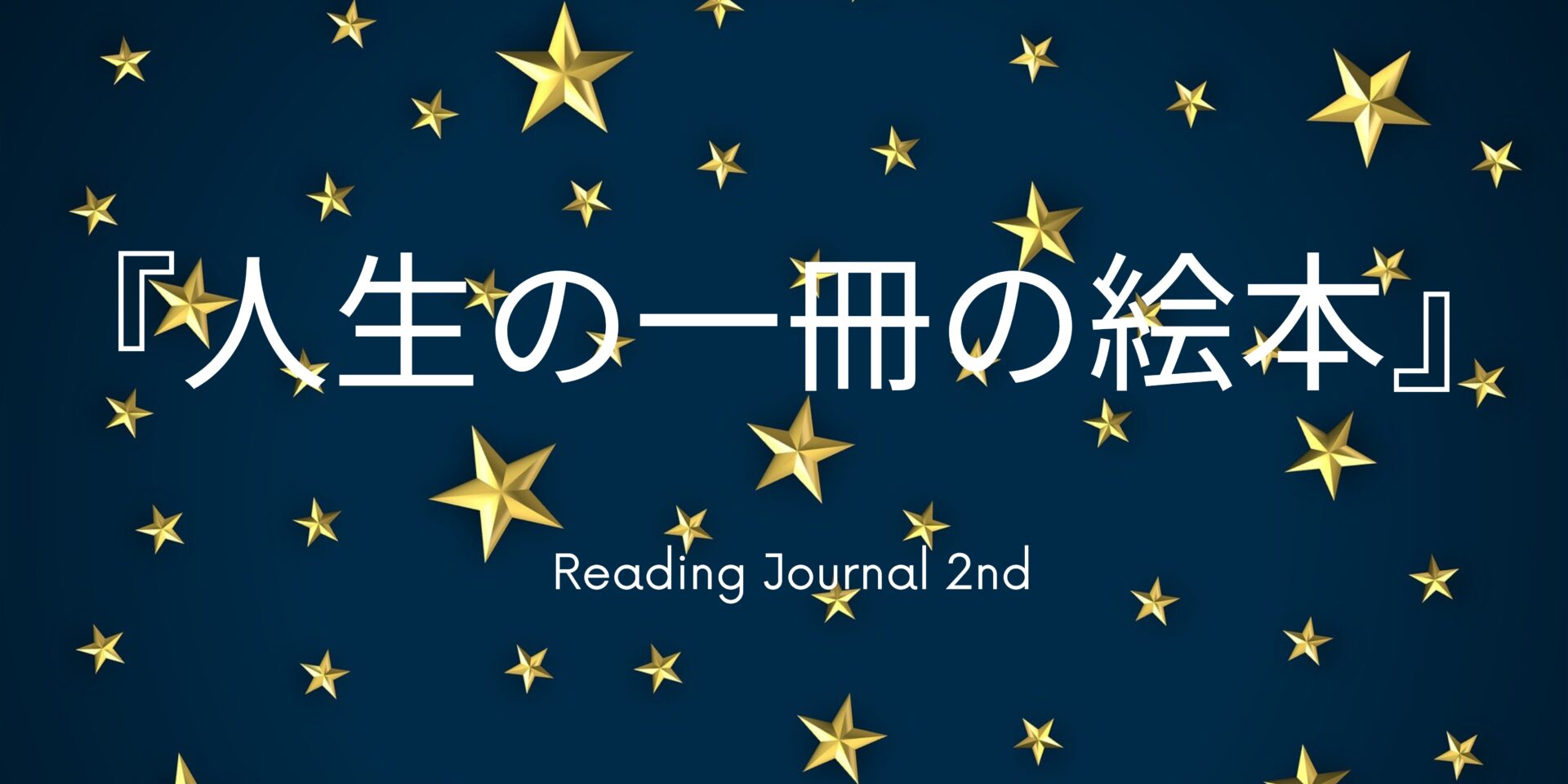


コメント