『人生の一冊の絵本』 柳田邦男 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
言葉のない絵本のインパクト
絵本の中には、言葉がまったくないか、ごく簡単な言葉がほんの一~二か所あるだけのものがある。そういう絵本は、言葉がない分、絵の一枚一枚にメッセージを持たせている。ここでは、柳田邦男が翻訳を頼まれた、言葉がほんの少ししかない絵本を2冊とそれに関連した絵本を1冊紹介している。
この言葉のない絵本の翻訳とは、何をすることなのか。それは、タイトルをどうするかだ。(抜粋)
『ぞうさん、どこにいるの?』
一冊目は、『ぞうさん、どこにいるの?』である。この絵本はジャングルの密林を水彩の木を一本一本切り離し立体感をだすようなコラージュ方法で描いている。
最初は見開きいっぱいの森の中にゾウとオウムとヘビの切り絵を張り付けてある。頁をめくっていくと、森が徐々に伐採されていき、ゾウとオウムとヘビは、どこかにちょこっとだけ姿の一部が見えるだけになる。“さがし絵の絵本”として読み進めていくうちに、とうとう森には木が無くなり、ゾウたちは柵の中に入れられてしまう。そして最後は、こんなところでは生きていけないとゾウたちは柵を壊して脱走し、船で新たな新天地を目指す。
『やめて!』
柳田が翻訳を引き受けたもう一冊の言葉のほとんどない絵本は、『やめて!』である。
主人公は小学生くらいの男の子。表紙の絵とタイトルが強烈だ。少年が必死の形相で、“NO!”と叫んでいる。その叫び声を吹き出しの中に大文字で印刷して、そのままタイトルにしているのだ。(抜粋)
少年が(だいとうりょうさま)と書かれて手紙をもって街を歩いている。その頭上では戦闘機が通過して爆弾を落とし、横を戦車が通り過ぎ砲撃している。軍隊が住宅に侵入し、知識人が警察に追いかけられる。そのような状態が続く。そして少年がポストに手紙を入れようとすると、不良少年にからまれ暴力を振るわれそうになる。
そこではじめて、少年が不良少年をしっかりと見つめて、<やめて!>と叫ぶ言葉が吹き出しのなかに記される。(抜粋)
少年の毅然とした態度に不良少年がひるんでいる間に少年は手紙を投函し、帰っていく。
すると、情景が一変する。軍隊は市民にプレゼントを贈り、洗車はトラクターの代わりになって農耕を助け、戦闘機は空から落下傘に吊るした自転車を投下してプレゼントしてくれる。不良少年は優しくなって自転車に少年を乗せて走ってくれる。
最後に少年が出した手紙の文面が載せられている。
<だいとうりょうさま ぼくの学校には、きちんとした きそくがあります。 つきたおしは いけない。なぐっては いけない。このくにには、そういうきそくが ないのですか?>(抜粋)
柳田はこの本の原題の”NO!“は、積極的な拒否の意思表示であるので、「やめて!」としたと言っている。この絵本『NO!』は、以前に台湾の民主化運動で市民・学生デモと座り込みが広がったときに、子ども連れの母親たちがプラカードのように手にもって掲げていた。
『戦争と平和を見つめる絵本 – わたしの「やめて」』
章の最後に、自由と平和のための京大有志の会(文)、塚本やすし(絵)による『戦争と平和を見つめる絵本 – わたしの「やめて」』が題名のみだが紹介されている。
関連図書:
バルー(作)、柳田邦男(訳)『ぞうさん、どこにいるの?』、光村教育図書、2015年
デイビッド・マクフェイル(作)、柳田邦男(訳)『やめて!』、徳間書店、2009年
自由と平和のための京大有志の会(文)、塚本やすし(絵)『戦争と平和を見つめる絵本 – わたしの「やめて」』、朝日新聞図書出版、2015年
空襲、こころに刻まれるあのこの死
『あのこ』
絵本のなかには、物語も情景も額縁のなかに封じ込められた灰色の遠い昔の幻想的な出来事のように感じられる作品がある。ところが、その幻想的な気配に思わず引きこまれて、読み進んでしまうことがある。そして、いよいよ大詰めになったところで、稲妻が走るように鋭い言葉が登場したり、劇的な場面転換があったりすると、とつぜん、物語が額縁のなかから飛び出してきて、今の時代の出来事であるかのような思いになることが少なくない。そういう転換は、リアリティに満ちているので、思わずハッとなる。(抜粋)
冒頭で柳田はこのように言っている。ここでは、児童文学の代表的な作家である今江祥智の作品を宇野亞喜良の絵によって絵本に仕上げらえた「あのこ」を取り上げる。
「あのこ」は、戦争末期、都会から地方へ疎開していった子どもたちの話である。疎開地では村の子どもは、都会の子供を”よそ者“視し都会の子どもは気位がた高く村の子どもと交わらなかった。
そんな中、集団で暮らす都会の子どもたちに、不思議は女の子が加わった。女の子は、〈――わたし、馬と話ができるのよ――〉と言った。
疎開児たちは、あのこが本当に馬と話せるかを試してみようということになる。村では馬という馬が軍に徴用され、残っているのは庄屋さんのところの足の悪い馬だけだった。
疎開児たちがあのこを取り囲みそして村のわんぱくたちもその回りを取り囲んで庄屋さんの家まで進んだ。
あのこは、馬の頸をとんとんとたたくと、お祈りでもするかのような調子で、なにやらつぶやきはじめたのだ。すると馬はあのことこころが通い合ったのだろう、すこしずつ耳を立て、目の色がやさしくなって、ひとみのなかに青空が広がったのだった。(抜粋)
しかし都会の子も村の子も、馬の反応を理解できず、ワイワイと騒ぎたしたため、馬が突然、庄屋の子の太郎を引きづって走り出した。あのこは太郎にしがみついていた。馬が疾駆をやめたとき、あのこの肩に血がにじんでいた。
その日から、あのこは口をきかなくなった。そしてある雪の日に、いなくなる。
ある朝、庄屋の太郎がはじめて疎開児たちを尋ねてきて、あの日の真実をうなだれたまま語った。あのこはほんとに馬と話せたのだと。それを聞いて何があったのかをはじめて知った先生が、それまで黙っていた重大なことを子どもたちに話した。
〈――あのこがかえった夜、あのこの町が空襲ですっかり焼かれてしまったよ〉(抜粋)
柳田邦夫は、この『あのこ』と今西祐行[氏の『一つの花』、そして野坂昭如氏の『火垂るの墓』の三冊を、戦争の残酷さ、不条理さを伝える児童文学のもっとも重要な作品であるとしている。
関連図書:今江祥智(文)、宇野亞喜良(絵)『あのこ』、BL出版、2015年
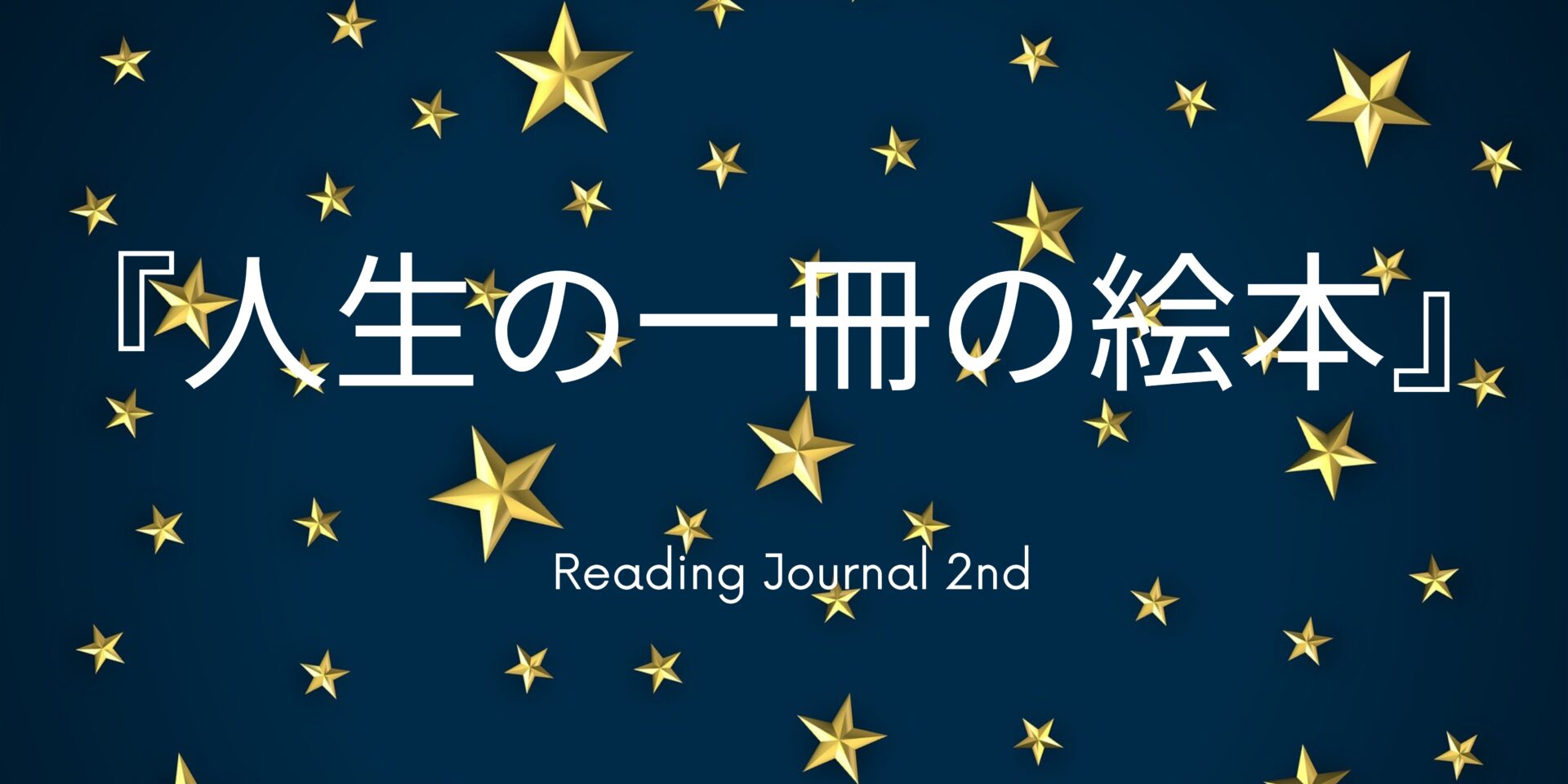


コメント