『人生の一冊の絵本』 柳田邦男 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
目に見えないものこそ
柳田は、冒頭で東山魁夷の画集・『白い馬の見える風景』(新潮社)について語っている。東山の絵は幻想的な風景の中に、必ず白い馬が登場する。
つまり一頭の白い馬が登場することで、森と湖の風景が突然、見るものの想像力を刺激して、一編の物語を生み出していくのだ。(抜粋)
そして、同じように絵本にも一頁ごとの絵に想像力を働かせ空想の世界の遊びに誘うものがある。ここではそのような絵本を三冊紹介されている。
『うみべのいす』
一冊目は『うみべのいす』である。詩人で絵本作家の内田麟太郎さんのこの絵本は、まさにそのような想像力を引き出してくれる。
絵本は<しろい はまべに、いすが ひとつ>という言葉で始まっている。その絵はフランスの新印象派スーラを思わせる点描で描かれている。はじめ椅子にはだれも座っていない。頁をめくると<すわっているのは だれかしら>と問われ、絵には白ネコの姿がえがかれている。・・・・物語はこのように少しずつすんでいく。
こういう絵本は、頁をめくるのを急がずに、椅子に座る人物あるいは動物を、あれこれ想像してから、麟太郎さんが出してくる答えを見るという楽しみ方をするのがいいだろう。自分の想像力がどれくらい新鮮でみずみずしいかを試してみるいい機会になるだろう。(抜粋)
『まちの ひろばの どうぶつたち』
二冊目は『まちの ひろばの どうぶつたち』である。この絵本は見えるものと見えないものの混在する街を、ユニークな形で表現している。
ゾウ、キリン、サル、コトリ、ライオンの子どもたちは、透明なので、街の中を歩いても、誰も気づかれない。見えない彼らは、散歩中にこっそり人の仕事を手伝ったりして驚かしている。
ある日、男の子がスケッチした絵を落としたとき、透明動物たちが落とした絵を拾って男の子に返してあげる。すると男の子は見えないはずの動物たちに<ありがとう>と言って、五匹の動物たちに並んでもらって、絵を描きそれぞれに色をつける。突然、動物たちに色がつきみんなに見えるようになる。五匹が見えるようになって歩くと、街は大歓迎した。
人は日常の暮らしのなかで、いろいろな人々に支えられて生きている。だが、支えらえていることに気づかないことが多い。病気や災害など大変な事態に直面したとき、それまで気づいていなかった「人は支え合うことで生きている」ということにはじめて気づく。-- 私たちは日常の風景のなかでに、見えていない大切なものをぽんと挿入して、その存在をしっかりと見つめる感性を養わなければいけないのではないか。そんなことを、この絵本は語りかける。(抜粋)
『やぎのしずかのしんみりしたいちにち』
三冊目は『やぎのしずかのしんみりしたいちにち」である。しずかという名のヤギに、川の中から友達のナマズが<しんみりする うた>をうたってあげるが、あぶくが浮かんでくるだけで、何をうたっているのかわからない。そうしていると、木の上で歌っていたセミが突然泣き止みポトンと地面に落ちる。アリたちがセミを運んでいく。みんなで食べてしまうのかと思って、草の茂みに首を突っ込むと、クモの巣に美しい朝露が光っていた。そのうち草のつぼみが花びらの少し出かかっているのを見て、思わずパクリと食べてしまう。ヤギは、咲くことが出来なかった花のことを思い、鳴かなくなったセミやクモの巣の朝露につながり、しみじみと涙をながす。
人も動物も、目に見えない大いなる存在のもとで、生まれ、育ち、死んでいく。そのいのちの宿命的な循環のなかで、私たちの今日というささやかな一刻も、すぐに流れゆく朝露のようなものなのか。この絵本は、案外哲学的な問題を語っているかもしれない。(抜粋)
関連図書:
内田麟太郎(文)、nakaban(絵)『うみべのいす』、佼成出版社、2014年
井上コトリ(作)『まちの ひろばの どうぶつたち』、あかね書房、2015年
田島征三(作)『やぎのしずかのしんみりしたいちにち』、偕成社、2015年
夢幻の世界にこころ漂わせて
絵本というジャンルの表現手段をつかうと、こんなふうに魅力的な世界を描き出すことができるのだと、あらためて深い感銘を覚えた二つの作品に出合えた。(抜粋)
冒頭で柳田は、このように述べている。ここでは、柳田が感銘を受けた二つの作品が紹介されている。
『ねむりとり』
一冊目は『ねむりとり』である。この絵本は、「強烈な色がひらく異界」で取り上げられた、イザベル・シムレールの作品である。
まず柳田は、表紙にくぎ付けになったと言っている。それは、強烈な色彩で構図が大胆で謎めいている。そしてその扉をあけると
〈このほんを よむ あなたへ
このほんの なかでは ふしぎな いきものが ねむっています ページは そっとめくって ちいさな こえで よみながら さがしにいきましょう>(抜粋)
と書いてある。
そして、赤いパジャマでパイロット帽をかぶり飛行メガネをつけた少女が登場する。そして大きな赤いくちばしをもつ鳥の頭まで登っていく。すると大きな鳥は目を覚まし、大きな羽を広げて、夢の世界へと飛び立つ。
絵本は、そこで終わる。たったそれだけ? ――― と言うなかれ。そこからどんな物語が展開していくのか、それはあなたがみる夢です――― ということなのだろう。(抜粋)
『100年たったら』
もう一冊は『100年たったら』である。大草原にライオンが一頭だけいる。ほかに動物はいなくなっている。ライオンは、草と虫しか食べていない。そこに、旅鳥のヨナキウグイスがやってくる。ライオンは、そっと近づくと、ヨナキウグイスは、〈自分はもう飛べないから、私を食べてもいいわ>と言った。ライオンは〈おれは肉はくわない。おれの好物は草と虫だ>という。それから二人は一緒に日々をすごした。そして満月の夜に鳥はライオンの背中から転げ落ちた。
〈わたし、もういくよ。(中略)とおいところに〉。ライオンは、〈じゃ、おれも いくよ〉と言うが、〈だめ〉とたしまめられる。〈おれはただ、あんたといたいんだよ〉と、ライオンがおいおい泣く。鳥が〈また あえるよ〉と慰める。
〈いつ?(中略)ねえ、いつさ?〉
〈う~ん。そうだね、100年たったら〉(抜粋)
そして100年後、ライオンは岩場の貝になり、鳥だった波に海を届けてもらう。そしてて、また100年後、ライオンだったおばあさんは、孫娘に赤いひなげしの花をもらう。ひなげしの花はあとの鳥だった。そして100年後・・・・・
ファンタジーの物語であるのに、不思議なリアリティがある。輪廻転生などという仏教用語を持ち出すと観念的になってしまうが、この絵本では、いのちのめぐり合いが決して形而上学的な次元でなく、自然体で現実感のある物語として読めてしまう。(抜粋)
関連図書:
イザベル・シムレール(作)、河野万里子(訳)『ねむりとり』、フレーベル館、2018年
石井睦美(文)、あべ弘士(絵)『100年たったら』、アリス館、2018年
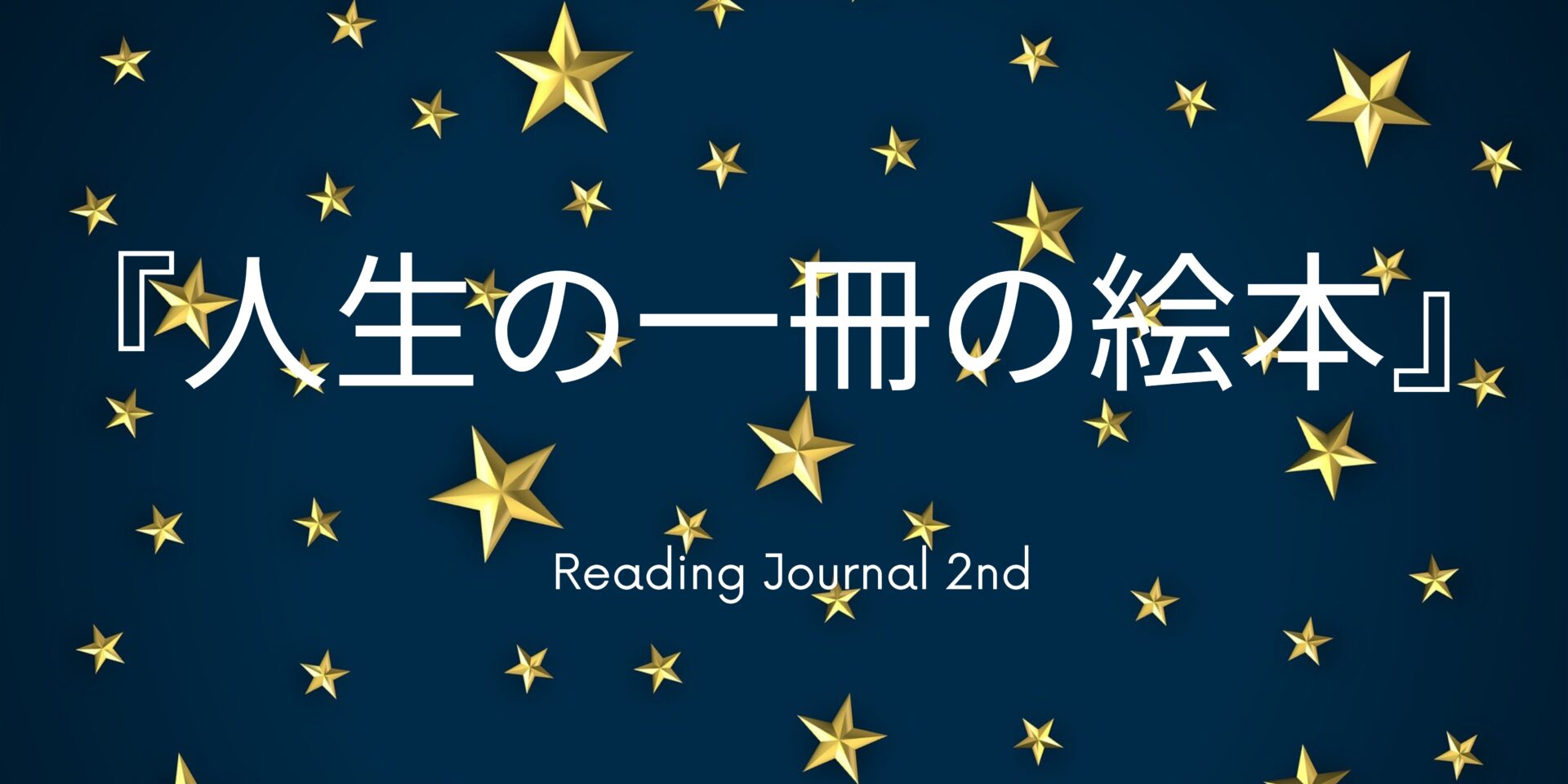


コメント