『陰翳礼讃・文章読本』 谷崎 潤一郎 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
現代文と古典文(後半) — 一 文章とは何か
今日のところは、「実用的な文章と芸術的な文章」の“後半”である。”前半“では、現代では口語文の実用的な文章を書くことが大事であるが、かといって文章体の文章の精神を無視することはできないことが説明された。口語体の欠点は語彙の多さから饒舌になることである。それを防ぐには、文章が表現できることと出来ないことの限度を知ることである。そして、語彙が少なかった古典を学ぶことはその役に立つ。
そして、今日のところ”後半“では、古典の持った字面や音調の美しさに学ぶことも重要である、ことが示される。それでは読み始めよう。
文章の音楽的効果、視覚的効果
次に私は、古典の持つ字面や音調の美しさも、ある程度まで、 -- いや、時には大いに、 -- 参考とすべきであると思います。(抜粋)
文章の音楽的効果、視覚的効果は、口語文でも無視することはできない。なぜならば、そのような効果も「理解」を助けるものであるからである。言葉(文章)とは不完全なものであるから、
われわれは読者の眼と耳に訴えるあらゆる要素を利用して、表現の不足を補って差支えない。(抜粋)
字面の効果
文章は、多くの場合に視覚的な要素と共に記憶される。筆記や活字の字体などはもとより、並びの文字の宛て方、漢字で書くか平仮名、片仮名で書くかのようなことまで文章の理解の手助けとなる。そして、
文章の第一の条件は「分からせる」ように書くことでありますが、第二の条件は「長く記憶させる」ように書くことでありまして、口でしゃべる言葉と違いは、主に、後者にあるのでありますから、役目としては或いはこの方が大切かもしれません。(抜粋)
文字の字面などには、この「長く記憶させる」効果がある。
われわれはわれわれに独自なる形象文字を使っているのでありますから、それが読者の眼に訴える感覚を利用することは、たとい活字の世になりましても、ある程度まで有効でありまして、・・・(中略)・・・われわれにのみ許される折角の利器を捨てておくと云う法はありません。(抜粋)
ここでいう「字面」は、むずかしい文字を使うことではなく、漢語を片仮名で書いて一種の効果をあげるなど、の様々なもの言っている。
耳に訴える音調の美
口語に最も欠けているのは、耳に訴える効果音調の美である。西洋においては、朗読法が研究されているが、日本では朗読法はなく音読の習慣もすたれてしまった。しかし、
音読の習慣がすたれかけた今日においても、全然声と云うものを想像しないで読むことはできない。(抜粋)
黙読と言っても結局は頭のなかで音読しているのである。しかしどのような抑揚やアクセントをつけるかの基準がない。
ここで谷崎は、現代の文章が多量の漢字を乱用するという問題について、
この弊害の由って来る今一つの原因は、昨今音読の習慣がすたれ、文章の音楽的効果と云うことが、忽諸に附されている所に存すると思います。(抜粋)
我々は、文章を見ると同時に聴いて理解するのである。そのため
文章を綴る場合に、まずはその文句を実際に声を出して暗唱し、それがすらすらと云えるかどうかを試してみることが必要でありまして、もしすらすらと云えないようなら、読者の頭に這入りにくい悪文で極めてしまっても、間違いありません。(抜粋)
素読について
ここで谷崎は素読という教授法を説明し、その効果について解説している。
素読とは、講義をしないでただ音読することであります。(抜粋)
意味は訪ねれば答えてくれるが、普通は説明されない。しかし、わけがわからないながらも文句が耳に残りそれが、歳をとるにつれて自然に意味が解ってくる。
古い諺に、「読書百遍、意 自ら通ず」と云うのはここのことであります。(抜粋)
そして、この素読は真の理解力を与えるのに最も適している方法であるかもしれません、と言っている。
「分からせるように書くこと」と「記憶させるように書くこと」
このように「分からせるように書くこと」と「記憶させるように書くこと」は、同じである。
即ち真に「分からせるように」書くためには「記憶させるように」書くことが必要なのであります。(抜粋)
字面の美しさや音調の美は、記憶を助けるばかりでなく、実際の理解にも役立つ。現代の口語文の言葉を多く使ってしまう欠点を、字面や音調で補ってこそ立派な文章と云える。
このような文章の感覚的要素が備わっていない現代の口語文は、不完全な発達をしたものである。そして、古典の文章は、この感覚的要素を多分に備えているため、それを大いに勉強して長所を学ぶべきである。
ここで谷崎は、前に引用した志賀直哉の『城の崎にて』の文(ココを参照)を例にとり、具体的に字面と音調の効果を解説している。
書簡文体(候文)について
音楽的効果、視覚的効果の章の最後に、谷崎は「書簡文体」(候文)について触れている。
この「書簡文体(候文)」は、和文調とも漢文調とも云えない文であり、すたれる運命にあるが、これもやはり口語文をつくるのに参考になる。
この候文は、一つのセンテンスと一つのセンテンスの間に相当の間隙あり、意味の切れ目があって、そこに余情がうまれ面白い。
この間隙が、美しい日本文を作るのに大切な要素でありまして、口語文には最もそれが欠けております。故にわれわれは、候文は書かないまでも、候文のコツを学ぶことは必要であります。(抜粋)
関連図書:志賀直哉(著)『小僧の神様・城の崎にて』 、新潮社(新潮文庫))、1968年
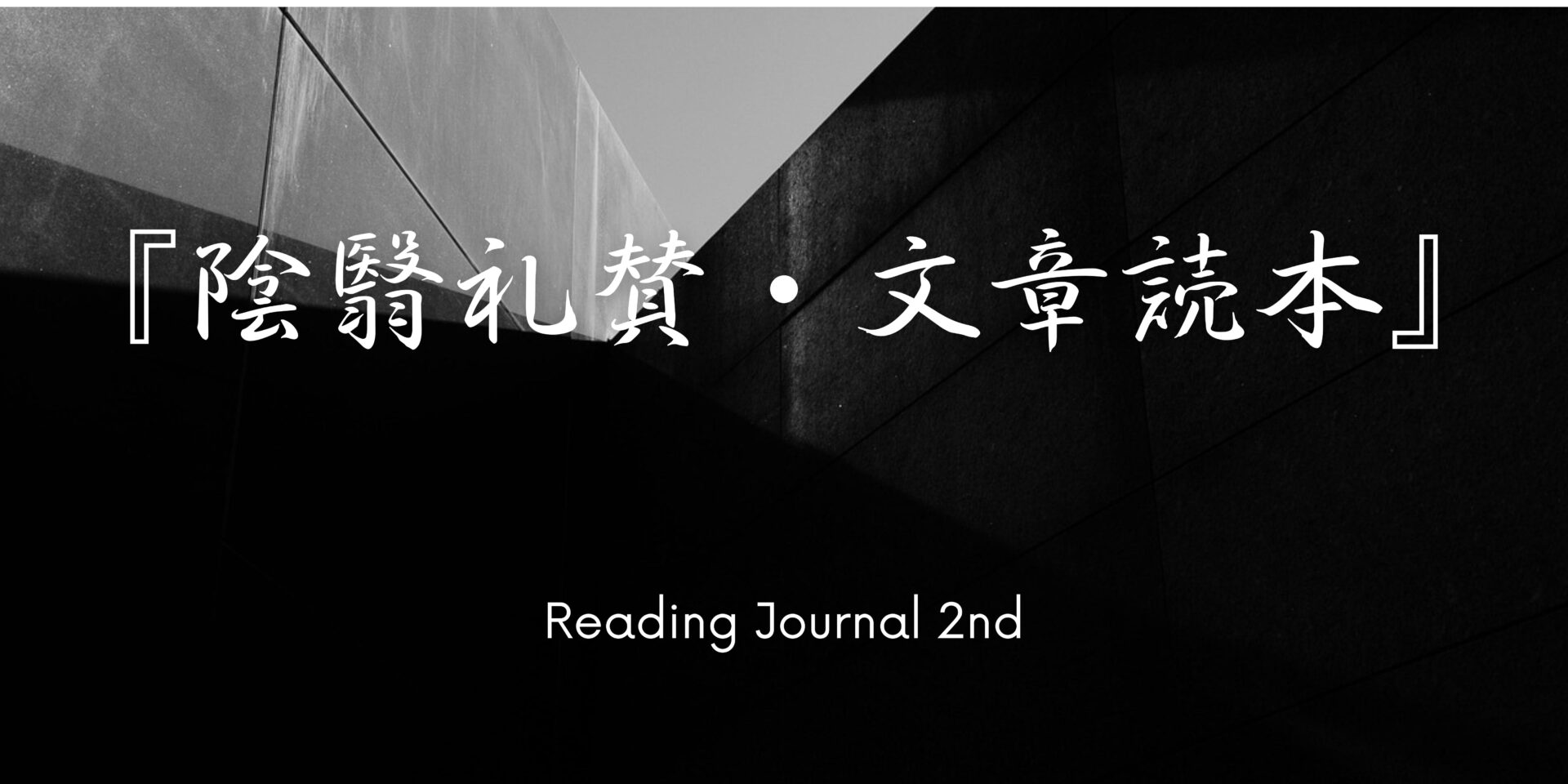


コメント