『陰翳礼讃・文章読本』 谷崎 潤一郎 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
実用的な文章と芸術的な文章 —- 一 文章とは何か
今日のところは、「実用的な文章と芸術的な文章」である。前回の「言語と文章」では、人がその思想などを伝えるには言語を使用するしかないが、言語は万能ではなくむしろ不自由なものであること、さらに文章は、口で話すものとは違い、「話す方は、その場で感動させることを主眼するが、文章の方はその感銘が長く記憶されることに重きを置く」ことなどが説明された。
そして今日のところでは、文章には芸術的な文章と実用的な文章の違いはなく、その要点は、「自分の云いたいことを明瞭に伝えること」であると説明されている。それでは読み始めよう。
私は、文章に実用的と芸術的との区別はないと思います。(抜粋)
文章の要は、自分の云いたいことを明瞭に伝えることである。昔は「華を去り実に就く」のが、文章の本旨であるとされ、それは余計な飾り気を除いて実際に必要な言葉だけで書くということである。つまり、実用的なものが、最もすぐれた文章である。
明治時代には、美文体というものがあった。競ってむずかしい漢語を連ねて、語調のよい、綺麗な文字を使って、景を叙する文章である。しかし、これでは装飾が勝ちすぎ自分の思想や感情を表すのに不便である。実用的でない文章とはまずはこのようなものとなる。
文章には韻文と散文の区別がある。韻文とは、詩や歌のことであり、普通の文章とは目的が異なり、特別な発達をしている。
私がこの本の中で説こうとするものは、韻文でない文章、即ち散文のことでありますから、そえは予めご承知を願っておきます。(抜粋)
この韻文でない文章に関しては、実用的と芸術的との区別はない。芸術的な目的で作られる文章も、実用的に書いた方が効果がある。
実際に理解されるように書こうとすれば、なるべく口語に近い文体を用いるようにしなければならない。韻文では、分からせること以外に眼で見て美しいことと耳で聞いて快いことが必要であったが、口語文では、「分からせる」「理解させる」ことに重点が置かれ、その他の二つは、あるには越したことはないが、こだわっては間に合わない、分からせることで文章の役目は手いっぱいである。
ここで著者は、文章をもって現わす芸術は小説であるとし、志賀直哉の『城の崎にて』の一文を長文引用し、分かりやすい実用的な文章でありかつ芸術的な「華を去り実に就く」文章の例としている。そして
最も実用的に書くと云うことが、即ち芸術的の手腕を要するところなので、これはなかなか容易に出来る業ではないのであります。(抜粋)
とし、引用した志賀の形容詞の使い方などの技巧的な部分を説明し、
実用文においても、こう云う技巧があればあった方がよいのであります。(抜粋)
と言っている。
関連図書:志賀直哉(著)『小僧の神様・城の崎にて』 、新潮社(新潮文庫))、1968年
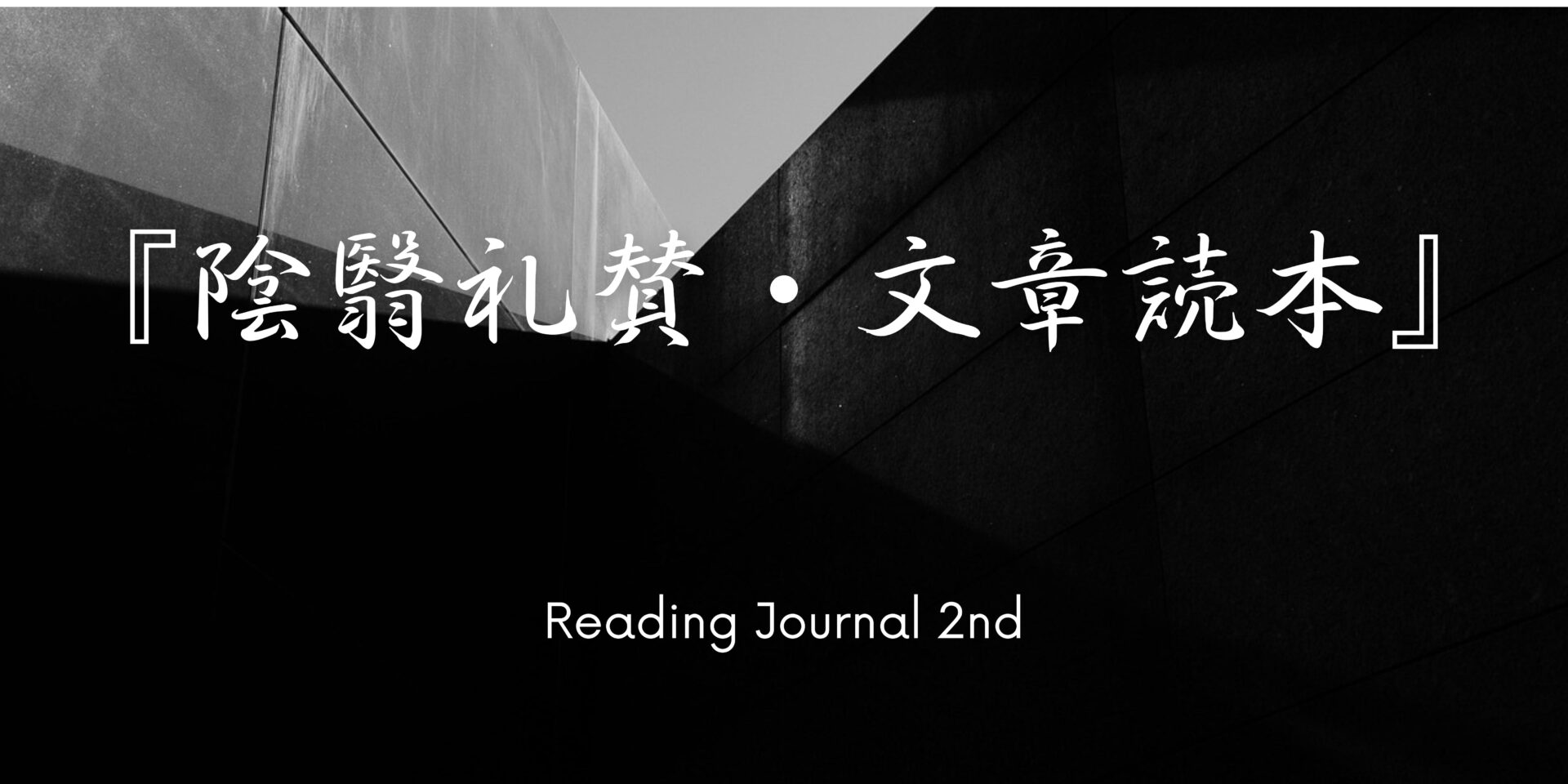


コメント