『陰翳礼讃・文章読本』 谷崎 潤一郎 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
体裁について(その1)—- 三 文章の要素
今日から文章の要素(ココ参照)の4つ目「体裁について」である。
体裁とは文章の視覚的要素を指すが、これには「イ 振り仮名、送り仮名」「ロ 漢字及び仮名の宛て方」「ハ 活字の形態の問題」「二 句読点」の四つがある。
この体裁は、3つに分け、“その1”で(イ)、“その2”で(ロ)、“その3”で(ハ)、(二)をまとめる。それでは読み始めよう。
文章の体裁
体裁とは、文章の視覚的要素である。それには、
- イ 振り仮名、送り仮名
- ロ 漢字及び仮名の宛て方
- ハ 活字の形態の問題
- 二 句読点
がある
言葉というものは不完全であるので、読者の眼と耳に訴えるあらゆる要素を利用する必要があり、字面は必ず内容に影響する。また、形象文字と音標文字を混用する日本語ではその影響は大きくなる。
ですから体裁と申しましても、実は内容の一部と見なしてもよいわけでありますて、決してゆるがせには出来ないのであります。(抜粋)
イ 振り仮名、及び送り仮名
振り仮名
まず谷崎は、芥川龍之介の「読者に一番親切なやり方は、全部に振り仮名を附けることだ」という言葉を紹介する。
そして、それは読者に親切というばかりでなく作者にとっても一番迷が少ないと言っている。そして、以前に「二人の稚児」という作品を「フタリノチゴ」と読ませたいところを「ニニンノチゴ」と読まれたという逸話を紹介し、
こう云う間違いは、作者が聞くとあまり好い気持はしないものでありますが、しまもわれわれの口語文においては常に頻々と起こるであります。(抜粋)
と言っている。
問題は、難しい文字よりも易しい文字の方が却って間違えられやすいことである。難しい文字は読み方も一定していて辞書を引けばよいが、易しい語は、辞書を引いてもいくつも読み方がある。つまりこのような間違いは常に起きる可能性がある。
ところが高級な文芸作品におきましては、これらの何でもない文字の読み方の適不適が、時としてその文章の順序や気分に重大な影響を及ぼすのでありますから、作者としては神経質にならざるを得ません。で、そう云う点から考えますと、全部に振り仮名を打つことが安全な策だと云えるのであります。(抜粋)
ここで問題になるのは、総振り仮名(総ルビ)を打つと、活字面の美しさが犠牲になるということである。
流麗調の文芸作品ならば、総振り仮名を打つことも妨げないかもしれない。流麗調は、一字一字がはっきりすることを必要とせず、全体をなだらかに読んで貰うことを欲するので、読者が難しい文字で停滞しないように、読み方を振っておくのも一つの手段である。さらに振り仮名は、漢字の堅さを和らげて平仮名との続き具合をぼかす役目もする。
しかし、簡潔調の文章では、総振り仮名の持つそれらの効果が害となる。この調子では、字面が清澄であることを欲していて、振り仮名により活字の周囲に黒いシミをつけるのは面白くない。さらに、読者が難しい語に出会って停滞しても、差し支えなく、却ってその方が印象は深くなる。冷静調においても同様であるが、これは簡潔調よりも一層字面の清澄と透明とを要する。
結局、文芸作品では、総ルビ(総振り仮名)でなく、ところどころにルビを振るバラルビが多くなる。しかし、このバラルビもどの語にルビを振り、どの語に振らないかという標準を定めるのは思いの外困難である。
そこで、振り仮名は孰れにしましても好ましいものではありませんから、真に已むを得ざる場合の外は施さないことにいたしますと、ここで新たな難問題が発生するのでありますが、その第一が送り仮名であります。(抜粋)
送り仮名
国文法では、送り仮名は「動詞・形容詞・副詞等の語尾の変化する部分だけに附ければよい」と定められている。この時、総振り仮名であればこれで問題はないが、振り仮名がないと問題が起こる。
たとえば、「コマカイ」という字は
細い
と書くのが文法的に正しいが、これは「ホソイ」と読まれる恐れがあるため、
細かい
と書く必要が出てくる。すると「短い」「柔い」→「短かい」「柔かい」としないと統一が取れなくなる。類似の語根を持つ形容詞は、同じような送り仮名をしないと不ぞろいになるため、書く人の気分本意になってしまう。
同様なことが、動詞でも起こり「アラワス」は、
現す
が正しいが、「現わして」を「アラワシテ」と読む人と「ゲンジテ」と読む人がいるため
現わして
と書く。同様なことが多くあり、銘々かって次第になってしまう。
これは形容詞・動詞に限ったことではなく、同様なことはまた名詞においても起こってしまう。名詞においてもっとも極端な例は、
少くない
とか書いて、これに
少ない
とルビを振らずに
少くない
と振る人がある。
もし現代の口語文のおける送り仮名の乱脈と不統一を調べましたら、際限もないことでありましょう。さればさすがに芥川氏の総ルビ説の卓見であったことを感じるのでありますが、なおこの問題に、漢字の宛て方が絡んで参りますと、一層煩わしくなるのであります。(抜粋)
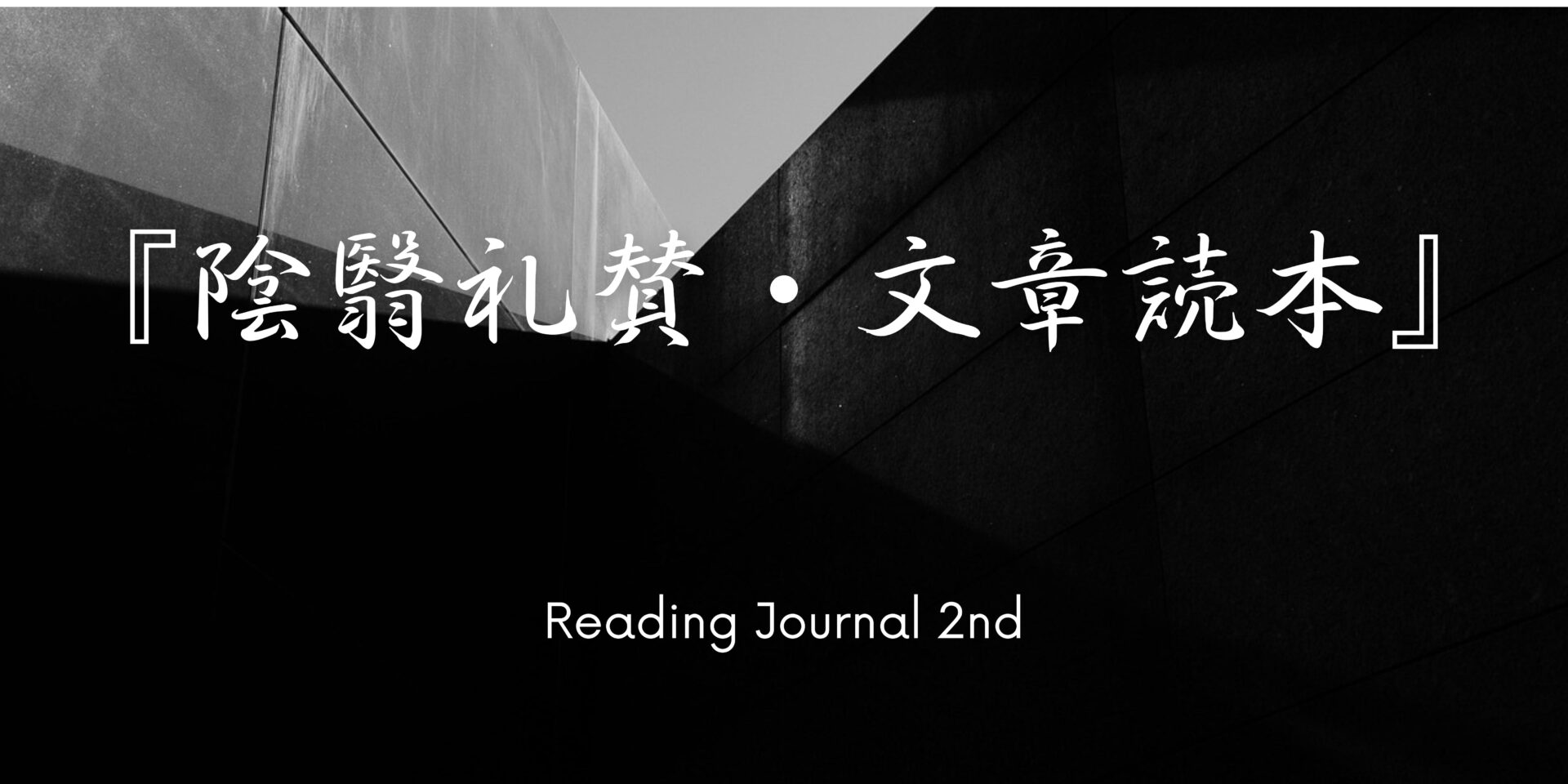


コメント