『本を読む本』 M.J.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二部 分析読書 — 読書の第三レベル 6 本を分類する
今日から、「第二部 分析読書」に入る。第二部では、6節から12節にかけて読書の第三レベルである「分析読書」が扱われる。今日のところは、本にはどのような分類があり、それをどのように判別するかなどが書かれている。この「本の種類を知る」ということは、分析読書の第一の規則である。それでは読み始めよう。
分類の重要性と分析読書 第一の規則「本の種類を知る」
「読者は、いま読んでいるのがどんな種類の本かを知らなければならない。これを知るのは早いほどよい。できれば読み始める前に知る方がよい」(抜粋)
「本の種類を知る」ということが分析読書の第一の規則である。
たとえば、いま読んでいる本がフィクション(小説、戯曲、叙事詩など)であるか「教養書」であるかを知らなければならない。ここでいう「教養書」は、広い意味で知識の伝達を第一の目的とする本のことである。
だがここで問題とするのは、教養書の中のいろいろな種類を見分けることである。
「できれば読み始める前にその本の種類を知る」には、「点検読書」(ココ参照)をすることである。書名、タイトル、目次、序文やまえがき、索引、さらには出版社の紹介文にまで目を通しその本の種類について調べることが大切である。
本を分類することの重要性は、教室での講義を思い浮かべるとわかる。教室での講義は、先生の教え方によりそれが、歴史か、科学か、哲学かすぐにわかる。それは科目がが違えば教え方も違うからである。読書もそれと同じで、種類が違えば読み方の技術も変えなければならない。そのため、読み始める前にどの種類の本であるかを知ることが大切な技術となる。
理論的な本と実践的な本
この分析読書の第一の規則に従うには、「本の種類とは何か」を知らなければならない。まずフィクションと「教養書」の大きく二つに分類した。次に「教養書」の区分を考える。
この教養書には基本的な区分をひとつ設ける。それは「理論的な本」と「実践的な本」である。
- 実践的な本は、何らかの形で目に見える効果を生むもので、行動と関係がある。
- 理論的な本とは、見たり聞いたり理解したり本で、知識と関係がある。
つまり、教養書の区分は、知識(「理論的な本」)と行動(「実践的な本」)の二つの区分となる。
知識を実用化するためには、知識を行為の規則に作り変えなければならない。「実態を知ること」から、「どうしたら目的に達することができるかを知ること」に移行しなければならない。つまり、事実を知ることと、方法を知ることの二つとなる。理論の本は事実を教え、実践の本は方法を教える。(抜粋)
実践的な本の種類
実践的な本の種類としては、たとえば本書のような技芸の学び方を教える本は実践的な本である。工学、医学、料理などの技術の案内書や指導書、さらに経済、政治、倫理(この三つは「規範的」というカテゴリーに含まれる)も実践的な本である。
ここで倫理が実践的な本に入るのは倫理は、人がどのように生きるべきか、すべきこととすべきでないことを教えるからである。同様な意味で経済の本も実践的である。
さらに演説も広い意味で実践的と考えられる。
理論的な本の種類
理論的な本については、歴史、科学、哲学と分けて考えるのが普通である。しかし歴史は過去と関わり歴史家はこれに洞察を加える。科学と哲学はどちらに属するかの判断が必要時も多い。
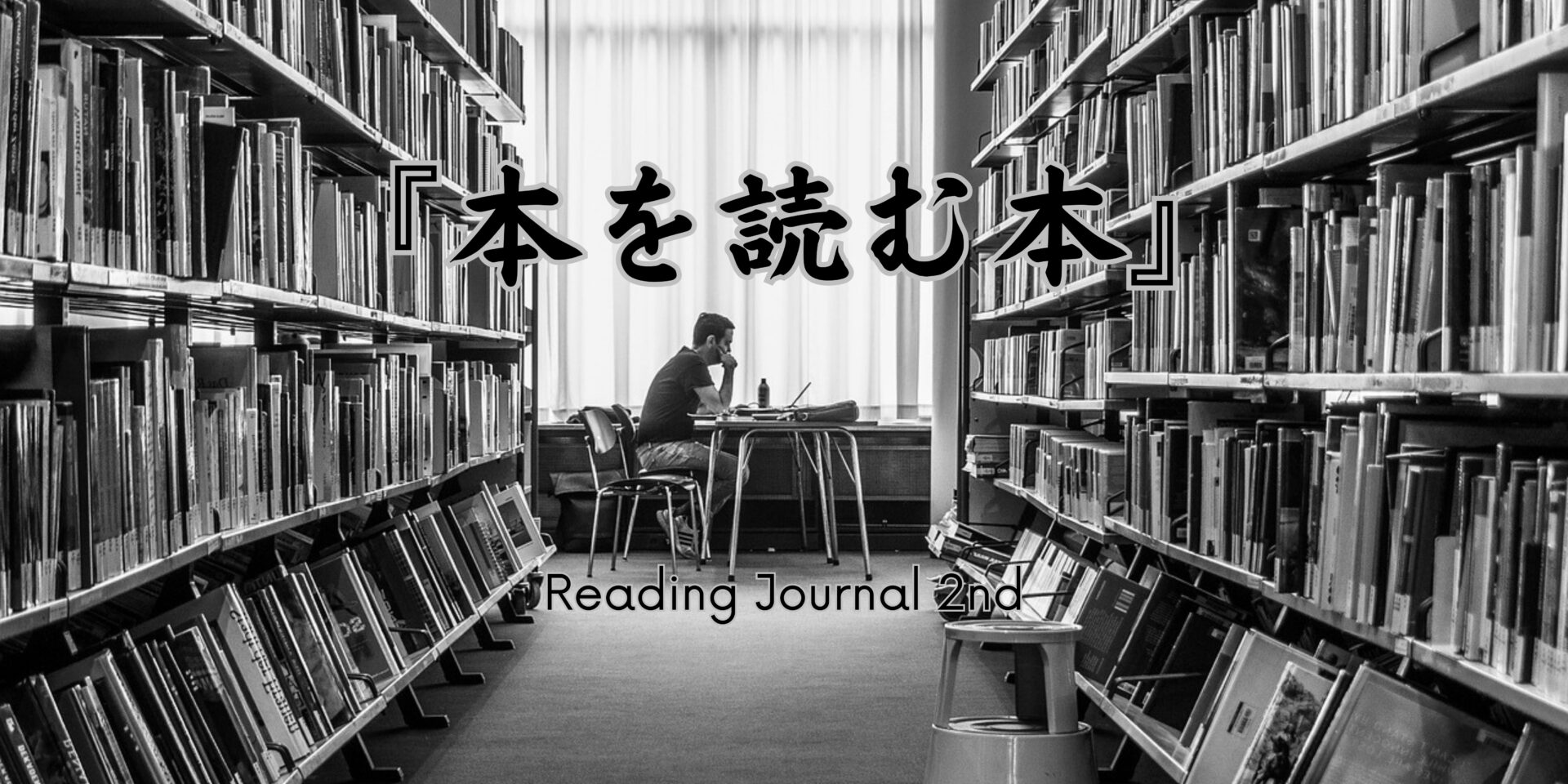


コメント