『人を助けるとはどういうことか』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
③ 成功する支援関係とは?(その3)
今日のところは「③ 成功する支援とは?」の”その3“である。”その2“では、支援をする状況でクライアントが陥りやすい感情的な罠が取り扱われた。今日のところ”その3“では、今度は、支援者が陥りやすい罠が取り扱われる。そして、最後に成功する支援関係を築くためには、”その1“で示された「人間関係のバランスの悪さに起因するこのような罠をさけ、支援者がどのような役割を演ずるかを明確にする必要性がある」とまとめられる。それでは、読み始めよう。
支援者が陥りやすい六つの罠
支援者となった人はワン・アップの立場になるため、この立場を利用したいという感情が生まれる。それは普通のことであるが、人間関係に問題を作り出す罠となり得る。
①.時期尚早に知恵を与える
まず、あまりに早く助言を与えると、クライアントの立場をさらに下に置くことになる。そしてあまりに早い反応は、提示された問題が仮の問題で支援者を試しているという可能性があることを無視している。
公式や準公式の支援の場合は、実態を探る時間を取ることが普通にされるが、非公式の支援の状況では、時期尚早に知恵をさずける罠に陥りやすい。まず、相手が本当に求めているのが何か考えなければならない。
②.防衛的な態度にさらに圧力をかけて対応する
支援者は、クライアントが本当に問題を解決したいと思い、提供した解決策を実行するスキルや能力もあると考えがちである。このような罠に陥ると、自分の助言が正しいとクライアントを説得し、理解されるまで議論や説明をする。
支援者は戸惑いを覚えるだろうが、こうした態度は人間関係が壊れる状況に通じる。(抜粋)
③.問題を受け入れ、(相手が)依存してくることに過剰に反応する
クライアントが助けが得られるか分からない状況で、支援者に依存してしまうことがある。しかし、関係が始まったばかりの段階では、支援者がどんな助けを与えられるかはっきりしていない、そのため初期の段階で依存状態が高くなると機能不全に陥りかねない。
解決策が編み出される中で、さまざまな問題にクライアントが積極的に参加する必要があるからだ。(抜粋)
支配権を握るという罠に落ちると、支援者は提案するだけでなく、次のステップを指示してしまう。
④.支援と安心感を与える
支援することが適切でなく、クライアントの地位の低さを助長する場合もある。(抜粋)
状況を合理的に評価して支援することと、クライアントに同情して、その支えになることは別のことである。このようなとき、支援者は権力を握り、クライアントの地位の低さを助長してしまう。
いったん支援者が同情心を見せてしまうと、クライアント自身が作り出したかもしれない問題の責任を認識させるのが難しくなる。(抜粋)
⑤.距離をおいて支援者の役割を果たしがらない
支援者が、感情的に距離を置いてしまうため、まったく関わりたくないという気持ちを伝えてしまうことがある。公式な支援の場合は、感情面の隔たりがあっても適切だと思われるが、非公式の支援の場合は、感情的に距離を置くと、この問題に関わりたくないというメッセージを伝えてしまうことがある。
支援者は、支援が本当に必要なときに人間関係が築かれるよう、客観性と関わりとのちょうどよいバランスを見つけるというジレンマに陥る。(抜粋)
このような無関心態度があらわれる背景には、クライアントとの関りを深めると、支援者も何らかの影響を受け、状況に対する見方の変化や見解を変えなければならない状況になる可能性があるからである。その時支援者は権力あるワン・アップの地位を諦めざるを得ない。
実を言えば、影響を受けることを厭わないというこの気持ち --- クライアントが本当に言わんとしていることに耳を傾け、問題への先入観を捨てること --- が、人間関係の平衡を保つ最も効果的な方法なのだ。(抜粋)
支援者は、クライアントの話に心から耳を傾けることによって、相手に地位と重要性をあたえられる。そしてクライアントによる状況の分析が価値あるものだとメッセージをつかえることでもある。
支援というものが、影響をあたえることの一つの形と考えるならば、自分が影響されてもかまわない場合しか他人に影響を与えられない、という原則はきわめて適切だ。(抜粋)
ここは、なかなか深い話である。①から④までは、支援者が前のめりになって、ろくに話も聞かずに、指示してしまったり、どんな時でも味方になるぞ、と相手を完全に依存状態に置いたりということだった。
ここは、そういう罠にはまらないように、遠くで眺めているような態度の罠について何だろうと思う。そういう態度が、結局は無関心であるようなメッセージを伝えてしまう。
そうではなくって、早急に自分が思った正解を指示するのではなく、かといってそっと眺めているのでもなく、じっくり相手の話を聞くことが大切だと言うことを言っている。相手の話を聞くと、自分が思っていた正解が実は誤りとわかるかもしれない。それでもじっくりと聞いてあげるってことだな。きっとね(つくジー)
⑥.ステレオタイプ化、事前の期待、逆転移、投影
支援者は過去の経験に左右されやすい。クライアントが以前にかかわった誰かと似ている場合にその過去の経験が無意識に働く危険がある。
著者も、「私は反依存型のクライアントのほうがうまくかかわることができる」と自己分析をしている。
支援者は自分の感情の性質を自覚するべきだし、支援者とクライアントの関係の中には、成り立たないものがあることを自覚していなければならない。(抜粋)
支援関係を築くということ
支援関係を築くとは、突き止めた罠を認識して避け、修復することを意味している。(抜粋)
支援者はクライアントとの交流の最初の段階で、適切な役割を認識しクライアントの地位を高める必要がある。
これを実行するのは簡単ではない。(抜粋)
支援者は、クライアントよりも、自分がワン・アップにいる状態で関係に入っていく。そして、自分がクライアントに有益として行った支援が受け入れられないと失望し、イライラしフラストレーションがたまってしまう。支援者は、自分の素晴らしい見識や助言が目を留めてもらえず、苛立つ。一方、ありふれた質問や意見をクライアントが高く評価する場合もある。
支援の状況では、人間関係のバランスが悪いためこのような罠に陥るやすい。成功する支援関係を実行するには、クライアントの立場を確立する支援者の介入が必要である。それを実行するためには、まず支援者が自分の役割を明確にしなければならない。
あまり意識されていないことだが、支援者は役割を選択できる。その方法は、長期にわたる人間関係から生まれる。次の章でこれについて探ろう(抜粋)
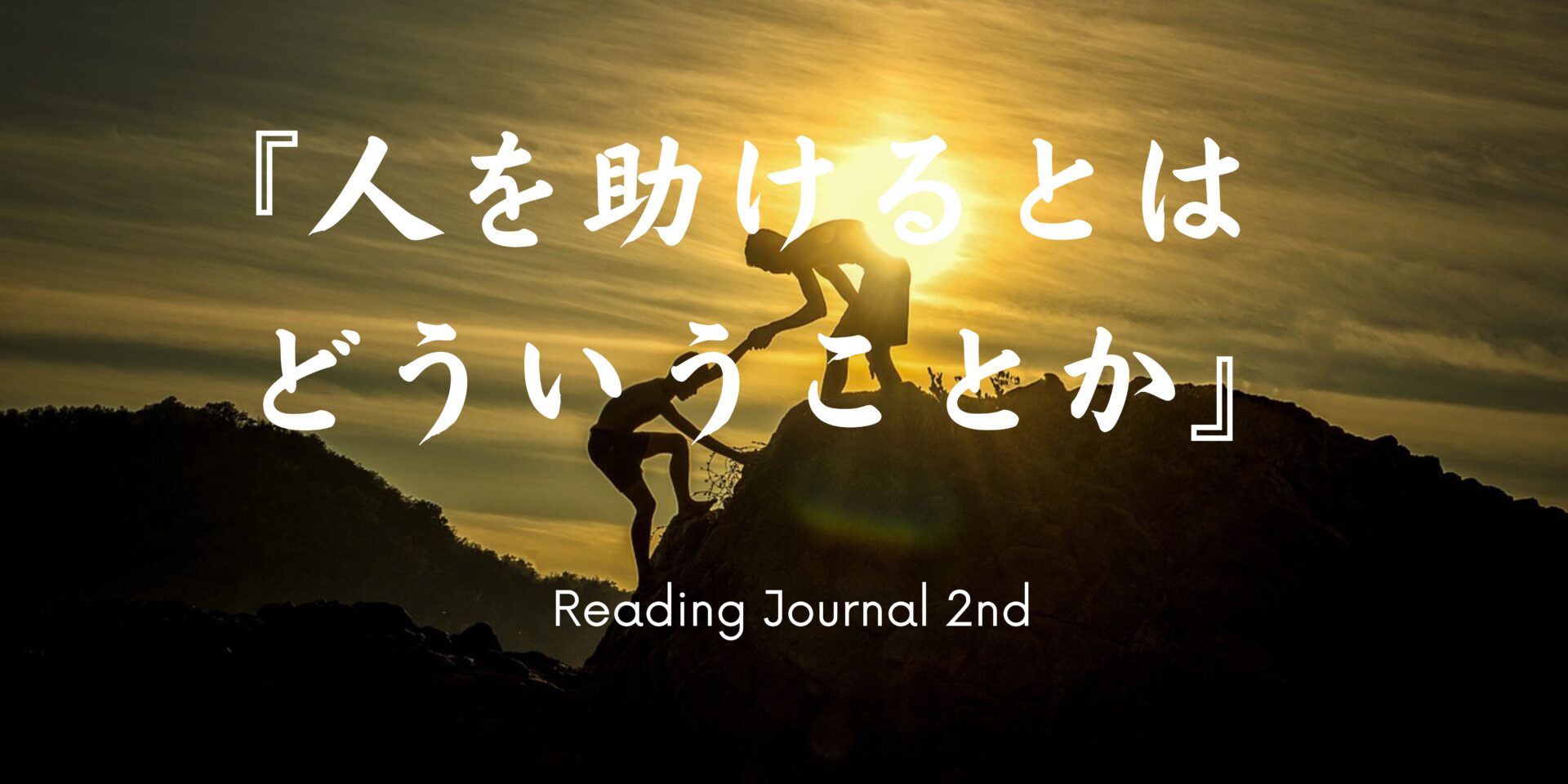


コメント